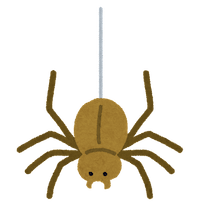8月は、なんだか全くやる気が起きなくて、とうとうブログをお休みしてしまいました。
休日に食べる量を少し減らしたりして、最近はわりと元に戻ってきたような気がします。
今回は、俳優さんがアニメなどの声優に起用された時に、あれ、なんだか抑揚がないかなぁと、いわゆる「棒」に聞こえてしまう理由について、ふと思いついたことがあったので、書いてみようと思います。
ただ、ディズニーなどのアニメーションは声優の声を先に録って後から絵の表情をつけたりと制作手法が異なるようなので、おそらく今回のブログは日本のアニメにしか当てはまらないかもしれません。
朝はいろいろ準備をしながらラジオを聞いていることが多いのですが、今週は黒木瞳さんの「あさナビ」という短い番組に、落語家の春風亭一之輔さんが出ておられました。
そこで、落語家は登場人物を演じ分けるのに声質は変えない、男でも女でも子どもでもご隠居でも声質はほぼ同じで、語尾や表情や仕草などで演じ分ける、という話をされていました。
(下の方の「落語の稽古」というところで触れられています)
これを聞いて、おお、そう言われるとそうだよなぁ、と、新たな発見なのでした。
落語は、噺家が一人で状況などを言葉で説明しながらストーリーを綴っていくものですから、噺家の仕草などの視覚情報はあるものの、物語を理解するためにかなりの部分で聞き手・受け取り手の「想像力」が必要とされます。
そこへ、登場人物を演じ分けるのに声質を変えてしまうと、その想像力をフル活動させている最中には、かえって「雑音」になってしまうのかもしれないなぁと思いました。
そこでアニメファンとしては、アニメの方へ気が向いてしまいます。
アニメとは何かを考えると、諸説あると思われますが、元の根っこにあるものは「マンガに動きと音をつけたもの」と言えるかもしれません。
多くの手法が生まれたり技術が発達していくにつれ、アニメはアニメとして発展を遂げたわけではあります。
そしてマンガとは何か、と考えると、「象形文字」や「記号」の発展したもの、と言えるかもしれません。
これは別に私が考えたわけではなくて、手塚治虫さんが「マンガ記号論」として提唱したと言われています。
例を挙げて考えてみると、サザエさんに出てくるタイ子さんは、美人キャラとして認知されているのではないでしょうか。
サザエさん公式ホームページのキャラクター紹介でも、「美人でおしとやか」と紹介されています。
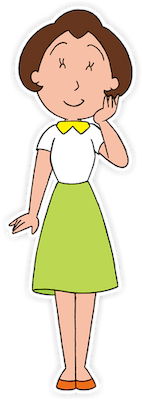
※画像はサザエさん公式ホームページより
冷静に絵だけを見て考えてみると美人なのかどうか、よくわからなくなってしまいますが、まつ毛が長い、とか、鼻筋が通っている、などの(日本人が)美人と感じる要素、「記号」が詰め込まれているため、タイ子さんを美人、と認識してしまうものと思われます。
それを踏まえてアニメの声優について考えてみると、声で演技をする際にも、「記号」化したほうが違和感なく聞こえるのではないか、という予測が立ちます。
ツンデレ美少女はこういう感じ、とか、ガタイのいいおっさんはこんな感じ、とかの「記号」というか「お約束」です。
そのような「お約束」の元に演技した方が「記号」としての絵に乗っかった時に、受け取り手としては違和感なく物語に入れるような感じが、あるような気がします。
もしかしたら日本独自のものなのかもしれませんが。
もちろん声優さんにも個性があり、全く同じものにはならないわけですが、それでも「型」「お約束」「記号」に則った上での個性、ということになりそうです。
別に声優さんに個性が足りない、というわけではなく、俳句でいえば5・7・5で表現しなければならない、みたいな制限という感じでしょうか。
そして必ずしも物語の登場人物が「型」を持ったキャラクターとは限らないので、そのような時にどのような演技をするか、という悩みも声優さんにはありそうです。
その「お約束」はあくまでもアニメの中だけのことであり、普段の生活ではアニメの「お約束」に沿って会話をすることはあまりありませんが、一部のアニメファンは普段からアニメのような言葉遣いや抑揚を実生活の中でも使用してしまうため、周りからすると、ちょっとめんどくさい人だな…ということになってしまうのでござるよ。

そして俳優さんがアニメの声優に起用された時に、俳優さんはそのような「お約束」の勉強や訓練をしてきたわけではないので、演技としてはアニメの「お約束」から逸脱したものとなってしまい、あれ、なんかちょっと違う、という違和感が、「棒」と言われてしまうものなのだと思われます。
そして、アニメファンであればあるほど、「お約束」に接する濃度が濃いはずなので、違和感はより強いものとなっていくものでしょう。
しかし、ジブリだったり、新海監督だったり、細田監督だったり、俳優を声優に起用しがちな方々の作品を見てみると、背景が絵画というか実写というかという感じで描きこまれていたり、キャラがめっちゃぬるぬる動くとか、「絵」として見た場合も「記号」としてのマンガ・アニメから逸脱したものとなっています。
というわけで、物語に引き込まれていくうちに、俳優さんの声優としての演技にも違和感を感じなくなっていくような気がします。
俳優さんの声優起用には、従来のアニメとは違ったものを作り上げたいという、制作者の意図も込められているのかもしれません。
(まぁ、知名度を利用した集客目的という大人の事情もあるのかもしれませんが…)
器用な俳優さんや、プライベートでアニメが好きという俳優さんなどは、アニメの「お約束」に沿って演技できる方もいるのだと思いますが、そのような制作者の意図があるならば、演技としても現実感のあるものを求められるのかもしれませんね。
また、テレビアニメでも「記号」にとどまらないような作り込まれた作品も多く存在するので、もしかしたらアニメの声優さんもこれからは徐々に、演技の手法などの移り変わりがあったりもするのかもしれません。
3Dアニメにはどんな演技が合っているのか、などの問題提起も起こりそうです。
まぁ個人的にはザ・記号って感じのベタなアニメも、消えないで残っていってほしいなぁと思います。
ここまで書いて冷静に読み返してみると、なんだかごく普通のようなことを大袈裟に書いてしまったというか、どこかで読んだものも多く含まれているような気がしますが、ご容赦くださいませ。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
休日に食べる量を少し減らしたりして、最近はわりと元に戻ってきたような気がします。
今回は、俳優さんがアニメなどの声優に起用された時に、あれ、なんだか抑揚がないかなぁと、いわゆる「棒」に聞こえてしまう理由について、ふと思いついたことがあったので、書いてみようと思います。
ただ、ディズニーなどのアニメーションは声優の声を先に録って後から絵の表情をつけたりと制作手法が異なるようなので、おそらく今回のブログは日本のアニメにしか当てはまらないかもしれません。
朝はいろいろ準備をしながらラジオを聞いていることが多いのですが、今週は黒木瞳さんの「あさナビ」という短い番組に、落語家の春風亭一之輔さんが出ておられました。
そこで、落語家は登場人物を演じ分けるのに声質は変えない、男でも女でも子どもでもご隠居でも声質はほぼ同じで、語尾や表情や仕草などで演じ分ける、という話をされていました。
(下の方の「落語の稽古」というところで触れられています)
これを聞いて、おお、そう言われるとそうだよなぁ、と、新たな発見なのでした。
落語は、噺家が一人で状況などを言葉で説明しながらストーリーを綴っていくものですから、噺家の仕草などの視覚情報はあるものの、物語を理解するためにかなりの部分で聞き手・受け取り手の「想像力」が必要とされます。
そこへ、登場人物を演じ分けるのに声質を変えてしまうと、その想像力をフル活動させている最中には、かえって「雑音」になってしまうのかもしれないなぁと思いました。
そこでアニメファンとしては、アニメの方へ気が向いてしまいます。
アニメとは何かを考えると、諸説あると思われますが、元の根っこにあるものは「マンガに動きと音をつけたもの」と言えるかもしれません。
多くの手法が生まれたり技術が発達していくにつれ、アニメはアニメとして発展を遂げたわけではあります。
そしてマンガとは何か、と考えると、「象形文字」や「記号」の発展したもの、と言えるかもしれません。
これは別に私が考えたわけではなくて、手塚治虫さんが「マンガ記号論」として提唱したと言われています。
例を挙げて考えてみると、サザエさんに出てくるタイ子さんは、美人キャラとして認知されているのではないでしょうか。
サザエさん公式ホームページのキャラクター紹介でも、「美人でおしとやか」と紹介されています。
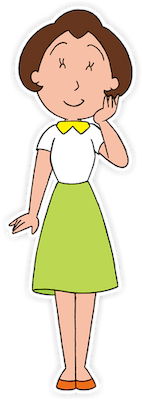
※画像はサザエさん公式ホームページより
冷静に絵だけを見て考えてみると美人なのかどうか、よくわからなくなってしまいますが、まつ毛が長い、とか、鼻筋が通っている、などの(日本人が)美人と感じる要素、「記号」が詰め込まれているため、タイ子さんを美人、と認識してしまうものと思われます。
それを踏まえてアニメの声優について考えてみると、声で演技をする際にも、「記号」化したほうが違和感なく聞こえるのではないか、という予測が立ちます。
ツンデレ美少女はこういう感じ、とか、ガタイのいいおっさんはこんな感じ、とかの「記号」というか「お約束」です。
そのような「お約束」の元に演技した方が「記号」としての絵に乗っかった時に、受け取り手としては違和感なく物語に入れるような感じが、あるような気がします。
もしかしたら日本独自のものなのかもしれませんが。
もちろん声優さんにも個性があり、全く同じものにはならないわけですが、それでも「型」「お約束」「記号」に則った上での個性、ということになりそうです。
別に声優さんに個性が足りない、というわけではなく、俳句でいえば5・7・5で表現しなければならない、みたいな制限という感じでしょうか。
そして必ずしも物語の登場人物が「型」を持ったキャラクターとは限らないので、そのような時にどのような演技をするか、という悩みも声優さんにはありそうです。
その「お約束」はあくまでもアニメの中だけのことであり、普段の生活ではアニメの「お約束」に沿って会話をすることはあまりありませんが、一部のアニメファンは普段からアニメのような言葉遣いや抑揚を実生活の中でも使用してしまうため、周りからすると、ちょっとめんどくさい人だな…ということになってしまうのでござるよ。

そして俳優さんがアニメの声優に起用された時に、俳優さんはそのような「お約束」の勉強や訓練をしてきたわけではないので、演技としてはアニメの「お約束」から逸脱したものとなってしまい、あれ、なんかちょっと違う、という違和感が、「棒」と言われてしまうものなのだと思われます。
そして、アニメファンであればあるほど、「お約束」に接する濃度が濃いはずなので、違和感はより強いものとなっていくものでしょう。
しかし、ジブリだったり、新海監督だったり、細田監督だったり、俳優を声優に起用しがちな方々の作品を見てみると、背景が絵画というか実写というかという感じで描きこまれていたり、キャラがめっちゃぬるぬる動くとか、「絵」として見た場合も「記号」としてのマンガ・アニメから逸脱したものとなっています。
というわけで、物語に引き込まれていくうちに、俳優さんの声優としての演技にも違和感を感じなくなっていくような気がします。
俳優さんの声優起用には、従来のアニメとは違ったものを作り上げたいという、制作者の意図も込められているのかもしれません。
(まぁ、知名度を利用した集客目的という大人の事情もあるのかもしれませんが…)
器用な俳優さんや、プライベートでアニメが好きという俳優さんなどは、アニメの「お約束」に沿って演技できる方もいるのだと思いますが、そのような制作者の意図があるならば、演技としても現実感のあるものを求められるのかもしれませんね。
また、テレビアニメでも「記号」にとどまらないような作り込まれた作品も多く存在するので、もしかしたらアニメの声優さんもこれからは徐々に、演技の手法などの移り変わりがあったりもするのかもしれません。
3Dアニメにはどんな演技が合っているのか、などの問題提起も起こりそうです。
まぁ個人的にはザ・記号って感じのベタなアニメも、消えないで残っていってほしいなぁと思います。
ここまで書いて冷静に読み返してみると、なんだかごく普通のようなことを大袈裟に書いてしまったというか、どこかで読んだものも多く含まれているような気がしますが、ご容赦くださいませ。
最後まで読んでいただきありがとうございました!