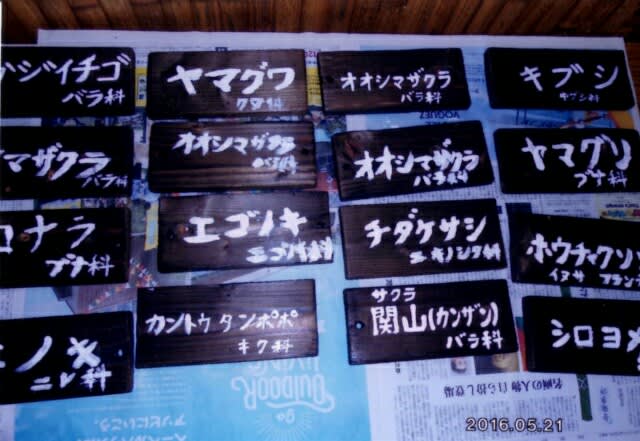そもそも自然環境とは何なのでしょう。
一言で言うとしたら、自然の生きものたちの集合体です。
もう少し詳しく言うと、色々な生きものたちのそれぞれの営みが繋がりあって成り立っている一まとまりの場所で、それはその土地の地理的な成り立ちと深く関わっているものです。
自然の生きものたち、言い換えると野生の生きものたちは、人間がエサや肥料を与えたりと世話をしなくても、他の生きものたちと繋がりを持って自力で生きています。
このことが自然環境においては非常に重要です。
私が自然が大切だというのは、これらの繋がりこそが自然の生産力、循環力、さらには復元力・再生力となっていて、人間もその恩恵を受けているからです。
具体的な自然環境としては前にも挙げたとおりです。
たとえば、小川には流水性の小魚や水生植物の生育・生息環境となっていますし、池は止水性の水生植物やトンボやカエルたち生育・生息環境に、雑木林は様々な樹木や草花の生育環境となっているとともに、カナブンやルリタテハなどの昆虫たちの生息環境となっています。また草っぱらはイネ科植物の生育場所となっているとともにそこがバッタやイトトンボの成虫の生息場所となります。
このように地面や水底が植物の生育する基盤となり、そうしてできた森林や草地には、それぞれ森林性の鳥類や昆虫類、草地性の鳥類や昆虫類が生息したり飛来したりします。
私たちの町に残されていた小川や池、雑木林や草っぱらこそが、断片的ではありますが、それぞれ自然環境なのです。
これらも元々は断片的ではなく繋がっていました。
里山と呼ばれる一まとまりの大きな、人と自然とが共存する場所だったのです。
人に生息環境という言葉を用いるのはおかしいかもしれませんが、この里山こそが私たち日本人元来の生息環境のようなものと言っても決して過言ではないと思います。
山にある森からは木材や燃料や山菜などを採取し、山の裾野や谷の小川沿いには池や田畑を作って食物を得ていました。
このように自給自足の生活をしていた里山こそが、日本人元来の生活圏・生活環境であったことに間違いありません。
一言で言うとしたら、自然の生きものたちの集合体です。
もう少し詳しく言うと、色々な生きものたちのそれぞれの営みが繋がりあって成り立っている一まとまりの場所で、それはその土地の地理的な成り立ちと深く関わっているものです。
自然の生きものたち、言い換えると野生の生きものたちは、人間がエサや肥料を与えたりと世話をしなくても、他の生きものたちと繋がりを持って自力で生きています。
このことが自然環境においては非常に重要です。
私が自然が大切だというのは、これらの繋がりこそが自然の生産力、循環力、さらには復元力・再生力となっていて、人間もその恩恵を受けているからです。
具体的な自然環境としては前にも挙げたとおりです。
たとえば、小川には流水性の小魚や水生植物の生育・生息環境となっていますし、池は止水性の水生植物やトンボやカエルたち生育・生息環境に、雑木林は様々な樹木や草花の生育環境となっているとともに、カナブンやルリタテハなどの昆虫たちの生息環境となっています。また草っぱらはイネ科植物の生育場所となっているとともにそこがバッタやイトトンボの成虫の生息場所となります。
このように地面や水底が植物の生育する基盤となり、そうしてできた森林や草地には、それぞれ森林性の鳥類や昆虫類、草地性の鳥類や昆虫類が生息したり飛来したりします。
私たちの町に残されていた小川や池、雑木林や草っぱらこそが、断片的ではありますが、それぞれ自然環境なのです。
これらも元々は断片的ではなく繋がっていました。
里山と呼ばれる一まとまりの大きな、人と自然とが共存する場所だったのです。
人に生息環境という言葉を用いるのはおかしいかもしれませんが、この里山こそが私たち日本人元来の生息環境のようなものと言っても決して過言ではないと思います。
山にある森からは木材や燃料や山菜などを採取し、山の裾野や谷の小川沿いには池や田畑を作って食物を得ていました。
このように自給自足の生活をしていた里山こそが、日本人元来の生活圏・生活環境であったことに間違いありません。