日本国憲法全文 - 法学館憲法研究所
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
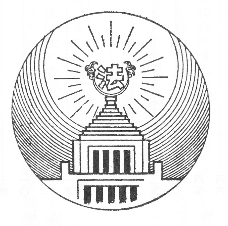
文部省 あたらしい憲法のはなし - 青空文庫 www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
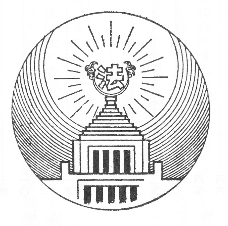
http://chuplus.jp/paper/article/detail.php?comment_id=361916&comment_sub_id=0&category_id=112より転載
中日新聞+ 2016/4/29 朝刊
今、憲法が問われている。夏の参院選では、改憲問題が大きな焦点となる。安倍晋三首相らは改憲を訴えるが、憲法は本当に変える必要があるのか。守らなければならないものではないのか。施行から六十九年となる憲法を今こそ読み、主な条文の意味や価値を考えてみたい。
戦争は国家権力が引き起こすもの。国民が主権を持って国家権力の暴走を抑えることで、戦争を二度と起こさせない-。
日本国憲法全体を貫くこの思想を、最初にはっきりと宣言したのが前文です。第一段落の「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうに」「主権が国民に存することを宣言」というくだりに、端的に表現されています。多大な犠牲を生んだ先の大戦への反省が込められています。憲法によって権力を抑える「立憲主義」を言い表した文章とも言えます。
第二段落の「日本国民は、恒久の平和を念願し」以下は、軍事的手段ではなく、諸国民を信頼することで自国の安全を保つという決意を示しています。戦争放棄や戦力不保持を定めた九条につながる考え方です。「全世界の国民」以下は、日本国民だけでなく人類全体に平和が保障されるべきだとうたっています。
ちなみに憲法は連合国軍総司令部(GHQ)が起草を進めたため、前文は英文を直訳したような表現が多いです。「そもそも国政は」以下は、十六代米大統領リンカーンの演説「人民の、人民による、人民のための政治」を引いたと言われます。
自民党は前文を「翻訳調で違和感がある」「ユートピア的発想による自衛権の放棄」と批判。二〇一二年四月に決定した党の憲法改正草案(改憲草案)では全面的に書き換えました。草案には国民主権という言葉はありますが、政府が戦争を起こさないように国民が抑えるという考え方は見当たりません。諸国民への信頼によって安全を保つとの決意も削られ、国民が国と郷土を自ら守ると定めています。
現行憲法より短い割に、「国家」という言葉や、歴史・文化を誇る表現が目立ちます。総裁の安倍首相は前文について、敗戦国の「わび証文」のような宣言があると自著で評したことがあります。
◇
「いま読む日本国憲法」は、憲法の主な条文を解説し随時掲載します。
********************************************

![]() http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/politics/politics/1-0264851.html
http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/politics/politics/1-0264851.html
04/29 07:00、04/29 09:30 更新
5月3日の憲法記念日を前に、北海道新聞社は憲法に関する道民世論調査を行った。今年で公布から70年を迎える憲法が戦後の日本で果たした役割を「大いに評価する」と「ある程度評価する」が計88%に上り、「あまり評価しない」「全く評価しない」の計11%を大きく上回った。憲法改正については「改正する必要はない」が58%を占め、「改正すべきだ」は39%にとどまった。
憲法を「評価する」とした人の理由は「平和主義に基づき、日本が戦後70年間、戦争に巻き込まれなかったから」が50%で最多。「基本的人権を尊重し、民主主義社会を築いたから」が31%で続いた。
一方、「評価しない」と回答した人の理由は「権利の主張が多く、国民の義務がおろそかになっているから」が46%、「憲法改正手続きの要件が厳しすぎて、時代に見合った改革ができなかったから」が45%だった。
憲法改正の「必要はない」と答えた人の理由は「世界に誇る平和憲法だから」が33%でトップ。「変えたい部分はあるが、いま変えれば9条改正につながるから」が26%で続いた。改憲派の理由は「時代の変化に合わせて改めた方がよいから」が74%を占めた。
安倍内閣支持層では53%、自民党支持層では56%が改憲を支持。公明党支持層は50%ずつで、賛否が割れた。昨年までの調査は回答の選択肢が「全面的に改正すべきだ」「一部を改正すべきだ」「改正する必要はない」の三つだったが、今回から「改正すべきだ」「改正する必要はない」の二つにした。昨年夏の前回調査は「全面改正」が10%、「一部改正」が44%、「改正する必要はない」が44%だった。
憲法9条が規定する「戦力の不保持」については「変更しなくてよい」が56%で、「変更して、自衛隊を持つことを明記すべきだ」の36%、「変更して、軍隊を持つことを明記すべきだ」の6%を上回った。・・・・・

http://dot.asahi.com/ent/publication/reviews/2013120400050.htmlより転載
半藤一利、保阪正康著 定価:1,575円(税込)
日本人全体がバカだったと思うんです。
希代の悪法・特定秘密保護法案が今国会で成立しようとしている。1年前の衆院選で安倍自民党を大勝させた結果がコレである。どんだけ歴史に学ばない国なんだろう。
半藤一利+保阪正康『そして、メディアは日本を戦争に導いた』はこのタイミングでこそ読んでおきたい本。昭和史の碩学2人が戦争に突入するまでのメディアの状況を語り合った、戦慄を誘う対談である。
明治の初期には反政府的だった新聞は、日露戦争を境に体制に擦り寄っていく。〈日露戦争で部数が伸びたことは、新聞各社の潜在的な記憶として残ったんですね〉(保阪)。昭和6年の満州事変で新聞が一朝にして戦争協力の論調に変わったのも〈商売に走ったんですよ〉(半藤)。
主たるテーマは、戦前の日本がいかなる過程を経てモノ言えぬ国に変わっていったかだ。昭和7年の5・15事件で「義挙」の名の下にテロを容認する雰囲気が醸成され、昭和8年には新聞紙法が、9年には出版法が強化されて検閲に拍車がかかる。国定教科書が改訂され〈ススメ ススメ ヘイタイ ススメ〉という文言が登場したのも昭和8年。教育と情報の国家統制が進み、特高警察の設置によって言論が封殺され、一方では暴力が横行する。ジャーナリズムはそれに〈全く乗っかっちゃった〉(半藤)。〈尖兵(せんぺい)になったという側面さえありますよね〉(保阪)。
ゾッとするのは昭和初期と現在との驚くべき類似である。教科書検定制度の見直し、内閣法制局やNHKへの人事介入、昭和15年の皇紀2600年祭にも似た主権回復の日の式典。幻に終わった東京五輪。
歴史を顧みれば、ことは特定秘密保護法案による情報統制に終わらないように思えてくる。〈対米戦争を始めてしまったとき、軍の指導者には知的な訓練のできている人はいなかった〉(保阪)。軍人や官僚だけでなく〈日本人全体がバカだったと思うんです。ジャーナリストもその中に入ります〉(半藤)という言葉を私たちは噛みしめるべきだろう。
※週刊朝日 2013年12月13日号
かばさわ洋平 オフィシャルブログ
http://ameblo.jp/takumiuna/entry-12154756219.htmlより転載
April 28, 2016
ベストセラー『昭和史』で知られる昭和史研究の重鎮で作家の半藤一利さんが、安保法制を強行した安倍政権の手法はナチスのまねだと厳しく批判しています。内政がうまくいかないときは外国に対する危機感や恐怖感をあおり、愛国心をあおり国民の意識を外にそらすという権力者が使う古典的な手法についても言及されています。自身の戦争経験も赤裸々に語られており、改めて失敗の歴史を学ばなければならなと強く思います。
秘密保護法が出来たあたりから、これは危ない時代に入りつつあると感じていました。ただ、戦前と違い、まだいくつかのメディアはがんばっています。戦後、言論の自由を大事にしてきたことで、日本は戦前と根本的に違う国家になりました。憲法の一番大事なところは、9条の平和主義と言論の自由、そして基本的人権の尊重だと思います。この三つはこれからも大事にしていかなければ。
一内閣の勝手な判断でこれまでの憲法解釈を変え、安保法制=戦争法を強行した安倍政権の手法は、あれはヒトラーのまねですよ。日本の政府のやり方はナチスのまねばかり。例えばナチスは国会議事堂放火事件の後、政府が立法権を行使できる授権法を成立させ、民主的なワイマール憲法を骨抜きにして独裁体制を固めました。麻生大臣の『ナチスの手口を学ぶ』という発言は冗談ではなく本音で、本当に政権内部で話し合っていたのだろうと思います。
私は3月10日の東京大空襲で火と煙に追われ、川に落ちて死ぬ思いをしました。何とか助かりましたが、たくさんの人が死んでいくのを見ました。お母さんと子どもの死体などがごろごろしていた。それを見ても、何の感情もわかなかったんです。後で思うと不思議でしょうがない。疎開先の新潟県長岡市でも、空襲による死体をたくさん見ました。でも何とも思わなかった。終戦を伝える8月15日の天皇の放送を聞いた時も、助かったとは思ったけど、たくさんの犠牲者のことは考えませんでした。
私は戦争で、実に非人間的な男になっていました。戦争は人間を殺すことでしかない。戦争は、人間をとことん非人間的にする愚劣なものです。そのことを、戦後しばらくたってから、やっと痛感しました。こうした体験は、ちゃんと残しておかなければ。それが昭和史に食いつくようになった始りです。空襲で逃げる時、川のなかで人を蹴飛ばしたり、はねのけたりしました。歴史の本を書きながら、自分自身の戦争体験は戦後何十年も書いたり、話したりしませんでした。こういうことは、好んで話したいようなことではないですよ。でもやがて、歴史を書いているものとして、自分はどういう体験をしたのかを、東京の下町の戦争を知る者として伝えなければ、と思うようになりました。
昭和前期の歴史のような、失敗の歴史のなかにこそ、教訓がたくさんあります。これをよく学んでほしいですね。内政がうまくいかない時は、外国に対する危機感や恐怖感をあおる。国民の意識を外にそらす。これは権力者がよくやる古典的な手であり、これがなかなか有効なんです。
今度の選挙で共産党さんが本当に共闘してくれるのなら、ありがとうございますと、お礼を申し上げたい。よくぞ踏み切ってくれたと思います。第2次大戦前のドイツでは、小党分立でバラバラでナチスの台頭を許していまいましたから。参院選で野党が共闘して、戦争に向かいかねないこの流れを止めてほしい。いまの日本にはまるで昭和13、14年ごろのような不気味さも感じます。同時に、戦前と違い現在は、戦後70年間で築いてきた民主主義の理念がまだ大きく根付いています。若い人たちの間にも、シールズのように自分の頭で考え自発的に行動を起こす動きが出ている。私はとても期待しています。
***********************************
<半藤一利さんの記事>