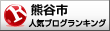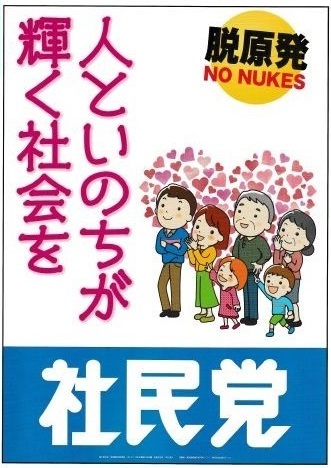きょうも歩く 「くろかわしげる(黒川滋)の活動日記&報告です。」のブログから転載しています。
現職の朝霞市議会議員です。(社民党に所属する議員ではありません。)
12/16 総選挙の結果を受けて
16日の総選挙の結果を受けて考えていることです。
1.わが選挙区の結果で言えば、自民党候補の独走でした。
男ばっかりの政治風土のなかで、
38歳女性、官僚候補としての博識、
あぐらをかかない努力などが評価されたのだと思います。
また、民主党候補の弱点としては、
上田党というアイデンティティの弱体化、
議員としての個性のなさ、
配られる印刷物が有権者とのコミュニケーションがなくて、
成果や地位を自慢するような内容がずっと続いていたことも大きいと思います。
また良い意味での民主党らしさのない雰囲気も、
離れていくときには急に離れる感じではないかと思います。
2.<略>
3.今回の衆議院議員選挙は脱原発を争点に設定すべきだったと思います。
しかし脱原発の運動の側が、
東京都知事選に盛り上がってしまい、
脱原発の権限がなく、
都庁に都民が求めていることでもないのに都知事選が争点化され、
一方で、脱原発への決定権がある国政選挙では政局ばかりがテーマになるミスマッチを起こす結果になったのではないかと思います。
とてももったいないことだったと思います。
脱原発運動の側に猛省が必要だと思います。
4.社民党はとうとう九州の局地的政党になってしまいました。
その最大の課題は人材の流失で、
その原因を作っているのは福島党首ではないかと思います。
自民党を利しても社民党の独自性を訴えるのか、
主要敵のために近い政党との関係を重視して引き出すものは引き出すのか、
路線を整理していく必要があると思います。
社民党の惨敗を受けて党首の交代や世代交代を図らないと存在意義そのものが問われていくことになると思います。
5.<略>
6.民主党は60議席弱になったことを悲観するばかりではなく、
党の組織や思想を少数精鋭で整理する機会ととらえるべきではないかと思います。
今までは烏合の衆で話がまとまらず、
大して勉強もしていない議員が声を大きくすると消費税の反対だとか、
インフレターゲットやれとか、
とんちんかんな政策ばかり言う状態を克服するよい機会ではないかと思います。
また新しい人材発掘の機会ではないかと思います。
新陳代謝している自民党に対して民主党もある程度人を新しくしていく必要があります。
7.<略>
8.厚生労働大臣経験者で、
政策をメチャクチャにした長妻昭が小選挙区でも当選し、
実務に徹した細川律夫、
子ども政策の体系化と充実を図った小宮山洋子が小選挙区でも比例区でも落選したというのは、
まさに日本人が政治を通じて社会保障政策を判断するということに、
いかに不得手かと感じるところです。
あるいは社会保障政策の整備は、
人物本位の選挙制度・選挙風土にそぐわないものかと語る結果ではないかと思います。
9.<略>
10.菅直人氏の苦戦を見るにつけ、
日本人は先入観で政治を議論することが得意なんだと思わざるを得ません。
原発災害への対応に大きな失策はなく、
むしろ当事者としての責任を失いかけた東電にたがをはめたという意味では首相として十分な仕事をしたはずなのに、
足を引っ張った自民党や小沢一派から、
菅首相だから災害が止められなかったかのようなデマ宣伝が行われたことが、
選挙に大きく響いていると思わざるを得ませんでした。
<略>
現職の朝霞市議会議員です。(社民党に所属する議員ではありません。)
12/16 総選挙の結果を受けて
16日の総選挙の結果を受けて考えていることです。
1.わが選挙区の結果で言えば、自民党候補の独走でした。
男ばっかりの政治風土のなかで、
38歳女性、官僚候補としての博識、
あぐらをかかない努力などが評価されたのだと思います。
また、民主党候補の弱点としては、
上田党というアイデンティティの弱体化、
議員としての個性のなさ、
配られる印刷物が有権者とのコミュニケーションがなくて、
成果や地位を自慢するような内容がずっと続いていたことも大きいと思います。
また良い意味での民主党らしさのない雰囲気も、
離れていくときには急に離れる感じではないかと思います。
2.<略>
3.今回の衆議院議員選挙は脱原発を争点に設定すべきだったと思います。
しかし脱原発の運動の側が、
東京都知事選に盛り上がってしまい、
脱原発の権限がなく、
都庁に都民が求めていることでもないのに都知事選が争点化され、
一方で、脱原発への決定権がある国政選挙では政局ばかりがテーマになるミスマッチを起こす結果になったのではないかと思います。
とてももったいないことだったと思います。
脱原発運動の側に猛省が必要だと思います。
4.社民党はとうとう九州の局地的政党になってしまいました。
その最大の課題は人材の流失で、
その原因を作っているのは福島党首ではないかと思います。
自民党を利しても社民党の独自性を訴えるのか、
主要敵のために近い政党との関係を重視して引き出すものは引き出すのか、
路線を整理していく必要があると思います。
社民党の惨敗を受けて党首の交代や世代交代を図らないと存在意義そのものが問われていくことになると思います。
5.<略>
6.民主党は60議席弱になったことを悲観するばかりではなく、
党の組織や思想を少数精鋭で整理する機会ととらえるべきではないかと思います。
今までは烏合の衆で話がまとまらず、
大して勉強もしていない議員が声を大きくすると消費税の反対だとか、
インフレターゲットやれとか、
とんちんかんな政策ばかり言う状態を克服するよい機会ではないかと思います。
また新しい人材発掘の機会ではないかと思います。
新陳代謝している自民党に対して民主党もある程度人を新しくしていく必要があります。
7.<略>
8.厚生労働大臣経験者で、
政策をメチャクチャにした長妻昭が小選挙区でも当選し、
実務に徹した細川律夫、
子ども政策の体系化と充実を図った小宮山洋子が小選挙区でも比例区でも落選したというのは、
まさに日本人が政治を通じて社会保障政策を判断するということに、
いかに不得手かと感じるところです。
あるいは社会保障政策の整備は、
人物本位の選挙制度・選挙風土にそぐわないものかと語る結果ではないかと思います。
9.<略>
10.菅直人氏の苦戦を見るにつけ、
日本人は先入観で政治を議論することが得意なんだと思わざるを得ません。
原発災害への対応に大きな失策はなく、
むしろ当事者としての責任を失いかけた東電にたがをはめたという意味では首相として十分な仕事をしたはずなのに、
足を引っ張った自民党や小沢一派から、
菅首相だから災害が止められなかったかのようなデマ宣伝が行われたことが、
選挙に大きく響いていると思わざるを得ませんでした。
<略>