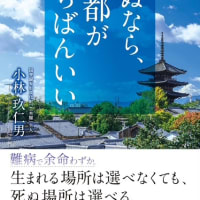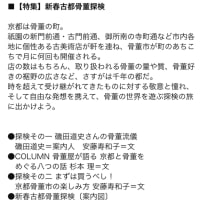|
Kindle以後10年 ─ BOOK1: Web時代の出版とKindleの十大発明 (E-Book2.0シリーズ) |
| 鎌田 博樹 | |
| メーカー情報なし |
◇
「 Kindle登場から10年が経過した。
この間に起きたことの多くは当時では予想できなかったことだ。
クラウド・ストア(日本開始は2012年)と読書デバイスのほかに、
出版サプライチェーンに沿って 次々と繰り出されるサービスは、
出版界が目にしていなかったものだった。
またKindleの延長にアマゾン出版やアマゾン書店、オーディオ出版、
スマートスピーカなどの
新旧ビジネスが登場することは予想困難だったが
周到なプランがあったことを窺がわせる。
創出された市場は最初からクロスメディアでグローバルで、しかも正確に拡大を続けている。
我々は今、改めてKindleが何であったか(あるか)を見つめ直すべきだろう。
それを理解する中から、出版のデジタル転換の方向とこれからの出版が見えてくる。
本書は以下の疑問に答えることを目ざしている。
・アマゾンのプラットフォームとビジネスモデルとは何か
・Kindleプラットフォームは他とどう違うか、なぜ成功したのか
・Kindle市場はまだ成長しているのか
・デジタル時代の「本」とは何か、出版のデジタル転換とは
・商業出版社を介さない「著者出版環境」KDPは、なぜ必要か
・伝統的出版社の戦略はなぜ機能しなかったのか
・アマゾンはなぜ「街の書店」を展開したのか
・アマゾンは紙の出版を必要としているのか
・エコーとアレクサ(Echo/Alexa)は出版をどう変えていくか
・アマゾンはなぜソーシャルな読書空間を必要とするのか
・アマゾン出版(社)は、従来の出版社とどこが違うのか
【本書の構成/目次】
まえがき アマゾンはどこから来たか、出版はどこへ行くのか
第1章 出版のデジタル的脱構築(デコンストラクション)
1.1 ビジネスモデルとしての出版環境のデザイン
1.2 「10大発明/模倣/買収」
第2章 ガジェットにあらず
2.1 天才が変えた「世界」と人間の運命
2.2 スティーブ・ジョブズの「誓戒」を破ったアップルの代償
2.3 ソフト、ハード、ネットワークの「惑星直列」
2.4 「Swatch」と「VALIS」
第3章 「メディアとしてのストア」と「読書空間」
3.1 読まれ・語られて決まる評価:本の2つの価値 紙の権威性に頼らない本の価値探求/コンテンツはいつ本として生まれるか?他
3.2 Goodreadsと読書空間の社会化 市場と読書の区別と連関/読書におけるソーシャル、他
第4章 顧客志向の書店:パーソナライゼーションとIT - Amazon.comとAmazon Books
4.1 “You are what you read.”
4.2 アマゾンのパーソナライゼーション
4.3 ITアーキテクチャとビジネスモデル
4.4 KindleがAmazon 2.0を再構築した
4.5 データがアシストする書店:AmazonBooks
第5章 著者の自立と出版ビジネス:KDPとアマゾン出版
5.1 伝統的出版ビジネスとアマゾン アマゾンの「出版観」/著者に「出版」が出来るか?他
5.2 デジタル時代の「出版社」モデル ブレイクスルーは「雑誌の崩壊」から生まれた、他
第6章 「共同性」を志向する出版市場モデル:Kindle Unlimited
6.1 社会の構造変化で問われる出版の社会性
6.2 定額制による「貸本」の復活:Kindle Unlimited (KU)
6.3 Kindleシステム恒常性を支えるKU
6.4 「ポスト非対称性」時代の出版モデル
第7章 メディアの誕生―音から声へ:AudibleとEcho
7.1 言語をめぐる人間とコンピュータ
7.2 見えないけれど「雄弁」だった音声の復活
7.3 オーディオ「ブック」の創造:Audible
7.4 出版メディアとしてのA-Bookとスマートスピーカ
あとがき 「Kindle以後10年」シリーズについて
☆詳細目次は「無料サンプルを送信」するとご覧いただけます。
【解説/解題】
本書はアマゾン「Kindle」ビジネスを、(1)ビジネスモデル、(2) Web/テクノロジー、(3)出版メディアという 3つの視点からアプローチし、10年を経た時点での分析を試みたものです。
Kindleは、リーダ・コンテンツ・クラウド(ストア)の3つが一体として機能する 世界初の出版プラットフォームとして2007年に(米国で)生まれました。
英語の「火をつける、灯りをともす」という言葉の由来通り、 E-Bookをデジタル出版のフォーマットとして定着させたほか、
著者&読者中心の新しいデジタル出版をサポートするサービスを次々立上げ、 定額制など自由な発行形態を実現、音声出版も普及させています。
これらは読者がコンテンツの体験を深め、発展する環境にフォーカスすることで可能となりました。
「顧客中心主義」というアマゾンのビジネスモデルの根幹に「本」が置かれていることは、 偶然ではありません。
本/出版は人類の文化的・社会的活動であり、未来へと継承するものですが、 これらと分かちがたく結びつくことをアマゾンの全ビジネスが必要としているためです。
「本からすべて(世界)へ」「読者の体験から顧客体験へ」という、一つの商品、一つのサービスから 巨大なビジネスを構築するアマゾンのアプローチは、ITを土台としたビジネスモデルが可能としたものです。
Kindleは「デジタルで出版に何が出来るか」という課題に対するアマゾンの解答であるとともに、
「顧客との関係を通じた事業の持続的発展」を実現するビジネスの大規模実験という 性格を持っていると考えられます。
Kindleで生まれた要素はロールモデルとしての性格を持っており、各自・各社がそのモデルを使って 新しい出版プロセスに参加できますし、
あるいは参考にして別のモデルを(あるいは大きなストーリーを) つくることも出来ると思います。
本書は第一にビジネス/マーケティング論ですが、ネット/デジタル論、アマゾン論、ITシステム論、 出版/社会論としても読めるでしょう。
ビジネスモデルや情報アーキテクチャ、ユーザー体験(UX)、プラットフォームなどの 現代的コンセプトの運用を知る上でも役立つと思われます。 」(内容)
◇
◇
京都移住について考える・「老後は京都で」~トップページに戻る
( インスタグラム版「老後は京都で」は → コチラ )