
伊勢管弦楽団 第26回定期演奏会
メンデルスゾーン/ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調
ブルックナー/交響曲第8番ハ短調(ハース版)
ピアノ:井上 ヒロミ
指揮:大谷 正人
2007年5月20日(日)14時00分開演
場所:伊勢市観光文化会館
伊勢管弦楽団を聴いてきました。
伊勢の地にブル8が鳴り響くということで、ちょっと期待して、ちょっと不安で、出かけました。
オケの音の第一印象はなかなかよかったです。
前半のメンデルスゾーンは、今まで聴いた記憶がない曲。
せわしなく動き回るピアノ・パートは、シューマンのような翳りは無く「お上品」な音楽に聴こえました。
さて、お目当てのブルックナーですが、編成もぐっと大きくなってパワー・アップ。
このオケの良さである「前向き・ひた向き」な姿勢がよく感じられ、多少の瑕疵はアマゆえに散見されますが、それを帳消しにする熱い演奏でした。
先のHP内「指揮者の部屋」にもあるように、指揮者の大谷さんは、どちらかというと「遅いテンポ」の演奏がお好みのようですが、ご自身が指揮される場合は、また違うのか、けっこう速い目(普通?)の速度でした。
また、同記事内にて「ブルックナーの演奏を聴く時に、個人的には一番大切にしたいのは、その響きがどれほど祈りをつくれているか、どれほどこの曲の構造を洞察できているかです」と述べておられますが、今日の演奏は「祈り」も、もちろん意識されていたと思いますが、それ以上に「躍動感」「攻撃的」というイメージが強く出ていたように感じました。
あの大人数の金管群が(もちろん咆哮する場面は多々あるにしても)オルガンのように溶け合って重く柔らかいハーモニーを形成し、私達を魅了する・・・そんな場面を期待していたのですが、特にトランペット諸氏がはりきり過ぎたのかどうか、かなり刺激的な音を響かせておりました。
で、スケルツォは(音的に)やや単調になっていたかと思います。
Tp.以外の金管群は健闘されており、ワーグナー・チューバ持ち替え隊を含むホルン陣など、なかなかでありました。
弦の、特にヴァイオリンの前のめりな姿勢も、「一人相撲の空回り」に陥らず、ベルリン・フィルみたいなオーバー・アクションも嫌味なく見れました。
Tさんはティンパニを女性の方に譲って(?)シンバルを受持っておられましたが、二発目はちょいとスカっちゃったかと・・・。
そのティンパニ女史も音量控えめながら、なかなか健闘でありました。
が、しかし・・・、
やっぱり、この曲では、かつてのMPO・ザードロの如く阿修羅ティンパニにて濃い味付けを願いたかったですが・・・大谷先生、人がいいのかなぁ?
こっちがハラハラドキドキするくらいの豪打が欲しかったです・・・我がままですけどね。
で、まとめですが・・・・
今日、何より強く感じたことは、ブルックナーの偉大さであり8番の素晴らしさでした。
それを本当に再認識しました。
その聖なる楽曲には「祈り」も「エンタティメント」も「禁欲」も「官能」も「攻撃」も「懺悔」も、どれがどれか分からない程に一体化して存在していました。
第4楽章の何度か訪れるクライマックスの設定は、なんと啓示的でありながら同時になんと痛快であることでしょう!
一人の人間に内包されている全ての煩悩を区別することなく一体化し、私達の日々の所業に無意味なことなど無いことを教えてくれる不思議な力が、何故かブルックナーにはあることを再認識しました。
今まででも、ブルックナーを聴いている時に薄ら薄ら感じていたことなのですが、今日は、今まで以上に鮮明に感じました。
聖俗、そんな表面的な区別がアホらしくなるほどの位置に彼の音楽は居るのですね。
プログラムにも引用されていました、チェリビダッケの言葉「ブルックナーの《第8番》はエゴから逃れられない人間にとって、それを脱するこの上ない教材である。ブルックナーの《第8番》は交響曲作法の頂点をなす。」という言葉も、なぁんとなく雰囲気的に納得してしまう。
何やら訳がわからなくなってきましたが、「音楽を通して永遠との対話を可能にしてくれる稀有な作品」との言葉を実感したコンサートでした。
今度は、ハイレベルのオケで味わってみたいです。
会場で、旧知の友人と久しぶりに顔を合わせ、終了後に暫し歓談。
まあ、みんなズタズタな人生ながらも笑顔で生きてるってことが判明。
ちょっと寒さの戻った中を電車にて帰りました。
写真は、松阪駅から歩いて自宅へ向かう道中。
この道のはるか先に我が家があります。












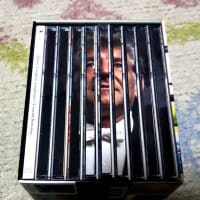

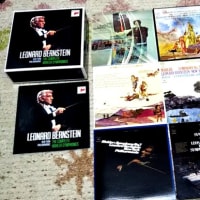
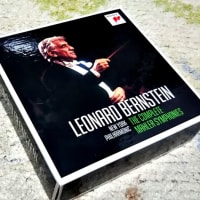

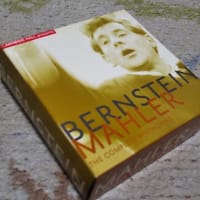

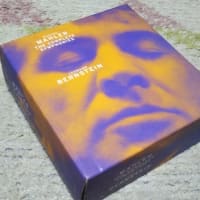


やっと落ち着いたし、明日の仕事の準備はしなくてよさそうなので、ひさしぶりにゆっくりしてます。
今年の定演も楽しかったです。団員も楽しそうでした。
どこまでも自己で満足するのが、うちのいいとこかなーと思ったりもします。
しかし、まあ、後で録音を聴くと、安定しない演奏とピッチにはがっくりきますが…自分の反省ですよっ
うまくいったかなと思っていた部分がよくなかったり、あんまりだなと思っていたところがよかったりと、聴く場所によっても違うのかもしれませんが、所詮、主観というものはあてにならないものです。
この熱さのまま、落ち着いて演奏できれば、演奏しながらいろんなことが判断できるし、何かが変わる気がするのですが。
これに懲りずに、また聴きにきてくださいね。
修業しておきます!!
そういえば指揮者は、『遅いテンポもいいんだけどねぇ、大変だから…奏者も聴衆も。』とおっしゃってました。
出張業務お疲れ様。
私も出張業務の勤務調整とかで、今日はちょっとだけ早く帰宅できました。
和具中(?)、お疲れ様でした。
トップについで拍手もらってましたね。
よかったですよ。
アマチュアの「熱さ」は必要条件みたいなものだと思いますが、「勝手に盛り上がってる」んじゃないところがいいかと思います。
ところで来年度はブラームスやラヴェルですね。
なかなか楽をさせてくれない指揮者氏ですね(笑)。
ラ・ヴァルス・・・・楽しみです。
貴団HPの、プログラム選定までの経過で、指揮者氏の次の表記に思わず笑っちゃいました。
(失礼!)
非常に難しい(難度1):プログラム2,6
相当難しい(難度2):プログラム4,5
かなり難しい(難度3):プログラム1,3
結局、みぃんな難しいのですね。
まあ、「簡単」なんて傲慢な表記は、偉大な作品を前にして畏れ多くてできないかも知れませんが・・・。