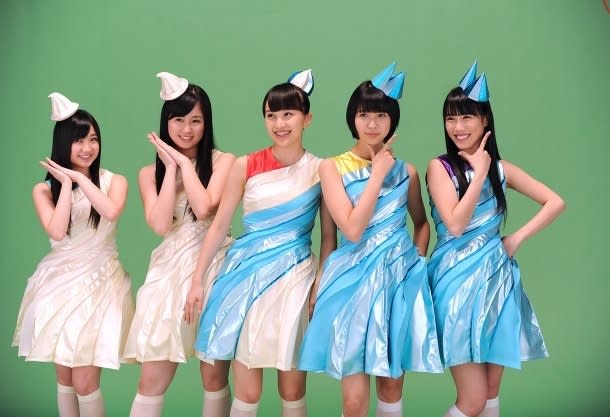
さて兄弟たちよ。
わたしたちの主イエス・キリストの名によって、
あなたがたに勧める。
みな語ることを一つにし、
お互の間に分争がないようにし、
同じ心、同じ思いになって、
堅く結び合っていてほしい。
「コリント人への第一の手紙」 1章10節
新約聖書 口語訳
神様は常にあなたのことを
愛しておられます。
ですから、あなたは
神様に愛された分だけ
多くの人に尽くしてあげなさい。
人の和は、与えることによって
大きく広がっていきます。

★カトリックの危機感 仏教に関心示す
ヨーロッパの若者
◆SankeiBiz 2014年2月9日(サンケイビズ)
前ローマ教皇ベネディクト16世がドイツの大学の講演で「我々カトリック教会において脅威なのは仏教だ」と語ったと聞いたことがある。バチカンのトップになる前の話だ。ほんとうに「脅威」と言う言葉を使ったのかは確認のしようがないが、政治的な反目に巻き込まれやすいイスラム教ではなく、仏教が話題の対象になったというのは目を引く。
自然を克服する相手としてみない、というだけでも仏教は十分にエコロジー時代の潮流にあっている。
ダボス会議に出席した臨済宗妙心寺退蔵院副住職の松山大耕さんが、先週ミラノのホテルでこう語った。
「最近、エルメスのようなヨーロッパのブランドメーカーの方が盛んに京都の私のところでワークショップを行います。ダボスではヨーロッパの若い人たちが仏教に強い関心をもっているのが印象的でした」
日本の仏教界はカトリック教会とさまざまな交流を試みてきたが、松山さんが知る限り、プロテスタント教会との交流はそこまで目立った印象がない。「海外出張はほとんどヨーロッパかアジアです。米国はありませんね」と松山さん。
そのヨーロッパにおいてカトリック教会の存在感が低下している。20数年前、ぼくがイタリアに住み始めた当時、普段は教会に行かなくてもクリスマスにはミサに出かける人が多かった。が、最近ではクリスマスさえ教会に足が向かない。
クリスマスは休暇であり家族と会う日なのだ。あるいは日本と同じく商業的イベントとしての色彩が強くなっている。そしてミサに出かけるとイタリア人の高齢者と南米出身の信者の姿が目につく。
ぼくの自宅近くには教会の内装を改造したクラブがあり、夜遅くまで若い人たちが踊っている。ダブリンで入った流行のパブも元教会だった。教会の不動産物件としての売り出しはローマにさえある現象であり、新しい教会が資金不足のために10数年以上「建設途中」になっている例もある。
神父も不足している。地方にいくと複数の教区を一人の神父で担当していることもある。かつて子沢山の時代、一人か二人は定職を確保させておく必要があった。両親にとって神父は親孝行をしてくれる自慢の息子だった。少子化の今、神父になられたら逆に家族としては困る。
それでもミラノの公立中学に通う息子の宗教の教科書をみると歴史の教科書と並んで分厚いし、友人たちは教会に教理を学びに通っている(宗教は選択科目で息子は宗教をとるのを嫌がったが、キリスト教は生きる知恵の集積なのでイタリアで生活するに得だ、とぼくたち夫婦は説得した)。教会のサッカー場では練習に夢中だ。したがって日本の寺よりはイタリアの日常生活の風景のなかに教会が入っている。
が、松山さんは「ある意味、日本の仏教以上にヨーロッパのカトリックは危機感が強いかもしれない」と呟く。
ヨーロッパのビジネスパーソンが京都の寺で禅をすることに関心をもち、若い人たちが仏教について興味をもつ。ヨーロッパで宗教心が薄れたのではなくカトリックへの信仰の問題なのか?
このあたりのテーマを語るにはぼく自身、もっと勉強が必要だが、一つ大切だと思うポイントがある。ヨーロッパにおいて仏教へ関心をもつ人たちが増えているという傾向をとらえ、日本のなかで「これからは日本でカタチづくられた仏教思想が世界をリードする」とやや前のめりの表現が闊歩しがちであることだ。
米国経済とハリウッド文化の世界への浸透力を関係づけて「文化発信力」というレベルで論じられることはアリだ。しかし、それぞれのローカルの精神文化をそのような目で見てはいけない。
かつて和魂漢才や和魂洋才という言葉を作ったことをよく思い出すといい。ヨーロッパのコアをなすキリスト教が他の宗教の考え方の影響を受けることがあるかもしれないが、あくまでもそれは「参考」なのだ。
もちろん結果的に「大いなる参考」と「たいしたことのない参考」の二通りの場合がありうる。松山さんも年内バチカンで講演するかもしれないという。日本の仏教が他の文化の「大いなる参考」になってくれることを願っている。
◾️ローカリゼーションマップとは?
異文化市場を短期間で理解するためのアプローチ。ビジネス企画を前進させるための異文化の分かり方だが、異文化の対象は海外市場に限らず国内市場も含まれる。
◾️安西洋之(あんざい ひろゆき)
上智大学文学部仏文科卒業。日本の自動車メーカーに勤務後、独立。ミラノ在住。ビジネスプランナーとしてデザインから文化論まで全方位で活動。現在、ローカリゼーションマップのビジネス化を図っている。著書に『ヨーロッパの目 日本の目 文化のリアリティを読み解く』 共著に『「マルちゃん」はなぜメキシコの国民食になったのか? 世界で売れる商品の異文化対応力』。ローカリゼーションマップのサイト(β版)とフェイスブックのページ ブログ「さまざまなデザイン」 Twitterは@anzaih
http://www.sankeibiz.jp/smp/macro/news/140209/mcb1402090600000-s.htm
(SankeiBiz 2014年2月9日)
【今日の御言葉】










