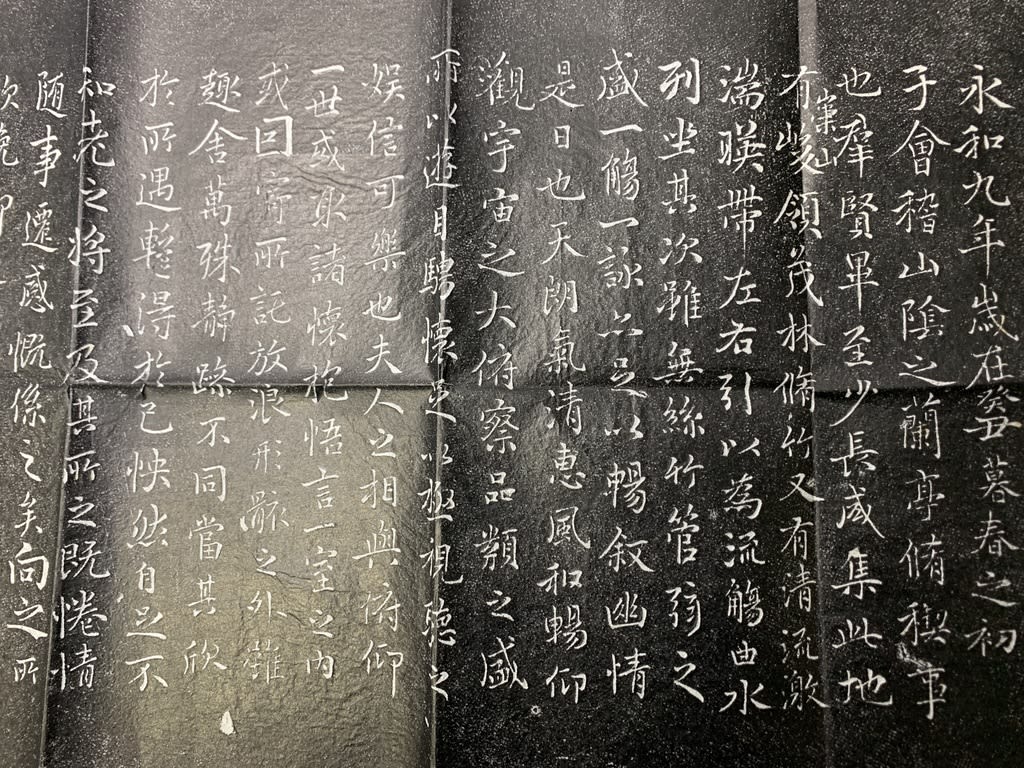一昨日、日中の気温が20度を超えておりましたが、昨日は15度、北風が吹いてきました。そしてこれから週末に向かってだんだん冷え込んでくるようであります。一昨日が10月、昨日は平年並みの11月、そして金土あたりから12月の天気、と1週間で3か月が一気に進むのです。
ある意味分かりやすい季節の変わり目で、今週から冬と考えて体制を整えなければなりません。ワタシの日記には、明後日から冬、と書くことにします。これから2月までの3か月は油断することなく過ごし、植物や動物が無事に春を迎えるための大事な時期でもあります。
まずは、コロナ。政府と自治体が責任のなすり合いを演じております。Go-toで、業界を救い、安く旅行がいける、安く食事ができる、と庶民の支持を集められると踏んでいた政府は、第三波が、限界に来るギリギリまで、「移動自体では感染しない」だとか、「Gotoでの感染者は170名位」などと寝ぼけたことを言っていました。
全国で感染者が過去最大レベルに達し、医療現場から医療崩壊の危機が迫ってきたら、ようやくまずいと思い始めたか、今度はマスクして食事をしろ、から「自治体の判断で」と相変わらず無責任なことを言っております。寝言は寝て言え、であります。マスクしたまま、飲み物食べ物を口に運ぶ時だけマスクをつまんで口を開けるなんて、バカみたい。マスクはぐちゃぐちゃに汚れるし、マスクにコロナウィルスがついていれば、よけい感染しやすくなるでしょう。
忘年会は少人数で、と官房長官が言っています。今年は忘年会無し!でいいんじゃないでしょうか。酒が飲みたきゃ家で一人で飲む、会話したけりゃリモートでやればいい。一生に一回くらいは辛抱して、来年落ち着いたら盛大にやればよかろう、と思いますな。
寒くなる師走ともなれば、ボーナスが支給され、歳末商戦、クリスマス、忘年会のシーズン、そして帰省ラッシュとお正月。室内に居る時間が長くなり、換気も弱くなります。もはや三密も外出自粛もマスクもなにもあったもんじゃありません。 コロナじゃコロナ ワッショイワッショイ
ワタシら年寄りは、ひたすら大人しく、しゃべらず出かけず息をひそめるしかありません。ここまで来たらとことん自粛しましょう。ウナギのかば焼きと牛丼の冷凍もまとめてとりよせてあります。息子たちが帰省しても、外出禁止と徹底した除菌、検温などの健康状態チェックと、考え得る限りの対策をとります。医療用の高価なマスクとゴーグルも準備してあります。まだ開封もしていませんが、肺炎かどうかを測定するパルスオキシメーターもネットで買いました。政府にも自治体にも任せておけません。自衛あるのみです。
次は、植物。すでに、2割程度の植物は室内に移動し越冬体制に入りました。残りの植物たちは、非耐寒性の植物の鉢をまとめてコンクリートの上に置き、殺虫剤を撒いて鉢内にダンゴムシやナメクジがいないようにしてあります。気温の推移に応じて徐々に室内と温室に振り分けます。
今週末には温室用の電気ヒーターも電源オンにいたします。屋外で冬越しする弱耐寒性の植物、カンナ、ダチュラなどには、株元にもみ殻・牛糞・たい肥・腐葉土などでマルチングします。一番の焦点は今年植えたアイスクリームバナナです。ようやく手に入れた希少な苗、耐寒性があるというふれこみですが、それでも1年目には厳しかろうと思います。マルチング、葉っぱを藁や不織布で巻いておこうと思います。あとは、簡易温室を上から被せて、しっかりビニールでふさぐのです。無加温でなんとかしのげると考えております。
非耐寒性の植物でも、室温(大体10℃以上)で、一定の日照があれば、落葉させず、あるいは地上部が枯れずに冬越しも可能です。しかし、温室に入れられるのはわずかであります。夜中に暖房をつけるのも馬鹿らしく、限られた南向きの室内にごちゃごちゃ土の入った鉢を置くわけにもいきません。結局は、普段空いている陽の射さない資材置き場に並べて格納し、半ば休眠状態にさせるしかありません。勿論暖房も何もなし。
ハイビスカスは1/3くらいまで剪定します。プルメリアなどは自分で葉を落としてしまいます。そうなれば、ほとんど水も切って手間もかかりません。今年初めて実をつけたロンガンだけは、少し陽に当てなければなりません。
あとはメダカでありますな。こいつらは気温が10℃を下回るようになると、徐々に食べなくなります。水に手を突っ込むとかじかむような気温になるころには、水替え・給餌は不要となります。冬眠に入るのです。ただし、ここ数年に限って言えば、メダカプールが凍結することが減り、2,3度薄氷が張る程度の暖冬です。冬でも暖かな日が続けば、餌を食べ泳ぎ回ります。
数日がかりで十数個のプールの水を全部交換いたします。寒くなれば、フンもしなくなり水質の悪化もほとんど心配がなくなります。綺麗に水替えしておけば、来春まで少しづつ水を足す程度で間に合います。
この夏以降に生まれたブランドメダカの稚魚たちは、外での冬越しは厳しいので、温室の片隅と室内に退避させようと思います。
冬用に保温・防風機能が高いズボンをワークマンで買ってきました。こうして冬を目前にして、備えは完璧!・・・・ともいきません(笑)
あれを忘れ、これが抜けてる、で毎年失敗を重ねております。
「後悔は忘れた頃にやって来られても、何のお構いも出来ません。」と昔読んだ雑誌に書かれておりました。後悔しないよう今一度冬支度のチェックをいたします。コロナに罹ってからでは、後悔しても手遅れであります。