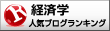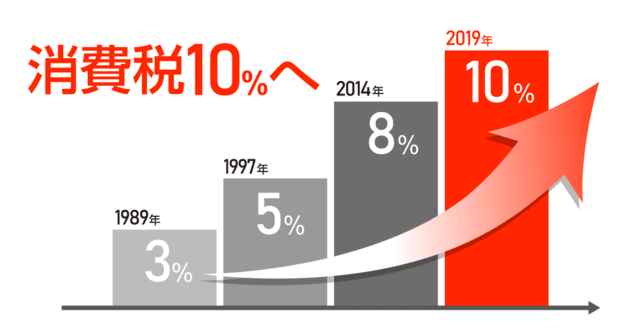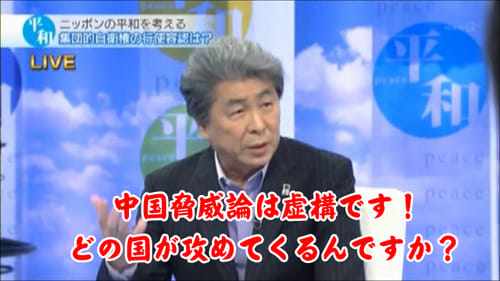当方の年来の天皇観がいかほどのものか、正直なところを述べておきましょう。
当方は左翼ではないので、天皇という存在は是が非でも廃止しなければならないものであると思ったことは一度もありません。というか、諸外国から訪日する国賓がそろいもそろって天皇陛下に謁見したがるところから察するに、天皇が存在することがどうやら日本にとって、特にソフト・パワーの面で、けっこう得のようだとはずいぶん昔から思っていました。
しかし、天皇は男系でなければならないという確固たる信念を持ち続けてきたわけでもありません。2004年から2005年にかけて小泉内閣で女系天皇を認める皇室典範の改正が議論になったとき、当方は「男系が危ういなら女系天皇容認でも仕方がないかもしれない」とさしたる確信もなく思っていました。少なくとも当時私の周りで男系維持の立場を堅持した人はほとんどいませんでした。これは、当人の名誉のために言っておきますが、故・宮里立士氏ひとりだけが遠慮深そうに「できうるかぎり男系でいかないとまずいんですけど」と言っていたのを、いま思い出しました。
さはさりながら、小室某をめぐる秋篠宮家バッシングに乗じて愛子さまを天皇にしようとする左翼的な策謀が見え隠れすることに対しては、少なからず危惧の念を抱いてはおりました。左翼勢力が、天皇なる存在を事実上骨抜きにしてその解体を図っているのは明らかだからです。しのこの言おうとなにをしようと結局のところ本音では「反日がしたい」「日本を壊したい」。そういう連中なのです、彼らは。
それはとにかくとして、要するにこれまでの当方は、お世辞にも、確固たる天皇観の持ち主であるとは言い難かったのです(いまでもそうですが)。
そんな当方に、知人のSさんが「これ、いまのわたしの一押しです」と言って紹介してくれたのが、いまから紹介する、竹田恒泰氏と谷田川惣(おさむ)氏の『入門 「女性天皇」と「女系天皇」はどう違うのか 今さら人に聞けない天皇・皇室の基礎知識』(PHP)です。
本書を読むことによって、当方、タイトルにあるとおり「天皇は、男系でなければならない」と強く思うに至りました。本書を読むことによって、当方がこれまでうっすらと感じていたことに鮮やかな光が当てられた、と申しましょうか。
以下、女性天皇論者や女系天皇論者の典型的な意見や疑問に答えるQ&A方式で、なにゆえ天皇が男系でなければならないのかを論じようと思います。
その前に、「女性天皇」と「女系天皇」の違いをはっきりしておきましょう。というのは、NHKが令和元年の九月に実施した「皇室に関する意識調査」によって、国民の94%が、女性天皇と女系天皇との違いがよく分かっていない実態が判明したからです。
歴史上女性天皇は、推古天皇をはじめとして十代八人存在しましたが、女性天皇はお父さんの血筋だけをたどっていけば初代・神武天皇につながります。一方、女系天皇はお父さんの血筋だけをたどっていくと、初代天皇につながりません。お父さんの血筋だけで初代天皇につながれば女性天皇。お父さんの血筋だけで初代天皇につながらなければ女系天皇。前者は歴史上存在しますが、後者は歴史上存在しません。たとえば、愛子さまが天皇になれば女性天皇であり男系天皇ですが、愛子さまが山田太郎さんと結婚なさって、そのお子さんが天皇になれば、その性別に関係なく、お父さんの血筋をさかのぼっても初代天皇にはつながらないので、女系天皇となります。
では、Q&Aを始めましょう。
Q1:歴史的に天皇の男系継承が連綿と続いてきたことは認めるが、それは近代の男女同権の原則に反するもはや時代遅れのルールにすぎないのではないか。
A1:これまで天皇になれる血統は決まっていて、その血統にない人はなれなかった。女系天皇容認論というのは、歴史的に天皇になれない人でもなれるようにしようということであり、皇室で男子の人数が減っているからといって、これまでの歴史において決して天皇になりえない人までなれるようにしようと主張している。伝統無視のけっこう乱暴な議論なのである。
Q2:歴代天皇の三分の二が嫡子(正妻との間に生まれた子)ではなくて庶子(正妻以外の女性との間に生まれた子)である。近代の一夫一婦制では男系継承を続けるのはきわめて困難なのではないか。
A2:歴代天皇の母に正妻以外が多かったのは、宮家よりも側室を優先しただけのことであって、側室がなければ男系継承が維持できなかったなどということはない。近代以前においては乳幼児死亡率が高いので、側室を置いてなるべくたくさん子どもを作ることと、いざというときに宮家から皇位を継ぐことのふたつの要素によって、これまで男系継承=皇統を保ってきた。一夫一婦制になったのは乳幼児死亡率が低下したことの表れとしてとらえることができるし、一定数の宮家を確保することによって、男系継承断絶のリスクをカバーできる。
Q3:男系継承論者が主張する旧宮家復活は、現在の皇室と血が離れすぎている。旧宮家とはいうものの、現皇室と離れすぎているのだ。その意味で旧宮家復活は、非現実的である。だから、直系を重視する方がいいのではないか。
A3:これまで血が離れていても宮家を維持できたのは、男系の血筋という大前提があったからである。直系重視で血統論理を放棄すると、血の離れた宮家と本家との関連性がなくなってしまい、宮家が機能しなくなる。さらに直系重視となれば、子を産むプレッシャーが一か所に集中してしまう。その悲劇を体現したのが現皇后である。
Q4:宮家から天皇が出るのは、何百年に一度あるかどうかである。そういうまれな事態を想定することは、非現実的ではないか。
A4:そもそも歴史的に世襲親王家をつくったのは、何百年に一度の危機に備えたものである。だから宮家は、今上天皇と血が離れることが前提の仕組みである。例えば、現在の天皇の直系の先祖の光格天皇も、江戸末期の後桃園天皇の御代に直系の皇位継承者が不在になって閑院宮から即位した。光格天皇と後桃園天皇とは七等身も離れていた。宮家とは、そういうもの。
Q5:Q1の繰り返しになるが、あえて言おう。女性が天皇になれないのは男女平等の理念に反する。それでは、愛子さまがかわいそうだ。
A5:男女平等理念は、平等原理に根差すものである。天皇の存在そのものがその平等原理に反する。だから、平等原理を持ち出せば、天皇の存在を否定することにつながる。「天皇の存在は平等に反しないが、皇族女子が天皇になれないことだけ平等に反する」というのは不徹底であり論理的な一貫性がない。天皇をなくせと言わないと論理が一貫しない。そもそも、男女平等に当てはまるには前提がある。個人の能力や努力によって成し遂げられる地位や立場についてなら、男女は平等でなければならない。しかし、当人の才能や努力によってなれない地位や立場については、男女平等の例外になる。また、「愛子さまがかわいそう」という意見には無責任なものを感じる。天皇という地位は、多忙で、責任が限りなく重く、完璧が要求され、耐え難いからといって逃げ出すこともできない。いわば苦役である。好きな男性と一緒になって皇籍を離れ自由に暮らすことのほうが愛子さまにとって幸せなのは明らかではないか。国民の世論の7割、8割が女性天皇・女系天皇を支持しているが、それは、愛子さまに、女性として幸せになる自由を捨てさせ天皇という苦役のような地位を強制することを意味するのである、という感度があまりにも鈍いのではないか。
Q6:伊勢神宮でお祀りしている皇祖神が女性の天照大御神(あまてらすおおみかみ)なのだから、皇統とはそもそも女系で始まっている。だから女系でも問題がないのではないか。
A6:あくまで初代の天皇は神武天皇だから、神武天皇より前には、皇位は存在しない。皇位継承はあくまで神武天皇を起点に考えるべきである。天照大御神とどうつながっているかではなくて、神武天皇とどうつながっているかが重要なのだ。神様に人間レベルの血統はない。神話に皇位継承の話を持ち込むべきではない。
Q7:長らく民間で過ごしていた旧皇族が皇室に戻るのは、国民が納得しないのではないか。「一般人とどこが違うんだ」と。
A7:普通に考えれば、次に皇位継承の危機が訪れるのは、どんなに早くても悠仁親王殿下の次の世代である。もし将来、天皇の世継ぎが生まれなかったとしても、皇室に復帰した旧宮家の子どもが皇嗣として早くから注目されていけば、国民にも馴染み感が生じてくるはず。旧皇族からいきなり天皇が出て、国民が驚くようなことにならないためにも、旧皇族から早く皇室に戻っていただき、生まれながらに皇族となる男子を育てなければならない。その意味で、旧皇族からの復帰が、もし赤ちゃんで行われたら最良のケースである。これらのどこに国民が不満を持つのか、よくわからない。
これくらいにしておきましょう。いくらQ&Aを重ねても、納得しない人は納得しないでしょうから。
思うに、天皇の男系継承の破棄は、自然環境の破壊に似ているところがあります。私たちに有形無形の喜びと慰藉と恵みとをもたらしてくれる自然環境を破壊するのは一瞬のことです。ところが、失ったものは二度と元には戻りません。そうして、失った後はじめて、失ったものの巨さやありがたみが身に染みて分かる。当方は、数十年ぶりに帰った生まれ故郷の対馬が、無益な護岸工事を徹底的に施されて、なつかしい海が無残に死んでしまったのを目の当たりにしてとても残念でもあり哀しくもあった自分の経験を念頭に置きながら、そう書いております。
当方は、天皇をそういう存在にしたくありません。最後は感性・感度の問題だと思います。