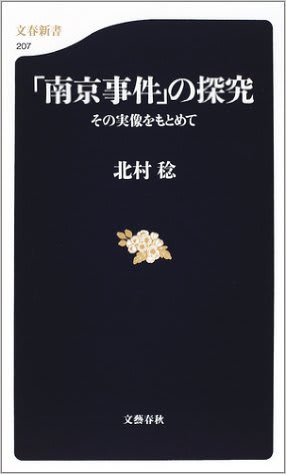中共は、歴史問題についてなぜ堂々とウソをつくのか(その4)南京事件3 (美津島明)

前回は、北村稔氏『「南京事件」の探求』のポイント10項目のうち五つまでを終えました。今回は、残りの五項目を扱います。話を分かりやすくするために、残りの五項目をもう一度掲げておきます。
(6)当時の欧米人や中国は盛んに日本兵による南京占領後の放火を非難・告発した。だが、放火は占領政策の妨げになるだけなので、その動機が希薄であるといえる。だから、そういう非難や告発は再検討を要する。
(7)「大虐殺」が敢行されているはずの占領下の南京市が意外に平穏であったことを示す有力な資料がある。凄惨な状況とのつじつまがあわない。
(8)事件当時において犠牲者の人数を検討した『スマイス報告』を徹底検証すると、市内の民間人殺害者数・約2400人という推計はおおむね妥当であるが、市外近郊六県における民間人殺害者数・約30000人という推計には合理的根拠が見出しがたい。
(9)当事件関連の遺体埋葬数について。紅卍会は処理数四万体あまりを、崇善堂は十一万体を報告した。紅卍会の報告数は信用できるが、崇善堂の報告数は過大である疑いが濃厚である。
(10)「南京大虐殺30万人」説のルーツを探し求めると、ティンパーリーの脚色という線が浮かんでくる。
では、まず(6)について。郭岐の『陥都血涙録』は、「大虐殺」の決定的証拠として一九四六年の南京の戦犯裁判の判決文に特筆された資料です。彼は国民党軍の士官で、南京陥落後三ヶ月間市内に留まり、いわゆる「大虐殺」の全期間を経験した人物です。『陥都血涙録』第六節「空前の大火災」について、北村氏は次のように述べています。
第六節の構成は以下のとおりである。
第(一)項:空気も変色した。第(二)項:中華門から内橋まで焼き尽くされた。第(三)項:交通部の消失。第(四)項:下関が燃え尽きた。
郭岐は火災を全て日本兵のしわざだと記述するが、同時代の中国語資料に基づけば、第(三)項:「交通部の消失」と第(四)項:「下関の全焼」は、中国軍が南京撤退に際して火をはなった結果であることが明瞭である。
焦土作戦は、堅壁清野(けんぺきせいや)と言って、中国における伝統的な戦法です。「城壁に囲まれた市街地内に人員を集中させ(堅壁)、城外は徹底して焦土化する(清野)」という意味です。そうすることで、進攻してきた敵軍が何も接収できないようにして疲弊させ、持久戦を有利に運ぶ狙いで行われます。
Wikipediaの「堅壁清野」の項には、次のような、重要な指摘があります。
日中戦争時には、国民党軍は日本軍・中国共産党軍の双方に対しこの作戦を取った。焦土化の対象は、軍事施設や食糧倉庫のみならず田畑や民家にまで及んだ。南京攻略戦の際、国民党軍により南京城外の周囲15マイル(およそ24km)が焦土化された。
交戦中の放火や、占領後における南京市街での放火のすべてを日本軍の仕業にされてしまったのでは日本軍としてもたまったものではありませんね。北村氏が指摘しているように、特に占領後の南京市街での放火は、日本軍にとって占領統治の妨げにこそなっても、益することはなにもありません。日本側は三八年の一月初めに南京市自治委員会を組織し、安全区に居住する市民の原住所への復帰を促しています。一方で帰宅を命じ他方ではその住居に火を付けるという矛盾した振る舞いをするほどに日本軍がおろかであったとはどうも考えにくい気がします。
ちなみに「安全区」とは、南京攻略戦に際し、戦災で家を失い南京に流入してきた難民や、南京から避難できない貧しい市民などを救済するために市の一部に設定されたものです。それを設定した組織を南京安全区国際委員会といい、アメリカ人宣教師を中心とする十五名ほどによって構成されています。その委員長が、かの有名なラーベです。
次に、(7)について。郭岐の『陥都血涙録』には郭岐自身の日常生活の描写があり、それを通じて、同時進行中であるはずの大虐殺状況とはうらはらの、意外に平穏な南京市内の日常が浮かび上がります。

郭岐は当初、安全区の南端に位置した五台山のイタリア領事館に他の人々と住んでいた。そして互いに金を出し合い、生活物資の買い入れのために外出していた。外出すれば拉夫(軍用の人夫として連れさられること)を含む危険が存在したことが記述されるが、午前中は館内に存在した書籍に読み耽り、時には諸子百家の書物を購入したことも記されている。この書籍購入の部分は生活物資の買い入れの記述とは別に記述されており、書物だけを買うために外出していたことが想像される。そして次のように続く、「正午になると雎(日本語の音読みでは「ショ」――引用者注)さん(同僚の軍人)の家へ行き昼食を食べ、同時に日本の情報を探るか、あるいは碁を打つかした。いずれにしても平々凡々と過ごした(略)」と。
ここには、銃声が終日絶えることのない日々が三ヶ月続いた大虐殺の影がまったくといっていいほどに認められません。じつにのんびりとした生活ぶりです(よね?)。
郭岐には、五百人ほどの部下がいました。彼らは南京市内に潜伏していましたが、生活資金を求めて頻繁に郭岐を訪ねてきています。部下の兵士たちの来訪に関する記述を、北村氏は、「彼らが飢えと寒さに迫られて命の危険があるのをまのあたりにしても、自分には少しの金のすべも無く」と訳したうえで、次のように述べています。
言うまでもなく「生命危険」は、生活資金の欠乏による「飢えと寒さで死亡する危険」であり、日本兵により「虐殺される」危険ではない。以上のとおり、『陥都血涙録』の文章には、兵士達の来訪が大虐殺進行中の出来事であり命懸けで訪ねてきているという認識は全く示されていない。
北村氏は、これを裏付ける歴史的事実を提示しています。それは、日本軍が一九三八年一月初旬に発行した安居之証です。これを所持するものは、生存の保証をされました。安居之証の表面には所持する人間の性別・年齢・体格・容貌の特徴が記され、日本軍に対し害意を持たないことを証すると記されていたそうです。郭岐もイタリア大使館に同居中の住人もそれを所得しており、「郭岐を訪ねた元兵士らも同様であったと思われる」と北村氏は述べています。この証明書を持っていれば、要するに、町を歩けたということのようなのです。
では、この証明書は、どれくらい発行されたのでしょうか。インターネットで調べてみたところ、「特務機関資料では12月22日より1月5日までに、概数として15万人登録」されている、とありました。また、同じ資料によれば、「二月の末で登録数が25万」だそうです(これらは、城外区域も含む数字のようです。)http://nankin.digi2.jp/nankinrein.hp.infoseek.co.jp.page007.html
私のいまの力量では、ここまでしかお話しできませんが、これは、「大虐殺」時の南京市の様子をうかがううえで、極めて重要な指摘であると思われます。
このことに関連して、強く印象に残った箇所をひとつ引いておきます。カタカナ表記の部分は、国民政府側が一九四六年二月に完成させた「敵人罪行調査報告」です(この報告について、本当はいろいろと補足すべきことがらがあるのですが、それは略します)。文中に登場する人々は、一九三八年に実施された調査の対象となった南京市民です。
「敵人罪行調査報告」の述べる調査時の状況には、理解に苦しむ文面が存在する。調査された人々の反応である。南京地方法院検察処の調査に対する市民の反応は、「敵側ノ欺瞞妨害工作激烈ニシテ民心消沈シ、進ンデ自発的二殺人ノ罪行ヲ申告スル者甚ダ少ナキノミナラズ、委員ヲ派遣シテ訪問セシムル際二於イテモ、冬ノ蠅ノ如ク口ヲ噤ミテ語ラザル者、或イハ事実ヲ否認スルモノ、或イハ又自己ノ体面ヲ憚リテ告知セザル者、他所二転居シテ不在ノ者、生死不明ニシテ探索ノ方法ナキ者等アリ」という状況であった。それ故に、事実の調査は「何レモ異常ナル困難ヲ経テ調査セルモノ」であったというのである。
人々の反応の不可解さは、かつての日本軍による大量虐殺の記憶が南京市民の間であまり鮮明ではなかったと考えると雲散霧消する、という意味のことを北村氏は指摘します。これは、かなりの説得力があります。
次は、(8)について。北村氏は、ティンパーリーの『WHAT WAR MEANS』とともに南京事件に関する初期の(というより南京事件の語り方を規定した、あるいは決定づけた)基礎文献として名高い『スマイス報告』を取り上げて、南京市内と近郊における民間人の被殺害数の徹底検証をしています。
著者のルイス・スマイスは、南京にあった著名なミッション系の金陵大学の社会学教授です。南京安全区国際委員会書記として委員長のドイツ人ラーベらと難民保護に当たりました。
彼は多数の中国人の助手を使って、南京攻防戦直後の一九三八年三月から六月にかけて南京市と郊外六県を調査の対象にして、戦争被害をサンプリング方式によって調査しました。その結果報告が、上記の『スマイス報告』です。
民間人の被殺害数は、おおむね次のように調査しました。
まず、家屋番号に従い五十戸から一戸を選び、居住する家族の人数・人的被害・収入・職業などが調査されました。次にその結果を五十倍した結果、南京市内における兵士の暴力による死亡二四〇〇人、南京市の人口約二十二万人という基本的数字が割り出されました。このほか別の方法で行われた南京近郊六県を対象とする調査では、民間人の被殺害数三万人という結果が出ました。
「虐殺派」は、この「南京市内における殺害二四〇〇人」という数字に対して「過少である」と難色を示しているようです。
しかし北村氏によれば、南京周辺地域の水害被害調査にも携わったことのある調査のプロであるスマイス氏の、南京市内の被殺害者数を割り出す方法はごく妥当なものです。また、彼の背景を考えれば、彼には「被害状況を過大に評価する動機は存在するが、過小に評価する動機は存在しない」という指摘は説得力があります。それゆえ、「南京市内における殺害二四〇〇人」はおおむね妥当である、と氏は評価します。
では、「南京近郊六県における民間人の被殺害数三万人」はどうでしょうか。氏は、この数字はきわめて疑わしいと言います。その理由は次のとおりです。
・調査対象となった南京近郊六県の総面積は、南京市内の面積のおよそ二〇〇倍である。またその調査地域は、日本軍の侵攻経路と必ずしも緊密に重なっているようには思えない。
・南京市内に関しては、五〇家族のなかから一家族を抽出して調査が行われ、その結果を五〇倍して全体状況が割り出された。これは誰にでも理解できる、合理的な集計方法である。それに対して郊外の調査では、三つに一つの村を選びその村の十家族から一家族を選んで調査したうえで、その結果に五つの県の総家族数一八万六千が掛けられているのである。ここは、合理的に考えるならば三〇が掛けられるべきところである。
以上より北村氏は、ここには近郊六県の被殺害数を誇大に計上する意図があり、「巧みなトリックが施されている」と断じます。
このあたりの論の運びには、高い説得力があります。
同じような説得力は、次の(9)についても感じます。すなわち、南京事件関連の埋葬者数について、紅卍会は処理数四万体あまりを、崇善堂は十一万体を報告したことについて、北村氏が、〈紅卍会の報告数は信用できるが、崇善堂の報告数は過大である疑いが濃厚である〉と結論づける論の運び方がごく妥当なものに感じられるのです。
(8)で、かなり詳細なところにまで触れた(これでもかなり端折っています)ので、(9)で同じようなことをして、読み手のみなさまをさらに煩わせることは避けましょう。できうるならば、ご自身の目でお確かめいただければ幸いです。
ちょっと脱線します。北村氏のまともな考察に接していて思うのですが、犠牲者数が多ければ多いほど喜色満面の笑顔を浮かべていそうな「虐殺派」(のなかの過激分子?)は、どうもマトモな精神構造の持ち主たちではなさそうな気がします。不健全といいましょうか、なんといいましょうか。
閑話休題。やっと(10)にたどりつきました。「南京大虐殺30万人」説のルーツの話です。この論点については、北村稔氏の議論を踏まえて、それをより確実な資料を基に論じ直した秦郁彦氏『南京事件』(中公新書・2007年増補版初版)の議論を紹介するほうが妥当かと思われます。
南京の国際安全区委員会が犠牲者数を四万人と伝えていたのに対して、ティンパーリーは『WHAT WAR MEANS』英語版の冒頭で「華中の戦闘だけで中国軍の死傷者(casualties)は少なくとも三十万人を数え、ほぼ同数の民間人(civilians)の死傷者が出た」と書いています。
このうち軍人の死傷者については、南京陥落直後の一九三七年十二月十七日に蒋介石が漢口で発表した「我軍退出南京告国民書」で、〈抗日戦争開始以来の全軍の死傷者が三十万人に達した〉と述べているのを、ティンパーリーが、上海‐南京戦での死傷者数としてアレンジした(これ自体ひどい誇張ですね)のではないかと北村氏は推測しています。しかし「ほぼ同数の民間人」という記述には典拠が見当たらず、北村氏は、ティンパーリーの脚色ではないかと推測します。つまり、この段階では推測の域を出ていなかったのですね。
ところが秦氏は、外務省が広田弘毅大臣名で三八年一月十九日に欧米各地に打った暗号電二〇六号の存在を探り当てました。ちなみに、ティンパーリーの『WHAT WAR MEANS』が、その中国版『外人目賭中之日軍暴行』とともに出版されたのは、その約四ケ月後です。
それは十六日にティンパーリーが本社(英マンチェスター・ガーディアン紙――引用者注)あてに打とうとした電報を上海の日本検閲官が差し押さえ、英総領事館と係争になっている件を伝えていた(事を大きくするために、ティンパーリーは差し押さえられることを十分承知の上であえて電報を打ったようです――引用者注)。添付された十六日付のティンパーリー電には「私が数日前に上海へ帰っていらい、南京などの日本軍によるフン族の蛮行を思わせる残虐行為の詳細について、信頼できる目撃者の口頭および手紙によって調査を進め」たが、「三十万を下らない中国人シビリアンが虐殺された(Not less than three hundred thousand Chinese civilians slaughtered)」とあった。
つまり、「民間人三十万人虐殺」は、やはりティンパーリーが発信源である可能性が高い、ということです。秦氏は、「あるいは漢口の中央宣伝部との謀議に基づく意図的なプロパガンダなのかもしれない」とも言っています。いずれにしても、どうやらこのあたりが、「南京三十万」の発信源のようですね。
長々と北村氏の所説の祖述のようなことをしました。なんのためにそうしたのか。それは、南京事件に関して日本政府が国際社会にどう発信すべきかということについて、私が前々回に提示した内容の当否をあらためて吟味するためです。前々回、私はこう申し上げました。
日本政府は、人数のことばかりぐちゃぐちゃ言ってないで、「南京事件」を「南京大虐殺」と呼ぶことには根拠がない、とはっきり主張すべきです。そうして、同事件には、国家が計画的に関与する、ナチスのホロコーストのような「大虐殺」などなくて、戦闘員のやむをえざる処刑と、心得違いの日本兵による個別的偶発的な略奪・強姦・殺人だけがあった、と主張しなければなりません。それくらいに端的なことを言わなければ、部外者の耳には入りません。つまり、国際世論を動かす力を持つことにはなりません。そう私は考えます。政府には、腹を据えて臨んでいただきたい。
二点、訂正すべき文言があります。
三行目の「計画的」は「計画的組織的」と、同じ行の「やむをえざる」は「不幸としか言いようのない」と訂正すべきではないでしょうか。以上です。
付記:北村氏の『「南京事件」の探求』についての、南京事件の研究のグローバルスタンダードをふまえたうえでの優れた論考が見つかったので、そのURLを掲げておきます。正確に言えば、論評の対象は本書それ自体ではなくて、その英訳です(加筆あり)。論者のアスキュー・ディヴィッドは、北村氏と立命館大学の同僚で、南京をめぐる共同研究プロジェクトに共に従事している方です。なれ合いに陥らず、言うべきことはきちんと言っている良心的な書評です。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/lt/rb/609/609PDF/david.pdf
(次回は、同シリーズ完結編の予定です)

前回は、北村稔氏『「南京事件」の探求』のポイント10項目のうち五つまでを終えました。今回は、残りの五項目を扱います。話を分かりやすくするために、残りの五項目をもう一度掲げておきます。
(6)当時の欧米人や中国は盛んに日本兵による南京占領後の放火を非難・告発した。だが、放火は占領政策の妨げになるだけなので、その動機が希薄であるといえる。だから、そういう非難や告発は再検討を要する。
(7)「大虐殺」が敢行されているはずの占領下の南京市が意外に平穏であったことを示す有力な資料がある。凄惨な状況とのつじつまがあわない。
(8)事件当時において犠牲者の人数を検討した『スマイス報告』を徹底検証すると、市内の民間人殺害者数・約2400人という推計はおおむね妥当であるが、市外近郊六県における民間人殺害者数・約30000人という推計には合理的根拠が見出しがたい。
(9)当事件関連の遺体埋葬数について。紅卍会は処理数四万体あまりを、崇善堂は十一万体を報告した。紅卍会の報告数は信用できるが、崇善堂の報告数は過大である疑いが濃厚である。
(10)「南京大虐殺30万人」説のルーツを探し求めると、ティンパーリーの脚色という線が浮かんでくる。
では、まず(6)について。郭岐の『陥都血涙録』は、「大虐殺」の決定的証拠として一九四六年の南京の戦犯裁判の判決文に特筆された資料です。彼は国民党軍の士官で、南京陥落後三ヶ月間市内に留まり、いわゆる「大虐殺」の全期間を経験した人物です。『陥都血涙録』第六節「空前の大火災」について、北村氏は次のように述べています。
第六節の構成は以下のとおりである。
第(一)項:空気も変色した。第(二)項:中華門から内橋まで焼き尽くされた。第(三)項:交通部の消失。第(四)項:下関が燃え尽きた。
郭岐は火災を全て日本兵のしわざだと記述するが、同時代の中国語資料に基づけば、第(三)項:「交通部の消失」と第(四)項:「下関の全焼」は、中国軍が南京撤退に際して火をはなった結果であることが明瞭である。
焦土作戦は、堅壁清野(けんぺきせいや)と言って、中国における伝統的な戦法です。「城壁に囲まれた市街地内に人員を集中させ(堅壁)、城外は徹底して焦土化する(清野)」という意味です。そうすることで、進攻してきた敵軍が何も接収できないようにして疲弊させ、持久戦を有利に運ぶ狙いで行われます。
Wikipediaの「堅壁清野」の項には、次のような、重要な指摘があります。
日中戦争時には、国民党軍は日本軍・中国共産党軍の双方に対しこの作戦を取った。焦土化の対象は、軍事施設や食糧倉庫のみならず田畑や民家にまで及んだ。南京攻略戦の際、国民党軍により南京城外の周囲15マイル(およそ24km)が焦土化された。
交戦中の放火や、占領後における南京市街での放火のすべてを日本軍の仕業にされてしまったのでは日本軍としてもたまったものではありませんね。北村氏が指摘しているように、特に占領後の南京市街での放火は、日本軍にとって占領統治の妨げにこそなっても、益することはなにもありません。日本側は三八年の一月初めに南京市自治委員会を組織し、安全区に居住する市民の原住所への復帰を促しています。一方で帰宅を命じ他方ではその住居に火を付けるという矛盾した振る舞いをするほどに日本軍がおろかであったとはどうも考えにくい気がします。
ちなみに「安全区」とは、南京攻略戦に際し、戦災で家を失い南京に流入してきた難民や、南京から避難できない貧しい市民などを救済するために市の一部に設定されたものです。それを設定した組織を南京安全区国際委員会といい、アメリカ人宣教師を中心とする十五名ほどによって構成されています。その委員長が、かの有名なラーベです。
次に、(7)について。郭岐の『陥都血涙録』には郭岐自身の日常生活の描写があり、それを通じて、同時進行中であるはずの大虐殺状況とはうらはらの、意外に平穏な南京市内の日常が浮かび上がります。

郭岐は当初、安全区の南端に位置した五台山のイタリア領事館に他の人々と住んでいた。そして互いに金を出し合い、生活物資の買い入れのために外出していた。外出すれば拉夫(軍用の人夫として連れさられること)を含む危険が存在したことが記述されるが、午前中は館内に存在した書籍に読み耽り、時には諸子百家の書物を購入したことも記されている。この書籍購入の部分は生活物資の買い入れの記述とは別に記述されており、書物だけを買うために外出していたことが想像される。そして次のように続く、「正午になると雎(日本語の音読みでは「ショ」――引用者注)さん(同僚の軍人)の家へ行き昼食を食べ、同時に日本の情報を探るか、あるいは碁を打つかした。いずれにしても平々凡々と過ごした(略)」と。
ここには、銃声が終日絶えることのない日々が三ヶ月続いた大虐殺の影がまったくといっていいほどに認められません。じつにのんびりとした生活ぶりです(よね?)。
郭岐には、五百人ほどの部下がいました。彼らは南京市内に潜伏していましたが、生活資金を求めて頻繁に郭岐を訪ねてきています。部下の兵士たちの来訪に関する記述を、北村氏は、「彼らが飢えと寒さに迫られて命の危険があるのをまのあたりにしても、自分には少しの金のすべも無く」と訳したうえで、次のように述べています。
言うまでもなく「生命危険」は、生活資金の欠乏による「飢えと寒さで死亡する危険」であり、日本兵により「虐殺される」危険ではない。以上のとおり、『陥都血涙録』の文章には、兵士達の来訪が大虐殺進行中の出来事であり命懸けで訪ねてきているという認識は全く示されていない。
北村氏は、これを裏付ける歴史的事実を提示しています。それは、日本軍が一九三八年一月初旬に発行した安居之証です。これを所持するものは、生存の保証をされました。安居之証の表面には所持する人間の性別・年齢・体格・容貌の特徴が記され、日本軍に対し害意を持たないことを証すると記されていたそうです。郭岐もイタリア大使館に同居中の住人もそれを所得しており、「郭岐を訪ねた元兵士らも同様であったと思われる」と北村氏は述べています。この証明書を持っていれば、要するに、町を歩けたということのようなのです。
では、この証明書は、どれくらい発行されたのでしょうか。インターネットで調べてみたところ、「特務機関資料では12月22日より1月5日までに、概数として15万人登録」されている、とありました。また、同じ資料によれば、「二月の末で登録数が25万」だそうです(これらは、城外区域も含む数字のようです。)http://nankin.digi2.jp/nankinrein.hp.infoseek.co.jp.page007.html
私のいまの力量では、ここまでしかお話しできませんが、これは、「大虐殺」時の南京市の様子をうかがううえで、極めて重要な指摘であると思われます。
このことに関連して、強く印象に残った箇所をひとつ引いておきます。カタカナ表記の部分は、国民政府側が一九四六年二月に完成させた「敵人罪行調査報告」です(この報告について、本当はいろいろと補足すべきことがらがあるのですが、それは略します)。文中に登場する人々は、一九三八年に実施された調査の対象となった南京市民です。
「敵人罪行調査報告」の述べる調査時の状況には、理解に苦しむ文面が存在する。調査された人々の反応である。南京地方法院検察処の調査に対する市民の反応は、「敵側ノ欺瞞妨害工作激烈ニシテ民心消沈シ、進ンデ自発的二殺人ノ罪行ヲ申告スル者甚ダ少ナキノミナラズ、委員ヲ派遣シテ訪問セシムル際二於イテモ、冬ノ蠅ノ如ク口ヲ噤ミテ語ラザル者、或イハ事実ヲ否認スルモノ、或イハ又自己ノ体面ヲ憚リテ告知セザル者、他所二転居シテ不在ノ者、生死不明ニシテ探索ノ方法ナキ者等アリ」という状況であった。それ故に、事実の調査は「何レモ異常ナル困難ヲ経テ調査セルモノ」であったというのである。
人々の反応の不可解さは、かつての日本軍による大量虐殺の記憶が南京市民の間であまり鮮明ではなかったと考えると雲散霧消する、という意味のことを北村氏は指摘します。これは、かなりの説得力があります。
次は、(8)について。北村氏は、ティンパーリーの『WHAT WAR MEANS』とともに南京事件に関する初期の(というより南京事件の語り方を規定した、あるいは決定づけた)基礎文献として名高い『スマイス報告』を取り上げて、南京市内と近郊における民間人の被殺害数の徹底検証をしています。
著者のルイス・スマイスは、南京にあった著名なミッション系の金陵大学の社会学教授です。南京安全区国際委員会書記として委員長のドイツ人ラーベらと難民保護に当たりました。
彼は多数の中国人の助手を使って、南京攻防戦直後の一九三八年三月から六月にかけて南京市と郊外六県を調査の対象にして、戦争被害をサンプリング方式によって調査しました。その結果報告が、上記の『スマイス報告』です。
民間人の被殺害数は、おおむね次のように調査しました。
まず、家屋番号に従い五十戸から一戸を選び、居住する家族の人数・人的被害・収入・職業などが調査されました。次にその結果を五十倍した結果、南京市内における兵士の暴力による死亡二四〇〇人、南京市の人口約二十二万人という基本的数字が割り出されました。このほか別の方法で行われた南京近郊六県を対象とする調査では、民間人の被殺害数三万人という結果が出ました。
「虐殺派」は、この「南京市内における殺害二四〇〇人」という数字に対して「過少である」と難色を示しているようです。
しかし北村氏によれば、南京周辺地域の水害被害調査にも携わったことのある調査のプロであるスマイス氏の、南京市内の被殺害者数を割り出す方法はごく妥当なものです。また、彼の背景を考えれば、彼には「被害状況を過大に評価する動機は存在するが、過小に評価する動機は存在しない」という指摘は説得力があります。それゆえ、「南京市内における殺害二四〇〇人」はおおむね妥当である、と氏は評価します。
では、「南京近郊六県における民間人の被殺害数三万人」はどうでしょうか。氏は、この数字はきわめて疑わしいと言います。その理由は次のとおりです。
・調査対象となった南京近郊六県の総面積は、南京市内の面積のおよそ二〇〇倍である。またその調査地域は、日本軍の侵攻経路と必ずしも緊密に重なっているようには思えない。
・南京市内に関しては、五〇家族のなかから一家族を抽出して調査が行われ、その結果を五〇倍して全体状況が割り出された。これは誰にでも理解できる、合理的な集計方法である。それに対して郊外の調査では、三つに一つの村を選びその村の十家族から一家族を選んで調査したうえで、その結果に五つの県の総家族数一八万六千が掛けられているのである。ここは、合理的に考えるならば三〇が掛けられるべきところである。
以上より北村氏は、ここには近郊六県の被殺害数を誇大に計上する意図があり、「巧みなトリックが施されている」と断じます。
このあたりの論の運びには、高い説得力があります。
同じような説得力は、次の(9)についても感じます。すなわち、南京事件関連の埋葬者数について、紅卍会は処理数四万体あまりを、崇善堂は十一万体を報告したことについて、北村氏が、〈紅卍会の報告数は信用できるが、崇善堂の報告数は過大である疑いが濃厚である〉と結論づける論の運び方がごく妥当なものに感じられるのです。
(8)で、かなり詳細なところにまで触れた(これでもかなり端折っています)ので、(9)で同じようなことをして、読み手のみなさまをさらに煩わせることは避けましょう。できうるならば、ご自身の目でお確かめいただければ幸いです。
ちょっと脱線します。北村氏のまともな考察に接していて思うのですが、犠牲者数が多ければ多いほど喜色満面の笑顔を浮かべていそうな「虐殺派」(のなかの過激分子?)は、どうもマトモな精神構造の持ち主たちではなさそうな気がします。不健全といいましょうか、なんといいましょうか。
閑話休題。やっと(10)にたどりつきました。「南京大虐殺30万人」説のルーツの話です。この論点については、北村稔氏の議論を踏まえて、それをより確実な資料を基に論じ直した秦郁彦氏『南京事件』(中公新書・2007年増補版初版)の議論を紹介するほうが妥当かと思われます。
南京の国際安全区委員会が犠牲者数を四万人と伝えていたのに対して、ティンパーリーは『WHAT WAR MEANS』英語版の冒頭で「華中の戦闘だけで中国軍の死傷者(casualties)は少なくとも三十万人を数え、ほぼ同数の民間人(civilians)の死傷者が出た」と書いています。
このうち軍人の死傷者については、南京陥落直後の一九三七年十二月十七日に蒋介石が漢口で発表した「我軍退出南京告国民書」で、〈抗日戦争開始以来の全軍の死傷者が三十万人に達した〉と述べているのを、ティンパーリーが、上海‐南京戦での死傷者数としてアレンジした(これ自体ひどい誇張ですね)のではないかと北村氏は推測しています。しかし「ほぼ同数の民間人」という記述には典拠が見当たらず、北村氏は、ティンパーリーの脚色ではないかと推測します。つまり、この段階では推測の域を出ていなかったのですね。
ところが秦氏は、外務省が広田弘毅大臣名で三八年一月十九日に欧米各地に打った暗号電二〇六号の存在を探り当てました。ちなみに、ティンパーリーの『WHAT WAR MEANS』が、その中国版『外人目賭中之日軍暴行』とともに出版されたのは、その約四ケ月後です。
それは十六日にティンパーリーが本社(英マンチェスター・ガーディアン紙――引用者注)あてに打とうとした電報を上海の日本検閲官が差し押さえ、英総領事館と係争になっている件を伝えていた(事を大きくするために、ティンパーリーは差し押さえられることを十分承知の上であえて電報を打ったようです――引用者注)。添付された十六日付のティンパーリー電には「私が数日前に上海へ帰っていらい、南京などの日本軍によるフン族の蛮行を思わせる残虐行為の詳細について、信頼できる目撃者の口頭および手紙によって調査を進め」たが、「三十万を下らない中国人シビリアンが虐殺された(Not less than three hundred thousand Chinese civilians slaughtered)」とあった。
つまり、「民間人三十万人虐殺」は、やはりティンパーリーが発信源である可能性が高い、ということです。秦氏は、「あるいは漢口の中央宣伝部との謀議に基づく意図的なプロパガンダなのかもしれない」とも言っています。いずれにしても、どうやらこのあたりが、「南京三十万」の発信源のようですね。
長々と北村氏の所説の祖述のようなことをしました。なんのためにそうしたのか。それは、南京事件に関して日本政府が国際社会にどう発信すべきかということについて、私が前々回に提示した内容の当否をあらためて吟味するためです。前々回、私はこう申し上げました。
日本政府は、人数のことばかりぐちゃぐちゃ言ってないで、「南京事件」を「南京大虐殺」と呼ぶことには根拠がない、とはっきり主張すべきです。そうして、同事件には、国家が計画的に関与する、ナチスのホロコーストのような「大虐殺」などなくて、戦闘員のやむをえざる処刑と、心得違いの日本兵による個別的偶発的な略奪・強姦・殺人だけがあった、と主張しなければなりません。それくらいに端的なことを言わなければ、部外者の耳には入りません。つまり、国際世論を動かす力を持つことにはなりません。そう私は考えます。政府には、腹を据えて臨んでいただきたい。
二点、訂正すべき文言があります。
三行目の「計画的」は「計画的組織的」と、同じ行の「やむをえざる」は「不幸としか言いようのない」と訂正すべきではないでしょうか。以上です。
付記:北村氏の『「南京事件」の探求』についての、南京事件の研究のグローバルスタンダードをふまえたうえでの優れた論考が見つかったので、そのURLを掲げておきます。正確に言えば、論評の対象は本書それ自体ではなくて、その英訳です(加筆あり)。論者のアスキュー・ディヴィッドは、北村氏と立命館大学の同僚で、南京をめぐる共同研究プロジェクトに共に従事している方です。なれ合いに陥らず、言うべきことはきちんと言っている良心的な書評です。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/lt/rb/609/609PDF/david.pdf
(次回は、同シリーズ完結編の予定です)