*ブログ主人より:同日に、(その4)と(その5)を連続アップしました。もしも(その4)をお読みでなければ、まずはそちらからお読みいただければ幸いです。→(その4)http://blog.goo.ne.jp/mdsdc568/e/8254988c34d9b3def33e9ba402acf69d

沖縄タイムス社の『鉄の暴風』や大江健三郎氏の『沖縄ノート』が主張する軍の命令説に対して、曽野氏が深い疑問を抱くに至った理由を以下に列挙します。なお、一九七三年に文芸春秋から出版された『ある神話の背景』は、一九九二年にPHP研究所からPHP文庫として出版されました。それが、二〇〇六年にWACからタイトルを『沖縄戦・渡嘉敷島 集団自決の真実』と変えて出版し直されました。私が読んだのは、それです。
〔1〕軍の命令説の原典にして原点でもある『鉄の暴風』は、沖縄タイムス社によって、やっと捕らえられた直接体験者ではない二人から、むしろ伝聞証拠という形で固定された。
昭和二五年当時、政府に勤めていた太田良博氏は、沖縄タイムス理事・豊平良顕(りょうけん)氏から、『鉄の暴風』の企画出版の手伝いを乞われました。当時は、渡嘉敷島に渡るのも一苦労で、漁船さえまともにない状態でしたから、太田氏は、島から二人の証言者に来てもらいました。そのうちの一人は、当時の助役でありその後沖縄テレビ社長になった山城安次郎氏。もう一人は、南方から復員して島に帰ってきていた宮平栄治氏。宮平氏は事件当時南方にいました。山城氏が目撃したのは、渡嘉敷島ではなくてとなりの座間味島の集団自殺でした。もちろん、二人ともに渡嘉敷島の話はほかの人から詳しく聞いていましたが、直接の体験者や目撃者ではありませんでした。本書から興味深い箇所を引きましょう。
太田氏は、この戦記について、まことに玄人らしい分析を試みている。太田氏によれば、この戦記は、当時の空気を反映しているという。当時の社会事情は、アメリカ側をヒューマニスティックに扱い、日本軍側の旧悪をあばくという空気が濃厚であった。太田氏は、それを私情をまじえずに書き留める側にあった。「述べて作らず」である。とすれば、当時のそのような空気を、そっくりその盡、記録することもまた、筆者としての当然の義務であったと思われる。
『鉄の暴風』の企画執筆の担当者がみずから、日本軍を絶対悪として描き出すフィクションの創作に加担したことを事実上認めてしまっているのは注目に値します。
〔2〕事件当時渡嘉敷村の村長で集団自決の現場にいた古波蔵惟好氏によれば、彼が軍から集団自決の命令を直接受けることはありえず、軍からのあらゆる命令は、当時の駐在巡査の安里喜順氏を通じて受け取ることになっていた。だから、赤松隊長から自決命令が出されたかどうかをいちばんはっきりと知っているのは、安里氏であるということになる。それで曽野氏は、安里氏に直接会って確認してみたところ、彼の口から軍の命令があったという話は出てこなかった。
出てこなかったどころか、それとは正反対の事実を示唆するような話が飛び出してきました。それを次に引きましょう。なお、安里氏が渡嘉敷島に来て赤松隊長とはじめて会ったのは、集団自決の日だったそうです。
(赤松)隊長さんに会った時はもう敵がぐるりと取り巻いておるでしょう。だから民をどうするか相談したんですよ。あの頃の考えとしては、日本人として捕虜になるのはいかんし、又、捕虜になる可能性はありましたからね。そしたら隊長さんの言われるには、我々は今のところは、最後まで(闘って)死んでいいから、あんたたちは非戦闘員だから、最後まで生きて、生きられる限り生きてくれ。只、作戦の都合があって邪魔になるといけないから、部隊の近くのどこかに避難させておいてくれ、ということだったです。
安里氏の話しぶりからは、極限状況において、自らの死の覚悟を決めた上で、なおも戦闘員と非戦闘員との区別をきちんとするだけの正常な判断力を残している赤松隊長の姿が浮かび上がります。ただし古波蔵元村長が、「そこで自決した方がいいというような指令が来て、こっちだけがきいたんじゃなくて住民もそうきいた」と発言していることは記しておきます。しかしそれは、赤松隊長から直接伝えられたものでないことは彼自身が言っていることなので、信憑性の点で、安里氏に軍配が上がることはいうまでもないでしょう。
〔3〕曽野氏と取材時の渡嘉敷村の村長の玉井氏と事件当時若い娘であり若い主婦であった四人の女性とのざっくばらんな会話のなかで、軍の命令の話がまったくでてこないこと。
軍の命令説との関連で核心部分と思われる会話は次の箇所です。
曽野「私、本島のほうで、最後の時の話を伺うと誰か一人、わりとはっきりと《死のう》と言っている人がいるというんですよ」
B「あのね、みんな家族のうちで、家庭内のうちで誰かが・・・・・」
玉井「それを一番最初にやったのは・・・・・」
皆「(くちぐちに)わからんよ」
A「軍から命令しないうちに、家族、家族のただ話し合い」
B「海ゆかば、うたい出して」
C「芝居みるように人を殺したですね、天皇陛下万歳も」
玉井「そのとき、天皇陛下万歳という音頭は、誰がとったの?」
B「わからん、だれかがとったいね。あんとき、あれ《日本魂》だもの」
〔4〕旧厚生省援護局調査課沖縄班によれば、戦傷病者戦没者遺族等援護法ができたのは昭和二七年で、渡嘉敷の場合は軍の要請で気の毒にも戦闘に参加したということで、島民全員が準軍属とみなされ、戦闘中の死亡は、非戦闘員でも戦死とみなされた。そこで、渡嘉敷をめぐる周囲の空気が「軍命令による玉砕」を主張することは、遺族年金を得るために必要であり、自然であり、賢明でもあった、といえること。
軍命令説賛成派からすれば、赤松部隊の生き残り組の発言を取り上げるのは、泥棒の釈明を聞いてやるようなものだと言われてしまいそうですが、ここは、大江健三郎氏が全否定してみせた、赤松隊長の人間性に関わる大切なところなので、取り上げることにします。
この点に関しては、もと赤松部隊の連下政一氏と谷本小次郎氏からの回答があった。
「軍が命令を出していないということを隊員があらゆる角度から証言したとなると、遺族の受けられる年金がさしとめられるようなことになるといけない、と思ったからです。我々が口をつぐんでいた理由はたった一つそれだけです」
厚生省の話によると、一旦調査が決定したものは再びその資格を剥奪されることはない、というから、今やその点も伏せておく必要は全くなくなったのである。
赤松部隊は、戦後においても、赤松隊長を中心とする強い絆で結ばれています。赤松隊長の一声で、全国に散らばっている元隊員たちが、万難を排して集結するのですから。それゆえ、もしも連下氏と谷本氏の回答が事実であるのならば、そこには、赤松隊長の強い意向が反映されていると見るほかないと思われます。つまり赤松隊長は、渡嘉敷島の集団自決に対して痛切に責任を感じ続けている、と。なぜなら、軍命令であることを甘受して、世間の冷眼視を背中に感じ続ける茨の人生を甘受することと引き換えに、集団自決によって亡くなった島民の遺族に年金がきちっと行き渡るようにするという振る舞いの動機は、赤松隊長の強い責任意識に求めるよりほかはないと思われるからです。大江健三郎氏が、妄想を逞しくして描き出そうとした「極悪人赤松」とは、かけ離れた人間像が、そこから浮びあがってきます。私には、それこそがまともな文学者が抱く赤松隊長のイメージなのではないかと感じられて仕方がありません。大江氏の赤松像は、修羅場をくぐり抜けた現場の指導者のそれとして、あまりにも幼稚な感じがします。彼が思っているほどに、世間の人々は単純ではないのです。私は、赤松部隊の元隊員たちの詐術に引っかかっているのでしょうか。どうも、そうではないような気がします。その傍証をひとつだけ挙げておきます。
巻末の解説で、石川水穂氏(産経新聞論説委員)は、次のように述べています。
同島(渡嘉敷島のとなりの座間味島のことを指している――引用者注)を守備していた日本軍は、梅沢裕少佐が率いる海上挺身隊第一戦隊だ。沖縄タイムス社の『鉄の暴風』はこう書いていた。
「米軍上陸の前日(昭和二十年三月二十五日)、軍は忠魂碑前の広場に住民をあつめ、玉砕を命じた」「村長初め役場吏員、学校教員の一部やその家族は、ほとんど各自の壕で手榴弾を抱いて自決した。その数五十二人である」「隊長梅沢少佐のごときは、のちに朝鮮人慰安婦らしきもの二人と不明死を遂げたことが判明した」
だが、座間味島の集団自決から三十二年後の命日(三十三回忌)にあたる昭和五十二年三月二十六日、生き残った元女子青年団員は娘に「梅沢隊長の自決命令はなかった」と告白した。梅沢少佐のもとに玉砕のための弾薬をもらいにいったが帰されたことや、遺族が援護法に基づく年金を受け取れるように事実と違う証言をしたことも打ち明けた。
また、昭和六十二年三月、集団自決した助役の弟が梅沢氏に対し、「集団自決は兄の命令で行われた。私は遺族年金のため、やむを得ず、隊長命令として(旧厚生省に)申請した」と証言した。
これらの事実は神戸新聞が取材し、昭和六十年七月三十日付、六十一年六月六日付、六十二年四月十八日付で伝えている。
年金の話が出ていますね。集団自決において軍命令があったとされていることやとなりの島であることや同じ日に米軍が上陸してきたことや海上挺進隊が出発をひかえていたことなど、渡嘉敷島と座間味島には、類似点が多い。だから、座間味島における年金事情と同じような事情が渡嘉敷島にもあったと考えるのが自然でしょう。ましてや、座間味島の事情が明るみに出るはるか前に赤松隊員の口から年金の話が洩れていたのですから、彼らが神戸新聞を読んであわててそれを猿真似した可能性はゼロです。
赤松部隊の元隊員たちの証言のなかで、無視し難い重要なものが、ほかにひとつあります。それは、赤松部隊には『鉄の暴風』が強調した「安全な地下壕」などなかったということです。『鉄の暴風』によれば、その地下壕のなかで将校会議が開かれ、赤松隊長は、「事態はこの島に住むすべての人間の死を要求している」と言って、渡嘉敷島の住民の集団自決を示唆しました。同書には、「これを聞いた副官の知念少尉(沖縄出身)は悲憤のあまり、慟哭し、軍籍にある身を痛嘆した」と書き添えられています。曽野氏は、昭和四六年七月十一日、知念元少尉に会い、次のような会話を交わしています。
「地下壕はございましたか?」
私は質問した。
「ないですよ、ありません」
知念氏はきっぱりと否定した。
「この本の中に出て来るような将校会議というのはありませんか」
「いやあ、ぜんぜんしていません。只、配備のための将校会議というのはありました。一中隊どへ行け、二中隊どこへ行けという式のね。全部稜線に配置しておりましたんでね」
私たちは、「安全な地下壕」が、渡嘉敷島の現地日本軍をなるべく貶めて描き出すためのフィクテシャスな舞台装置であったことが、白日の下に晒された瞬間を目撃したことになります。
そのほか、『鉄の暴風』が執拗に暴き立てた赤松隊長の悪行三昧の数々について、曽野氏は、ひとつひとつ丁寧に取り上げて検証しているのですが、いまはその詳細について触れるのは控えます。事実は、『鉄の暴風』が主張したがっているほどに単純ではない、とだけ申し上げておきます。
軍命令説の是非について長々と論じてきましたが、このあたりでやめておきます。その説は、限りなく疑わしいことが判明しただけで、私としてはよしとします。左翼リベラル派は、「広義の強制性」などという言葉を持ち出して、いつかどこかで聞いたような議論の仕切り直しをしたがっているようですが、それはこの際、どうでもいいことです。彼らは日本が滅びるその日まで、そういうことを言い続けるのでしょう。
大本営が「国民総玉砕」「本土決戦」などと嘯くことで、我知らず手放そうとした大東亜戦争の義を、住民の集団自決が頻発するような極限状況において、沖縄戦を戦う現場の隊長クラスは、放り出すようなバカなマネはしなかった可能性が高いことを、とりあえず確認しました。しかし、私が言いたいのは、実はそういうことにとどまりません。
沖縄戦における島民の「献身的な」というレベルを超えた命がけの軍への協力ぶりを、言いかえれば、不可避的に集団自決にまで自分たちを追い込むほどの協力ぶりを、いまに生きる私たちがどう受けとめたらよいのか、という問題について、わずかながらでもいいから、触れてみたいのです。おそらく、そのことに対してきちんとした言葉を発することができなければ、戦後レジームからの脱却もなにもあったものではないのだろうと、私はぼんやりとではありますが感じています。
曽野氏も、同書でそのことをめぐってあれこれと考えています。そのなかで、氏によって引用されたある文章が、私にはもっとも鮮やかな印象を残しています。曽野氏によれば、それは新里恵二、喜久里峰夫、石川明の三氏によって『歴史評論』昭和二十二年一月号に書かれたものです。氏は、それを「昭和二十年の空気を最もよくあらわした文章」と評しています。孫引きしましょう。
「私たちは、ここで(戦場へ)かりだされたと書いておきました。それは事がらの本質においてそのとおりでした。然し、私達はこみあげてくる悲憤をおさえつつ、次のように書きとめておかねばならないと思います。これらの行為は、その殆どが、特に青年層の場合には百%までが『自発的な意志』に基づいてなされていた、と。軍隊の中でも、沖縄出身の初年兵は、『斬込み』の先頭に立っていました。『護郷』『郷土防衛』、それが当時、帝国主義戦争の本質に関する知識は欠きながらも、自らの生まれ育った地を荒らす兇暴な戦争に抗議するために、沖縄県民がとりえた唯一つの態度だったのです。この合言葉の下に、多くの若い生命が惜しげもなく捨てられ、有為の人々がむざむざと非命に斃れてゆきました。・・・・・歴史の上で常に異民族ででもあるかのように扱われ『忠君愛国の志乏しき』ことを、ことごとにあげつらわれ、一種の劣等感、民族意識における特殊のコンプレックスをすら抱かされていた沖縄青少年にとって、『醜(しこ)の御楯(みたて)』たることに疑問を持つのは道徳に反することでした。沖縄戦は『吾々もまた帝国の忠良たる臣民である』ことを、身をもってあかしする格好の機会とすら考えられたのです」
今日から振り返れば、「帝国主義戦争の本質に関する知識は欠きながらも」の箇所は、敗戦直後という、左翼全盛期の痕跡として受けとめるのが妥当で、カッコに入れて読む方がよいでしょう。その手続きを経たうえでのことではありますが、これらの言葉は沖縄戦の最中の沖縄県民の心を忌憚なく吐露したものとして私たちの胸に迫ってきます。また、これらは、児島襄氏『太平洋戦争』の「沖縄戦の最後に勇戦したのは、本来の兵士を除けば、鉄血勤皇隊の少年たちだった」という言葉と符合しますし、「沖縄県民五七万人のうち、約一〇万人は島外に疎開し、老幼者の一部は北部に避難したが、大半の約三〇万人は南部に残り、多くは陣地構築、補給作業に従事した」というくだりにおける県民の秘められた心を明らかにしてもくれるような気がします。先に私が離島コンプレクスという言葉で舌っ足らずながらも言おうとしたのは、要するにそういうことだったのです。
ここで私の脳裏に、次の文章がおのずと浮かんできます。それは、一九四五年六月十三日に拳銃で自決した、海軍・沖縄方面根拠地隊司令官大田実少将が、その七日前の六月六日に、海軍次官に宛てた電文です。知っていらっしゃる方も少なくないのではないでしょうか。
沖縄県民斯(か)く戦えり
発 沖縄根拠地隊司令官
宛 海軍次官
左の電文を次官に御通報方取り計らいを得たし
沖縄県民の実情に関しては、県知事より報告せらるべきも、県には既に通信力なく、三二軍司令部また通信の余力なしと認めらるるに付き、本職、県知事の依頼を受けたるに非ざれども、現状を看過するに忍びず、これに代わって緊急御通知申し上げる。
沖縄島に敵攻略を開始以来、陸海軍方面、防衛戦闘に専念し、県民に関しては殆ど顧みるに暇(いとま)なかりき。
然れども、本職の知れる範囲に於いては、県民は青壮年の全部を防衛召集に捧げ、残る老幼婦女子のみが、相次ぐ砲爆撃に家屋と財産の全部を焼却せられ、僅(わず)かに身を以って軍の作戦に差し支えなき場所の小防空壕に避難、尚、砲爆撃下□□□風雨に曝されつつ、乏しき生活に甘んじありたり。
しかも若き婦人は、率先軍に身を捧げ、看護婦烹炊(ほうすい)婦はもとより、砲弾運び、挺身斬り込み隊すら申し出る者あり。
所詮、敵来たりなば、老人子供は殺されるべく、婦女子は後方に運び去られて毒牙に供せらるべしとて、親子生き別れ、娘を軍衛門に捨つる親あり。
看護婦に至りては、軍移動に際し、衛生兵既に出発し、身寄り無き重傷者を助けて□□、真面目にして、一時の感情に駆られたるものとは思われず。
さらに、軍に於いて作戦の大転換あるや、自給自足、夜の中に遥かに遠隔地方の住民地区を指定せられ、輸送力皆無の者、黙々として雨中を移動するあり。
これを要するに、陸海軍沖縄に進駐以来、終始一貫、勤労奉仕、物資節約を強要せられつつ(一部はとかくの悪評なきにしもあらざるも)ひたすら日本人としての御奉公の護を胸に抱きつつ、遂に□□□□与え□ことなくして、本戦闘の末期と沖縄島は実情形□□□□□□
一木一草焦土と化せん。糧食6月一杯を支うるのみなりという。沖縄県民斯く戦えり。県民に対し、後世特別の御高配を賜らんことを。
私が、この電文にはじめて接したのは、いまから十七年前、沖縄那覇市南部の小禄にある海軍壕においてでした。そのとき私は、一種名状し難い感情に襲われて、それをどういう言葉で表したらいいのか、皆目見当がつきませんでした。すっかり混乱してしまったのです。一語一語をかみしめるようにして読み進めると、おのずと熱いものがこみ上げてくるのです。大田少将自身、死の覚悟を決めたうえで、これだけは書き留めて残しておかなければ、死ぬに死ねないという、やむにやまれぬ切迫感に突き動かされて、これを書いているのではないかと思われます。
大田少将は、沖縄県民が日米軍の熾烈な戦いによって被っている、筆舌に尽くしがたい惨状を訴えているのでしょうか。「風雨に曝されつつ、乏しき生活に甘んじありたり」「一木一草焦土と化せん」とあるとおり、それを訴えているのも間違いないでしょう。しかし大田少将は、沖縄県民を戦争の被害者としてのみ描いているわけではありません。それらすべてを無言で引き受けて、命を供するようにして、それぞれの立場で沖縄戦を戦い抜く県民の姿に、太田少将は、畏敬の念すら覚えて、これを書き記したのではないでしょうか。「沖縄県民斯く戦えり」という一文には、少将の万感の思いが込められている。そう感じられます。死に臨み、太田少将は、あらためて県民の″『吾々もまた帝国の忠良たる臣民である』ことを、身をもってあかしする″という思いの深さと大きさに触れて、絶句する思いを味わったのではないかと思います。「沖縄島に敵攻略を開始以来、陸海軍方面、防衛戦闘に専念し、県民に関しては殆ど顧みるに暇なかりき」という書き出しの文には、いままでそのことにはっきりと気づかずにまことにかたじけないという少将の思いがおのずとにじみだしています。
「県民に対し、後世特別の御高配を賜らんことを」という言葉は、直接的には当時の海軍次官に向けられていますが、実は私たち本土の心ある人間すべてに向けられていると考えるよりほかにない、といまでは考えています。慌てて先回りしておきますが、私は、これを機に不戦の誓いを新たにしたいなどという寝ぼけた綺麗事を言いたがっているわけではありません。
ここからは、端的に、本土決戦を覚悟していたが結局は戦わなかった「やまとんちゅ」の末裔として話します。
沖縄県民は、本土の人々が潜在的に覚悟していた本土決戦を、沖縄の地で本当に戦い切ってしまったのです。そこには当然、集団自決をした人々も含まれます。親から頭を痛打されて絶命した赤ん坊も含まれます。そうして、沖縄県民に「一種の劣等感、民族意識における特殊のコンプレックス」があり、彼らが「沖縄戦は『吾々もまた帝国の忠良たる臣民である』ことを、身をもってあかしする格好の機会」と考えて戦い切ったのだとしても、彼らが「戦い切った」事実それ自体には、いささかの瑕疵も生じません。人間は、常に時代に制約された不完全な存在として、あることを成し遂げるのです。
では沖縄県民が、本土の人々が潜在的に覚悟していた本土決戦を、沖縄の地で本当に戦い切ってしまったことの意味とはいったい何なのでしょうか。それをうまく言い当てるには、大東亜戦争の本質について押さえておく必要があります。
私見によれば、大東亜戦争には、ざっくりと言ってしまえば、大きくふたつの意味があります。ひとつは、身も蓋もないパワー・ポリティクスとしての国際政治の、極限状況における姿としての近代戦争という意味です。これは、要するに強いほうが勝つというドラスティックな世界であって、時の政府と軍首脳が戦略的思考のありったけを振り絞って敵国に臨むべき世界です。この面で、日本が英米との戦いにおいてボロ負けの惨状を呈するに至ったことは、当論考の「その1」から「その3」までで、しつこいほどに申し上げました。
国際政治学者・高坂正堯氏が述べる、国家の三つの体系に即すならば、以上は、おもに「力の体系」と「利益の体系」に関わる領域であると一応言うことができるのではないでしょうか。
大東亜戦争には、もうひとつ、欧米と日本という歴史的にまったく異なるふたつの価値の体系の、避けようにもどうにも避け得なかった衝突、思想戦としての文明の衝突という意味があります。この戦いは、たかだか時の権力を手中にしたに過ぎない一政府によって担い切れるものではありません。心ある国民が民族の記憶のすべてを動員して担うよりほかにないものです。つまり、この戦いの主体は、共同体の良き伝統・慣習を体現した総体としての国民なのです。戦争において、時の権力者は、この「価値の体系」に関してあくまでも謙虚かつ禁欲的でなければなりません。それゆえ、″自分たちは、あくまでも、「力の体系」と「利益の体系」に関する責任を全うするに過ぎない″という自覚こそが、ノーブレス・オブリージュの根拠なのです。そこを踏み外すと、権力者は、醜くて情けない姿を晒すことになります。その典型例として、私は、大本営がサイパン島陥落の衝撃によって呆然自失状態になり、「残るは一億玉砕に依る敵の戦意放棄に俟つあるのみ」などと口走って、自分たちの失敗を国民の命を弄ぶことでカモフラージュしようとした事実を挙げました。だから、時の権力者にとって、戦争の義とはどこまでも無辜の一般国民の生命を守ることとのつながりにおいて存すると考えるべきなのです。それは、繰り返しになりますが、国家の「価値の体系」の側面に関して、時の権力者はあくまでも脇役に徹し、主役は、良き伝統や慣習それ自体であることを肝に銘じなければならない、ということでもあります。これは、″国家権力なるものは、国民道徳や道徳教育に容喙することにあくまでも慎重であるべきだ″という見解につながっていきます。むろん私は、そうあるべきだと考えています(このことがきちんと理解できない政治家や思想家を、私はあまり高く評価できません)。
以上のことから、戦争には、それにふたつの意味が存することに対応して、もうひとつの義があることに私たちは気づかされます。共同体の良き伝統・慣習を体現した総体としての国民が戦いの主体となる、思想戦としての文明の衝突において、無辜の一般国民の生命を守ることがすなわち戦争の義とは言い切れなくなるのです。この戦いにおいて、義を守る主体が、時の権力者から総体としての国民に移るのですから、そういうよりほかはありません。端的に言えば、この意味での戦争においては、国民がみずから自発的に命を賭けてでも戦い抜くことによって義を守る局面が存する可能性を排除できないのです。そうして、その局面が表面化し顕在化してきたのが、サイパン陥落を機に、軍首脳の戦略的思考の欠如に起因する総体としての戦争の失敗が誰の目にも明らかになってきた大東亜戦争末期なのでした。この場合、命を賭しても主体的に戦い抜くことそれ自体が、戦いの義そのものの様相を帯びることになります。なぜなら、共同体が長い時間をかけて培ってきた良き伝統・慣習なるものは、結局のところ言葉に表し得ないものとして存在するからです。
心ある国民は、そういう深刻な事態の現出を暗黙のうちに感じ取っていました。児島襄氏が『太平洋戦争』に、敗戦の色が濃厚になってきた状況下で「国民の多くは、一方で″諦観自棄″の風を生みながらも、最後の戦いの覚悟は捨てていなかった」と書き記しているのには、そういう意味があるのではないかと思われます。また、吉本隆明氏や桶谷秀昭氏が、必敗の悲惨な状況下でまったくひるまなかったのは、"自分は本土決戦で死ぬ"という覚悟が定まっていたからである、という意味のことを言っているのも、そのことと大いに関わりがあると、私は考えます。
長谷川三千子氏は、『神やぶれたまはず』に、吉本隆明氏の次の言葉を書き記しています。
戦後すぐに、児玉誉士夫と宮本顕治と鈴木茂三郎が大学に来て、勝手なことを講演して帰っていったことがあるんです。なかで、もっとも感心したのは児玉誉士夫の話で、米軍が日本に侵攻してきた時に日本人はみんな死んでいて焦土にひゅうひゅうと風が吹き渡っているのを見たら連中はどう思っただろう(笑)、と発言して、ああいいことを言うなと僕は感心して聞きました。
吉本氏はここで、自分を含めた日本国民が、思想戦としての大東亜戦争を戦い切った後の荒涼としていて底知れぬ迫力に満ちたイメージを、戦後においても心の奥底に存する、実現できなかったみずからの秘められた願望をそこに重ね合わせながら素直に語っています(こういう無類の率直さが、思想家・吉本氏の掛け値なしの美質です)。
ところが天皇の決断によって、日本国民は、本土決戦を目の前にしながらそれを戦う機会を永遠に失うことになりました。私は、そういう決断をした天皇を決して非難しようとは思いません。「おおみたから」としての国民を守るためのやむを得ざる現実的な決断であったと思っています。しかし、それが日本国民にとってきわめて大きな精神史的事件をもたらしたこともまた、確かなのです。つまり、そのことによって、国民の心のど真ん中にポッカリと虚ろな穴が空き、戦前と戦後がうまくつながらなくなってしまったのです。それが、敗戦トラウマの核心を成すものです。GHQのウォー・ギルド・インフォメーション・プログラムによって、それが強化されたことは確かですが、そういう洗脳政策を受け入れる精神状態があらかじめ十分に存在したことも確かなのです。
本土の人々は、精神的な空白状態と戦後のどさくさによって我を忘れ、沖縄の存在をすっかり忘れてしまったのです。それと同時に、沖縄県民が、あの小さな島で民族精神としての本土決戦を戦い抜くことによって、図らずも思想戦としての大東亜戦争の義を命がけで守り抜くことになったこともすっかり忘れてしまったのです。
本土の人々の情けないほどの健忘症によって精神的な孤立を余儀なくされた沖縄は、戦後、左翼勢力の巣窟となり、彼らの被害者史観が猖獗を極めることになります。大田実少将が訴えた沖縄県民の悲惨にして崇高な戦いぶりは、県民に寄り添ったふりをする連中によって、見事に泥塗られ貶められてしまったのです。
また、精神的な空白を抱えた本土では、その間隙を突くことで、いわゆる自虐史観が大手を振ってまかり通り、相も変わらず時代の支配思想で有り続けています。決定的な場面で義を貫けなかったという集合的記憶が、そういう病んだ歴史観を呼び寄せたのでしょう。つまり、敗戦トラウマを仲立ちにして、沖縄の被害者史観と本土の自虐史観とは、合わせ鏡の関係にあるのです。大江健三郎氏などは、そういう悲惨で病んだ精神状況にどっかりと胡座をかいて、ちょっと深刻ぶった表情をしてみせるだけで、けっこう大した力を発揮できたりしてしまうわけです。戦後民主主義とは、要するにそういうものです。
結論です。私を含めた本土の人々が、敗戦トラウマや自虐史観から脱却し、新たな歴史観を力強く未知の地平に切り開いてゆくには、沖縄県民が、あの小さな島でかつて思想戦としての大東亜戦争の義を命がけで守り抜いたという精神史的な、ある意味で神学的な事実を、一度は無条件に、素直に、全面的に、身体の隅々に行き渡るまで受け入れることが必須となります。これが、大田実少将が本土の人々に送ったメッセージに、いまの私が応えうるもののすべてであります。それは同時に、沖縄の人々が、病んだ被害者史観から脱却し精神的に自由になる道筋でもあることは言うまでもありません。なぜ、「ある意味で神学的」なのか。端的に申し上げましょう。沖縄戦における沖縄県民は、『旧約聖書』の「イサク奉献」におけるイサクそのものであるからです。その意味で沖縄戦は、イサク問題でもあるのです。これはこれで、きちんと話そうとするとけっこう長くなってしまうような気がしますので、未完の、『神やぶれたまはず』についての論考の続きを書くときにでも、あらためて触れようと思います。(この稿、終わり)

沖縄タイムス社の『鉄の暴風』や大江健三郎氏の『沖縄ノート』が主張する軍の命令説に対して、曽野氏が深い疑問を抱くに至った理由を以下に列挙します。なお、一九七三年に文芸春秋から出版された『ある神話の背景』は、一九九二年にPHP研究所からPHP文庫として出版されました。それが、二〇〇六年にWACからタイトルを『沖縄戦・渡嘉敷島 集団自決の真実』と変えて出版し直されました。私が読んだのは、それです。
〔1〕軍の命令説の原典にして原点でもある『鉄の暴風』は、沖縄タイムス社によって、やっと捕らえられた直接体験者ではない二人から、むしろ伝聞証拠という形で固定された。
昭和二五年当時、政府に勤めていた太田良博氏は、沖縄タイムス理事・豊平良顕(りょうけん)氏から、『鉄の暴風』の企画出版の手伝いを乞われました。当時は、渡嘉敷島に渡るのも一苦労で、漁船さえまともにない状態でしたから、太田氏は、島から二人の証言者に来てもらいました。そのうちの一人は、当時の助役でありその後沖縄テレビ社長になった山城安次郎氏。もう一人は、南方から復員して島に帰ってきていた宮平栄治氏。宮平氏は事件当時南方にいました。山城氏が目撃したのは、渡嘉敷島ではなくてとなりの座間味島の集団自殺でした。もちろん、二人ともに渡嘉敷島の話はほかの人から詳しく聞いていましたが、直接の体験者や目撃者ではありませんでした。本書から興味深い箇所を引きましょう。
太田氏は、この戦記について、まことに玄人らしい分析を試みている。太田氏によれば、この戦記は、当時の空気を反映しているという。当時の社会事情は、アメリカ側をヒューマニスティックに扱い、日本軍側の旧悪をあばくという空気が濃厚であった。太田氏は、それを私情をまじえずに書き留める側にあった。「述べて作らず」である。とすれば、当時のそのような空気を、そっくりその盡、記録することもまた、筆者としての当然の義務であったと思われる。
『鉄の暴風』の企画執筆の担当者がみずから、日本軍を絶対悪として描き出すフィクションの創作に加担したことを事実上認めてしまっているのは注目に値します。
〔2〕事件当時渡嘉敷村の村長で集団自決の現場にいた古波蔵惟好氏によれば、彼が軍から集団自決の命令を直接受けることはありえず、軍からのあらゆる命令は、当時の駐在巡査の安里喜順氏を通じて受け取ることになっていた。だから、赤松隊長から自決命令が出されたかどうかをいちばんはっきりと知っているのは、安里氏であるということになる。それで曽野氏は、安里氏に直接会って確認してみたところ、彼の口から軍の命令があったという話は出てこなかった。
出てこなかったどころか、それとは正反対の事実を示唆するような話が飛び出してきました。それを次に引きましょう。なお、安里氏が渡嘉敷島に来て赤松隊長とはじめて会ったのは、集団自決の日だったそうです。
(赤松)隊長さんに会った時はもう敵がぐるりと取り巻いておるでしょう。だから民をどうするか相談したんですよ。あの頃の考えとしては、日本人として捕虜になるのはいかんし、又、捕虜になる可能性はありましたからね。そしたら隊長さんの言われるには、我々は今のところは、最後まで(闘って)死んでいいから、あんたたちは非戦闘員だから、最後まで生きて、生きられる限り生きてくれ。只、作戦の都合があって邪魔になるといけないから、部隊の近くのどこかに避難させておいてくれ、ということだったです。
安里氏の話しぶりからは、極限状況において、自らの死の覚悟を決めた上で、なおも戦闘員と非戦闘員との区別をきちんとするだけの正常な判断力を残している赤松隊長の姿が浮かび上がります。ただし古波蔵元村長が、「そこで自決した方がいいというような指令が来て、こっちだけがきいたんじゃなくて住民もそうきいた」と発言していることは記しておきます。しかしそれは、赤松隊長から直接伝えられたものでないことは彼自身が言っていることなので、信憑性の点で、安里氏に軍配が上がることはいうまでもないでしょう。
〔3〕曽野氏と取材時の渡嘉敷村の村長の玉井氏と事件当時若い娘であり若い主婦であった四人の女性とのざっくばらんな会話のなかで、軍の命令の話がまったくでてこないこと。
軍の命令説との関連で核心部分と思われる会話は次の箇所です。
曽野「私、本島のほうで、最後の時の話を伺うと誰か一人、わりとはっきりと《死のう》と言っている人がいるというんですよ」
B「あのね、みんな家族のうちで、家庭内のうちで誰かが・・・・・」
玉井「それを一番最初にやったのは・・・・・」
皆「(くちぐちに)わからんよ」
A「軍から命令しないうちに、家族、家族のただ話し合い」
B「海ゆかば、うたい出して」
C「芝居みるように人を殺したですね、天皇陛下万歳も」
玉井「そのとき、天皇陛下万歳という音頭は、誰がとったの?」
B「わからん、だれかがとったいね。あんとき、あれ《日本魂》だもの」
〔4〕旧厚生省援護局調査課沖縄班によれば、戦傷病者戦没者遺族等援護法ができたのは昭和二七年で、渡嘉敷の場合は軍の要請で気の毒にも戦闘に参加したということで、島民全員が準軍属とみなされ、戦闘中の死亡は、非戦闘員でも戦死とみなされた。そこで、渡嘉敷をめぐる周囲の空気が「軍命令による玉砕」を主張することは、遺族年金を得るために必要であり、自然であり、賢明でもあった、といえること。
軍命令説賛成派からすれば、赤松部隊の生き残り組の発言を取り上げるのは、泥棒の釈明を聞いてやるようなものだと言われてしまいそうですが、ここは、大江健三郎氏が全否定してみせた、赤松隊長の人間性に関わる大切なところなので、取り上げることにします。
この点に関しては、もと赤松部隊の連下政一氏と谷本小次郎氏からの回答があった。
「軍が命令を出していないということを隊員があらゆる角度から証言したとなると、遺族の受けられる年金がさしとめられるようなことになるといけない、と思ったからです。我々が口をつぐんでいた理由はたった一つそれだけです」
厚生省の話によると、一旦調査が決定したものは再びその資格を剥奪されることはない、というから、今やその点も伏せておく必要は全くなくなったのである。
赤松部隊は、戦後においても、赤松隊長を中心とする強い絆で結ばれています。赤松隊長の一声で、全国に散らばっている元隊員たちが、万難を排して集結するのですから。それゆえ、もしも連下氏と谷本氏の回答が事実であるのならば、そこには、赤松隊長の強い意向が反映されていると見るほかないと思われます。つまり赤松隊長は、渡嘉敷島の集団自決に対して痛切に責任を感じ続けている、と。なぜなら、軍命令であることを甘受して、世間の冷眼視を背中に感じ続ける茨の人生を甘受することと引き換えに、集団自決によって亡くなった島民の遺族に年金がきちっと行き渡るようにするという振る舞いの動機は、赤松隊長の強い責任意識に求めるよりほかはないと思われるからです。大江健三郎氏が、妄想を逞しくして描き出そうとした「極悪人赤松」とは、かけ離れた人間像が、そこから浮びあがってきます。私には、それこそがまともな文学者が抱く赤松隊長のイメージなのではないかと感じられて仕方がありません。大江氏の赤松像は、修羅場をくぐり抜けた現場の指導者のそれとして、あまりにも幼稚な感じがします。彼が思っているほどに、世間の人々は単純ではないのです。私は、赤松部隊の元隊員たちの詐術に引っかかっているのでしょうか。どうも、そうではないような気がします。その傍証をひとつだけ挙げておきます。
巻末の解説で、石川水穂氏(産経新聞論説委員)は、次のように述べています。
同島(渡嘉敷島のとなりの座間味島のことを指している――引用者注)を守備していた日本軍は、梅沢裕少佐が率いる海上挺身隊第一戦隊だ。沖縄タイムス社の『鉄の暴風』はこう書いていた。
「米軍上陸の前日(昭和二十年三月二十五日)、軍は忠魂碑前の広場に住民をあつめ、玉砕を命じた」「村長初め役場吏員、学校教員の一部やその家族は、ほとんど各自の壕で手榴弾を抱いて自決した。その数五十二人である」「隊長梅沢少佐のごときは、のちに朝鮮人慰安婦らしきもの二人と不明死を遂げたことが判明した」
だが、座間味島の集団自決から三十二年後の命日(三十三回忌)にあたる昭和五十二年三月二十六日、生き残った元女子青年団員は娘に「梅沢隊長の自決命令はなかった」と告白した。梅沢少佐のもとに玉砕のための弾薬をもらいにいったが帰されたことや、遺族が援護法に基づく年金を受け取れるように事実と違う証言をしたことも打ち明けた。
また、昭和六十二年三月、集団自決した助役の弟が梅沢氏に対し、「集団自決は兄の命令で行われた。私は遺族年金のため、やむを得ず、隊長命令として(旧厚生省に)申請した」と証言した。
これらの事実は神戸新聞が取材し、昭和六十年七月三十日付、六十一年六月六日付、六十二年四月十八日付で伝えている。
年金の話が出ていますね。集団自決において軍命令があったとされていることやとなりの島であることや同じ日に米軍が上陸してきたことや海上挺進隊が出発をひかえていたことなど、渡嘉敷島と座間味島には、類似点が多い。だから、座間味島における年金事情と同じような事情が渡嘉敷島にもあったと考えるのが自然でしょう。ましてや、座間味島の事情が明るみに出るはるか前に赤松隊員の口から年金の話が洩れていたのですから、彼らが神戸新聞を読んであわててそれを猿真似した可能性はゼロです。
赤松部隊の元隊員たちの証言のなかで、無視し難い重要なものが、ほかにひとつあります。それは、赤松部隊には『鉄の暴風』が強調した「安全な地下壕」などなかったということです。『鉄の暴風』によれば、その地下壕のなかで将校会議が開かれ、赤松隊長は、「事態はこの島に住むすべての人間の死を要求している」と言って、渡嘉敷島の住民の集団自決を示唆しました。同書には、「これを聞いた副官の知念少尉(沖縄出身)は悲憤のあまり、慟哭し、軍籍にある身を痛嘆した」と書き添えられています。曽野氏は、昭和四六年七月十一日、知念元少尉に会い、次のような会話を交わしています。
「地下壕はございましたか?」
私は質問した。
「ないですよ、ありません」
知念氏はきっぱりと否定した。
「この本の中に出て来るような将校会議というのはありませんか」
「いやあ、ぜんぜんしていません。只、配備のための将校会議というのはありました。一中隊どへ行け、二中隊どこへ行けという式のね。全部稜線に配置しておりましたんでね」
私たちは、「安全な地下壕」が、渡嘉敷島の現地日本軍をなるべく貶めて描き出すためのフィクテシャスな舞台装置であったことが、白日の下に晒された瞬間を目撃したことになります。
そのほか、『鉄の暴風』が執拗に暴き立てた赤松隊長の悪行三昧の数々について、曽野氏は、ひとつひとつ丁寧に取り上げて検証しているのですが、いまはその詳細について触れるのは控えます。事実は、『鉄の暴風』が主張したがっているほどに単純ではない、とだけ申し上げておきます。
軍命令説の是非について長々と論じてきましたが、このあたりでやめておきます。その説は、限りなく疑わしいことが判明しただけで、私としてはよしとします。左翼リベラル派は、「広義の強制性」などという言葉を持ち出して、いつかどこかで聞いたような議論の仕切り直しをしたがっているようですが、それはこの際、どうでもいいことです。彼らは日本が滅びるその日まで、そういうことを言い続けるのでしょう。
大本営が「国民総玉砕」「本土決戦」などと嘯くことで、我知らず手放そうとした大東亜戦争の義を、住民の集団自決が頻発するような極限状況において、沖縄戦を戦う現場の隊長クラスは、放り出すようなバカなマネはしなかった可能性が高いことを、とりあえず確認しました。しかし、私が言いたいのは、実はそういうことにとどまりません。
沖縄戦における島民の「献身的な」というレベルを超えた命がけの軍への協力ぶりを、言いかえれば、不可避的に集団自決にまで自分たちを追い込むほどの協力ぶりを、いまに生きる私たちがどう受けとめたらよいのか、という問題について、わずかながらでもいいから、触れてみたいのです。おそらく、そのことに対してきちんとした言葉を発することができなければ、戦後レジームからの脱却もなにもあったものではないのだろうと、私はぼんやりとではありますが感じています。
曽野氏も、同書でそのことをめぐってあれこれと考えています。そのなかで、氏によって引用されたある文章が、私にはもっとも鮮やかな印象を残しています。曽野氏によれば、それは新里恵二、喜久里峰夫、石川明の三氏によって『歴史評論』昭和二十二年一月号に書かれたものです。氏は、それを「昭和二十年の空気を最もよくあらわした文章」と評しています。孫引きしましょう。
「私たちは、ここで(戦場へ)かりだされたと書いておきました。それは事がらの本質においてそのとおりでした。然し、私達はこみあげてくる悲憤をおさえつつ、次のように書きとめておかねばならないと思います。これらの行為は、その殆どが、特に青年層の場合には百%までが『自発的な意志』に基づいてなされていた、と。軍隊の中でも、沖縄出身の初年兵は、『斬込み』の先頭に立っていました。『護郷』『郷土防衛』、それが当時、帝国主義戦争の本質に関する知識は欠きながらも、自らの生まれ育った地を荒らす兇暴な戦争に抗議するために、沖縄県民がとりえた唯一つの態度だったのです。この合言葉の下に、多くの若い生命が惜しげもなく捨てられ、有為の人々がむざむざと非命に斃れてゆきました。・・・・・歴史の上で常に異民族ででもあるかのように扱われ『忠君愛国の志乏しき』ことを、ことごとにあげつらわれ、一種の劣等感、民族意識における特殊のコンプレックスをすら抱かされていた沖縄青少年にとって、『醜(しこ)の御楯(みたて)』たることに疑問を持つのは道徳に反することでした。沖縄戦は『吾々もまた帝国の忠良たる臣民である』ことを、身をもってあかしする格好の機会とすら考えられたのです」
今日から振り返れば、「帝国主義戦争の本質に関する知識は欠きながらも」の箇所は、敗戦直後という、左翼全盛期の痕跡として受けとめるのが妥当で、カッコに入れて読む方がよいでしょう。その手続きを経たうえでのことではありますが、これらの言葉は沖縄戦の最中の沖縄県民の心を忌憚なく吐露したものとして私たちの胸に迫ってきます。また、これらは、児島襄氏『太平洋戦争』の「沖縄戦の最後に勇戦したのは、本来の兵士を除けば、鉄血勤皇隊の少年たちだった」という言葉と符合しますし、「沖縄県民五七万人のうち、約一〇万人は島外に疎開し、老幼者の一部は北部に避難したが、大半の約三〇万人は南部に残り、多くは陣地構築、補給作業に従事した」というくだりにおける県民の秘められた心を明らかにしてもくれるような気がします。先に私が離島コンプレクスという言葉で舌っ足らずながらも言おうとしたのは、要するにそういうことだったのです。
ここで私の脳裏に、次の文章がおのずと浮かんできます。それは、一九四五年六月十三日に拳銃で自決した、海軍・沖縄方面根拠地隊司令官大田実少将が、その七日前の六月六日に、海軍次官に宛てた電文です。知っていらっしゃる方も少なくないのではないでしょうか。
沖縄県民斯(か)く戦えり
発 沖縄根拠地隊司令官
宛 海軍次官
左の電文を次官に御通報方取り計らいを得たし
沖縄県民の実情に関しては、県知事より報告せらるべきも、県には既に通信力なく、三二軍司令部また通信の余力なしと認めらるるに付き、本職、県知事の依頼を受けたるに非ざれども、現状を看過するに忍びず、これに代わって緊急御通知申し上げる。
沖縄島に敵攻略を開始以来、陸海軍方面、防衛戦闘に専念し、県民に関しては殆ど顧みるに暇(いとま)なかりき。
然れども、本職の知れる範囲に於いては、県民は青壮年の全部を防衛召集に捧げ、残る老幼婦女子のみが、相次ぐ砲爆撃に家屋と財産の全部を焼却せられ、僅(わず)かに身を以って軍の作戦に差し支えなき場所の小防空壕に避難、尚、砲爆撃下□□□風雨に曝されつつ、乏しき生活に甘んじありたり。
しかも若き婦人は、率先軍に身を捧げ、看護婦烹炊(ほうすい)婦はもとより、砲弾運び、挺身斬り込み隊すら申し出る者あり。
所詮、敵来たりなば、老人子供は殺されるべく、婦女子は後方に運び去られて毒牙に供せらるべしとて、親子生き別れ、娘を軍衛門に捨つる親あり。
看護婦に至りては、軍移動に際し、衛生兵既に出発し、身寄り無き重傷者を助けて□□、真面目にして、一時の感情に駆られたるものとは思われず。
さらに、軍に於いて作戦の大転換あるや、自給自足、夜の中に遥かに遠隔地方の住民地区を指定せられ、輸送力皆無の者、黙々として雨中を移動するあり。
これを要するに、陸海軍沖縄に進駐以来、終始一貫、勤労奉仕、物資節約を強要せられつつ(一部はとかくの悪評なきにしもあらざるも)ひたすら日本人としての御奉公の護を胸に抱きつつ、遂に□□□□与え□ことなくして、本戦闘の末期と沖縄島は実情形□□□□□□
一木一草焦土と化せん。糧食6月一杯を支うるのみなりという。沖縄県民斯く戦えり。県民に対し、後世特別の御高配を賜らんことを。
私が、この電文にはじめて接したのは、いまから十七年前、沖縄那覇市南部の小禄にある海軍壕においてでした。そのとき私は、一種名状し難い感情に襲われて、それをどういう言葉で表したらいいのか、皆目見当がつきませんでした。すっかり混乱してしまったのです。一語一語をかみしめるようにして読み進めると、おのずと熱いものがこみ上げてくるのです。大田少将自身、死の覚悟を決めたうえで、これだけは書き留めて残しておかなければ、死ぬに死ねないという、やむにやまれぬ切迫感に突き動かされて、これを書いているのではないかと思われます。
大田少将は、沖縄県民が日米軍の熾烈な戦いによって被っている、筆舌に尽くしがたい惨状を訴えているのでしょうか。「風雨に曝されつつ、乏しき生活に甘んじありたり」「一木一草焦土と化せん」とあるとおり、それを訴えているのも間違いないでしょう。しかし大田少将は、沖縄県民を戦争の被害者としてのみ描いているわけではありません。それらすべてを無言で引き受けて、命を供するようにして、それぞれの立場で沖縄戦を戦い抜く県民の姿に、太田少将は、畏敬の念すら覚えて、これを書き記したのではないでしょうか。「沖縄県民斯く戦えり」という一文には、少将の万感の思いが込められている。そう感じられます。死に臨み、太田少将は、あらためて県民の″『吾々もまた帝国の忠良たる臣民である』ことを、身をもってあかしする″という思いの深さと大きさに触れて、絶句する思いを味わったのではないかと思います。「沖縄島に敵攻略を開始以来、陸海軍方面、防衛戦闘に専念し、県民に関しては殆ど顧みるに暇なかりき」という書き出しの文には、いままでそのことにはっきりと気づかずにまことにかたじけないという少将の思いがおのずとにじみだしています。
「県民に対し、後世特別の御高配を賜らんことを」という言葉は、直接的には当時の海軍次官に向けられていますが、実は私たち本土の心ある人間すべてに向けられていると考えるよりほかにない、といまでは考えています。慌てて先回りしておきますが、私は、これを機に不戦の誓いを新たにしたいなどという寝ぼけた綺麗事を言いたがっているわけではありません。
ここからは、端的に、本土決戦を覚悟していたが結局は戦わなかった「やまとんちゅ」の末裔として話します。
沖縄県民は、本土の人々が潜在的に覚悟していた本土決戦を、沖縄の地で本当に戦い切ってしまったのです。そこには当然、集団自決をした人々も含まれます。親から頭を痛打されて絶命した赤ん坊も含まれます。そうして、沖縄県民に「一種の劣等感、民族意識における特殊のコンプレックス」があり、彼らが「沖縄戦は『吾々もまた帝国の忠良たる臣民である』ことを、身をもってあかしする格好の機会」と考えて戦い切ったのだとしても、彼らが「戦い切った」事実それ自体には、いささかの瑕疵も生じません。人間は、常に時代に制約された不完全な存在として、あることを成し遂げるのです。
では沖縄県民が、本土の人々が潜在的に覚悟していた本土決戦を、沖縄の地で本当に戦い切ってしまったことの意味とはいったい何なのでしょうか。それをうまく言い当てるには、大東亜戦争の本質について押さえておく必要があります。
私見によれば、大東亜戦争には、ざっくりと言ってしまえば、大きくふたつの意味があります。ひとつは、身も蓋もないパワー・ポリティクスとしての国際政治の、極限状況における姿としての近代戦争という意味です。これは、要するに強いほうが勝つというドラスティックな世界であって、時の政府と軍首脳が戦略的思考のありったけを振り絞って敵国に臨むべき世界です。この面で、日本が英米との戦いにおいてボロ負けの惨状を呈するに至ったことは、当論考の「その1」から「その3」までで、しつこいほどに申し上げました。
国際政治学者・高坂正堯氏が述べる、国家の三つの体系に即すならば、以上は、おもに「力の体系」と「利益の体系」に関わる領域であると一応言うことができるのではないでしょうか。
大東亜戦争には、もうひとつ、欧米と日本という歴史的にまったく異なるふたつの価値の体系の、避けようにもどうにも避け得なかった衝突、思想戦としての文明の衝突という意味があります。この戦いは、たかだか時の権力を手中にしたに過ぎない一政府によって担い切れるものではありません。心ある国民が民族の記憶のすべてを動員して担うよりほかにないものです。つまり、この戦いの主体は、共同体の良き伝統・慣習を体現した総体としての国民なのです。戦争において、時の権力者は、この「価値の体系」に関してあくまでも謙虚かつ禁欲的でなければなりません。それゆえ、″自分たちは、あくまでも、「力の体系」と「利益の体系」に関する責任を全うするに過ぎない″という自覚こそが、ノーブレス・オブリージュの根拠なのです。そこを踏み外すと、権力者は、醜くて情けない姿を晒すことになります。その典型例として、私は、大本営がサイパン島陥落の衝撃によって呆然自失状態になり、「残るは一億玉砕に依る敵の戦意放棄に俟つあるのみ」などと口走って、自分たちの失敗を国民の命を弄ぶことでカモフラージュしようとした事実を挙げました。だから、時の権力者にとって、戦争の義とはどこまでも無辜の一般国民の生命を守ることとのつながりにおいて存すると考えるべきなのです。それは、繰り返しになりますが、国家の「価値の体系」の側面に関して、時の権力者はあくまでも脇役に徹し、主役は、良き伝統や慣習それ自体であることを肝に銘じなければならない、ということでもあります。これは、″国家権力なるものは、国民道徳や道徳教育に容喙することにあくまでも慎重であるべきだ″という見解につながっていきます。むろん私は、そうあるべきだと考えています(このことがきちんと理解できない政治家や思想家を、私はあまり高く評価できません)。
以上のことから、戦争には、それにふたつの意味が存することに対応して、もうひとつの義があることに私たちは気づかされます。共同体の良き伝統・慣習を体現した総体としての国民が戦いの主体となる、思想戦としての文明の衝突において、無辜の一般国民の生命を守ることがすなわち戦争の義とは言い切れなくなるのです。この戦いにおいて、義を守る主体が、時の権力者から総体としての国民に移るのですから、そういうよりほかはありません。端的に言えば、この意味での戦争においては、国民がみずから自発的に命を賭けてでも戦い抜くことによって義を守る局面が存する可能性を排除できないのです。そうして、その局面が表面化し顕在化してきたのが、サイパン陥落を機に、軍首脳の戦略的思考の欠如に起因する総体としての戦争の失敗が誰の目にも明らかになってきた大東亜戦争末期なのでした。この場合、命を賭しても主体的に戦い抜くことそれ自体が、戦いの義そのものの様相を帯びることになります。なぜなら、共同体が長い時間をかけて培ってきた良き伝統・慣習なるものは、結局のところ言葉に表し得ないものとして存在するからです。
心ある国民は、そういう深刻な事態の現出を暗黙のうちに感じ取っていました。児島襄氏が『太平洋戦争』に、敗戦の色が濃厚になってきた状況下で「国民の多くは、一方で″諦観自棄″の風を生みながらも、最後の戦いの覚悟は捨てていなかった」と書き記しているのには、そういう意味があるのではないかと思われます。また、吉本隆明氏や桶谷秀昭氏が、必敗の悲惨な状況下でまったくひるまなかったのは、"自分は本土決戦で死ぬ"という覚悟が定まっていたからである、という意味のことを言っているのも、そのことと大いに関わりがあると、私は考えます。
長谷川三千子氏は、『神やぶれたまはず』に、吉本隆明氏の次の言葉を書き記しています。
戦後すぐに、児玉誉士夫と宮本顕治と鈴木茂三郎が大学に来て、勝手なことを講演して帰っていったことがあるんです。なかで、もっとも感心したのは児玉誉士夫の話で、米軍が日本に侵攻してきた時に日本人はみんな死んでいて焦土にひゅうひゅうと風が吹き渡っているのを見たら連中はどう思っただろう(笑)、と発言して、ああいいことを言うなと僕は感心して聞きました。
吉本氏はここで、自分を含めた日本国民が、思想戦としての大東亜戦争を戦い切った後の荒涼としていて底知れぬ迫力に満ちたイメージを、戦後においても心の奥底に存する、実現できなかったみずからの秘められた願望をそこに重ね合わせながら素直に語っています(こういう無類の率直さが、思想家・吉本氏の掛け値なしの美質です)。
ところが天皇の決断によって、日本国民は、本土決戦を目の前にしながらそれを戦う機会を永遠に失うことになりました。私は、そういう決断をした天皇を決して非難しようとは思いません。「おおみたから」としての国民を守るためのやむを得ざる現実的な決断であったと思っています。しかし、それが日本国民にとってきわめて大きな精神史的事件をもたらしたこともまた、確かなのです。つまり、そのことによって、国民の心のど真ん中にポッカリと虚ろな穴が空き、戦前と戦後がうまくつながらなくなってしまったのです。それが、敗戦トラウマの核心を成すものです。GHQのウォー・ギルド・インフォメーション・プログラムによって、それが強化されたことは確かですが、そういう洗脳政策を受け入れる精神状態があらかじめ十分に存在したことも確かなのです。
本土の人々は、精神的な空白状態と戦後のどさくさによって我を忘れ、沖縄の存在をすっかり忘れてしまったのです。それと同時に、沖縄県民が、あの小さな島で民族精神としての本土決戦を戦い抜くことによって、図らずも思想戦としての大東亜戦争の義を命がけで守り抜くことになったこともすっかり忘れてしまったのです。
本土の人々の情けないほどの健忘症によって精神的な孤立を余儀なくされた沖縄は、戦後、左翼勢力の巣窟となり、彼らの被害者史観が猖獗を極めることになります。大田実少将が訴えた沖縄県民の悲惨にして崇高な戦いぶりは、県民に寄り添ったふりをする連中によって、見事に泥塗られ貶められてしまったのです。
また、精神的な空白を抱えた本土では、その間隙を突くことで、いわゆる自虐史観が大手を振ってまかり通り、相も変わらず時代の支配思想で有り続けています。決定的な場面で義を貫けなかったという集合的記憶が、そういう病んだ歴史観を呼び寄せたのでしょう。つまり、敗戦トラウマを仲立ちにして、沖縄の被害者史観と本土の自虐史観とは、合わせ鏡の関係にあるのです。大江健三郎氏などは、そういう悲惨で病んだ精神状況にどっかりと胡座をかいて、ちょっと深刻ぶった表情をしてみせるだけで、けっこう大した力を発揮できたりしてしまうわけです。戦後民主主義とは、要するにそういうものです。
結論です。私を含めた本土の人々が、敗戦トラウマや自虐史観から脱却し、新たな歴史観を力強く未知の地平に切り開いてゆくには、沖縄県民が、あの小さな島でかつて思想戦としての大東亜戦争の義を命がけで守り抜いたという精神史的な、ある意味で神学的な事実を、一度は無条件に、素直に、全面的に、身体の隅々に行き渡るまで受け入れることが必須となります。これが、大田実少将が本土の人々に送ったメッセージに、いまの私が応えうるもののすべてであります。それは同時に、沖縄の人々が、病んだ被害者史観から脱却し精神的に自由になる道筋でもあることは言うまでもありません。なぜ、「ある意味で神学的」なのか。端的に申し上げましょう。沖縄戦における沖縄県民は、『旧約聖書』の「イサク奉献」におけるイサクそのものであるからです。その意味で沖縄戦は、イサク問題でもあるのです。これはこれで、きちんと話そうとするとけっこう長くなってしまうような気がしますので、未完の、『神やぶれたまはず』についての論考の続きを書くときにでも、あらためて触れようと思います。(この稿、終わり)












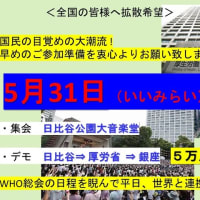
















あなたは、対馬の出身の方だったのですか。遠いむかしに何度か行ったことがあります。たしか浅茅湾のあたりに美津島町という地名があったような。
ずっと気になっている疑問があります。
対馬は朝鮮半島のすぐそばで、九州本土からは大きく離れていますよね。それで、どうして朝鮮にならなかったのでしょう。べつに日本政府が朝鮮から奪ったわけではない。
対馬に海の向こうから本格的に人がやって来るようになったのは、おそらく弥生時代以降のことだろうが、そのとき、九州からやってくることはあっても、朝鮮からはほとんど人が来なかったのでしょう。その後の時代でも、きっとそうだった。昔は、アイヌみたいな朝鮮集落というのがあったのですか。
つまり何が気になるかというと、弥生時代に朝鮮半島から対馬にやってきた人などほとんどいないということは、日本列島本土にはさらに少ないということですよね。そしたら、一般にいわれているような、弥生人は縄文人と朝鮮半島からやってきた人たちとの混血だという日本史の通説はどうなるのでしょう。渡来人のほうが多いといっている歴史家もいるけど、あんなもの大嘘でしょう。対馬にすらやってこられない人たちが、どうして大挙して本土にやって来ることができるのか。
考えられることは、日本から行った船が帰りに朝鮮半島の人を連れてきただけでしょう。弥生時代の日本列島に先進地域の朝鮮半島と交易できる品の何があったかといえば、人=女だけでしょう。それと交換に朝鮮半島の品物や技術者を持ち帰った。しかしそんな人の数なんか、たかが知れている。
あなたの沖縄玉砕の話をうかがってもつくづく思うのだけれど、日本人は死を賭してでも玄界灘を渡ってゆこうとするメンタリティや、新しいものや珍しいものと出会いたいという好奇心というか進取の気性を持っていたが、朝鮮半島や中国大陸の人は、そんな荒海を渡ってゆこうというような玉砕精神も、日本列島に対する好奇心もなかったのでしょう。
そのころの朝鮮半島の人々の意識は、日本列島よりも中国大陸に向いていた。中国大陸に移住していった人はたくさんいたのでしょう。
もしも弥生時代の日本列島にたくさんの渡来人がいたのなら、対馬なんか、ほとんど朝鮮半島の人ばかりになっていたんじゃないですか。そうしてことばも習俗もメンタリティも顔かたちも、どんどん朝鮮風になってゆく。古墳時代にはもう、完全に朝鮮というか百済の一部になっていてもおかしくありません。
でも、実際は、九州の人がどんどん住み着いていっただけじゃないのですか。
弥生時代は、文化的にも遺伝子的にも、一般的に考えられているほどには朝鮮半島の影響はなかったのではないのか。
それと、沖縄と対馬で、どちらが本土との言葉をはじめとする文化的落差が大きいかといえば、沖縄のほうでしょう。対馬はほとんど九州弁と変わらない。沖縄は、ことばも食べ物も、かなり違う。対馬の人もキムチを漬けるのですか。
沖縄が本格的に本土との関係を持ち始めたのが鎌倉時代以降だとしたら、対馬はもっと早くから交流していた。だから文化的に日本そのものである対馬の人は、歴史的にはあれこれの受難はあったにせよ、沖縄の人ほどの切実なアイデンティティの不安は持っていない。離島意識があるといっても、それは佐渡や隠岐の島とそう変わらないのだろうし。
しかし沖縄は、そうはいかない。地理的にも文化的にも、沖縄は沖縄以外の何ものでもない、というような部分がある。それでも彼らは、今も昔も、日本人であるほかない運命を背負って歴史を歩んでいる。あのとき、軍の命令で自決させられたというより、自分たちで自決したということのほうがもっと切実で悲劇的な何かがあるのでしょうね。
おそらく昔から沖縄の人にとっての本土は、「鬼(=侵略者)の棲む国」だったはずです。薩摩なんか、ずっと沖縄を植民地扱いし、搾取し続けてきた。それで儲けた金で明治維新をやった。それでも沖縄の人々は、日本人としての歴史を歩むほかなかった。何がなんでも「鹿児島県民」ではありたくなかったが、せつないほどに「日本人」になろうとしていた。
対馬は、日本人だと認めてもらえるなら、自分たちが行政的に長崎県民であろうと福岡県民であろうとどちらでもいいのだろうし、日本人だという自覚も、すくなくとも沖縄県民よりはスムーズに抱いている。しかし沖縄県民は、その「自覚」そのものの基盤が、対馬よりもずっと不安定なのではないでしょうか。人種的には日本人以外の何ものでもなく、氷河期の原日本人の末裔に違いないのだが、歴史・文化的には本土とはずいぶん異質になってしまっている。本土の住民も、沖縄県民自身も、その異質性は意識している。
江戸時代までの沖縄は、たぶん本土の植民地だった。薩摩は、沖縄をそのように扱ってきた。
沖縄には「海の向こうには<にらいかない>の国がある」という言い伝えがある。柳田國男も折口信夫も、この「にらいかない」を、神の住む理想郷のことだとずっといっていました。そうでしょうか。僕にはこの言葉の語感からは「おっかなくてわけがわからない」というニュアンスしか受け取れません。台風のことを「にらいかない」から吹いてくる風だといったり、「にらいかない」の神に祈る祭りをするといっても、「どうか怒らないでくれ、暴れないでくれ」と祈っていたのかもしれない。
「にら」は、「にらむ」の「にら」、「韮(にら)」はとても癖の強い植物です。「かな」は親密な感慨をあらわすことばだが、「い」がついているということは、もともとは「かなわない」というその否定の表現だったのかもしれない。たとえば「にらかなない」が音変化したということも考えられます。まあ語源的な証明は難しいが、沖縄にとっての海の向こうの本土に対する思いがどれほど屈折してやるせないものだったかということの歴史的な痕跡はいくらでもあるはずです。ただ無邪気にあこがれてきただけじゃない。
日本列島の祭りのコンセプトは、基本的に「魂鎮め」ですからね。極楽浄土を賛美する、というような祭りはほとんどない。沖縄だろうと本土だろうと最終的にはどんちゃん騒ぎの賑わいになってゆくから、何か極楽浄土を賛美しているように見えるが、そうじゃない。日本人の本心は極楽浄土なんか信じていないし、よくわからない。ただ、人の心は、「もう死んでもいい」と生きてあることを嘆ききるところから華やいでゆくのですね。そうやって日本列島の祭りのダイナミズムが生まれてくる。まあそれだけのことなのに、折口信夫なんか、ここに海の向こうの極楽浄土(まれびとの国)をあこがれ賛美する祭りがある、これが日本の祭りの原点だ、とはしゃぎまくっていた。ほんとに、何をくだらないことをほざいてやがる、と思います。そんなおためごかしのへりくつで沖縄の人々の歴史感情が解き明かせるものかと思います。江戸時代以前の沖縄の人々がこの「にらいかない」ということばにどんな思いをこめてきたのか。そこのところを再検証する義務が本土の人間にはあると思えます。あの戦争で沖縄玉砕に追いつめてしまった当事者として、その「魂鎮め」として。
折口信夫の傲慢で独善的な解釈はひとまず白紙に戻して再検証しないといけない。あなたが大江健三郎の「沖縄ノート」なんかとんでもなく愚劣な書きざまだとおっしゃるのと同じ意味で、折口信夫の「まれびと論」をはじめとする民俗の起源論なんてほんとにどうしようもなく愚劣でいかがわしいものばかりで、折口信夫を屠り去ることができなければ日本の民俗学ははじまらないとも僕は思っています。
長文のコメントをありがとうございます。いまは、当方、激務の最中にあり、まともな返事を書く余裕がありません。仕事が終わってバタンキュウ、の日々が続いております。いましばらくのご猶予を。
あなたの長文のコメントを何度か読み返してみました。どうやらあなたは、私が自分の出身地である対馬を引き合いに出して、沖縄の人々の心がよく分かると言いたげなのが気に入らないようですね。「おまえなんぞに、沖縄の人々の悲しみや苦しみなど、分かるはずがない」と。私は、あなたの文章を読んで、そう受けとめました。またぞろ新手の被害者史観か、とため息をついているというのが、正直なところです。
個人的なことに話が及びます。私には、沖縄出身の親友がいます。彼は無類に率直な人で、酔っ払うと両手を挙げて「天皇陛下、万歳!」と叫ぶ人です。ほかの客がいる店内で何度それを制止したことでしょうか。また彼は、繊細な神経の持ち主でもあります。博覧強記の人なのですが、どこかそのことに対してさえも恥じらいの念を抱いているようです。それをひけらかそうなどとは夢にも思っていないことでしょう。
彼は、いちども所帯を持ったことがありません。おそらく女性とつきあったこともないのではないか。彼は、ひとりの女を愛するかわりに、家族と沖縄をこよなく愛した人です。
そんな彼が、突然この世からいなくなった。そう、今年の三月に死んでしまったのです。しかしながら不思議なことに、いまでも彼の存在感は、そっくりそのまま残っています。彼の現身が失われた代わりに、彼の精霊のようなものがどうやら私の心に棲みついてしまったようなのです。彼には、言いたかったことや言うべきことがたくさんあった。それを抱えこんだままあの世へ逝った彼の無念が、我がことのように感じられるのです(そう言うと、彼がまるで怨念の人のように思われるかもしれませんが、私には、彼の、あの沖縄の海のような透明な笑顔しか浮かんできません)。
沖縄に関する私の一連の文章は、わが身に棲みついた彼に「どうだ?これでいいのか?こういうことが、あなたはいいたかったのか?」とていねいにひとつひとつ尋ねながら書き進められたものです。対馬の話も、そのなかで出てきたものです。友との私なりの真摯なやりとりに“俺様は、沖縄のことがよく分かる″などという怠惰な思いが介在する余地などない。
だから、あなたのような言い方をされると、率直にいえば、とても不愉快になります。政治主義的な垢まみれの手で、やわらかい心を鷲掴みにされたような不快感を抱いてしまうのです。おそらくこの感触は、ほかの話題に関することでも、変わらないと思います。あなたは、政治主義とはとても遠いところで、ものごとを本質的に考えているおつもりなのかもしれませんが、残念ながら、私の目にはそう映りません。
そういうわけで、私は、あなたのコメントには今後応えないことにします。あなたが、このコメントに返事を書くのはかまいません(長すぎるのはかんべんしてください)が、罵詈雑言の類と私が判断すれば削除することをご容赦願います。
自分が沖縄や沖縄の人のことをよくわかっていると思ったことなど一度もありません。では、このページの読者が、はたしてあなたのおっしゃるとおりにこれはあなたへの批判だと受け取ったでしょうか。
僕は、僕が考えるこの問題をあなたがどう展開してくれるだろうか、と期待しただけです。あなたに対する批判なんか、これっぽちもありません。対馬のことであろうと沖縄のことであろうと、あなたのほうがはるかによくわかっておられるという前提で書いたつもりです。僕には、相手はどんな人間かとか相手にどんな意図(下心)があるかということなどよくわかりません。ただ、その文脈から浮かんでくる問題について考えることができるだけです。ここでは「対馬とは何か」「沖縄とは何か」ということについてあなたに聞きたかったのだから、せめてどこがどうだめなのか教えて欲しかったです。しかしまあ僕のような自他共に認める政治オンチが「おまえは政治的な人間だ」といわれたのは生まれてはじめてのことで、少々面食らっています。