【書き込みを読んで】
<Unknown (Unknown):2015-02-24 02:30=
解決おめでとうございます。中腎でしたか。ヒトの腎臓は濾過以外に血圧を調整する機能も持ちますが、海の中のお魚にはそういう機能は必要なさそうです。いつ進化したのでしょうね。陸にあがった時(両生類か爬虫類)でしょうか。>
これについては岩堀修明『図解・内臓の進化』(講談社ブルーバックス、2014/2)がとても分かりやすく説明しています。(Fig.4 腎臓の進化)
 (Fig.4)
(Fig.4)
前腎は基本的に環形動物であるミミズの「腎管」に似ていて、ミミズでは腎管の外への排泄孔が体節毎にあるのに対して、前腎では「ウォルフ管」につながっているのが違うようです。
脊椎動物では前腎は発生途中で退化し、魚類・両生類では中腎が主体となるそうです。
これは糸球体がボーマン囊の中におさまっており、ユニット構造は後腎と同じですが、体節構造を残していて、前後に細長いのが特徴です。このため缶詰のイワシでは、茶褐色の細長いひも状体として認められ、寄生虫では?と疑ったわけです。
後腎が出現するのは爬虫類になってからで、鳥類、哺乳類は後腎が尿排泄の主な器官です。
ヒトでは前腎、中腎は発生途中には形成され一時的に機能するけれども、発生6週目に後腎形成がはじまり、3ヶ月目に尿産生を初め、前腎、中腎は相継いで退化してしまうとあります。
尿の大きな使命は余剰窒素の体外排泄にあります。
魚類はアンモニアの段階で窒素を排泄する。アンモニアは水溶性なので、鰓や体表からも排泄され、高度の機能をもつ後腎でなくても、中腎で間に合うわけでしょう。アンモニアは毒性が強いので、大量の水分で薄める必要があります。このため水中生活をする動物には適しています。軟骨魚のサメは血中にアンモニアを含んでいるので、肉が腐りにくいのです。
私は中国山地の僻村で育ったのですが、子どもの頃の刺身はこのサメ(フカ)肉で、土地の人は「ワニ」と呼んでいました。「因幡の白ウサギ」に出てくるワニは「鰐ざめ」のことです。江川水系沿いの村々は、広島県でも物流的には日本海側の港町と結ばれていました。(広島県の北部は江川水系に属し、南半分が瀬戸内水系に属します。いま住んでいる福富町は両者の分水嶺地帯で、「県央の森」というのがあります。)
ワニの刺身は、少し異臭がある刺身でしたが、タイとかヒラメとかそんなものは生ではとうてい食べられない地域なので、田植えの「ドロ落とし」と称して開かれる宴会の末席で、ワニの刺身が食べられるのが楽しみでした。
爬虫類と鳥類は尿酸のかたちで残余窒素を排泄します。尿酸はほとんど毒性も溶解性もないので、水で薄める必要がない。このため、空を飛ぶ鳥や砂漠で暮らす爬虫類は、大量の水を飲む必要がありません。その代わり鳥はこういう糞をし、尿酸性の白い尿が付着しています。((Fig.5)
 (Fig.5)
(Fig.5)
血中のアンモニアは肝臓で二酸化炭素と結合して尿素になります。(肝硬変患者の末期に息がアンモニア臭を帯びるのは、尿素形成ができなくなるからです。サメと同じ窒素代謝になる。)
尿素は毒性が少なく、水溶性なので、哺乳類はこの形で残余窒素を大量の尿として排泄します。ソラ豆型をした人間の腎臓が一日に沪過する血液の総量は150Lで、その水分の99%は再吸収され、わずか1%、1.5L程度が1日尿量となります。
これで血中の毒素がクリアされるのですが、人工透析患者はこれを透析装置でやるので、効率が悪く、1回4時間、週3〜4回の血液透析が必要となるわけです。
私の場合、N先生が送ってくれたネスカフェ・ゴールドブレンドに、武田さんのお布施のパルスィートを入れて、1杯200mlのコーヒーを1日10杯、2L飲んでいますから、毎日の尿量は2L以上あります。仕事場西の草原は、私の散水場兼自然観察の場です。
<Unknown (Unknown):2015-03-03 17:50
>黄色い丸い斑点と思っていたが、こうして見ると橙色で、体表に膨隆しており、寄生虫の卵のようにも見える。
平均棍では?>
永野為武『生物学用語辞典』(三共出版、1972)を引いてみたら「平均棍(balancer)」という用語がありました。で、Balancerを見たら「双翅類の昆虫では後翅は退縮して、太鼓のばち状をしている。それが飛翔の際に、体の平衡を保つのに役立つ。一種の感覚器官」とあった。
『岩波生物学辞典・第5版』(岩波書店、2013)には、平均棍(Haltere)=「双翅類の昆虫に後翅の退化・変形産物としてそなわる棍棒状の可動体」とあります。
Halteresについては英語WIKIにFig.6がありました。
 (Fig.6)
(Fig.6)
バックスバウム『背骨のない動物』(シカゴ大学版、ペンギンブック版)は、ともに同じ写真を用いていて、白黒写真です。(Fig.7はペンギンブックから)
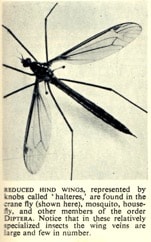 (Fig.7)
(Fig.7)
永野の「用語辞典」には「平均棍=昆虫の感覚器」としか書いてありません。(永野は東北大動物学の教授、故人)
「American College Dictionary」には、「ラテン語由来。通常複数形のhalteresで使用」とあります。
「岩波生物学辞典」には「平均体=Balancer」という項目が載っていて、「平均桿、平衡桿。有尾両生類の眼と鰓の間の、頭部左右側壁に見られる外胚葉性の棒状突起。尾芽期幼生で生じ、変態に先立ち退化する」とあります。(Fig.8)
 (Fig.8)
(Fig.8)
以上の記述から、オタマジャクシでは「平均体」ないし「平均桿」またはバランサーといい、後翅の退化した双翅目の昆虫類では、ハルテーレないし「平均棍」と呼ぶようです。「棍」と「桿」、まぎらわしいですね。永野の辞典の記載では、両者の混同が見られるようです。
「研究社・羅和辞典」にはHalterは「1.跳躍用のおもり、2.<動>平均棍」と載っていますが、この「跳躍用のおもり」というのが私にはわかりません。
両生類のバランサーの発生についてネット検索をしたら、NIHのサイトに面白い実験図がありました。http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9993/
 (Fig.9)
(Fig.9)
カエルの嚢胚から将来バランサーになる部分をイモリ嚢胚に移植すると、そこにカエルの吸盤ができ、イモリの嚢胚部分をカエルの嚢胚に移植すると、イモリのバランサーが出来るそうです。(図4)この辺の溜池でイモリの幼生やオタマジャクシを捕まえると、簡単に観察できるので、今年はイモリの平均体とオタマジャクシの吸盤を、実際に見てみたいと思います。
だが、これらの双翅目に見られるハルテーレは、シロホンのばちのような構造をしており、ショウジョウバエに認められた橙色の半球状突出物とは異なるように思いました。(Fig.10)
 (Fig.10)
(Fig.10)
ただ、私はその場で「あ、これは異物だ」と思い、寄生虫卵を考えたので(これが病理学者の悪いクセ)、反対側に対をなして存在していないことを確認していませんので、Unknownさんの説を否定するだけのエビデンスがありません。次回またショウジョウバエを見つけたら、再実験して確認したいと思います。
Unknownさん、ご教示ありがとうございました。
<追記>3/8(日)の夕方、生ゴミ捨て場に今年初めての「ユスリカの蚊柱」が立っているのを認めた。手を叩いたら、うまく1匹が採取できたのでUSB顕微鏡でさっそく観察した。胸節の翅の下に長さ0.1ミリ(100ミクロン)くらい(顕微ルーペでの実測)のドラム・スティック状の「平均棍(ハルテーレ)」を認めた。左右一対あった。(Fig.11)これは写真1,2と一致しています。
 (Fig.11)
(Fig.11)
だが、これは先端部が黒く、橙色のドーム状に見えるショウジョウバエのものとは違うかも知れない。
< Unknown (Unknown):2015-03-05 00:42=
>Habsburg(ハプスブルグ家)(ブルク=町、ハプス=持つ、で「町持ち」の意)
burgは町(城市)ですが、HabsはHabicht(鷹)に因んで名付けられたという説が有力です。http://en.wikipedia.org/wiki/Habsburg_Castle >
ご指摘ありがとうございました。英語WIKIには、
<It is believed that he named the castle after a hawk (German: Habicht) seen sitting on its walls. Some historians and linguists believe the name may come from the Middle High German word 'hab / hap' meaning ford, as it is located near a ford of the Aar River.>
とありますね。私はFordという言葉は固有名詞だとばかり思っていましたが、「川の浅瀬」という意味もあるのですね。
私は「鷲・鷹」のことはドイツ語で「アドラー(Adler)」というものとばかり思っていました。
「American College Dictionary(ACD)」には、「Habichtsburg (hawk’s castle)の短縮形, アールガウ, スイスにある城に由来」とあります。「アメリカーナ」の記載も同様です。
ただ「白水社・独和言林」によると、Haben(持つ、掴む)とHabicht(鷹)は、同根だそうです。
鷹が獲物を掴みあげるところから来ているようです。英語のHawkはゲルマン語のHabichtが古英語でHafocになり、中世英語でHauk(e)に変わって生じたとACDにあります。
言葉の起源は面白いですね。まさかあのハプスブルグ家の発祥の地が高地スイスにあるとは思わなかった。これで、「なぜ高地ドイツ語が低地ドイツ語を置換して、標準ドイツ語になったか」という、かねてからの疑問も解けました。
ハプスブルグ家が根拠地をオーストリアのウィーンに移し、「神聖ローマ帝国」として、スペインや地中海の島まで支配した時代に、高地ドイツ語が広まったのですね。
日本でも「白鷺城」とか「烏城」という異名を持つ城がありますから、「鷹の城(ハビヒツブルグ)」という名称からハプスブルグ家の家名が起こったという説は説得力がありますね。
Unknownさんのご指摘で、これらが理解できました。ありがとうございました。
<Unknown (Unknown):2015-02-24 02:30=
解決おめでとうございます。中腎でしたか。ヒトの腎臓は濾過以外に血圧を調整する機能も持ちますが、海の中のお魚にはそういう機能は必要なさそうです。いつ進化したのでしょうね。陸にあがった時(両生類か爬虫類)でしょうか。>
これについては岩堀修明『図解・内臓の進化』(講談社ブルーバックス、2014/2)がとても分かりやすく説明しています。(Fig.4 腎臓の進化)
 (Fig.4)
(Fig.4)前腎は基本的に環形動物であるミミズの「腎管」に似ていて、ミミズでは腎管の外への排泄孔が体節毎にあるのに対して、前腎では「ウォルフ管」につながっているのが違うようです。
脊椎動物では前腎は発生途中で退化し、魚類・両生類では中腎が主体となるそうです。
これは糸球体がボーマン囊の中におさまっており、ユニット構造は後腎と同じですが、体節構造を残していて、前後に細長いのが特徴です。このため缶詰のイワシでは、茶褐色の細長いひも状体として認められ、寄生虫では?と疑ったわけです。
後腎が出現するのは爬虫類になってからで、鳥類、哺乳類は後腎が尿排泄の主な器官です。
ヒトでは前腎、中腎は発生途中には形成され一時的に機能するけれども、発生6週目に後腎形成がはじまり、3ヶ月目に尿産生を初め、前腎、中腎は相継いで退化してしまうとあります。
尿の大きな使命は余剰窒素の体外排泄にあります。
魚類はアンモニアの段階で窒素を排泄する。アンモニアは水溶性なので、鰓や体表からも排泄され、高度の機能をもつ後腎でなくても、中腎で間に合うわけでしょう。アンモニアは毒性が強いので、大量の水分で薄める必要があります。このため水中生活をする動物には適しています。軟骨魚のサメは血中にアンモニアを含んでいるので、肉が腐りにくいのです。
私は中国山地の僻村で育ったのですが、子どもの頃の刺身はこのサメ(フカ)肉で、土地の人は「ワニ」と呼んでいました。「因幡の白ウサギ」に出てくるワニは「鰐ざめ」のことです。江川水系沿いの村々は、広島県でも物流的には日本海側の港町と結ばれていました。(広島県の北部は江川水系に属し、南半分が瀬戸内水系に属します。いま住んでいる福富町は両者の分水嶺地帯で、「県央の森」というのがあります。)
ワニの刺身は、少し異臭がある刺身でしたが、タイとかヒラメとかそんなものは生ではとうてい食べられない地域なので、田植えの「ドロ落とし」と称して開かれる宴会の末席で、ワニの刺身が食べられるのが楽しみでした。
爬虫類と鳥類は尿酸のかたちで残余窒素を排泄します。尿酸はほとんど毒性も溶解性もないので、水で薄める必要がない。このため、空を飛ぶ鳥や砂漠で暮らす爬虫類は、大量の水を飲む必要がありません。その代わり鳥はこういう糞をし、尿酸性の白い尿が付着しています。((Fig.5)
 (Fig.5)
(Fig.5)血中のアンモニアは肝臓で二酸化炭素と結合して尿素になります。(肝硬変患者の末期に息がアンモニア臭を帯びるのは、尿素形成ができなくなるからです。サメと同じ窒素代謝になる。)
尿素は毒性が少なく、水溶性なので、哺乳類はこの形で残余窒素を大量の尿として排泄します。ソラ豆型をした人間の腎臓が一日に沪過する血液の総量は150Lで、その水分の99%は再吸収され、わずか1%、1.5L程度が1日尿量となります。
これで血中の毒素がクリアされるのですが、人工透析患者はこれを透析装置でやるので、効率が悪く、1回4時間、週3〜4回の血液透析が必要となるわけです。
私の場合、N先生が送ってくれたネスカフェ・ゴールドブレンドに、武田さんのお布施のパルスィートを入れて、1杯200mlのコーヒーを1日10杯、2L飲んでいますから、毎日の尿量は2L以上あります。仕事場西の草原は、私の散水場兼自然観察の場です。
<Unknown (Unknown):2015-03-03 17:50
>黄色い丸い斑点と思っていたが、こうして見ると橙色で、体表に膨隆しており、寄生虫の卵のようにも見える。
平均棍では?>
永野為武『生物学用語辞典』(三共出版、1972)を引いてみたら「平均棍(balancer)」という用語がありました。で、Balancerを見たら「双翅類の昆虫では後翅は退縮して、太鼓のばち状をしている。それが飛翔の際に、体の平衡を保つのに役立つ。一種の感覚器官」とあった。
『岩波生物学辞典・第5版』(岩波書店、2013)には、平均棍(Haltere)=「双翅類の昆虫に後翅の退化・変形産物としてそなわる棍棒状の可動体」とあります。
Halteresについては英語WIKIにFig.6がありました。
 (Fig.6)
(Fig.6)バックスバウム『背骨のない動物』(シカゴ大学版、ペンギンブック版)は、ともに同じ写真を用いていて、白黒写真です。(Fig.7はペンギンブックから)
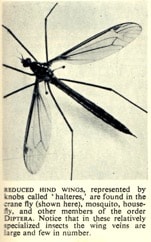 (Fig.7)
(Fig.7)永野の「用語辞典」には「平均棍=昆虫の感覚器」としか書いてありません。(永野は東北大動物学の教授、故人)
「American College Dictionary」には、「ラテン語由来。通常複数形のhalteresで使用」とあります。
「岩波生物学辞典」には「平均体=Balancer」という項目が載っていて、「平均桿、平衡桿。有尾両生類の眼と鰓の間の、頭部左右側壁に見られる外胚葉性の棒状突起。尾芽期幼生で生じ、変態に先立ち退化する」とあります。(Fig.8)
 (Fig.8)
(Fig.8)以上の記述から、オタマジャクシでは「平均体」ないし「平均桿」またはバランサーといい、後翅の退化した双翅目の昆虫類では、ハルテーレないし「平均棍」と呼ぶようです。「棍」と「桿」、まぎらわしいですね。永野の辞典の記載では、両者の混同が見られるようです。
「研究社・羅和辞典」にはHalterは「1.跳躍用のおもり、2.<動>平均棍」と載っていますが、この「跳躍用のおもり」というのが私にはわかりません。
両生類のバランサーの発生についてネット検索をしたら、NIHのサイトに面白い実験図がありました。http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9993/
 (Fig.9)
(Fig.9)カエルの嚢胚から将来バランサーになる部分をイモリ嚢胚に移植すると、そこにカエルの吸盤ができ、イモリの嚢胚部分をカエルの嚢胚に移植すると、イモリのバランサーが出来るそうです。(図4)この辺の溜池でイモリの幼生やオタマジャクシを捕まえると、簡単に観察できるので、今年はイモリの平均体とオタマジャクシの吸盤を、実際に見てみたいと思います。
だが、これらの双翅目に見られるハルテーレは、シロホンのばちのような構造をしており、ショウジョウバエに認められた橙色の半球状突出物とは異なるように思いました。(Fig.10)
 (Fig.10)
(Fig.10)ただ、私はその場で「あ、これは異物だ」と思い、寄生虫卵を考えたので(これが病理学者の悪いクセ)、反対側に対をなして存在していないことを確認していませんので、Unknownさんの説を否定するだけのエビデンスがありません。次回またショウジョウバエを見つけたら、再実験して確認したいと思います。
Unknownさん、ご教示ありがとうございました。
<追記>3/8(日)の夕方、生ゴミ捨て場に今年初めての「ユスリカの蚊柱」が立っているのを認めた。手を叩いたら、うまく1匹が採取できたのでUSB顕微鏡でさっそく観察した。胸節の翅の下に長さ0.1ミリ(100ミクロン)くらい(顕微ルーペでの実測)のドラム・スティック状の「平均棍(ハルテーレ)」を認めた。左右一対あった。(Fig.11)これは写真1,2と一致しています。
 (Fig.11)
(Fig.11)だが、これは先端部が黒く、橙色のドーム状に見えるショウジョウバエのものとは違うかも知れない。
< Unknown (Unknown):2015-03-05 00:42=
>Habsburg(ハプスブルグ家)(ブルク=町、ハプス=持つ、で「町持ち」の意)
burgは町(城市)ですが、HabsはHabicht(鷹)に因んで名付けられたという説が有力です。http://en.wikipedia.org/wiki/Habsburg_Castle >
ご指摘ありがとうございました。英語WIKIには、
<It is believed that he named the castle after a hawk (German: Habicht) seen sitting on its walls. Some historians and linguists believe the name may come from the Middle High German word 'hab / hap' meaning ford, as it is located near a ford of the Aar River.>
とありますね。私はFordという言葉は固有名詞だとばかり思っていましたが、「川の浅瀬」という意味もあるのですね。
私は「鷲・鷹」のことはドイツ語で「アドラー(Adler)」というものとばかり思っていました。
「American College Dictionary(ACD)」には、「Habichtsburg (hawk’s castle)の短縮形, アールガウ, スイスにある城に由来」とあります。「アメリカーナ」の記載も同様です。
ただ「白水社・独和言林」によると、Haben(持つ、掴む)とHabicht(鷹)は、同根だそうです。
鷹が獲物を掴みあげるところから来ているようです。英語のHawkはゲルマン語のHabichtが古英語でHafocになり、中世英語でHauk(e)に変わって生じたとACDにあります。
言葉の起源は面白いですね。まさかあのハプスブルグ家の発祥の地が高地スイスにあるとは思わなかった。これで、「なぜ高地ドイツ語が低地ドイツ語を置換して、標準ドイツ語になったか」という、かねてからの疑問も解けました。
ハプスブルグ家が根拠地をオーストリアのウィーンに移し、「神聖ローマ帝国」として、スペインや地中海の島まで支配した時代に、高地ドイツ語が広まったのですね。
日本でも「白鷺城」とか「烏城」という異名を持つ城がありますから、「鷹の城(ハビヒツブルグ)」という名称からハプスブルグ家の家名が起こったという説は説得力がありますね。
Unknownさんのご指摘で、これらが理解できました。ありがとうございました。




























http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail_3628.html
亡くなった笹井先生が研究されていた発生生物学の大御所の浅島誠先生がコメンテーターとして登場なさっていました。
来月より、文科省による新しい研究不正ガイドラインが運用され、大学・大学院で研究倫理の授業などの導入が始まるそうです。