【修復腎移植ものがたり(12)巨大な腎動脈瘤】
光畑直喜は1980年4月に岡山大から呉共済病院泌尿器科に赴任した。当時の科長は石(せき)正臣は名医の評判がたかく、朝の5時から受付待ち患者が病院の通用門に行列をつくり、開門を待った。2時間待ち3時間待ちはざらで、番取りの代行屋が出るほどだった。その石の下で光畑は鍛えられた。だが石は腎移植には関心を示さなかった。
光畑が廉介に誘われ宇和島で男の腎移植を見学し、その腕にしびれたのは翌年のことだ。以来、廉介の代行で移植術の助手として宇和島に通い、移植の腕を磨いた。やがてそれが役立つ日が来た。石が呉市内に開業し、患者をごっそりさらって行ったのだ。
当時の院長は岡田敬成といい、岡山医専の卒業で内科部長から院長になった。内科医長時代は「鬼軍曹」と呼ばれ、院長になってからは「天皇」とあだ名されていた。「モーレツ」という言葉と連続テレビドラマ「コンバット」が流行っていた時代だった。
天皇は「日経メディカル」を愛読し、新医療技術の導入に積極的だった。人工腎臓もはやくから導入し、内科には慢性透析の患者が洪ふれかえっていた。光畑にとって腎移植を開始するチャンスだった。彼が最初の腎移植をおこなったのは86年5月で、宇和島で腎移植の助手を最初につとめてから5年がたっていた。
宇和島から来た男が執刀して最初の腎移植が行われ、テレビや新聞が「呉市初の腎移植」と大きく報じた。喜んだ天皇が「皆で一杯やってくれ」と金一封をくれた。中に諭吉が十人いた。その頃の大卒初任給の半分よりも多かった。呉での腎移植はめったになかったが、それでも四人組の結束はかたく、移植の際には手伝いに来てくれた。
90年の暮、光畑は内科からまわってきた患者、三宅謙一(75歳)の左腎臓に、直径4.8センチの大きな腎動脈瘤(りゅう)があるのを見つけた。指三本を合わせたほどの太さがあり、いつ破裂してもおかしくなかった。普通の動脈瘤は径2センチになるまでに、高血圧、血尿、腰痛というトリアス(三徴候)がでる。
老人は千葉習志野市に住む農民で、呉市にいる息子を訪ねた際につよい左腰痛を訴え、「市民の病院」という定評がある呉共済病院に受診をすすめられたのだった。内科で高血圧と顕微血尿(ミクロヘマチュリア)を発見され、光畑に回されたのだ。不思議なことに、腎門部にあるこの巨大な動脈瘤は、血管造影(アンギオ)をしても内腔が造影されなかった。内部が充実性であるのなら、後腹膜腫瘍の可能性もあるということだ。
「一日でも早く家に帰りたい」という本人のつよい希望があった。
春の種まきは待ってくれないのだ。そこで手術時間が短くて済み、より安全な全摘術を行うことをすすめた。
その時、ふと光畑の脳裏に慢性糸球体腎炎から腎不全になり透析を続けている、まだ若い呉市職員三原(44歳)の顔が浮かんだ。最初、妻からの腎移植を検討したが、血液型が一致せず実行できなかった。死体腎の移植も一度試みたが、摘出した腎臓の状態が悪く中止せざるをえなかった。同僚の冷ややかな目を浴びながらの週3回の透析はつらく、三原は精神的にも落ちこんでいた。このままでは休職から失職へとつながるのは目にみえていた。
ドナーがいないこの患者の血液型はB型で、腎全摘を希望した老人と一致していた。
「何とかあの腎臓が移植に使えんものかのう…」
光畑はこれまで正常な腎臓しか移植したことがなかった。「親族間腎移植」では血管の奇形や小さな動脈瘤がある腎臓の病変部を切除し、修復した後で移植に用いられた例があることは、移植学会での演題や学会誌で知っていた。だが径4.8センチという巨大な腎動脈瘤を切除した後に、移植に使用できるとはとても思えなかった。宇和島に電話してCTとアンギオによる動脈瘤の状態を詳しく話し、男の意見を求めた。
男は飛び降り自殺したムラキサトコのことをよく覚えていた。あの悲劇を二度と繰り返してはならない。だがこれは特発性腎出血とは違う。動脈瘤を切除し、腎動脈を修復する外科的な技術だけが問題になる。移植さえうまく行けば後の問題はないはずだ。
かつて免疫抑制剤のため日和見感染により死亡した、コウノタダシのことも思い出した。あれは1981年、二度目のウィスコンシン詣でをやり、新免疫抑制剤サイクロスポリンを導入することで再発を防いだ。
「男はやってやって、やり抜け!」
酒気帯び運転のトラックに正面衝突され、後部エンジン搭載のフォルクスワーゲンに乗っていたばかりに、ほとんど即死状態で無念の死をとげた内科医の父の言葉が聞こえたように思った。
「やれるじゃろう…」男はぽつりといった。
光畑には寡黙な男のその一言が頼もしかった。
年が明けると、急いで双方の患者の同意を得て必要な検査を終え、「病腎移植」が行われた。91年1月25日に行われたこの手術には、光畑と泌尿器科医員の那須と渡辺の他に、宇和島の男と岡山協立病院にいた弟の廉介が参加した。
この手術では男が腎摘出にまわった。アノイリスム(動脈瘤)のある左腎臓を摘出し、この巨大な動脈瘤を切除して、移植に使えるように血管を修復する技術は男にしかない。
普通の腎手術では側腹部切開で腹を開ける。だが後腹膜腫瘍の可能性があるこの患者では、正中切開で腎臓にアプローチする方法が採用された。万一の場合に備えて、手術野をひろく確保し、大動脈に沿う後腹膜リンパ節などをチェックするためだ。腎臓を包む脂肪膜を剥離して、腎動脈から西洋梨型にとび出している巨大な動脈瘤にさわった。なんと中が固い。普通の動脈瘤ではない。
「だから光畑がアンギオで中が写らないといったのか…」と男は思った。
内腔に血流があれば当然、血管造影で写る。こうなると腫瘍の可能性もある。男は急いで腎動脈、腎静脈を結紮し、尿管も結紮して、メスで切断して腫瘤ごと腎臓を取り出した。幸い大動脈から腎動脈が分岐したすぐのところに、細い筒形をした腫瘤付着部があり、良性なら切除後の動脈修復は何とか可能で、移植可能だと男は判断した。
首の付け根のところで、腫瘤を切除した。形は小さな風船に似ていて、重さは小ぶりの鶏卵ほどもあった。立ち会っていた光畑が、さわって形や堅さを確かめた。視診・触診では腫瘍としか思えない。外科トレイに移すと、「大至急」で手術場ナースに病理検査部に持って行かせた。
病理検査部では病理専門医の佐木が待機していた。佐木は腎移植が可能かどうかの判断は、自分の病理診断にかかっていることを知っていた。強いストレスで血中にアドレナリンが充満し、やり甲斐を感じていた。受付の折原が手早く受付番号を付与し、台帳に記入し、印字機で受理番号を「91−○○○○」と色テープに印字し、検査技師の後田にトレイごと渡した。彼は写真撮影台に腫瘤を載せ、テープを貼ったスケールをそばに置き、すばやく撮影をすませた。
佐木はビニール手袋をつけると、ピンクの卵に似た、長さが5センチちかい大きな腫瘤をよく触り、腫瘍が疑われる部分をメスでくさび形に切り出し、ピンセットでつまむと後田技師が手に載せたガーゼに落とし、迅速標本を頼んだ。それから腫瘤の計測と肉眼所見の観察を始めた。佐木の口述を医療秘書の資格を持つ折原が「摘出臓器肉眼所見」用紙に書き取った。腎門部にあった動脈腫瘤の表面は薄い赤みを帯び、鶏卵状で、長径が48ミリ、短径が35ミリ、重さが25グラムもあった。幅がやや細くなった長軸の端に、太さ4ミリの筒状をした腎動脈への付着部があった。
腫瘤の被膜は部位により固さが異なり、石灰化の存在によると思われた。腫瘤を縦に半分に切った。替え刃式メスの刃触りから、壁に部分的な石灰化があるのがわかった。外壁は固く線維性で、内腔は茶褐色の泥状物で完全に満たされていた。
その間、後田は急いで組織片をクリオスタットという装置を使い、瞬間凍結させて薄い切片を切り出し、色素で染めて、顕微鏡で見られるように組織標本をつくった。
待ちかねていた佐木が顕微鏡を覗いた。壁にはかなり変性があるが、3層をなす動脈壁が認められ、一番内側の内膜とその外にある中膜が線維性に肥厚し、アテローム硬化の所見だった。内腔には古くなった血液塊が付着し、二次的に壊死して泥状化していた。
それにしても腎動脈瘤の95パーセントは径2センチ以下で発見される。5センチ近い腎動脈瘤など『ヘプティンスタール・腎臓病理学』にも『シマーズ・体系病理学:腎臓』にも記載がない。
「巨大腎動脈瘤の内腔に血栓ができ、それが器質化し一部壊死に陥ったものだろう。それにしても、ギネスブックものだな」
佐木はそう診断するとすぐにオペ室に電話をかけ、光畑を電話口に呼び出した。
「ベナインです。アノイリスム。悪性所見なし」と手短に告げた。
この間10分ほど手を休めていた摘出チームはほっとした。
同時に別室でレシピエントの手術も開始された。
間もなく提出した腫瘤がウエットガーゼに覆われて、トレイごと病理から戻ってきた。患者と家族に見せたあと、この動脈瘤は最終診断のためにまた病理に提出される。
その前に材料は10%ホルマリン水が入ったガラスビン内で固定し、このビンと泌尿器科医による「病理診断依頼書」に患者氏名、患者番号、生年月日、生検または手術日、住所、職業、原爆被爆の有無、臨床所見と経過、臨床診断、手術所見、手術臓器のスケッチと説明を記入して、いっしょに病理部に届ける。
ホルマリン固定された臓器や生検材料から、新にパラフィンで固めたブロックを作り、薄切りして厚さ1000分の2ミリという切片を作り、染色して最終診断用の標本とする。これが「最後の診断」である。
呉共済病院では、病理検査関係の書類はすべてカーボン複写式になっており、依頼書も病理診断書も病理部と各科に永久保存されている。もし記録の改ざんを主治医が行っても、病理部原本と照合すればすぐに明らかになる。原本は貸し出ししないし、閲覧も科長の許可がないとできない。
病理の厳しさを臨床各科は知っているので、書類に嘘は書かない。1週間後に再提出された巨大腎動脈瘤の検査申込書には「左腎・左尿管上部は移植に使用しました」と書かれていた。この時点で病理部の7人の医師と技師が病腎移植手術を知った。そしてすぐに院内にひろまった。
戻ってきた動脈瘤を見ながら光畑は考えた。なるほど、腰痛は動脈瘤が背部を内側から圧迫するために起こった。高血圧がここまで動脈瘤を生長させた。顕微血尿は内腔の泥状物が腎動脈内へ少しずつこぼれ落ち、細動脈に詰まり、小さな腎梗塞を生じさせるために起きていたのか…。
「それにしても腰痛が主訴のクランケを整形外科に回さず、ウロ(泌尿器科)に紹介した、うちの内科のレベルは高いな…」
間もなく男が動脈瘤を切除したため細くなった腎動脈の修復を終えた。幸い腎動脈の側副枝が一本あったので、これも使えそうだ。
男と光畑は移植のための前処理を終え、修復された腎臓を入れたトレイとともに、移植の準備手術が行われているオペ室に移動した。移植手術は光畑がおこなった。
全手術の所要時間はたった3時間半だった。レシピエントには拒絶反応も起こらず、術後経過は順調で3月22日に退院し、4月から市役所に復職するメドが立った。
折悪しくこの手術に参加できなかった西光雄は話を聞いて、思わず
「うわっ、コロンブスの卵だ!」と口にした。
うわさを聞きつけた読売新聞が退院の翌日に「美談」として全国版にスクープした。その記事の隣に京大第二外科の田中紘一講師らが、日本で第何例目かの生体肝移植をおこなったという記事が小さく載っていた。
ドナーの三宅は8年後の99年1月に83歳で亡くなった。男性の平均寿命をとっくに超えていた。
不思議なことが起こった。移植された腎臓からの顕微血尿が消失し、動脈壁にあった石灰化病変も消えたのだ。腎性高血圧も起こらなかった。移植された臓器が三原の体内で「同化」したのである。
この腎臓は20年以上も彼の体内で機能し、無事に役所の定年を迎えることができた。1914年にこの世に生まれた腎臓が2013年8月までの99年間、休まず働いたのだ。(続)
光畑直喜は1980年4月に岡山大から呉共済病院泌尿器科に赴任した。当時の科長は石(せき)正臣は名医の評判がたかく、朝の5時から受付待ち患者が病院の通用門に行列をつくり、開門を待った。2時間待ち3時間待ちはざらで、番取りの代行屋が出るほどだった。その石の下で光畑は鍛えられた。だが石は腎移植には関心を示さなかった。
光畑が廉介に誘われ宇和島で男の腎移植を見学し、その腕にしびれたのは翌年のことだ。以来、廉介の代行で移植術の助手として宇和島に通い、移植の腕を磨いた。やがてそれが役立つ日が来た。石が呉市内に開業し、患者をごっそりさらって行ったのだ。
当時の院長は岡田敬成といい、岡山医専の卒業で内科部長から院長になった。内科医長時代は「鬼軍曹」と呼ばれ、院長になってからは「天皇」とあだ名されていた。「モーレツ」という言葉と連続テレビドラマ「コンバット」が流行っていた時代だった。
天皇は「日経メディカル」を愛読し、新医療技術の導入に積極的だった。人工腎臓もはやくから導入し、内科には慢性透析の患者が洪ふれかえっていた。光畑にとって腎移植を開始するチャンスだった。彼が最初の腎移植をおこなったのは86年5月で、宇和島で腎移植の助手を最初につとめてから5年がたっていた。
宇和島から来た男が執刀して最初の腎移植が行われ、テレビや新聞が「呉市初の腎移植」と大きく報じた。喜んだ天皇が「皆で一杯やってくれ」と金一封をくれた。中に諭吉が十人いた。その頃の大卒初任給の半分よりも多かった。呉での腎移植はめったになかったが、それでも四人組の結束はかたく、移植の際には手伝いに来てくれた。
90年の暮、光畑は内科からまわってきた患者、三宅謙一(75歳)の左腎臓に、直径4.8センチの大きな腎動脈瘤(りゅう)があるのを見つけた。指三本を合わせたほどの太さがあり、いつ破裂してもおかしくなかった。普通の動脈瘤は径2センチになるまでに、高血圧、血尿、腰痛というトリアス(三徴候)がでる。
老人は千葉習志野市に住む農民で、呉市にいる息子を訪ねた際につよい左腰痛を訴え、「市民の病院」という定評がある呉共済病院に受診をすすめられたのだった。内科で高血圧と顕微血尿(ミクロヘマチュリア)を発見され、光畑に回されたのだ。不思議なことに、腎門部にあるこの巨大な動脈瘤は、血管造影(アンギオ)をしても内腔が造影されなかった。内部が充実性であるのなら、後腹膜腫瘍の可能性もあるということだ。
「一日でも早く家に帰りたい」という本人のつよい希望があった。
春の種まきは待ってくれないのだ。そこで手術時間が短くて済み、より安全な全摘術を行うことをすすめた。
その時、ふと光畑の脳裏に慢性糸球体腎炎から腎不全になり透析を続けている、まだ若い呉市職員三原(44歳)の顔が浮かんだ。最初、妻からの腎移植を検討したが、血液型が一致せず実行できなかった。死体腎の移植も一度試みたが、摘出した腎臓の状態が悪く中止せざるをえなかった。同僚の冷ややかな目を浴びながらの週3回の透析はつらく、三原は精神的にも落ちこんでいた。このままでは休職から失職へとつながるのは目にみえていた。
ドナーがいないこの患者の血液型はB型で、腎全摘を希望した老人と一致していた。
「何とかあの腎臓が移植に使えんものかのう…」
光畑はこれまで正常な腎臓しか移植したことがなかった。「親族間腎移植」では血管の奇形や小さな動脈瘤がある腎臓の病変部を切除し、修復した後で移植に用いられた例があることは、移植学会での演題や学会誌で知っていた。だが径4.8センチという巨大な腎動脈瘤を切除した後に、移植に使用できるとはとても思えなかった。宇和島に電話してCTとアンギオによる動脈瘤の状態を詳しく話し、男の意見を求めた。
男は飛び降り自殺したムラキサトコのことをよく覚えていた。あの悲劇を二度と繰り返してはならない。だがこれは特発性腎出血とは違う。動脈瘤を切除し、腎動脈を修復する外科的な技術だけが問題になる。移植さえうまく行けば後の問題はないはずだ。
かつて免疫抑制剤のため日和見感染により死亡した、コウノタダシのことも思い出した。あれは1981年、二度目のウィスコンシン詣でをやり、新免疫抑制剤サイクロスポリンを導入することで再発を防いだ。
「男はやってやって、やり抜け!」
酒気帯び運転のトラックに正面衝突され、後部エンジン搭載のフォルクスワーゲンに乗っていたばかりに、ほとんど即死状態で無念の死をとげた内科医の父の言葉が聞こえたように思った。
「やれるじゃろう…」男はぽつりといった。
光畑には寡黙な男のその一言が頼もしかった。
年が明けると、急いで双方の患者の同意を得て必要な検査を終え、「病腎移植」が行われた。91年1月25日に行われたこの手術には、光畑と泌尿器科医員の那須と渡辺の他に、宇和島の男と岡山協立病院にいた弟の廉介が参加した。
この手術では男が腎摘出にまわった。アノイリスム(動脈瘤)のある左腎臓を摘出し、この巨大な動脈瘤を切除して、移植に使えるように血管を修復する技術は男にしかない。
普通の腎手術では側腹部切開で腹を開ける。だが後腹膜腫瘍の可能性があるこの患者では、正中切開で腎臓にアプローチする方法が採用された。万一の場合に備えて、手術野をひろく確保し、大動脈に沿う後腹膜リンパ節などをチェックするためだ。腎臓を包む脂肪膜を剥離して、腎動脈から西洋梨型にとび出している巨大な動脈瘤にさわった。なんと中が固い。普通の動脈瘤ではない。
「だから光畑がアンギオで中が写らないといったのか…」と男は思った。
内腔に血流があれば当然、血管造影で写る。こうなると腫瘍の可能性もある。男は急いで腎動脈、腎静脈を結紮し、尿管も結紮して、メスで切断して腫瘤ごと腎臓を取り出した。幸い大動脈から腎動脈が分岐したすぐのところに、細い筒形をした腫瘤付着部があり、良性なら切除後の動脈修復は何とか可能で、移植可能だと男は判断した。
首の付け根のところで、腫瘤を切除した。形は小さな風船に似ていて、重さは小ぶりの鶏卵ほどもあった。立ち会っていた光畑が、さわって形や堅さを確かめた。視診・触診では腫瘍としか思えない。外科トレイに移すと、「大至急」で手術場ナースに病理検査部に持って行かせた。
病理検査部では病理専門医の佐木が待機していた。佐木は腎移植が可能かどうかの判断は、自分の病理診断にかかっていることを知っていた。強いストレスで血中にアドレナリンが充満し、やり甲斐を感じていた。受付の折原が手早く受付番号を付与し、台帳に記入し、印字機で受理番号を「91−○○○○」と色テープに印字し、検査技師の後田にトレイごと渡した。彼は写真撮影台に腫瘤を載せ、テープを貼ったスケールをそばに置き、すばやく撮影をすませた。
佐木はビニール手袋をつけると、ピンクの卵に似た、長さが5センチちかい大きな腫瘤をよく触り、腫瘍が疑われる部分をメスでくさび形に切り出し、ピンセットでつまむと後田技師が手に載せたガーゼに落とし、迅速標本を頼んだ。それから腫瘤の計測と肉眼所見の観察を始めた。佐木の口述を医療秘書の資格を持つ折原が「摘出臓器肉眼所見」用紙に書き取った。腎門部にあった動脈腫瘤の表面は薄い赤みを帯び、鶏卵状で、長径が48ミリ、短径が35ミリ、重さが25グラムもあった。幅がやや細くなった長軸の端に、太さ4ミリの筒状をした腎動脈への付着部があった。
腫瘤の被膜は部位により固さが異なり、石灰化の存在によると思われた。腫瘤を縦に半分に切った。替え刃式メスの刃触りから、壁に部分的な石灰化があるのがわかった。外壁は固く線維性で、内腔は茶褐色の泥状物で完全に満たされていた。
その間、後田は急いで組織片をクリオスタットという装置を使い、瞬間凍結させて薄い切片を切り出し、色素で染めて、顕微鏡で見られるように組織標本をつくった。
待ちかねていた佐木が顕微鏡を覗いた。壁にはかなり変性があるが、3層をなす動脈壁が認められ、一番内側の内膜とその外にある中膜が線維性に肥厚し、アテローム硬化の所見だった。内腔には古くなった血液塊が付着し、二次的に壊死して泥状化していた。
それにしても腎動脈瘤の95パーセントは径2センチ以下で発見される。5センチ近い腎動脈瘤など『ヘプティンスタール・腎臓病理学』にも『シマーズ・体系病理学:腎臓』にも記載がない。
「巨大腎動脈瘤の内腔に血栓ができ、それが器質化し一部壊死に陥ったものだろう。それにしても、ギネスブックものだな」
佐木はそう診断するとすぐにオペ室に電話をかけ、光畑を電話口に呼び出した。
「ベナインです。アノイリスム。悪性所見なし」と手短に告げた。
この間10分ほど手を休めていた摘出チームはほっとした。
同時に別室でレシピエントの手術も開始された。
間もなく提出した腫瘤がウエットガーゼに覆われて、トレイごと病理から戻ってきた。患者と家族に見せたあと、この動脈瘤は最終診断のためにまた病理に提出される。
その前に材料は10%ホルマリン水が入ったガラスビン内で固定し、このビンと泌尿器科医による「病理診断依頼書」に患者氏名、患者番号、生年月日、生検または手術日、住所、職業、原爆被爆の有無、臨床所見と経過、臨床診断、手術所見、手術臓器のスケッチと説明を記入して、いっしょに病理部に届ける。
ホルマリン固定された臓器や生検材料から、新にパラフィンで固めたブロックを作り、薄切りして厚さ1000分の2ミリという切片を作り、染色して最終診断用の標本とする。これが「最後の診断」である。
呉共済病院では、病理検査関係の書類はすべてカーボン複写式になっており、依頼書も病理診断書も病理部と各科に永久保存されている。もし記録の改ざんを主治医が行っても、病理部原本と照合すればすぐに明らかになる。原本は貸し出ししないし、閲覧も科長の許可がないとできない。
病理の厳しさを臨床各科は知っているので、書類に嘘は書かない。1週間後に再提出された巨大腎動脈瘤の検査申込書には「左腎・左尿管上部は移植に使用しました」と書かれていた。この時点で病理部の7人の医師と技師が病腎移植手術を知った。そしてすぐに院内にひろまった。
戻ってきた動脈瘤を見ながら光畑は考えた。なるほど、腰痛は動脈瘤が背部を内側から圧迫するために起こった。高血圧がここまで動脈瘤を生長させた。顕微血尿は内腔の泥状物が腎動脈内へ少しずつこぼれ落ち、細動脈に詰まり、小さな腎梗塞を生じさせるために起きていたのか…。
「それにしても腰痛が主訴のクランケを整形外科に回さず、ウロ(泌尿器科)に紹介した、うちの内科のレベルは高いな…」
間もなく男が動脈瘤を切除したため細くなった腎動脈の修復を終えた。幸い腎動脈の側副枝が一本あったので、これも使えそうだ。
男と光畑は移植のための前処理を終え、修復された腎臓を入れたトレイとともに、移植の準備手術が行われているオペ室に移動した。移植手術は光畑がおこなった。
全手術の所要時間はたった3時間半だった。レシピエントには拒絶反応も起こらず、術後経過は順調で3月22日に退院し、4月から市役所に復職するメドが立った。
折悪しくこの手術に参加できなかった西光雄は話を聞いて、思わず
「うわっ、コロンブスの卵だ!」と口にした。
うわさを聞きつけた読売新聞が退院の翌日に「美談」として全国版にスクープした。その記事の隣に京大第二外科の田中紘一講師らが、日本で第何例目かの生体肝移植をおこなったという記事が小さく載っていた。
ドナーの三宅は8年後の99年1月に83歳で亡くなった。男性の平均寿命をとっくに超えていた。
不思議なことが起こった。移植された腎臓からの顕微血尿が消失し、動脈壁にあった石灰化病変も消えたのだ。腎性高血圧も起こらなかった。移植された臓器が三原の体内で「同化」したのである。
この腎臓は20年以上も彼の体内で機能し、無事に役所の定年を迎えることができた。1914年にこの世に生まれた腎臓が2013年8月までの99年間、休まず働いたのだ。(続)












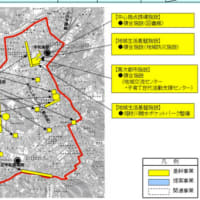
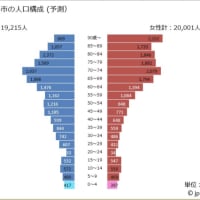



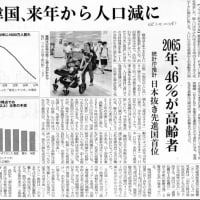










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます