【実験の結果】
これで2個目のイワシの味噌煮缶詰から、「寄生虫様の索状物」を2回とも見つけたわけだが、それを発見するにいたるいきさつは、焼酎を飲みながら箸で無意識に身をつついて気づいたので、そこに至るプロセスに問題があると思った。
そこで3夜目は、魚の解剖をするつもりで、片側から脊椎骨に到達するまで少しずつ身を取り除いて行った。缶詰にはイワシの後半分が2本入っているので、どちらもきれいに片身にした。(写真3)
 (写真3)
(写真3)
左端がどちらも頭側で、中央少し背側を白い脊椎骨が走っている。ところにより背中側に棘突起が目立つ部分もある。
前に「寄生虫では?」と思った黒褐色の太いひも状物は、どちらも背骨の下にくっついて一個だけ認められる。2匹とも左端の腹に黒い色素沈着があるが、ここは腹腔で胃と腸があった箇所と思われるが、缶詰では抜き取ってあると思われ、それらしいものはなかった。
そこで椎骨とその周囲組織と腹側の黒褐色紡錘状物だけを標本として小皿に保存し、後は酒の肴にして食った。今回は2匹とも「白い寄生虫様物」は見つからなかった。(写真4)
 (写真4)
(写真4)
これを書斎に運び、ステンレスバットに100円ショップで買った小皿3枚を並べて、水を張り、ピンセットを使って標本をよく洗い、付着物を洗い流した。(写真5)
 (写真5)
(写真5)
中仕切りのある小皿に背骨とその付着物を入れ、別の小皿に腹側の紡錘状物を入れ、第三の小皿にはさらに洗浄するための予備水を用意した。右の皿の白い索状物は写真を見ると、背中の棘が付着しており、棘突起の一部と思われた。
うっかりしていて、どっちの背骨からはずれたのかわからなくなった。
また黒褐色の紡錘状のものには尻尾のようなものがあることが、マクロ撮影してわかった。
で、まず左下の標本の左端部、椎骨と白い索状物が重なっている部分をUSB顕微鏡で拡大して見た。標本がよく見えるように茶色のビニール片を下に敷いた。(写真6)
 (写真6)
(写真6)
下が椎骨からなる脊椎で、索状物はそれに接して背側にあり、そこから骨の棘(棘突起)が出ているから、位置としてはヒトの脊髄がある位置だ。そうなると髄膜に被われていて、黒い点はやはりメラニン細胞ということになる。
この髄膜様のものをはぎ取るのが難しいので、半日ほどバットのままで放置しておき、別の仕事をしていて、ふと見たら半透明の膜様物が袋状になって膨大していた。そこで水を換えたら、うまい具合に膜様物がちぎれて流れてくれた。そこで撮影したのが写真7である。
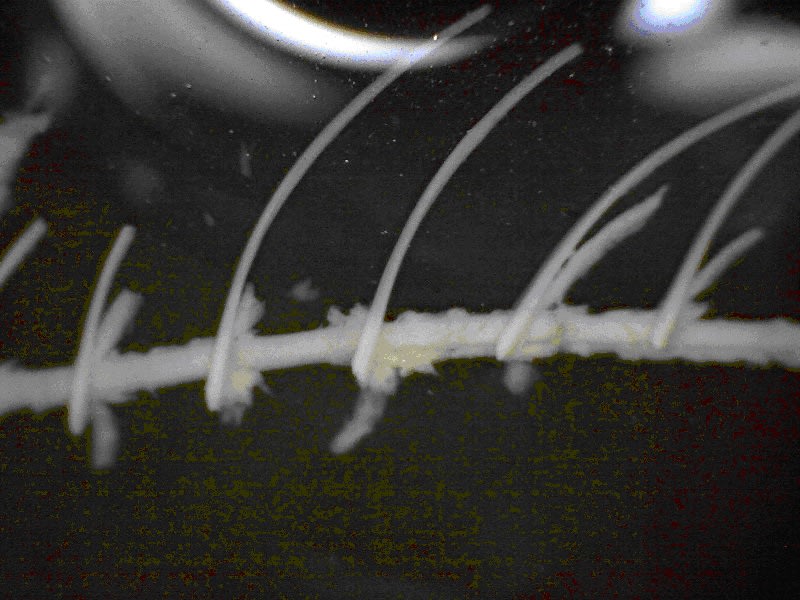 (写真7)
(写真7)
ヒトでは椎体から起こった棘突起はリング状の骨、椎弓を形成しその背後から棘突起が出る。脊髄は椎体と椎弓により形成される骨のトンネル「脊椎管」の中にあるが、魚(硬骨魚)では椎弓と椎体の接着が弱いらしい。
というわけで、写真7は、脊椎からはずれた椎弓と棘突起およびまだ椎弓に付着している「脊髄」であると判明した。
では紡錘状黒褐色のものは何か?
マクロ撮影で尻尾のようなものが見える部分をUSBで拡大して観察した。(写真8)
 (写真8)
(写真8)
これは明らかに細い管であり、椎骨の下側(腹側)にあり、褐色調で管が出る臓器なら腎臓をまず考える。しかしヒトではあれは対になっているが、これは一つしかない。
ここまで来て私の知識は限界なので、まずAmazonに下等脊椎動物(〜爬虫類)の「比較解剖学」の図譜と「魚類解剖学」の本を注文した。なかなか新刊書がないので中古を探した。届くまでに3〜4日かかるが、99%分かったところで後の1%を早く知りたい。
手持ちの本には、硬骨魚(Teleost)の骨系統と中枢神経系について、詳しく書いたものがないが、泌尿器系についてはかなり詳しいのがある。そこでG.C.Kent「Comparative Anatomy of the Vertebrates」(Mosby, 1965)を開いたら、そこに絵があった(写真9)。
 (写真9)
(写真9)
ここには脊椎も脊髄も描いてないが、なんと魚の腎臓(中腎Mesonephros)は左右が癒合して一本の棒状物となり、背骨のすぐ下側にある(図のピンク色)。だからそこから出る尿管(中腎管Mesonephric duct)も一本しかなく、これが膀胱(Urinary bladder:ピンク色の袋)につながっている。
腎臓と膀胱の間には、浮き袋(Swim bladder)と精巣(Testis)がある(オスの硬骨魚の絵)。
緑色は小腸で、これには腸管膜がある。面白いのは魚では肛門(Anus)と外尿道口(尿孔Urinary pore)と精液を出す孔(生殖孔Genital pore)と排泄孔が3つもあり、鳥類のように「総排泄孔Chloaca」になっていないことだ。図の説明文によると、胎生期に総排泄孔が退化してしまうのだそうだ。退化により複雑化が起こるというのも、珍しい現象だ。
腎臓の起源には「前腎」「中腎」「後腎」と3種あり、哺乳類では胎生期に前腎、中腎は姿を消し、一生機能する腎臓は後腎由来ですが、魚類では違うようです。
たまたま酒のつまみの「イワシの味噌煮」に白いひも状物を見つけ、「ひょっとしたら寄生虫では?」と疑問を抱いたのが、今回の「騒動」の発端ですが、3個目の缶詰のイワシで同じ位置に同じように存在することを確認し、さらに椎骨と密接しており、椎弓と棘突起が付着していることを確認できました。寄生虫ならまったく同じ位置にいることはありえません。
また脊椎の腹側に存在した黒褐色ひも状物が「中腎」であることも確認できました。
両方ともに「体節構造」が認められるのは、脊椎、中腎ともにホメオボックス遺伝子と呼ばれる体節形成遺伝子の作用で形成されるので、当たり前のことだとわかりました。
「寄生虫だとすれば、体節構造があるなら環形動物のはず。しかしそういう魚類の寄生虫は記載がないな」と不審に思い約1ヶ月いろいろ調べてみましたが、私の思い違いで、実際は脊髄と腎臓であることが確定しました。
初め上げた鑑別診断の中に、1)正常構造物、2)寄生虫、3)その他 の三つをあげましたが、その第一に該当することで、「確定診断」に至りました。どうもお騒がせして申し訳ありませんでした。なお「サンマの蒲焼き」という100円缶詰を開けてみましたが、調理法がちがうせいか、これでは背骨さえも見つけることができませんでした。
Mr.Sさん、安心してイワシの缶詰をお召し上がりください。Unknownさんも、いろいろご教示ありがとう存じます。
これで2個目のイワシの味噌煮缶詰から、「寄生虫様の索状物」を2回とも見つけたわけだが、それを発見するにいたるいきさつは、焼酎を飲みながら箸で無意識に身をつついて気づいたので、そこに至るプロセスに問題があると思った。
そこで3夜目は、魚の解剖をするつもりで、片側から脊椎骨に到達するまで少しずつ身を取り除いて行った。缶詰にはイワシの後半分が2本入っているので、どちらもきれいに片身にした。(写真3)
 (写真3)
(写真3) 左端がどちらも頭側で、中央少し背側を白い脊椎骨が走っている。ところにより背中側に棘突起が目立つ部分もある。
前に「寄生虫では?」と思った黒褐色の太いひも状物は、どちらも背骨の下にくっついて一個だけ認められる。2匹とも左端の腹に黒い色素沈着があるが、ここは腹腔で胃と腸があった箇所と思われるが、缶詰では抜き取ってあると思われ、それらしいものはなかった。
そこで椎骨とその周囲組織と腹側の黒褐色紡錘状物だけを標本として小皿に保存し、後は酒の肴にして食った。今回は2匹とも「白い寄生虫様物」は見つからなかった。(写真4)
 (写真4)
(写真4) これを書斎に運び、ステンレスバットに100円ショップで買った小皿3枚を並べて、水を張り、ピンセットを使って標本をよく洗い、付着物を洗い流した。(写真5)
 (写真5)
(写真5) 中仕切りのある小皿に背骨とその付着物を入れ、別の小皿に腹側の紡錘状物を入れ、第三の小皿にはさらに洗浄するための予備水を用意した。右の皿の白い索状物は写真を見ると、背中の棘が付着しており、棘突起の一部と思われた。
うっかりしていて、どっちの背骨からはずれたのかわからなくなった。
また黒褐色の紡錘状のものには尻尾のようなものがあることが、マクロ撮影してわかった。
で、まず左下の標本の左端部、椎骨と白い索状物が重なっている部分をUSB顕微鏡で拡大して見た。標本がよく見えるように茶色のビニール片を下に敷いた。(写真6)
 (写真6)
(写真6) 下が椎骨からなる脊椎で、索状物はそれに接して背側にあり、そこから骨の棘(棘突起)が出ているから、位置としてはヒトの脊髄がある位置だ。そうなると髄膜に被われていて、黒い点はやはりメラニン細胞ということになる。
この髄膜様のものをはぎ取るのが難しいので、半日ほどバットのままで放置しておき、別の仕事をしていて、ふと見たら半透明の膜様物が袋状になって膨大していた。そこで水を換えたら、うまい具合に膜様物がちぎれて流れてくれた。そこで撮影したのが写真7である。
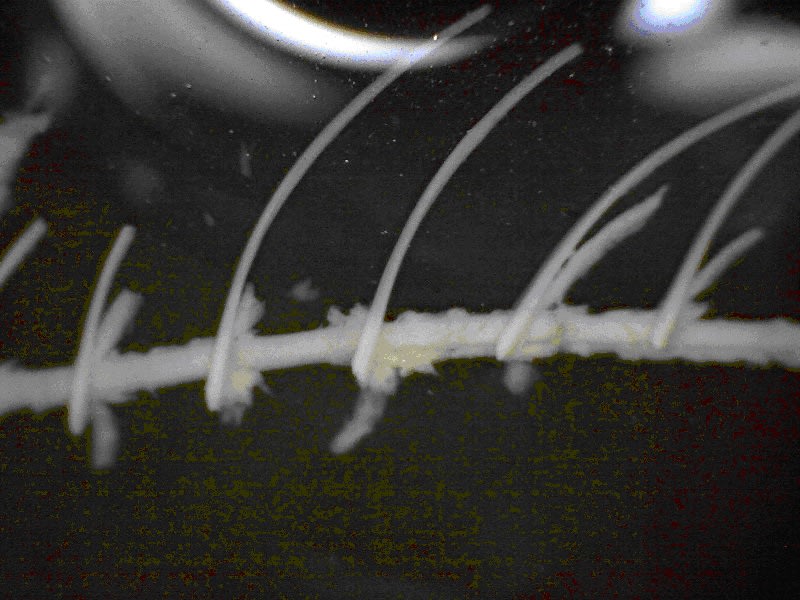 (写真7)
(写真7) ヒトでは椎体から起こった棘突起はリング状の骨、椎弓を形成しその背後から棘突起が出る。脊髄は椎体と椎弓により形成される骨のトンネル「脊椎管」の中にあるが、魚(硬骨魚)では椎弓と椎体の接着が弱いらしい。
というわけで、写真7は、脊椎からはずれた椎弓と棘突起およびまだ椎弓に付着している「脊髄」であると判明した。
では紡錘状黒褐色のものは何か?
マクロ撮影で尻尾のようなものが見える部分をUSBで拡大して観察した。(写真8)
 (写真8)
(写真8) これは明らかに細い管であり、椎骨の下側(腹側)にあり、褐色調で管が出る臓器なら腎臓をまず考える。しかしヒトではあれは対になっているが、これは一つしかない。
ここまで来て私の知識は限界なので、まずAmazonに下等脊椎動物(〜爬虫類)の「比較解剖学」の図譜と「魚類解剖学」の本を注文した。なかなか新刊書がないので中古を探した。届くまでに3〜4日かかるが、99%分かったところで後の1%を早く知りたい。
手持ちの本には、硬骨魚(Teleost)の骨系統と中枢神経系について、詳しく書いたものがないが、泌尿器系についてはかなり詳しいのがある。そこでG.C.Kent「Comparative Anatomy of the Vertebrates」(Mosby, 1965)を開いたら、そこに絵があった(写真9)。
 (写真9)
(写真9) ここには脊椎も脊髄も描いてないが、なんと魚の腎臓(中腎Mesonephros)は左右が癒合して一本の棒状物となり、背骨のすぐ下側にある(図のピンク色)。だからそこから出る尿管(中腎管Mesonephric duct)も一本しかなく、これが膀胱(Urinary bladder:ピンク色の袋)につながっている。
腎臓と膀胱の間には、浮き袋(Swim bladder)と精巣(Testis)がある(オスの硬骨魚の絵)。
緑色は小腸で、これには腸管膜がある。面白いのは魚では肛門(Anus)と外尿道口(尿孔Urinary pore)と精液を出す孔(生殖孔Genital pore)と排泄孔が3つもあり、鳥類のように「総排泄孔Chloaca」になっていないことだ。図の説明文によると、胎生期に総排泄孔が退化してしまうのだそうだ。退化により複雑化が起こるというのも、珍しい現象だ。
腎臓の起源には「前腎」「中腎」「後腎」と3種あり、哺乳類では胎生期に前腎、中腎は姿を消し、一生機能する腎臓は後腎由来ですが、魚類では違うようです。
たまたま酒のつまみの「イワシの味噌煮」に白いひも状物を見つけ、「ひょっとしたら寄生虫では?」と疑問を抱いたのが、今回の「騒動」の発端ですが、3個目の缶詰のイワシで同じ位置に同じように存在することを確認し、さらに椎骨と密接しており、椎弓と棘突起が付着していることを確認できました。寄生虫ならまったく同じ位置にいることはありえません。
また脊椎の腹側に存在した黒褐色ひも状物が「中腎」であることも確認できました。
両方ともに「体節構造」が認められるのは、脊椎、中腎ともにホメオボックス遺伝子と呼ばれる体節形成遺伝子の作用で形成されるので、当たり前のことだとわかりました。
「寄生虫だとすれば、体節構造があるなら環形動物のはず。しかしそういう魚類の寄生虫は記載がないな」と不審に思い約1ヶ月いろいろ調べてみましたが、私の思い違いで、実際は脊髄と腎臓であることが確定しました。
初め上げた鑑別診断の中に、1)正常構造物、2)寄生虫、3)その他 の三つをあげましたが、その第一に該当することで、「確定診断」に至りました。どうもお騒がせして申し訳ありませんでした。なお「サンマの蒲焼き」という100円缶詰を開けてみましたが、調理法がちがうせいか、これでは背骨さえも見つけることができませんでした。
Mr.Sさん、安心してイワシの缶詰をお召し上がりください。Unknownさんも、いろいろご教示ありがとう存じます。




























中腎でしたか。ヒトの腎臓は濾過以外に血圧を調整する機能も持ちますが、海の中のお魚にはそういう機能は必要なさそうです。いつ進化したのでしょうね。陸にあがった時(両生類か爬虫類)でしょうか。
4月1日まで解決しなかったら、「絶対にこれだと思います」といって
Bukashkina, V. V. New Parasitic Species of Colonial Rhinogradentia. Russian Journal of Marine Biology 30 (2). p. 150.
を紹介するつもりでした。