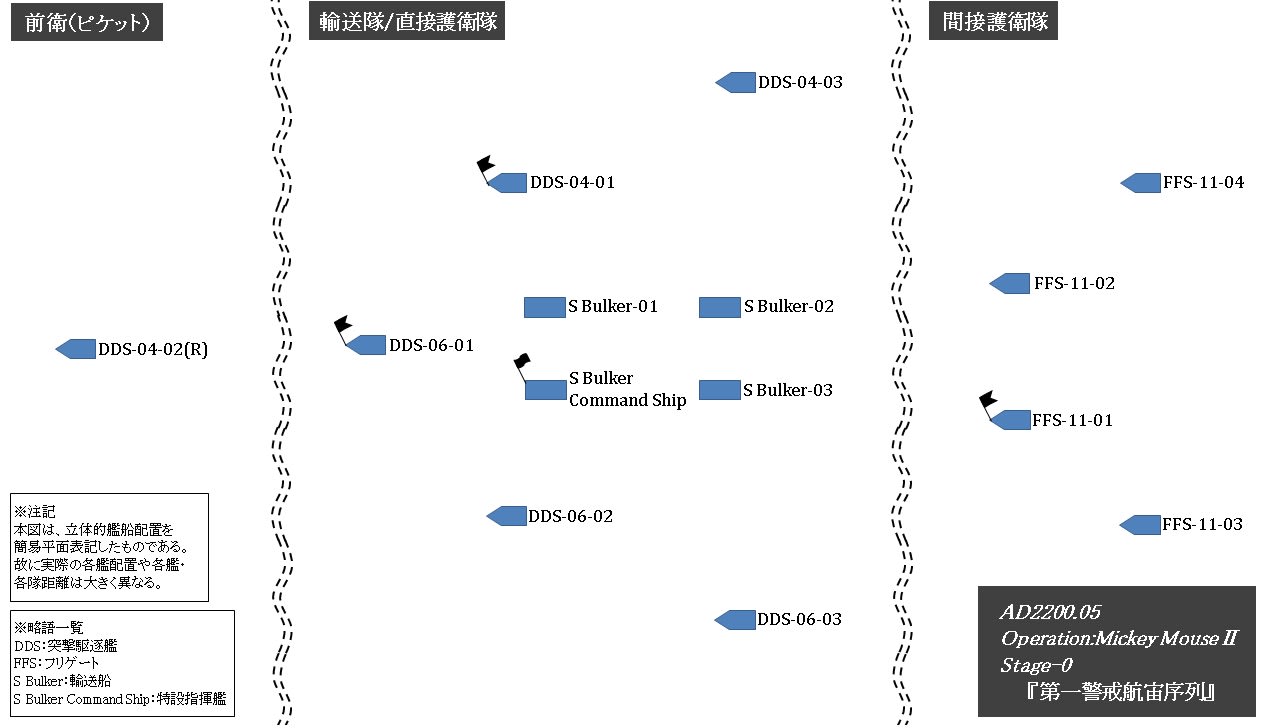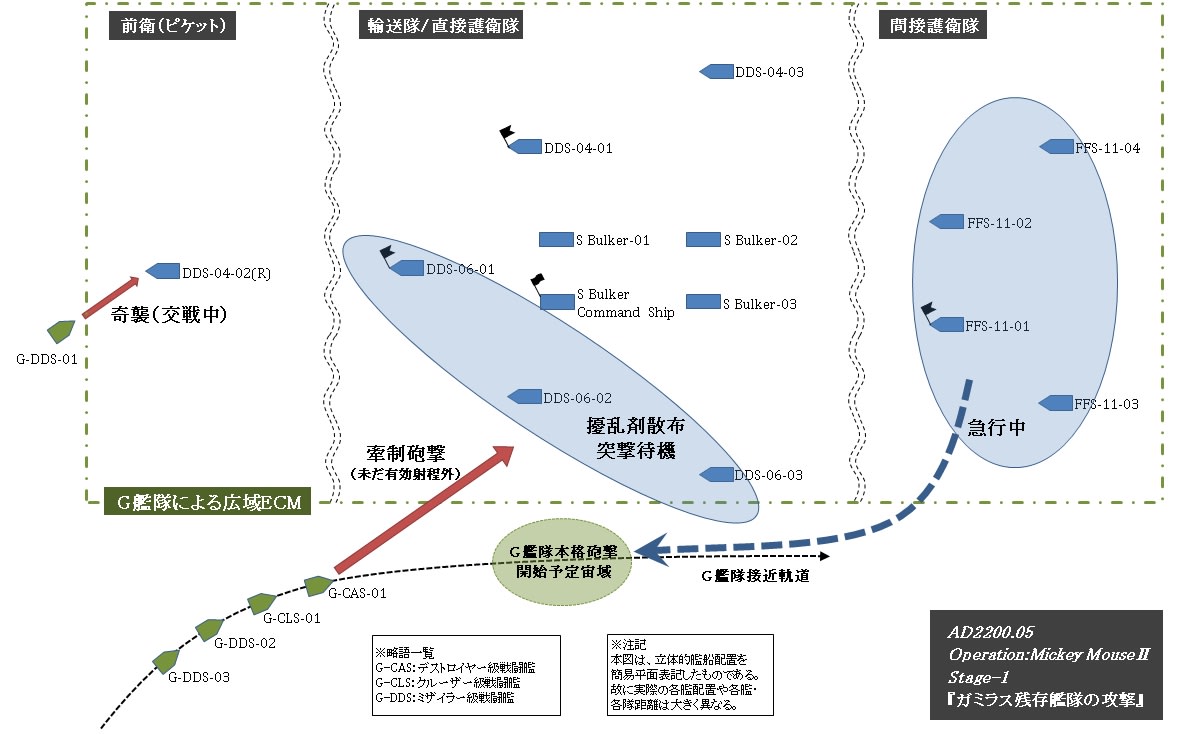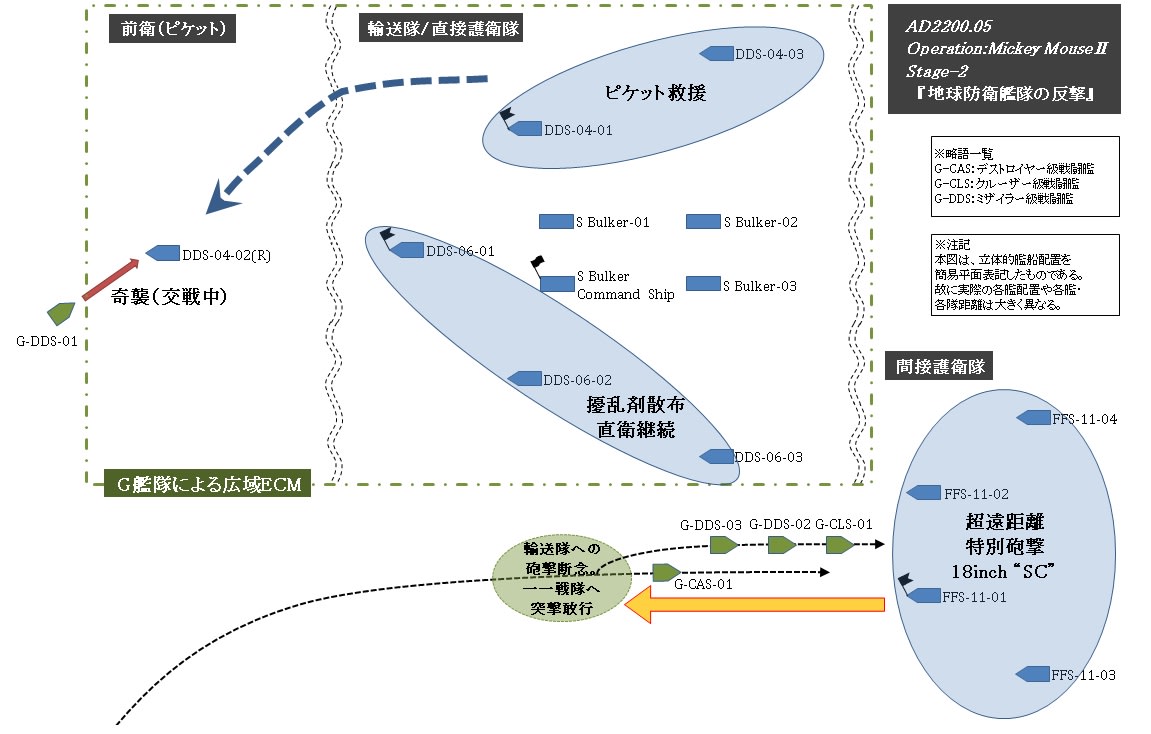ガミラス戦役中期以降、地球防衛軍の一線級航空(宙)機の主機には、一貫して低濃縮型波動機関の簡易型が採用されている。
艦艇搭載の波動機関は、それがいかなる国家・勢力のものであれ、基本的にはタキオン粒子を常時捕集しながら機関内で濃縮し、恒星間航行を可能とする莫大なエネルギーを得ている。しかし、いかに宇宙エネルギーの一種であるタキオン粒子といえども、濃縮度の低い状態のままではワープ・ドライブを可能とするほどの出力を得ることはできない。故に、恒星間航行用艦船に用いられる波動機関は、より高いタキオン濃縮度が達成可能な『高濃縮型』か、タキオン濃縮度は低くとも特殊な触媒――波動触媒――との接触によって出力増幅を果たした機関が搭載されるのである(媒接触型の代表例として、ガミラシウムを用いるガミラス式波動機関やボラーチウム100を用いたボラー式波動機関等がある)。
これに対し、短時間・短距離の戦術運用に特化した航空機用機関は、タキオン粒子の捕集や濃縮、触媒接触を行わないことで構造・規模共に大幅な小型化と簡略化を果たしている。
しかし、機関の“燃料”たるタキオン粒子を、機外から低濃縮状態で供給する形式を採っている為、波動機関最大の特長である“無限機関”足り得なくなっている。また、供給されるタキオンエネルギーは高濃縮も触媒接触も行っていない為、機関の発揮出力には限界があり、ワープ航法は全く不可能であった。
以上二つの制約から、同じタキオン粒子を用いる機関でも航空機用と艦艇用は区別され、航空機用は『タキオンエンジン』若しくは『コスモエンジン』と称されるのが一般的である(本稿では以後、艦艇用を『波動エンジン』、航空機用を『タキオンエンジン』と呼称する)。
しかし、それらの制約を勘案しても尚、タキオンエンジンには確たる優位があった。
まず、波動エンジン搭載艦船は、設置容積的に最低でも五〇メートル以上の船殻サイズが必要であるが、タキオンエンジン搭載機は十数メートル規模の小型機体でも十分に実現が可能である。また、前述した通りワープ航法こそ不可能だが、搭載機は亜光速域での戦闘行動に十分な加減速性能を有しており、外宇宙速度で航行中の波動エンジン搭載艦艇との共同行動はもちろん、対敵機動も可能であった。
そして何より、艦艇用と比べて圧倒的に低コストで製造可能という点が、以上の優位に何倍もの価値を与えていた。
艦船用の波動エンジンは、それが高濃縮型であれ低濃縮型(触媒接触型)であれ、大質量艦船の外宇宙速度航行に要する莫大な推力と、ワープ時の超々高出力エネルギーに対して継続的に耐久可能である必要があり、使用されている素材は勿論、基本構造からして堅牢でなくてはならない。しかし、発揮出力が極めて限られ、ワープ航法も行わないタキオンエンジンが要求する強度・耐久性は波動エンジンの数百分の一レベルに過ぎなかったからである。
この点で最も恩恵を受けたのがガミラス戦役時の地球防衛軍であった。
ガミラス戦役時、鹵獲したガミラス艦艇の波動エンジンを模倣することで、短期間での戦力化を企図した地球防衛軍であったが、ガミラスが一般的に使用している波動触媒――ガミラシウム――の入手や強度放射性物質であるが故の放射線遮断が壁となり、現実的な実用化は酷く難航した。
また、辛苦多難の末になんとか模倣製造に成功した波動エンジンも、機関としての安定性こそ確保されていたものの、艦艇用として期待した出力には遠く及ばないのが実情だった。ある意味ではそれも当然で、地球人が製造した波動エンジンはガミラスのそれと同じくタキオン粒子を低い濃度でしか濃縮していなかった上に、機関に大幅な出力増幅をもたらす波動触媒との接触を行っていなかった(行えなかった)からだ。
また、オリジナルと比して出力で大きく劣る地球製の模造品――モンキーモデルであっても、その製造にはコスモナイトをはじめとして、当時の人類には酷く入手が困難な(当時、既に地球の制宙権は地球―月近傍にまで追い詰められていた)希少金属が大量に必要である為、大量生産・配備も難しかった。
しかし、そうした問題点を多数抱えたガミラス式波動エンジン模倣の過程で、一つの副産物が得られていた。ガミラス軍航宙機の機関コピーの成功である(コピー元となったガミラス機は、ガミラス艦よりも前に鹵獲されていた)。

しかも、コピーに成功した航空機用機関は、オリジナルであるガミラス軍機のものと比較しても、性能的に極端な遜色はなかった。艦艇用の波動エンジンとは異なり、航空機用機関ではガミラスでも波動触媒との接触や高濃縮化といった高度な出力増幅措置が採られておらず、地球人類でも模倣のハードルが低かったのだ。また、製造に必要な部材や素材も、大半が地球で入手容易なもので代用可能であり、量産の観点での問題も艦艇用機関に比べて遥かに少なかった。
以上の事実は、当時の地球人類と地球防衛軍にとって大きな福音だった。なぜなら、軍事力でも科学技術力でも圧倒する大ガミラス帝国軍に対し、地球人類が初めて同等に限りなく近い軍事技術の実用化に成功したからである。
当然、以後の地球防衛軍は模倣機関の量産態勢確立と機関搭載機の開発、それらの実戦配備に全力を傾けた。そしてその努力は、人類史上初のタキオンエンジン搭載実用戦闘機である『九六式宇宙戦闘機“コスモ・タイガー”』として結実することになる。
同機に搭載されたタキオンエンジンは、艦艇用波動エンジンと比べれば機能も構造も遥かに簡易であったが、それでもれっきとした波動機関の一種であり、運転稼働中は航宙機レヴェルとしては破格のエネルギーを生み出すことができた。それを用いることで、ガミラス軍機並みの高速戦闘を行っても搭乗員を保護可能な慣性制御装置(耐G装置)を装備している他、レーザー系火器や各種エネルギーシールドも、既存機とは比較にならないほど強力なものが装備可能となった。
タキオンエンジンを稼働させるのは低濃縮状態のタキオン粒子(通称:タキオン燃料)であり、これを充填したものがタキオンタンクと称される。そして、このタンク容量がタキオンエンジン搭載機体の稼働時間(航続距離)を決定するのである。
但し、タキオン燃料は波動エンジンからでなければ供給が不可能である為、九六式の配備と同時期に、タキオン燃料精製用の波動エンジンが大規模根拠地に設置された。この機関は前述したガミラス艦艇のそれをデッドコピーした低濃縮型/触媒非接触式であり、大質量の艦艇を高速で機動させるには全く出力が不足していたが、単にタキオン燃料の精製・供給用として考えるのであれば、十分な性能を有していた。しかし当時の地球に、機能と性能を可能な限り限定したとはいえ、艦艇用クラスの波動エンジンを大量生産する力は既になく、製造されたタキオン燃料供給用波動エンジンは僅か五基(地球に二基、月に一基、アステロイドベルト内防衛軍基地に二基)に留まった。
その為、大規模根拠地で精製されたタキオン燃料は、宇宙空間では同時期に実戦配備が開始された簡易航空母艦とも言うべき『航空支援艦』内に設置された大型タキオンタンクに充填され、中規模以下の根拠地に供給する体制が採られた(地球上では既存の燃料給油機が大改造され、各地への供給を担った)。
後の波動機関が一般化した時代と比較すれば、かなり非効率な燃料供給体制であったが、当時の地球防衛軍には否応も無かった。現時点で唯一大ガミラス帝国軍に対抗可能な軍事ファクターを切り捨てることなどできる訳もなく、以後も経済性を度外視した運用が続けられることになる。
しかしそうした状況も、地球で本格的な波動エンジン搭載艦艇――宇宙戦艦ヤマトが登場したことで大きな転機を迎えることになる。波動エンジン搭載艦であれば、機関稼働中は常にタキオン燃料を精製しているのも同然である為、艦内に艦載機用燃料スペースを確保する必要が無かったからだ。ヤマトは、往復三〇万光年にも及ぶ航宙を単独で行わなければならない艦であり、艦内空間の確保と効率的使用は死活問題だった。その点、通常の液体や固体燃料を用いないタキオンエンジン搭載機は、イスカンダル往還を目指すヤマトにとって願ったり叶ったりの機材であった。
その結果、ヤマトには九六式の後継機である『九九式宇宙艦上戦闘機“ブラック・タイガー”』及び『零式宇宙艦上戦闘機“コスモ・ゼロ”』が一個増強航空隊編成で搭載され、縦横無尽の活躍を示すことになる。

ヤマトがイスカンダルから帰還し、ガミラス戦役が実質的な自然休戦を迎えた後、新たに設立した地球連邦政府は、戦役中に実用化された各種新技術を用いた軍事力の再建に乗り出した。勿論、その中にはタキオンエンジン搭載機によって編成された航空隊多数も含まれており。当面の主力機材はガミラス戦役時に開発された九六式と九九式が占めるが、新型機の開発と配備も急ピッチで進められていた。
開発・採用年次的には未だ“新鋭機”と評し得る九九式や零式から、さほど間を置かない新型機開発には勿論理由がある。
ガミラス戦役中に製造された地球製タキオンエンジンは、機関中枢に入手容易ではあるが、強度や耐久性に劣る素材をかなりの割合で採用せざるを得なかった。また、基礎技術力の乏しさから、エンジン補機類全般の性能もガミラス製と比べて明らかに劣っていた。
その為、第一線の戦闘部隊で使用されるタキオンエンジンは、航続距離の低下や消耗部品の増大を覚悟の上で、かなりピーキーな(職人芸的整備でのみ実現可能な)セッティングで運用されることが多かった。だが、そうした努力を払っても尚、発揮出力はガミラス機と比べて不足気味であった為、九九式のパイロット達は過荷重となりかねない誘導弾の搭載を最小限に留めていたのが実情だった(そうした状況は当時の記録映像からも確認することができる)。
しかし、ヤマトがガミラス帝国軍冥王星基地を破壊し、地球防衛艦隊が太陽系内制宙権を奪還して以降、コスモナイトをはじめとする各種の高機能性素材原料の入手状況は劇的に改善した。その結果、タキオンエンジンにもこれまでは入手困難であった希少素材を使用することが可能となり、従来と同一設計の機関であっても、かなりの性能向上が達成された。
更に、高精度・高純度の素材が安定的に供給される目処が立ったことで、新開発の機関はより限界を突き詰めた設計が可能となり、ガミラス戦役末期から精力的に開発が進められていた。
そして、そうした数々の努力の結晶が、遂に実動した地球防衛軍再建計画において実戦配備が開始された『一式宇宙艦上戦闘攻撃機“コスモ・タイガーⅡ”』である。

ガミラス戦役中の傑作機(九六式)からペットネームを継承しているのは伊達ではなく、従来機と比しての性能向上は圧倒的だった。
速度・運動性・航続距離・対弾性・ペイロード・生産性のいずれもが、非常に高い次元でバランスしており、その挑みかかるような精悍なスタイルも相まって、新時代の傑作機の名を欲しいままにした。もちろん、一部の性能に限れば、先発の零式が傑出する領域(運動性や航続距離)も存在したが、トータルバランスと取得コストでは比較にならなかった。
また、本機用に開発された新型タキオンエンジンには十分な出力余裕があり、後の大きな発達余裕をも本機に約束していた。事実、その後の二〇年間で開発された本機のバリエーションやサブタイプは優に三〇種類を超える。特にガトランティス戦役後に配備が開始された二二型は、ハードポイントの増加やそれに伴う機体強度の改善により、マルチロール・ファイターとして完成の領域に達し、以後の本機の進化の方向性を決定づける役割を果たした。
ガミラス戦役以来、地球防衛軍航空隊を悩ませた課題の一つに、対艦攻撃兵装の威力不足がある。機体の生産性確保と数の限られる搭乗員の有効活用を目的として、地球防衛軍の戦闘機と攻撃機(戦闘攻撃機)は、永らくコスモ・タイガーⅡ(CTⅡ)系列機で統一されてきた。しかし、CTⅡ系は艦載機、しかも格納庫容積の乏しい戦艦にも搭載可能な機体として原型が開発された為、機体規模が非常に限られていた。言い換えると、重防御且つ大質量の攻撃目標――大型戦艦――をも撃沈可能な大型対艦誘導弾を搭載するには、機体が小型過ぎたのである。
その結果、地球防衛軍航空隊のタクティカル・ドクトリンは、永らく防空と偵察、そして近接航空支援(直掩)に特化せざるを得なかった。フェーベ沖会戦における大規模対艦攻撃のような例外もあったが、本会戦における母艦航空戦力の集中投入にしても、当時の地球防衛艦隊司令長官の“奇策”に過ぎず、体系化された戦策・戦術というには程遠かった。
また、大戦果と引き換えに、ガミラス戦役以来のヴェテランパイロットの大半がフェーベ沖で喪われたことも、当面の航空隊編成に無視できない影響を残していた。長駆侵攻の上、敵防空網を突破、敵艦に対艦攻撃兵装を叩きつけるには、防空や近接支援とは比較にならない程の技量(と訓練時間)が要求されるが、そうした技量を持った搭乗員が一時的とはいえ、完全に枯渇してしまったからである。
こうした状況にある程度の改善が見られるようになったのは、2205年頃であった。この時期、新型空母『キエフ級戦闘空母』が就役し、戦略指揮戦艦や主力戦艦に搭載される戦闘機隊の充足率もようやく八〇パーセントの大台を超えようとしていた。
しかし、これらの航空隊にしても、キエフ級搭載部隊を除く大半が防空と近接航空支援に特化した部隊に過ぎなかった。ある意味、この時期の航空隊は多数配置された新人搭乗員の能力を極限まで限定することで、“促成栽培”と部隊としての定数確保を成し遂げていたと言えるだろう。
しかし、その判断の正しさは疑うべくもなく、少なくとも頭数において十分な搭乗員が確保されて以降は、航空隊全体の練度向上も急速だった。勿論、太陽危機やディンギル戦役においても少なくない搭乗員が喪われていたが、それでも定数以上の搭乗員が余裕をもって確保されていたことが有効に機能し、こと航空隊に限っては両戦役後も比較的良好な状態が維持されていた
その証拠に、ディンギル戦役以降、戦艦部隊に搭載された戦闘機隊(実質的には戦闘攻撃機隊)ですら、長駆しての制空権獲得任務や対艦攻撃任務が限定的ながら実施可能な部隊練度を有するようになっており、規模・練度共にガトランティス戦役直後の航空隊とは別次元の存在にまで成長していた。
だが、搭乗員の面では今や質・量共に第一級戦力に成長した航空隊にも、未だ逃れられぬ“呪縛”があった。2201年以来、主力機材として運用を続けているCTⅡ系列機のペイロード不足である。
タキオンエンジンの換装を含む度重なる改良により、CTⅡ系の機体性能はガトランティス戦役時の主力だった初期生産型(一一型)と比べれば隔世の感すら抱くほどに進化していた。しかし、機体寸法に起因する対艦攻撃兵装のサイズ的制約と、それに直結した威力不足ばかりは、如何ともし難かった。
勿論、当時の航空隊の急速な陣容強化は、配備・運用機種をCTⅡ系一本に統一したことで成し遂げられたものであり、仮に大威力兵器を搭載可能な大型攻撃機などの機種を多種多様に開発・配備していた場合、度重なる戦役の混乱も相まって、未だ航空隊は深刻な機材と人員不足に悩まされていたであろうことは想像に難くなかった。
ある意味、こうした状況は、人員機材の確保と育成を最優先事項としたこれまでの地球防衛軍の航空隊編成方針を維持している限り必然であり、その限界でもあった。航空隊自身もその点は重々承知しており、限りなく単能化された集団から、本来航空隊が有しているべき多能性と柔軟性に満ちた存在へと昇華すべき時だという声が、部内のみならず部外からも高まっていた。
もちろん、航空隊とは対照的に度重なる戦乱によって艦艇と人員を消耗し続けている地球防衛艦隊の状況を思えば、航空隊の全面的なドクトリン刷新や陣容強化は、特に予算面で大きな困難が予想された。しかし、ディンギル戦役後の防衛軍内部で最も高い練度と分厚い陣容を有するのが航空隊である以上、その有効活用は組織論的にみても十分な説得力を持っていた。
その結果、航空隊関連予算は2207年以降大幅に拡大され、技術部門の総本山とも言うべき航空本部の陣容も著しく強化された。そして、満を持してスタートした各種新型機開発計画の中で特に注目を浴びたのが、“ポスト・CTⅡ”とも言うべき『次期主力戦闘攻撃機(FA-X)』計画と、地球防衛軍初のカテゴリーとなる『大型攻撃機(A-X)』計画であった。前者は、これまでの航空隊方針からの決別を告げる象徴的な開発計画と捉えられ、後者は長年の懸案であった攻撃力不足を解消する決定打と考えられていた。
だが、これらの計画は、スタートから一年も経ずに大幅な見直しを強いられることになる。2208年末、画期的な空対艦誘導弾用弾頭――通称『波動融合弾』と呼ばれる大威力弾頭が開発されたからだ。

波動融合弾――2230年現在、地球防衛艦隊が主要装備として運用している実体弾頭の中では『波動カートリッジ弾』と双璧を為す存在であり、名称が近いこともあって混同されることも多いが、兵器体系的には別種の存在である。
波動カートリッジ弾とは、空間磁力メッキを施した弾頭内に波動エネルギーを充填し、それを爆縮させることで波動砲と同種の大規模空間歪曲現象を局所的に発生させる兵器である。充填されるエネルギー量は戦艦級大型波動砲の1/100程度であり、威力係数もほぼそれに比例する。しかし、弾頭の起爆には波動エネルギーの最小臨界量以上のエネルギー量が必要であることから、一定以上の弾頭容量が必要であり、ショックカノン用であれば一六インチ以上、宇宙魚雷用でも同程度の容量を持つ大型弾頭でなければ成立要件を満たすことは不可能であった。
波動カートリッジ弾実用化当初、本弾頭を空対艦誘導弾用弾頭に発展させる構想が持ち上がり、その実用化には航空隊関係者から大きな期待が寄せられた。だが、主砲弾や宇宙魚雷用と比べて遥かに小型・小容積の空対艦誘導弾の弾頭に、最小臨界量を超える波動エネルギーを充填することができず、開発はあえなく頓挫してしまう。
しかしその後、デザリアム戦役において二重銀河を全面崩壊に導く一因となった、波動エネルギーに強い反応を示す星間物質――波動融合物質(通称:D物質)――の研究が進み、限定的ながら波動融合反応のコントロールが可能になったことから、停滞していた大威力弾頭の開発は一気に進捗した。
具体的には弾頭を、波動エネルギーを充填した第一弾頭とD物質を充填した第二弾頭で構成される二重弾頭とし、命中と同時に第二弾頭が第一弾頭へ激突、任意に波動融合反応を発生させるのである(この弾頭構造は、ディンギル戦役において地球防衛艦隊を苦しめた“ハイパー放射ミサイル”の弾頭構造を参考にしたとも言われている)。
波動融合反応における両物質の最小反応量は、波動エネルギー単独での最小臨界量と比べて遥かに少量であり、それ故に弾頭の小型化・小容量化が容易であった。事実、波動融合弾頭を実装すべく新規開発された『仮称(特)九式空対艦誘導弾』は、サイズと重量共にフェーベ沖会戦時の主力誘導弾『一式空対艦誘導弾』とほぼ同等であり、最新型のCTⅡであれば、最大四発の搭載が可能であった。
四発同時命中時の威力係数は、一六インチショックカノン用波動カートリッジ弾一発の威力に相当するとされ、一個航空隊全力攻撃時(一八機)の威力は(あくまで算術上であるが)一六インチ砲搭載戦艦の波動カートリッジ弾射撃二斉発分にまで達した。
この威力は、既存の航空隊の攻撃力を一挙に数十倍化させるものであり、全ての航空隊関係者を狂喜させたと言われている。
しかし、当時の波動融合物質――D物質はウェポン・システムとして用いるには未だ不安定な部分を多々残しており、一夜にして地球防衛軍の航空機用兵備の全てを書き換えてしまうまでの存在にはなり得なかった。寧ろ、開発以後の完成と普及に至る道筋は辛苦多難の連続だった。
最初にして最大の苦難は、(特)九式誘導弾の運用試験中に発生した。試験艦に指定されたローマ級主力戦艦“メイン”でD物質が引火・誘爆し、一瞬で爆沈するという大惨事が発生したのである。爆発の規模は凄まじく、試験データ採取の為に随伴していた戦闘巡洋艦までもが巻き添えの形で中破したほどだった。

事故の原因は、実弾運用試験の為に格納庫に仮設されたD物質精製/充填装置からのリークと考えられた。
D物質は非常に劣化しやすい性質を持ち、物質を弾頭に充填したまま長期保管することは、当時の技術では不可能であった。故に、使用時に初めて、精製されたばかりの『新鮮な』D物質を弾頭に充填しなければならなかった。
その解決策として、D物質の精製/充填装置が“メイン”艦内に設置された訳だが、様々な形で波動エネルギーを常用している地球艦艇では、常に誘爆のリスクと隣り合わせの、あまりに危険なウェポン・システムと言えた。
事後調査の結果、“メイン”の爆沈は、D物質充填時の安全対策の不備によって発生した“事故”と判定された。しかし、平時ですら安全確保が困難なシステムを戦時に、しかも被弾や損傷が当たり前の戦艦や巡洋艦に搭載する是非については、事故調査委員会からも強い指摘と問題提議が為された。
最新鋭主力戦艦とその全乗員を一挙に失うという甚大な犠牲、そして事故調査会における糾弾から、波動融合弾は、一時は開発継続すら危ぶまれた。しかし、航空隊関係者の努力と融合弾の将来性に着目する防衛軍首脳部の理解により、辛うじて開発中止という最悪の事態だけは免れることができた。
しかし、誘爆事故の影響はあまりにも大きく、艦の構造上、波動エネルギーと融合物質の完全な隔離が難しい中小艦艇は勿論、空間打撃戦を主任務とする大型艦艇(戦艦・戦闘巡洋艦)への融合弾配備まで断念せざるを得なかった。つまり、波動融合弾の搭載はアマギ級唯一の生き残りである“グローリアス”とキエフ級以降の戦闘空母群に限定されてしまったのである。
だが、この決定に対し、最悪、開発の中止すら覚悟していた航空隊関係者は、寧ろ強く安堵したと言われている。彼らにとっても、主力戦艦一隻とその全乗員の犠牲は、それほどの重みがあったのだ。
波動融合弾の配備により、地球防衛艦隊戦闘空母群の対艦攻撃力は、事実上一挙に数十倍化した。しかし、融合弾配備による影響はそれだけに止まらなかった。
空母群の攻撃力向上は、即ち現行主力艦載機であるCTⅡの攻撃力向上に他ならず、開発がスタートしたばかりの新型機の必要性が著しく低下してしまったからだ。その結果、『大型攻撃機』計画は開発中止とされ、『次期主力戦闘攻撃機』計画も人員・予算が削減、開発ペースが大幅に落された。削減された予算は次年度以降、空母建造予算に充てられており、ここからも地球防衛軍の方針変更が見て取れる。
空母群の増勢は、航空隊と母艦を“攻撃戦力”として評価するに至った防衛軍の変化が最も顕著に現れた結果であり、以後かなりの期間継続されることになる。更に、こうした評価の変化は母艦群の戦略価値の変化に他ならず、以後の地球防衛艦隊の艦隊編成と空母設計にすら影響を及ぼした。
従来、地球防衛艦隊における空母運用は、一~二隻の空母に一個駆逐隊(三~四隻)程度の護衛戦力を付属させた“巡航空母戦隊”を基本単位としていた。戦艦に比べて建造優先順位に劣る各種空母は、建造隻数が少数であったこともあり、独立戦隊として束ねられ、必要に応じ各艦隊に派遣されるという編成方針が採られていたのである。
派遣された空母戦隊の任務は、直掩と偵察に集約できた。ここでの直掩は敵の航空攻撃に対するエアカヴァーのみならず、艦隊戦闘時の近接攻撃支援も含まれる。しかし、これらの任務はあくまでも“支援”であり、攻撃戦力の中核を担うのは同じ艦隊内の戦艦や宙雷戦隊であった。また、偵察についても前路哨戒と共に弾着観測が同様の理由で重視されていた。
こうした編成と運用は、洋上戦力として航空母艦の優越が証明される第二次世界大戦開戦前夜の、各国海軍の艦隊編成にも似ていた。
二〇世紀の中盤まで、世界の海軍では戦艦部隊が質・量共に主力を占め、相対的に少数の空母部隊は搭載機の攻撃力の小ささもあって漸減・補助戦力として扱われていた。しかし空母が、搭載機と兵装の進化によって旧来からの海洋の女王――戦艦を撃沈可能なまでの攻撃力を有するようになり、それが現実の海戦で証明されると、その価値は激変した。元より有していた高い機動力、柔軟性と集中性に、他を圧倒する攻撃力が加わったことで、海洋における最強・至高の地位にまで一気に登りつめたのである。
二百年以上の刻を経て、宇宙空間で起きた事象は一見するとその焼き直しにも見えたが、正確には異なる。
確かに、波動融合弾配備によって劇的なまでの攻撃力向上を果たした空母は、常に艦隊の中心にあって、厳重に守護されるべき高価値対象(HVU)となった。だが、地球防衛艦隊においては未だ各種波動砲搭載戦艦が主力の立場を維持し、投入される防衛予算・人員もそれを裏付けていた。現実的に見て、空母はそれに準じる立場に過ぎないのが実情だったのだ。
しかし、高い攻撃力の代償に、艦内に危険極まりない波動融合物質を搭載したことで付随的に発生した空母の極端な脆弱化が、こと艦隊運用においては空母に最も高い防護価値を与えるという皮肉な結果を与えてしまったのである。それは同時に地球防衛艦隊の“戦闘空母神話”の終焉をも意味した。

充分な護衛艦に厳重に防御され、自ら行う直接砲雷撃戦は誘爆リスクの点から実質的に不可能となったことを思えば、それも当然だった。ならば、建造コストを高騰させるだけでなく、空母にとって何より重要な艦載能力を低下させることになる波動砲やショックカノン等の砲雷装備は全く不要であるという結論は容易に導き出された。
幸い、この頃にはガミラス戦役後からガトランティス戦役勃発前の、極端な波動砲絶対信仰も大きく緩和されており、“非・戦闘空母”――本格空母建造に対する抵抗は殆どなかった。
劇的な攻撃力向上を果たした空母群、そしてその周囲を固める分厚い陣容の護衛艦隊――新たに完成した地球防衛艦隊の戦闘単位『空母任務群』は、長年航空隊関係者が夢にまで見た“空母機動部隊”に他ならなかった。
2210年、地球防衛艦隊は既存の戦闘空母で四つの空母任務群を編制し、更に2220年までに二個群の追加編成まで計画していた。この追加二個群用に建造されたのが、前述した地球防衛艦隊初の本格空母『ベアルン級宇宙空母』である。
各空母任務群は中核である二隻の戦闘空母と護衛艦艇約二〇隻で構成される。一個任務群による全力攻撃時には、最大一〇〇機のCTⅡが波動融合弾頭装着対艦ミサイルを各四発抱えて出撃し、その威力係数は大型戦艦の波動砲射撃にも匹敵した。しかも、その威力投射を非常に柔軟性の高い戦力である航空機が担っている為、戦場における実際の威力は、面制圧効果の高い拡散波動砲に比べても数倍化すると評された。これは、発射後は射線が固定される波動砲と比べて、個別の航空機から任意ターゲットに向けて発射されるミサイルの方が、遥かに威力ロス(無駄撃ち)が少ない為だ。
地球連邦を仮想敵国第二位(一位は言うまでもない)としているボラー連合軍(旧・ボラー連邦軍)も、地球防衛艦隊が新たに手にした長槍――空母任務群の動向を常に注視しており、これに対抗する形でボラー初の空母機動部隊の編制を開始した。
また、天の川銀河のもう一方の雄――ガルマン・ガミラス帝国も地球の空母任務群に注目していた。但し、既に多数の空母機動部隊を保有し、積極的に活用していた彼らの興味の対象は、戦闘空母や波動融合弾といったハードウェアよりもソフトウェア――用兵思想の方であったとされる。
地球人たちが波動エンジン実用化後一〇年近くをかけてようやく完成させた空母機動部隊が、従来のドクトリン(防空と近接支援)に対する反動故か、極端なまでに対艦攻撃能力を偏重した“決戦戦力”に仕立てられていたからだ。
ガルマン・ガミラス帝国軍空母機動部隊も、規模の巨大さ故、相応の攻撃能力を持ち合わせていたが、寧ろあらゆる戦術状況に対応可能な汎用性こそが重視されていた。各任務に特化した豊富な専用機種のラインナップこそ、その象徴と言えるだろう。新編されたボラー連合の空母機動部隊にしても、規模や戦闘能力こそ異なるが、基本的なドクトリンはガルマン・ガミラスとほぼ同様であり、巨大星間国家が空母部隊に求める本質が共通することを示している。

もちろん、未だ単一星系国家に過ぎなかった当時の地球に、二大国のような巨大な空母部隊や広範な機種ラインナップの整備は国力的に不可能であり、汎用性を犠牲にしてでも短期迎撃戦における瞬間的な破壊力と、平時における抑止効果を重視した空母部隊の建設に踏み切ったことは一つの見識であったと言える。しかしその代償として、地球防衛軍の空母機動部隊は2230年に至るも、攻撃力一辺倒のタクティカル・ドクトリンから未だ脱皮することができていないのもまた事実である。
波動融合弾の配備によって開発計画がスローダウンした次期戦闘攻撃機“FA-X”は一八式宇宙艦上戦闘攻撃機“コスモ・パルサー”として2218年にようやく完成、配備が開始された。本機はコスモ・タイガーⅡのコンセプトを手堅く受け継いだマルチロール・ファイターであり、装備換装による汎用性は先代機以上と高く評価されている。また、機体規模もCTⅡ譲りのコンパクトさを維持しており、更に主翼の折り畳み機構などの格納効率向上に向けた取り組みも徹底されていた。
しかし、そのコスモ・パルサーの高性能が、他の専用用途機の開発を実質的に阻害している点もまたCTⅡと同様であった。そして、どれほど汎用性に優れていようとも、用途に特化して開発された専用機には性能面で敵う訳もなく、その点で地球防衛艦隊の保有する空母は次なる進化への段階、本来あるべき空母の姿には未だ至っていないとされる。
そしてその姿こそ、『護衛空母』『攻撃空母』の先にある『多目的(汎用)空母』であり、その進化形の整備と保有こそが、規模の拡大にも係らず未だ星系内防護艦隊の色合いを拭い切れない地球防衛艦隊が、真の外宇宙艦隊へと脱皮したことを証明する何よりの試金石になると主張する研究者は数多い。
――おわり――
さて、gooブログへ引っ越し後初の妄想設定となりますが、如何だったでしょうか?
実は昔からヤマト世界の航空機用機関は謎に思っていました。
今回の妄想で、ようやくそれに一区切りすることができまして、実は個人的な満足度は極めて高かったりします(^o^)
ちなみに、妄想を書き上げるにあたり、頭を悩ましたのは、以下二つの事象です。
(1)波動機関搭載艦と同一の速度領域で戦闘行動が可能。
(2)ヤマト発進前に既に量産機が実戦配備済み。
他にも色々とありますが、筆頭はやはりこの二つでしょう。
これが昨今の『2199』であれば、航空機は星系内速度で航行中の状態でしか運用できない兵器として割り切ってしまってもいい気がしますし、正直言ってその方が現実的だと思います。
でも、ウチは外宇宙も星系内も関係なしにコスモ・タイガーやコスモ・ゼロが元気に飛び回るオリジナル版準拠の世界観なので、外宇宙航行時であっても戦闘可能なように設定を都合よく弄り回しました(笑)
本来は、宇宙空母の前編や中編を書く前にこれを書かないといけなかったのですが、当時は頭の中で妄想が整理し切れず、結果的に航空機用機関については確たる考えを整理しないまま(あまりそれには触れないようにw)宇宙空母の設定妄想を書き始めてしまったのです(^_^;)
その結果、今回の設定妄想と宇宙空母の前編に書いた内容に矛盾が生じてしまったので、後日宇宙空母の方を修正する予定です。
その後で、やっとこさ宇宙空母の後編に取り掛かります。
ちなみに、文中で計画中止になった『大型攻撃機(A-X)』はPS2ゲームに登場した『中距離ミサイル爆撃機』をイメージしています。
ゲームをやり込んでいた当時から、この機体はデザインも機能も、オーパーツとしか思えなかったので、そういう扱いになりました(^_^;)
設定資料集のデザイン画を見ると、無茶苦茶カッコいいんですけどねぇ・・・・・・。