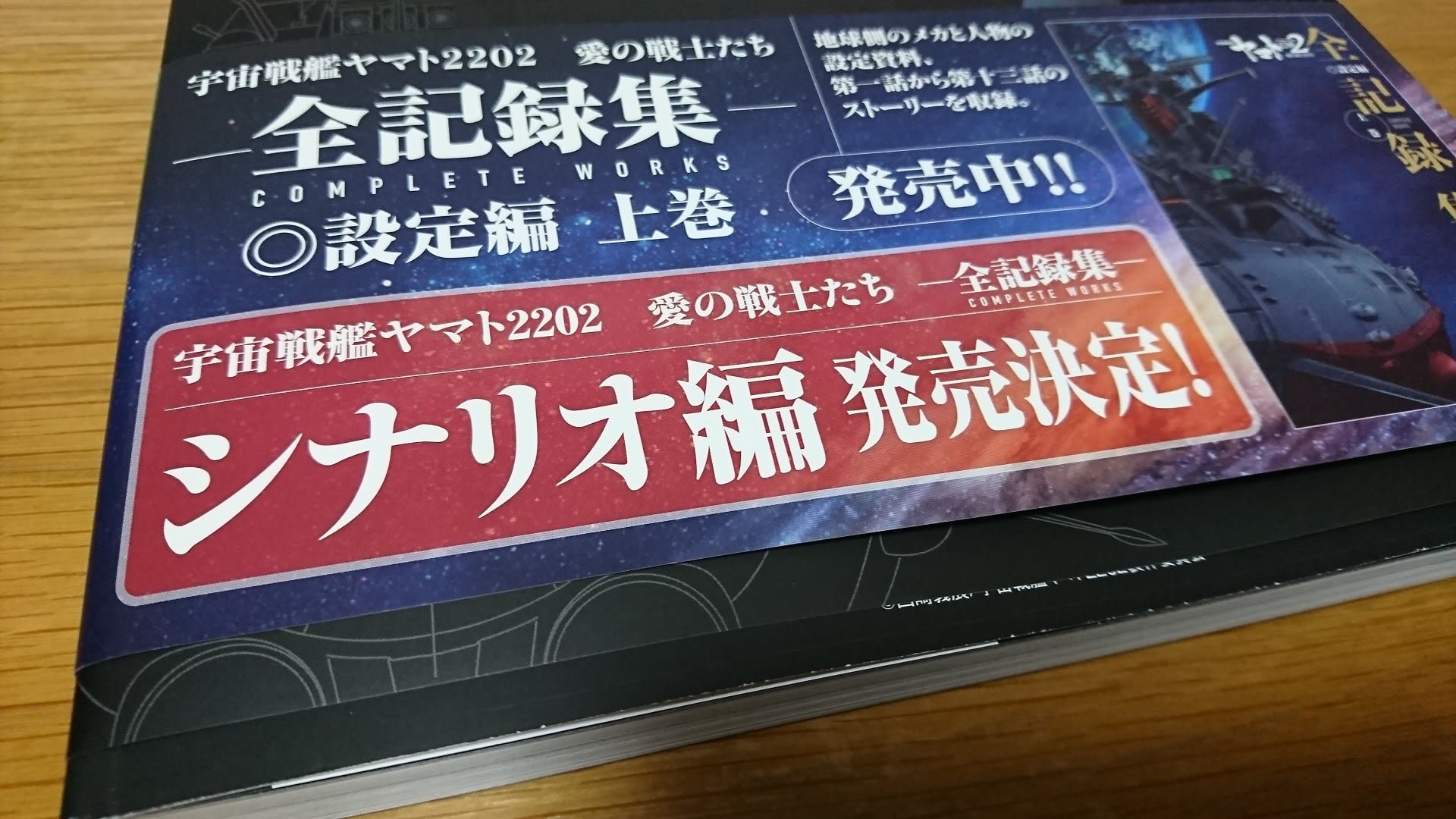――2203年6月4日 地球沖
――U.N.C.F ZZZ-0001 YF-2203“アンドロメダ改”艦橋内

「――寂しいな。なぁ、アンドロメダよ」
艦長シートでそう独りごちた男の視線が向けられた先には、一枚のポートレートがある。先進性と機能性に満ちた最新鋭戦艦の艦橋に、昔ながらのL版サイズにハードコピーされた写真――しかも乱暴にテープで留められただけの――は、いかにも違和感があった。
しかし写真を、いや、そこに写った人々を見つめる男の瞳は寂寥の色こそ含んでいるものの、どこまでも穏やかだ。その姿は僅か数日前、人類史上最大・最強の宇宙艦隊を率いて獅子吼していた人物のものとはとても思えない。
その男、地球連邦防衛軍 一等宙佐 山南修は飽きることなく写真を眺め続けていた。まるでそうしていれば、その頃の自分たちに戻れると心底から信じているかのように――だが、そんなことは夢物語に過ぎない。写真の中の二人は既に鬼籍に入り、更にもう一人もMIA(作戦行動中行方不明)だ。
(やれやれ、自動艦というのもやっかいだな。
本来は最も忙しく、騒がしい筈の出撃時に、艦長が想い出に浸る以外、何もする事がないなんて。
精神衛生上、非常によろしくない)
自他共に認めるリアリストである彼が先程から写真を眺め続けていたのは、決して感傷的な理由ではなく、単純に他にすることがなかったからだ。そしてそれこそが、フル・オートマチックでの高機動三次元戦闘すら可能なよう大規模改修を施された『アンドロメダ(改)』の真骨頂だった。いや、アンドロメダ改だけではない。山南が指揮する麾下の全艦が、AIによる完全自律制御艦『アンドロメダ・ブラック』で構成されているのだ。
いくら無人艦、省人艦とはいえ、人を乗せるなら、少しは忙しくさせないと駄目だ。慎重傾向の強い奴、思考にマイナスベクトルのかかりやすい奴ほど、いらぬ事を考えてしまう――今の俺のように。
山南は、航宙中の所感を書き留める為にいつも胸ポケットに潜ませている小型の手帳と万年筆に手を伸ばし――苦笑と共に引っ込めた。既に彼の全身は、艦固有の慣性制御装置では打ち消しきれないレベルの高機動戦闘に耐久可能な強化スーツに包まれており、当然そこに“胸ポケット”など無い。
(自ら志願したこととはいえ、全くひどい扱いだな、これは。
いや、新手の罰ゲームと言うべきか)
そんな自嘲に耽る艦の主の想いを悟ったかのように、目前のTCP――Tactical Ctrl Pad(戦術情報表示/操作盤)――が音響と発光で山南に注意を促した。僚艦とのトランス調整中の自艦とBBB戦隊のワープ準備が整うまで、残り3分を切ったのだ。
ワープ目標は、今現在も地・ガ連合艦隊が死力を尽くして白色彗星を食い止めている火星戦線。
『挺身艦隊』と名付けられた彼の艦隊は、白色彗星本体――通称:都市帝国――の直上へワープアウト、その中枢と思しき上部構造物の至近から最大出力で波動砲を集中射する予定だった。土星沖での戦いでは、地球艦隊の放った波動砲は悉く都市帝国の展開する強固な防護スクリーンで無効化されてしまったが、ガス帯の内部から、それも反応時間を与えない程の至近距離からならば――という訳だ。
ワープアウト直後の波動砲発射を可能とする為に、彼らの改A級及びBBB級は無人のD級二隻を“ブースター”としてそれぞれ接続している。ワープはD級によるトランス・ワープで実施し、波動砲発射をアンドロメダ級で行うという寸法だ。
あまりに危険で乱暴な作戦計画故、部内では彼の艦隊を正式名ではなく“殴り込み艦隊”や、欧米諸国軍では“カミカゼ・フリート”と呼ぶ者までいるらしい。
そんな、自殺行為と紙一重とまで評された作戦を遂行する艦隊に、山南が独りで乗艦しているのには当然理由がある。
本作戦はその危険さ故、当初は完全無人の艦隊で実施される予定だった。しかし、何度AIがシミュレーションを繰り返しても、都市帝国に波動砲を叩きつけられる艦は艦隊総数の20%にも満たず、その実施効果が疑問視された。だが、本作戦の直接指揮を強行に主張し続けていた山南が艦に乗り組んで指揮を行った場合のシミュレーションでは、波動砲発射を果たした艦の数は、実に七割にまで達したのである。
それでも、藤堂統括司令長官はあまりに生還の可能性が低いとして、山南の艦隊司令就任と乗艦に難色を示した。しかし、二度三度と繰り返されたシミュレーションの結果と、外ならぬ山南自身の強い希望が最後は決め手となった。
結果、山南の直接指揮は認められ、艦隊ただ一人の“人間”としてそこに在った。彼の役目は、最適なタイミングで挺身艦隊をワープさせると共に、波動砲発射の瞬間を見極めることにある。
(罰ゲーム・・・・・・いや、土星沖の敗北と損害を考えれば、これでも有難いくらいだ。
それよりも、お前まで巻き込んですまないな、アンドロメダ)
土星沖で大破しつつも辛うじて帰還したアンドロメダは、直ちに時間断層工廠での緊急修理に入った。しかし各種検査の結果、そのダメージは艦の命たる次元波動エンジンにまで及んでおり、最早修復は困難であるとして、廃艦処分の決定が下されたのである。
結果、山南の乗艦は新たに用意された“別の艦”になると説明されていた。しかし――。

「これが、その?」
「そう、アンドロメダ級試作艦だ。0番艦、零号艦などとも呼ばれているな。
こいつで諸々の新装備の実装試験をやった後、あんたらの一番艦以降が建造された。
その後、お役御免でモスボールされていたのを、無理やり引っ張り出したって訳だ。
――公(おおやけ)には、だがね」
彼が新たに乗り組むことになった艦の説明を請負ったのは、既に初老の域すら超えているように見える年かさの工廠責任者だった。その口調も態度もぶっきらぼう極まりなかったが、どこか悪戯小僧のような色を含んでいる。
そこは時間断層工廠に隣接した最終検査場。通常空間に設置されている為、行動力と行動時間が著しく制限される(そして暑く、重ったるい)時間障害防護装備が不要なのが有り難かった。
彼らの見上げる先には、見なれた防衛軍グレーに彩られたアンドロメダ級の姿がある。
波動砲口がD級の設計とパーツを流用して疑似四連装化された他、艦の各所に高機動用スラスターとその注意書きのイエローマーキングが目立つようになってはいたが、彼の知るアンドロメダ級からそれほど大きく変容したようには見えない。だが、外観がどれほど似通っていても、たとえ艦載AIを移植していたとしても、この艦は“俺のアンドロメダ”ではない――彼はそう聞いていたし、彼自身もそう思っていた。
故に、山南は工廠長の意味ありげな説明に眉をひそめた。自然と口を突く言葉も尖り気味になる。
「公には?では、非公式には?」
「こいつは正真正銘――“あんたのアンドロメダ”だ。試作艦なんかじゃない」
工廠長は、そこだけは山南の瞳を見つめてきっぱりと言い切った。そして驚く山南を後目に矢継ぎ早に言葉を続ける。
「驚いたろ?しかし苦労したんだぜ。
その試作艦や建造中のD級からありったけの部品を引き抜いて突貫で仕上げたんだ。
BBB?あれは絶対にダメだ。
無人艦だから素材も加工精度も有人艦よりかなりランクが落としてある。だから見た目よりも俄然脆いんだ。
懸案だったのはむしろ波動砲の修理の方さ。
幸い、BBB級の設計時、D級二隻分の波動砲システムをそのまんま流用するってアイデアがあったらしくってな。その設計が流用できたんで、なんとか間に合った。
・・・・・・まぁ、あんたも知っての通り、上からの命令は、真逆――アンドロメダから使える部品を引き剥がして、試作艦を実戦仕様にしろ――だったんだけどな、俺の判断で握りつぶした。
それでも、さすがに艦籍までは誤魔化しきれなかったんで、艦番号は変えざるを得なかったが。ま、その点だけは勘弁してくれや」
延々と、しかも嬉々として語られる説明に、さすがの山南も暫し言葉を失った。工廠長の口調はまるで茶飲み話のような気楽さだったが、その内容はあまりに重大な命令違反だったからだ。
「しかしそれでは――」
「あぁ、勝手に艦をすり替えたんだ。
今の政府と軍が続く限り、俺は軍刑務所で終身刑だろう。
しかし、いいんだ。俺は、あんたに借りがある」
「借り?すまない、とんと記憶にないんだが」
「そりゃそうだ。
俺の倅(せがれ)は、第二次火星沖海戦でテンリュウに乗り組んでた。
倅は言ってたよ、俺は、安田艦長とあんたの艦に救われたんだと」
工廠長の説明に、山南はようやく愁眉を開いた。まさかここで、安田と第二次火星沖海戦の名を聞くことになるとは。
「それで・・・・・・。御子息はご健勝か?」
「あぁ、きっと“向こう”で、嫁や孫や婆さんと楽しくやってるよ。
・・・・・・俺は、あんたには本当に感謝してるんだ。皮肉じゃないぜ。
倅があの戦いから生きて帰れたからこそ、俺も死んだ婆さんも生まれて初めて“孫”ってもんを抱くことができた。時間は短かったがな。だけど、その記憶も感触も幻じゃない」
「・・・・・・お察しする」
「なぁに、気づかいは不要さ。俺は自分が為すべきと信じたことを為しただけだ。
倅の恩人が任務を果たせる可能性を1%でも増やせるよう全力を尽くしたまで。
バカなお偉いさんと取り巻きどもは、艦載AIさえ乗せ換えれば同じだろうなんて言いやがったがな、あいつらは船乗りの心意気が分ってねぇ。フネは女房と同じだ、“按配”ってもんがあるんだ。
お前ら、夜な夜な女房のどこに乗っかってんだと聞いてやりたいね」
工廠長の突然の“ヘルダイブ”に思わず吹き出した山南だったが、直ぐに口調と表情を改めた。
「工廠長、もういいよ。しかし――誠にありがとう」
工廠長は、自らの仕事を正当に評価された職人に特有の、はにかんだ笑みを浮かべた。そして眩しげな表情で再びアンドロメダを見上げる。
その瞳に浮かんでいるのは紛れもない愛着であり、我が子に向けるのにも似た、純粋なまでの愛情だった。

「山南さん、こいつはちょっとツンとしてるが、素直ないいフネだよ。
俺には分るんだ。次の戦いでも、こいつはあんたを守りながら、あんたの望む全ての行動を完璧に果たしてくれる。
――だから、頼みます」
いつの間にか、工廠長の目はアンドロメダではなく、山南に向けられていた。そしてその口調もまるで別人のような真摯さに満ちている。
「山南さん、いや山南艦長。
俺は二度の内惑星戦争とガミラス戦争を幸運にも生き抜くことができた。
勝ち戦(いくさ)も負け戦もたくさん見たよ。しかし、勝とうが負けようが、どちらにせよ――その後は悲惨だった。
内惑星戦争じゃ、地球に移住させられた火星の連中が随分と酷い目に遭ってたし、ガミラス戦争は――言うまでもないな。
だから、俺はもう勝ってこい、勝ってきてくれとは言わない。
頼む、この戦争を終わらせてくれ。
土星では、ヤマトも喪われたと聞いた。
だからもう、それを頼めるのは、あんたとアンドロメダだけだ」
そう告げる工廠長の声は決して大きくはなかった。いや、休みなく騒音が響き渡る工廠内では、かき消されてしまいそうな程に小さかった。しかし山南にはそれが、この老人の魂が上げる絶唱、慟哭のようにも聞こえた。
最早この老人には、何もないのだ。家族も親族も友人すら殆どを戦争で失い、残されたのは工廠での仕事だけ。だが、それでもこの老人は何を恨むでも呪うでもなく、戦争を終わらせる為に、自分のような境遇の人間を一人でも減らす為に、自身の持ち場で今も戦い続けている――。
(・・・・・・ヤマト)
全ての動力を喪い、白色彗星に落下していく最期の姿が脳裏に甦る。
いや、俺は信じない。ヤマトは沈んでなどいない。必ず生きている。土方さんや古代が簡単にくたばったりするものか。
あのフネは、たった一隻で敵の本拠地に乗り込み、戦争を終わらせ、地球と人類を救った。そのフネを指揮し、魂を塗り込めた漢を、俺は知っている。否、俺もその人から教えを受け、かの地で共に戦ったのだ。
その因縁深き火星沖で再び俺は戦う。今度は沖田さんも安田もいないが、俺にはまだ、馴れ親しんだアンドロメダがある。俺とアンドロメダが命を懸けて戦えば、まだ何事かを為せるかもしれない――嘗て沖田さんとヤマトが為したように。
(第二次火星沖では沖田さんにしか見えなかった何かが、今度は俺にも見えるだろうか?土星沖では、俺は何も――)
指揮官として、研鑽と修練を積み重ねてきたつもりだが、先だっての土星沖会戦では、俺は“機”を見出すことができなかった。“勝機”などと言うつもりはない。戦場、戦争を変える事のできる“機”を。
いや、思えばそれも当然か。あの戦いでのガトランティス軍の行動予測も、それに対する地球艦隊の作戦計画も、全て銀河AIが立案したもので、俺の作戦指揮はそこから一歩として外れるものではなかった。あんな戦い方に、人間の感じる“機”が入り込む余地などない。
山南は再びアンドロメダを見上げた。
――ならば、あやかってみるか、あのフネに。
「工廠長。お気持ちは承りました」
山南は工廠長に対し、男でも惚れ惚れするほどの色気に満ちた敬礼をピシリと決めた。
そして制帽を取り、これまでとは対照的な男臭い笑いを浮かべて更に言葉を続ける。
「それで、という訳ではないが・・・・・・もう一つ頼まれてもらえないか?」
――その“頼み”の結果が、今現在山南が乗艦しているアンドロメダの姿だった。
艦の上半分をブルーグレー、下半分をダークレッドに塗り分けたカラーパターンは、ガミラス戦争を終わらせ、地球人とガミラス人に同盟関係を結ばせるきっかけを作った“あの艦”そのものだった。
なんでも、山南が最後に依頼したこの塗装をアンドロメダに施すために、工廠長は完成間近のBBB戦隊で作業中だったペインティング用ガミロイドを大量に引き抜いたらしい。結果、就役したBBB戦隊の1/3程は、舷側に描かれる予定だったプロパガンダ用のテキストが省略されたという。
それらの点も含め、本当に大丈夫かと心配する山南に対し、工廠長は大笑しながらこう言ってのけた――聖書だのお経だのでビビってくれるような敵さんなら、宇宙戦争なんて起きやしませんぜ。味方だって、あんなモン見てる暇ないでしょう。俺にはそれよりも、乗ってる人間様が気持ち良く戦えるよう艦を仕上げる方が大事でさぁ――と。
だがその一方で、山南の懸念通り怒り狂っている者たちもいる。
「っ!?なんなんだ、あの色は!!」
“あの艦”は地球を救った栄光の艦である一方、そのあまりの偉大さ故に、その存在を疎ましいと考えている者も決して少なくはないのだ。それは特に、波動砲艦隊構想を強く推進してきた地球連邦防衛軍中枢に多いとされる。彼らにしてみれば、一艦長風情が勝手に国家間条約を結ぶなど言語道断であり、そのせいで、真に地球を憂う自分たちが苦労させられたという怒りと反発は極めて大きかった。
今、統括司令部で、大スクリーンに映るアンドロメダ改に向けた指先を震わせている司令部幕僚もそんな一人だった。いや、彼一人だけではない。司令部に詰めている高級幕僚の多くが、怒りに満ちた目をスクリーンに向けている。
現在の統括司令部内にそれを諫めるものはおらず、いや、彼らの首魁とも言うべき芹沢司令副長は在室しているのだが、彼はいつもの鋭く強い視線をスクリーンに向けるだけで、何も発言しようとはしなかった。
結果、芹沢の意も自らと同様と判断した司令部幕僚たちの怒りと言動は更にヒートアップする結果となる。
「あんな塗装色は規定にない!!誰が指示した!!誰が許可した!?
あれは・・・あれではまるで――」
「――局地迷彩だな」
猛り狂う幕僚たちとは対照的な声を上げたのは、休憩を終え、遅れて司令部に入室してきた藤堂統括司令長官だった。
普段、よほどの重大事でなければ、そして決定的局面でなければ、自ら口を開かない長官だけに、その発言は自ずと重きが置かれる。それは司令部幕僚はもちろん、副長であっても例外ではない。
「君らは分らんかね。上面はアースグレー、下面はマーズレッド。
火星―地球絶対防衛線に合せた局地迷彩色だよ、あれは。
規定色とは多少色味が違うが、資材不足の中、ありあわせの部材で何とかしたのだろうな」
規定色に塗られた艦が続々と戦列に加わりつつある状況で、その解釈はかなり無理のあるものであったが、平素と全く変わらぬ藤堂の表情と口調で整然と言葉を並べられると、面と向かって反論できる者は統括司令部にはいなかった。
「いえ・・・・・・長官。あれは・・・・・・・あれは・・・・・・どう見ても・・・・・・」
それでも、よほど“あの艦”の幻想が強くちらつくのか、件の幕僚は懸命の反論を試みた。しかしその時、司令部内にドンっと鈍く重い音が響き渡った。
立ち上がった芹沢が拳で副長席の卓を殴りつけ、幕僚たちを睨め付けたのだ。
「貴様らは現在の戦況が分っているのか!!
我々は既に火星圏にまで敵に踏み込まれているのだぞっ!
一隻の戦艦の塗装色に四の五の言っている暇など、どこにあるっ!!」
そう怒鳴りつけた芹沢の鬼の形相に、幕僚たちは完全に色を失い、慌てふためきながら元の職務に復帰した。苦々しい表情でそれを一瞥すると、芹沢は大きな溜息を一度ついた後で通信士を呼んだ。
「時間断層工廠へ長官と私の連名で電文を送ってくれ。
貴工廠の尽力を謝す。臨機応変の対応見事なり。引き続き職務に邁進されたし――とな。
・・・・・・宜しいですな?」
最後の一言は藤堂に向けたものであったが、芹沢はその返事を待たず、視線も合わせないまま自らの席に戻った。それは見る者によっては酷く礼を欠いたように感じられる振舞いだったが、藤堂は芹沢に対し一瞬だけ面白そうな表情を浮かべたものの、こちらも何事もなかったように副長の隣――長官席に着いた。
芹沢の言う通り、彼らには対処しなければならない懸案が山積みだったからだ。
統括司令長官と司令副長の連名で発せられた電文の写しは、程なくして山南の元にも届けられた。
(まったく。沖田さんといい、藤堂長官といい、芹沢副長といい、本当に大したものだよ)
TCPに表示された電文を見た山南は、込み上げてくる笑いを抑えるのに苦労した。
古代や斉藤の前では一端の指揮官面をして見せても、やはり俺はまだまだあの人たちには敵わないらしい。あの人たちが後ろで支えてくれているからこそ、俺たちはこうして万全の状態で戦えるのだ。
(感謝します、長官、副長)
少なくともこれで、後顧の憂いはなくなった。
決意を固めた彼の瞳は今、火星沖からリアルタイムで送られてくる戦況図に注がれている。
増援であるガミラス艦隊――バレル大使直率艦隊――が大きく突出、それに喰らい付くようにガトランティスも艦隊ラインを前進させていた。更にアルデバランの谷艦長率いる第二艦隊がこれを迎撃し、戦場は一気に混戦の度合いを増す。
しかし、地・ガ連合艦隊の戦術行動は全て陽動。一隻でも多くの挺身艦隊が都市帝国に肉薄できるよう、彼らは積極的に前線を動かし続け、ガトランティス軍の戦力と注意を誘引しているのだ。だが、精鋭のガミラス軍を加えたとはいえ彼我の物量差は圧倒的であり、このような無茶な戦い方はそう長くは続けられない。
そして、戦場の実態もほぼ山南が想像した通りだった。第二艦隊旗艦AAAアルデバランの艦橋内は、既に数時間前から修羅場そのものの様相を呈している。
「バレル大使へ通信を繋げ!旗艦が突出し過ぎだ。あれでは“盾”もろとも喰われる。
103戦隊は前進、直衛につけ!」
「白色彗星の重力干渉波により通信リンク不調、繋がりません!」
「続けろ、大使が出るまで呼び出し続けろ」
「敵超大型空母より艦載機多数発艦!数およそ90、いえ・・・・・・200以上!!
ガミラス艦隊に向かう!!」
「阻止しろ!速射魚雷、多連装ミサイル発射準備!
続けて重力子スプレッド弾一斉射!――撃ぇぇぇぇ!!」
艦長と艦隊司令長官を兼任する谷は、戦闘開始以来、一時も休む暇なく艦と艦隊の指揮を執り続けていた。
(畜生、まるで第一次火星沖だ。いや、あの時よりも手荒く酷いぜ)
彼自身、連戦の疲労による注意力と判断力の低下を自覚しており、本当ならアルデバランの指揮だけでも副長に任せたいところであったが、その副長も経験が決定的に不足している以上、このまま踏ん張り続けるしかない。
加えて、今の彼にはもう一つ気がかりがあった。
(まったく。勇気は買うが、文官なら文官らしく後方にいて欲しいものだ)
ガミラス艦隊の先頭に位置しているのは、よりにもよって大ガミラス帝星在地球特命全権大使ローレン・バレルの座上艦であり、谷としては気が気ではない。たとえ座上艦が、ガミラス軍で最も高い直接・間接防御力を誇るゼルグート級であったとしても、だ。
ガミラスへの技術供与の結果完成したガ式空母型アンドロメダ――口さがない者は“ガミドロメダ”などとも呼んでいる――の運用指導を担当し、ガミラス軍関係者とも深い交流を持つ谷は、ローレン・バレルという男を最もよく知る地球人の一人だ。
デスラー失脚後のガミラスで俄かに権限を増した内務省保安情報局の出身、ガミラス本星とも太い政治的パイプを有するこのガミラス人は、その柔和で落ち着いた相貌からは想像できないほどの胆力と行動力を持ち、地球との外交交渉においてもその辣腕、剛腕ぶりは広く知られていた。にもかかわらず、ガミラスの強大な国力や軍事力を必要以上に誇示するようなことはせず、あくまで交渉相手との互恵性を重んじる彼の外交姿勢は、地球連邦大統領以下の要人たちにも概ね好評だった。
その点、地球とガミラスの歴史的経緯や、埋めようのない根本的な国力格差を考えれば、ローレン・バレルという男は、地球にとっても理想的な同盟国大使だったと言えるだろう。
谷の見るところ、どうやらガミラス軍はバレルのゼルグート級を餌に敵戦力を誘出、それを、ガ式空母型アンドロメダを主力とする快速戦闘団――バーガー戦闘団――で叩き潰すという戦術を採っているらしい。事実、緒戦においてバーガー戦闘団は、ゼルグート級を狙って突出してきた三隻の特殊砲艦とその護衛艦艇群を僅か数分で殲滅するという大戦果を挙げていた。
本来、一国の大使が軍人に“餌”や“囮”として利用されるなど、大激怒して当然であったが、谷には、バレル自身が喜んでその任を引き受けているように思えて仕方がなかった。そして同時に、彼がアンドロメダ級の運用を手ほどきしたフォムト・バーガーという若い艦長の(決して不快ではない)不敵な笑みを思い出すと、その想像は殆ど確信に変わる。
(まったく、ガミラス人って連中は、誰も彼もが妙な具合に戦慣れしてやがる)
とはいえ、何事にも限度というものがある。
ガトランティス軍もガミラス軍侮り難しと見て、艦隊旗艦と思しき超大型空母まで最前線に投入してきた。幸い、搭載していたのが通常兵装の艦載機であった為、先程は難を逃れたが、あれがもし、土星沖で初めて姿を見せた新型刺突式兵器の大群だったら、ゼルグート級といえども危なかったかもしれない。
(まだまだあなたに死なれては困るのですよ、大使。地球の為にも、ガミラスの為にも)
「バレル大使が出ました!」
ようやく通信が繋がった同盟国全権大使に後退を勧めた(実質的には叱りつけるように命令した)ことで、ようやく安堵した谷であったが、今度は、自らの置かれている状況が厳に戒められるべきワンマンフリート以外の何物でもないことに怒りを覚え始めている。この殺人的多忙の中、そんな点に思いを馳せている時点で、彼も中々に複雑な男であった。
(せめて――艦隊・戦隊指揮官と艦長だけでも分離できていれば)
国力と軍事力で圧倒的に優勢な敵軍を短期決戦で撃滅することを旨とする『波動砲艦隊構想』とそれに基づく建艦計画は、ガトランティス軍の第十一番惑星襲来後、極端なまでに先鋭化した。時間断層工廠での建造艦は、収束型と比べて圧倒的に高い艦艇撃破効率を誇る拡散波動砲を発射可能な最小艦――D級が大半を占め、それ以下の中小艦艇の建造はほぼ等閑に付されたのである。
その結果、火力はあっても機動力に乏しい戦艦級艦艇のみで編成された地球艦隊は、集団での波動砲戦についてはこれ以上ないほど効率的な運用が可能となったものの、それ以外の戦術状況においては柔軟性を欠く極めて硬直した戦力と化した。
つまり、この時の地球艦艇群は、最早“艦隊”というよりも“砲列”に近い戦力単位と化していたのである。
もちろんそれは、止むに止まれぬ苦渋の決断という側面が強かった。十一番惑星に襲来した二百万隻を超える大型戦艦群は、白色彗星本隊の露払い――前衛戦力――に過ぎず、彗星本隊による本格侵攻ともなれば、その物量が想像を絶する規模になることは確実だったからだ。
そして白色彗星が太陽系に襲来。地球艦隊は緒戦において波動砲艦隊と練りに練られた統制波動砲戦術をフルに活用することで、実に数十倍の規模を誇ったガトランティス艦隊を一度は退けることに成功した。しかしその直後、遂に前線にまで姿を現した白色彗星本体の強固過ぎる防御力によって、逆に地球艦隊は大損害を被ってしまったのである。
その結果、地球防衛艦隊は最も避けなければならなかった長時間の消耗戦に陥り、波動砲戦への特化の代償として切り捨てた要素――艦隊運用の柔軟性――の点で限界を露呈しつつあった。
彼らには、『艦隊』『戦隊』『艦』という戦力単位こそ存在したものの、ほぼ単一艦種で統一されたそれらは、単なる数的区分にしか過ぎなかった。各区分に求められる戦術判断のレベルも決して高くはなく、極論、波動砲戦のみを考えるのであれば、『進め』『止まれ』『並べ』『撃て』『下がれ』だけでも成立可能だった。
事実、地球艦隊はD級の大量配備(大量建造ではない)を実現する為に、圧倒的に不足する艦長や副長、各科長クラスの人員を極めて短期間に大量養成することで、大規模波動砲戦への対応をなんとか成し遂げた。しかしそれは、人員の能力を極限まで単能化することで成し遂げられた成果であり、そうして速成された人員に、波動砲戦以外の高度な戦術判断や独立した作戦遂行能力を望むのはあまりにナンセンスであった。
加えて、本来ならば設置されて然るべき戦隊司令部はもちろん、艦隊司令部すら、中級以上の指揮官の極度の不足から編成されず、全ては最先任の艦長が兼任する形での指揮体制が構築されたのである。もちろんこうした体制でも、波動砲戦に特化する限り、さしたる問題は発生しない。しかし現在の戦況は――という訳だ。
そして、こうした点をかねてより強く危惧していた谷は、何度なく艦隊及び戦隊司令部の開設を具申していた――たとえ十隻や二十隻のD級配備を諦めてでも、艦隊・戦隊司令部の設置は、それ補って余りある戦力増大効果を発揮する――と。しかし、彼の具申が容れられることは遂になかったのである。
(司令部と言っても、五人も十人も必要ないのだ。
戦隊なら司令と艦長を分離するだけでいい。艦隊なら、長官ともう一人補佐役の幕僚が加わるだけで、全く違うレベルの作戦展開が可能になるのだが・・・・・・)
内心ではそう毒つきつつも、アンドロメダ級艦長の中では最年長者である彼は、自分よりも経験の乏しい僚艦艦長についても案じずにはいられない。艦隊・戦隊司令部の不在はつまり、各艦隊の旗艦艦長に最も強い負荷と消耗を強いることになるからだ。
「アキレスと第五艦隊は?」
「十一時方向にて戦闘継続中。旗艦が撃沈された第八艦隊の指揮も兼任しています。
戦力は六二パーセントが健在、隊形も維持されています」
電測士の報告に谷は感嘆の吐息を漏らした。さすがは最年少でA級艦長を任されただけのことはある。
通常、軍事的に三十パーセントを超える損害を被った部隊は“全滅”と判定される。損害の大きさが部隊から士気と冗長性を奪い取り、戦力として維持できなくなるからだ。しかし、第五・第八艦隊は三割どころか四割近い損害を被りながらも、しぶとく戦闘を継続していた。しかも、両艦隊の艦艇の大半は、促成されたばかりの若い艦長らによって操られており、正直、モラルブレイクを起こして潰走していないのが不思議なくらいだった。
(大したものだ。あれだけの損害を受けてもなお、崩れないとは。
もうどんなヴェテランも、彼らを“粗製乱造”だの“雑木林”だのとは呼べんな)
谷が率いる第二艦隊も、艦隊司令部も戦隊司令部も置かれていない点では他艦隊と同様だったが、実戦経験を有する艦長が多く、地球艦隊では唯一柔軟な機動運用が可能な艦隊と目されていた。その結果、文句のつけようのない練度を有するガミラス増援艦隊と共に、数少ない機動予備戦力として先程から戦場を駆け回っていたのである。
これに対して、第二艦隊以外の地球艦隊は、短期養成故の練度・経験の不足と作戦能力の低さから、隊列をほぼ固定しての砲雷撃戦しか実質的に取り得る戦術がなかった。当然、自らの機動を捨て去ることで砲雷撃の命中率は向上するが、それは撃ってくる敵にとっても同様だった。
実は白色彗星本隊の襲来まで、この点が部内で問題視されることは殆どなかった。波動砲艦隊構想においては、必殺の波動砲戦で一気に決着をつけることが基本中の基本であったし、仮に波動砲戦後に通常の砲雷撃戦が生起することがあっても、彼らには波動防壁という鉄壁の防御システムがあったからだ。
たとえ練度や作戦遂行能力が低くとも、絶対的な安全が保障されたエリアから一方的に砲火を浴びせるだけならば、実行上は何の問題もない。
だが、地球側のそうした目論見は、土星沖での緒戦において脆くも瓦解する。ガトランティス軍が新たに投入した大型刺突式兵器――イーターⅠ――は、波動防壁中和・侵蝕機能を有しており、D級の波動防壁すら容易に貫いたからだ。
最大規模での統制波動砲戦を白色彗星に無効化されたことが地球艦隊にとって戦略級の衝撃であったとするならば、イーターⅠによる波動防壁突破は戦術級の衝撃だったと言えるだろう。
結果、地球艦隊は古代ギリシャ重装歩兵のファランクスを思わせる密集隊形で果敢に砲撃戦を挑んだものの、緒戦から損害が続出することになった。イーターⅠは高速な上に、前方投影面積も小さく、迎撃阻止が極めて困難だったからだ。
事実、現在に至るまで火星沖での地球艦隊の損害の殆どはイーターⅠと対消滅ミサイル、そしてカラクルム級の――
「っ!?第二八戦区のカラクルム級群、連結砲撃の兆候!」
「重力子スプレッドは!?」
「エネルギー充填中!残り46秒!!」
「二八戦区のカラクルム級を優先ターゲットγと認定、火力を集中しろ!撃たせるな!!」
「カラクルム発砲!!――第二二、三〇、八四戦隊消滅!!」
「くっ!後続の戦隊は?」
「二〇二及び二〇三戦隊が八分前に合流したばかりです」
「両戦隊に前進を命じろ!穴を塞げ!!絶対に突破させるな!!」
「第五、一八、一九、二四、二七戦隊、いずれも魚雷・ミサイルを全射耗。
後退と補給を要請しています」
「許可できない。砲撃での戦闘継続を命じろ」
ダメだ。ヴェテランも若い連中も歯を食いしばって頑張ってはいるが、このままでは艦も人間も参ってしまう。どれほど時間断層からの増援が後方から加わっても、元から戦っている連中を後方に下げられない以上、艦と乗員の疲労は蓄積される一方だ。遠からず限界がくる。
しかし――。
(俺たちは山南が戻ってくるまで、絶対に崩れる訳にはいかん。
山南、俺が総旗艦の艦長にお前を推したのは、お前の経験と技量、見識を見込んだからだ。
何も遠慮することはない。俺たちの肩を踏み台にして思い切り飛び込め)
そんな後輩への心の声を、この世の者ならざる誰かが聞き届けたのかもしれない。
「アンドロメダより入電!!」
通信士が叫ぶようにして入電を告げた。その声は紛れもない喜色に染まっている。
「読め」
「宛、アルデバラン艦長。発、アンドロメダ艦長。
本文、我之ヨリ戦闘ニ加入ス。今暫クノ健闘アレ。以上!」
――彼らが来たのだ。
谷は一瞬だけ瞑目した後、艦長席から立ち上がり、眦を決して叫んだ。
「本宙域にある全ての地球・ガミラス艦艇に第一級優先通信!
全艦にオート・スペシャルを許可!撃ち尽くして構わん!
一隻でも多くのガトランティス艦をこちらに引きつける!!」
その瞬間こそが、後に『ヤマト奪還作戦』や『第三次火星沖海戦』と呼ばれることになる地球・ガミラス連合艦隊の死戦の始まりだった。彼らはその後、実に総戦力の八割を喪いつつも、ヤマトとアンドロメダ、そして銀河が白色彗星内から脱出するまで、見事戦線を維持し続けたのである。
そして、地球沖――

「挺身艦隊、全艦ワープ開始!!目標、白色彗星内部、都市帝国直上 五〇〇〇!!」
山南の号令一下、ヤマトカラーに彩られたアンドロメダとアンドロメダ・ブラックの群が、漆黒の虚空に向かって一斉に突進を開始する。次の瞬間、目前の宇宙空間が眩い閃光に包まれるのを山南は見た。
(安田、見てろよ。そっちに行く前に、俺の本当の“最善”を見せてやる)
防人を乗せて艦は征く。
それは希望の艦。
土星沖での敗北と大損害から、不死鳥のように甦った復活の艦。
その艦を見送り、迎え入れる人々の祈りと願いと共に、今、防人は再び火星沖へと――。
――fin
(注)文中の『時間断層工廠』及び『工廠長』という表記は、2202の公式設定であればそれぞれ『時間断層工場』『工場長』と表記するのが正しいのですが、個人的な好みで文中の表現としました。
まずは本作に素晴らしい挿絵CGを御提供下さいましたHARUさんに厚く御礼申し上げます。
実は本作を書き出した頃に、丁度HARUさんが動画サイトに火星沖に向かって出撃する山南SPとアンドロメダブラック軍団の動画を公開されまして、それを一目見た時から、HARUさんに挿絵のお願いができないかと考えていました。
この度、思い切ってHARUさんに御相談しましたところ、快くお引き受けいただいたばかりか、更にオリジナル動画にはなかったドッグ内のCGまで新たにご用意いただきました。
お陰様で、私の味気ない文章にもこれ以上ない豪華な彩りを添えることができ、本当に感謝に堪えません。
ちなみに、私が一目惚れしたHARUさんのアンドロメダ動画はこちら↓です(^o^)
さてさて、本文のタイトルが『第二次火星沖海戦外伝』となっているのは、この文章はそもそも本夏公開予定の『MMD第二次火星沖海戦』の原作エンディング用に書き始めたものだったからです。
ところが、2202第6章の影響で山南さんへの想い入れ(笑)が強くなり過ぎ、文章も長くなり過ぎたものですから、独立した外伝として公開することにしました。
山南さんパートは概ね満足すべき仕上がりになりましたが、後半の谷さんパートはやや蛇足が過ぎて冗長になってしまったのが反省点ですね。
とはいえ、自分なりに宇宙戦艦ヤマト2202について思っていたこと、感じていたことを目いっぱい詰め込むことができたので、その点ではとても満足しています。
満足と言えば、実は本作は本ブログの創作物では初めての『小説』風作品となりました。
“風”としているのは、私は小説の書き方をちゃんと勉強したことがない為です。
書き終わってみると『やっぱり難しかったなぁ』というのが正直なところですが、いつもの説明調の文章では描くことが難しいキャラクターの心情を描くことができたのは面白かったです。
また機会があればやってみたいと思います。
さてさて、ではまたここから第二次火星沖海戦原作の方に戻ります。
本夏の公開までもう暫くお待たせしますが、引き続き宜しくお付き合い下さいませ(^o^)
――U.N.C.F ZZZ-0001 YF-2203“アンドロメダ改”艦橋内

「――寂しいな。なぁ、アンドロメダよ」
艦長シートでそう独りごちた男の視線が向けられた先には、一枚のポートレートがある。先進性と機能性に満ちた最新鋭戦艦の艦橋に、昔ながらのL版サイズにハードコピーされた写真――しかも乱暴にテープで留められただけの――は、いかにも違和感があった。
しかし写真を、いや、そこに写った人々を見つめる男の瞳は寂寥の色こそ含んでいるものの、どこまでも穏やかだ。その姿は僅か数日前、人類史上最大・最強の宇宙艦隊を率いて獅子吼していた人物のものとはとても思えない。
その男、地球連邦防衛軍 一等宙佐 山南修は飽きることなく写真を眺め続けていた。まるでそうしていれば、その頃の自分たちに戻れると心底から信じているかのように――だが、そんなことは夢物語に過ぎない。写真の中の二人は既に鬼籍に入り、更にもう一人もMIA(作戦行動中行方不明)だ。
(やれやれ、自動艦というのもやっかいだな。
本来は最も忙しく、騒がしい筈の出撃時に、艦長が想い出に浸る以外、何もする事がないなんて。
精神衛生上、非常によろしくない)
自他共に認めるリアリストである彼が先程から写真を眺め続けていたのは、決して感傷的な理由ではなく、単純に他にすることがなかったからだ。そしてそれこそが、フル・オートマチックでの高機動三次元戦闘すら可能なよう大規模改修を施された『アンドロメダ(改)』の真骨頂だった。いや、アンドロメダ改だけではない。山南が指揮する麾下の全艦が、AIによる完全自律制御艦『アンドロメダ・ブラック』で構成されているのだ。
いくら無人艦、省人艦とはいえ、人を乗せるなら、少しは忙しくさせないと駄目だ。慎重傾向の強い奴、思考にマイナスベクトルのかかりやすい奴ほど、いらぬ事を考えてしまう――今の俺のように。
山南は、航宙中の所感を書き留める為にいつも胸ポケットに潜ませている小型の手帳と万年筆に手を伸ばし――苦笑と共に引っ込めた。既に彼の全身は、艦固有の慣性制御装置では打ち消しきれないレベルの高機動戦闘に耐久可能な強化スーツに包まれており、当然そこに“胸ポケット”など無い。
(自ら志願したこととはいえ、全くひどい扱いだな、これは。
いや、新手の罰ゲームと言うべきか)
そんな自嘲に耽る艦の主の想いを悟ったかのように、目前のTCP――Tactical Ctrl Pad(戦術情報表示/操作盤)――が音響と発光で山南に注意を促した。僚艦とのトランス調整中の自艦とBBB戦隊のワープ準備が整うまで、残り3分を切ったのだ。
ワープ目標は、今現在も地・ガ連合艦隊が死力を尽くして白色彗星を食い止めている火星戦線。
『挺身艦隊』と名付けられた彼の艦隊は、白色彗星本体――通称:都市帝国――の直上へワープアウト、その中枢と思しき上部構造物の至近から最大出力で波動砲を集中射する予定だった。土星沖での戦いでは、地球艦隊の放った波動砲は悉く都市帝国の展開する強固な防護スクリーンで無効化されてしまったが、ガス帯の内部から、それも反応時間を与えない程の至近距離からならば――という訳だ。
ワープアウト直後の波動砲発射を可能とする為に、彼らの改A級及びBBB級は無人のD級二隻を“ブースター”としてそれぞれ接続している。ワープはD級によるトランス・ワープで実施し、波動砲発射をアンドロメダ級で行うという寸法だ。
あまりに危険で乱暴な作戦計画故、部内では彼の艦隊を正式名ではなく“殴り込み艦隊”や、欧米諸国軍では“カミカゼ・フリート”と呼ぶ者までいるらしい。
そんな、自殺行為と紙一重とまで評された作戦を遂行する艦隊に、山南が独りで乗艦しているのには当然理由がある。
本作戦はその危険さ故、当初は完全無人の艦隊で実施される予定だった。しかし、何度AIがシミュレーションを繰り返しても、都市帝国に波動砲を叩きつけられる艦は艦隊総数の20%にも満たず、その実施効果が疑問視された。だが、本作戦の直接指揮を強行に主張し続けていた山南が艦に乗り組んで指揮を行った場合のシミュレーションでは、波動砲発射を果たした艦の数は、実に七割にまで達したのである。
それでも、藤堂統括司令長官はあまりに生還の可能性が低いとして、山南の艦隊司令就任と乗艦に難色を示した。しかし、二度三度と繰り返されたシミュレーションの結果と、外ならぬ山南自身の強い希望が最後は決め手となった。
結果、山南の直接指揮は認められ、艦隊ただ一人の“人間”としてそこに在った。彼の役目は、最適なタイミングで挺身艦隊をワープさせると共に、波動砲発射の瞬間を見極めることにある。
(罰ゲーム・・・・・・いや、土星沖の敗北と損害を考えれば、これでも有難いくらいだ。
それよりも、お前まで巻き込んですまないな、アンドロメダ)
土星沖で大破しつつも辛うじて帰還したアンドロメダは、直ちに時間断層工廠での緊急修理に入った。しかし各種検査の結果、そのダメージは艦の命たる次元波動エンジンにまで及んでおり、最早修復は困難であるとして、廃艦処分の決定が下されたのである。
結果、山南の乗艦は新たに用意された“別の艦”になると説明されていた。しかし――。

「これが、その?」
「そう、アンドロメダ級試作艦だ。0番艦、零号艦などとも呼ばれているな。
こいつで諸々の新装備の実装試験をやった後、あんたらの一番艦以降が建造された。
その後、お役御免でモスボールされていたのを、無理やり引っ張り出したって訳だ。
――公(おおやけ)には、だがね」
彼が新たに乗り組むことになった艦の説明を請負ったのは、既に初老の域すら超えているように見える年かさの工廠責任者だった。その口調も態度もぶっきらぼう極まりなかったが、どこか悪戯小僧のような色を含んでいる。
そこは時間断層工廠に隣接した最終検査場。通常空間に設置されている為、行動力と行動時間が著しく制限される(そして暑く、重ったるい)時間障害防護装備が不要なのが有り難かった。
彼らの見上げる先には、見なれた防衛軍グレーに彩られたアンドロメダ級の姿がある。
波動砲口がD級の設計とパーツを流用して疑似四連装化された他、艦の各所に高機動用スラスターとその注意書きのイエローマーキングが目立つようになってはいたが、彼の知るアンドロメダ級からそれほど大きく変容したようには見えない。だが、外観がどれほど似通っていても、たとえ艦載AIを移植していたとしても、この艦は“俺のアンドロメダ”ではない――彼はそう聞いていたし、彼自身もそう思っていた。
故に、山南は工廠長の意味ありげな説明に眉をひそめた。自然と口を突く言葉も尖り気味になる。
「公には?では、非公式には?」
「こいつは正真正銘――“あんたのアンドロメダ”だ。試作艦なんかじゃない」
工廠長は、そこだけは山南の瞳を見つめてきっぱりと言い切った。そして驚く山南を後目に矢継ぎ早に言葉を続ける。
「驚いたろ?しかし苦労したんだぜ。
その試作艦や建造中のD級からありったけの部品を引き抜いて突貫で仕上げたんだ。
BBB?あれは絶対にダメだ。
無人艦だから素材も加工精度も有人艦よりかなりランクが落としてある。だから見た目よりも俄然脆いんだ。
懸案だったのはむしろ波動砲の修理の方さ。
幸い、BBB級の設計時、D級二隻分の波動砲システムをそのまんま流用するってアイデアがあったらしくってな。その設計が流用できたんで、なんとか間に合った。
・・・・・・まぁ、あんたも知っての通り、上からの命令は、真逆――アンドロメダから使える部品を引き剥がして、試作艦を実戦仕様にしろ――だったんだけどな、俺の判断で握りつぶした。
それでも、さすがに艦籍までは誤魔化しきれなかったんで、艦番号は変えざるを得なかったが。ま、その点だけは勘弁してくれや」
延々と、しかも嬉々として語られる説明に、さすがの山南も暫し言葉を失った。工廠長の口調はまるで茶飲み話のような気楽さだったが、その内容はあまりに重大な命令違反だったからだ。
「しかしそれでは――」
「あぁ、勝手に艦をすり替えたんだ。
今の政府と軍が続く限り、俺は軍刑務所で終身刑だろう。
しかし、いいんだ。俺は、あんたに借りがある」
「借り?すまない、とんと記憶にないんだが」
「そりゃそうだ。
俺の倅(せがれ)は、第二次火星沖海戦でテンリュウに乗り組んでた。
倅は言ってたよ、俺は、安田艦長とあんたの艦に救われたんだと」
工廠長の説明に、山南はようやく愁眉を開いた。まさかここで、安田と第二次火星沖海戦の名を聞くことになるとは。
「それで・・・・・・。御子息はご健勝か?」
「あぁ、きっと“向こう”で、嫁や孫や婆さんと楽しくやってるよ。
・・・・・・俺は、あんたには本当に感謝してるんだ。皮肉じゃないぜ。
倅があの戦いから生きて帰れたからこそ、俺も死んだ婆さんも生まれて初めて“孫”ってもんを抱くことができた。時間は短かったがな。だけど、その記憶も感触も幻じゃない」
「・・・・・・お察しする」
「なぁに、気づかいは不要さ。俺は自分が為すべきと信じたことを為しただけだ。
倅の恩人が任務を果たせる可能性を1%でも増やせるよう全力を尽くしたまで。
バカなお偉いさんと取り巻きどもは、艦載AIさえ乗せ換えれば同じだろうなんて言いやがったがな、あいつらは船乗りの心意気が分ってねぇ。フネは女房と同じだ、“按配”ってもんがあるんだ。
お前ら、夜な夜な女房のどこに乗っかってんだと聞いてやりたいね」
工廠長の突然の“ヘルダイブ”に思わず吹き出した山南だったが、直ぐに口調と表情を改めた。
「工廠長、もういいよ。しかし――誠にありがとう」
工廠長は、自らの仕事を正当に評価された職人に特有の、はにかんだ笑みを浮かべた。そして眩しげな表情で再びアンドロメダを見上げる。
その瞳に浮かんでいるのは紛れもない愛着であり、我が子に向けるのにも似た、純粋なまでの愛情だった。

「山南さん、こいつはちょっとツンとしてるが、素直ないいフネだよ。
俺には分るんだ。次の戦いでも、こいつはあんたを守りながら、あんたの望む全ての行動を完璧に果たしてくれる。
――だから、頼みます」
いつの間にか、工廠長の目はアンドロメダではなく、山南に向けられていた。そしてその口調もまるで別人のような真摯さに満ちている。
「山南さん、いや山南艦長。
俺は二度の内惑星戦争とガミラス戦争を幸運にも生き抜くことができた。
勝ち戦(いくさ)も負け戦もたくさん見たよ。しかし、勝とうが負けようが、どちらにせよ――その後は悲惨だった。
内惑星戦争じゃ、地球に移住させられた火星の連中が随分と酷い目に遭ってたし、ガミラス戦争は――言うまでもないな。
だから、俺はもう勝ってこい、勝ってきてくれとは言わない。
頼む、この戦争を終わらせてくれ。
土星では、ヤマトも喪われたと聞いた。
だからもう、それを頼めるのは、あんたとアンドロメダだけだ」
そう告げる工廠長の声は決して大きくはなかった。いや、休みなく騒音が響き渡る工廠内では、かき消されてしまいそうな程に小さかった。しかし山南にはそれが、この老人の魂が上げる絶唱、慟哭のようにも聞こえた。
最早この老人には、何もないのだ。家族も親族も友人すら殆どを戦争で失い、残されたのは工廠での仕事だけ。だが、それでもこの老人は何を恨むでも呪うでもなく、戦争を終わらせる為に、自分のような境遇の人間を一人でも減らす為に、自身の持ち場で今も戦い続けている――。
(・・・・・・ヤマト)
全ての動力を喪い、白色彗星に落下していく最期の姿が脳裏に甦る。
いや、俺は信じない。ヤマトは沈んでなどいない。必ず生きている。土方さんや古代が簡単にくたばったりするものか。
あのフネは、たった一隻で敵の本拠地に乗り込み、戦争を終わらせ、地球と人類を救った。そのフネを指揮し、魂を塗り込めた漢を、俺は知っている。否、俺もその人から教えを受け、かの地で共に戦ったのだ。
その因縁深き火星沖で再び俺は戦う。今度は沖田さんも安田もいないが、俺にはまだ、馴れ親しんだアンドロメダがある。俺とアンドロメダが命を懸けて戦えば、まだ何事かを為せるかもしれない――嘗て沖田さんとヤマトが為したように。
(第二次火星沖では沖田さんにしか見えなかった何かが、今度は俺にも見えるだろうか?土星沖では、俺は何も――)
指揮官として、研鑽と修練を積み重ねてきたつもりだが、先だっての土星沖会戦では、俺は“機”を見出すことができなかった。“勝機”などと言うつもりはない。戦場、戦争を変える事のできる“機”を。
いや、思えばそれも当然か。あの戦いでのガトランティス軍の行動予測も、それに対する地球艦隊の作戦計画も、全て銀河AIが立案したもので、俺の作戦指揮はそこから一歩として外れるものではなかった。あんな戦い方に、人間の感じる“機”が入り込む余地などない。
山南は再びアンドロメダを見上げた。
――ならば、あやかってみるか、あのフネに。
「工廠長。お気持ちは承りました」
山南は工廠長に対し、男でも惚れ惚れするほどの色気に満ちた敬礼をピシリと決めた。
そして制帽を取り、これまでとは対照的な男臭い笑いを浮かべて更に言葉を続ける。
「それで、という訳ではないが・・・・・・もう一つ頼まれてもらえないか?」
――その“頼み”の結果が、今現在山南が乗艦しているアンドロメダの姿だった。
艦の上半分をブルーグレー、下半分をダークレッドに塗り分けたカラーパターンは、ガミラス戦争を終わらせ、地球人とガミラス人に同盟関係を結ばせるきっかけを作った“あの艦”そのものだった。
なんでも、山南が最後に依頼したこの塗装をアンドロメダに施すために、工廠長は完成間近のBBB戦隊で作業中だったペインティング用ガミロイドを大量に引き抜いたらしい。結果、就役したBBB戦隊の1/3程は、舷側に描かれる予定だったプロパガンダ用のテキストが省略されたという。
それらの点も含め、本当に大丈夫かと心配する山南に対し、工廠長は大笑しながらこう言ってのけた――聖書だのお経だのでビビってくれるような敵さんなら、宇宙戦争なんて起きやしませんぜ。味方だって、あんなモン見てる暇ないでしょう。俺にはそれよりも、乗ってる人間様が気持ち良く戦えるよう艦を仕上げる方が大事でさぁ――と。
だがその一方で、山南の懸念通り怒り狂っている者たちもいる。
「っ!?なんなんだ、あの色は!!」
“あの艦”は地球を救った栄光の艦である一方、そのあまりの偉大さ故に、その存在を疎ましいと考えている者も決して少なくはないのだ。それは特に、波動砲艦隊構想を強く推進してきた地球連邦防衛軍中枢に多いとされる。彼らにしてみれば、一艦長風情が勝手に国家間条約を結ぶなど言語道断であり、そのせいで、真に地球を憂う自分たちが苦労させられたという怒りと反発は極めて大きかった。
今、統括司令部で、大スクリーンに映るアンドロメダ改に向けた指先を震わせている司令部幕僚もそんな一人だった。いや、彼一人だけではない。司令部に詰めている高級幕僚の多くが、怒りに満ちた目をスクリーンに向けている。
現在の統括司令部内にそれを諫めるものはおらず、いや、彼らの首魁とも言うべき芹沢司令副長は在室しているのだが、彼はいつもの鋭く強い視線をスクリーンに向けるだけで、何も発言しようとはしなかった。
結果、芹沢の意も自らと同様と判断した司令部幕僚たちの怒りと言動は更にヒートアップする結果となる。
「あんな塗装色は規定にない!!誰が指示した!!誰が許可した!?
あれは・・・あれではまるで――」
「――局地迷彩だな」
猛り狂う幕僚たちとは対照的な声を上げたのは、休憩を終え、遅れて司令部に入室してきた藤堂統括司令長官だった。
普段、よほどの重大事でなければ、そして決定的局面でなければ、自ら口を開かない長官だけに、その発言は自ずと重きが置かれる。それは司令部幕僚はもちろん、副長であっても例外ではない。
「君らは分らんかね。上面はアースグレー、下面はマーズレッド。
火星―地球絶対防衛線に合せた局地迷彩色だよ、あれは。
規定色とは多少色味が違うが、資材不足の中、ありあわせの部材で何とかしたのだろうな」
規定色に塗られた艦が続々と戦列に加わりつつある状況で、その解釈はかなり無理のあるものであったが、平素と全く変わらぬ藤堂の表情と口調で整然と言葉を並べられると、面と向かって反論できる者は統括司令部にはいなかった。
「いえ・・・・・・長官。あれは・・・・・・・あれは・・・・・・どう見ても・・・・・・」
それでも、よほど“あの艦”の幻想が強くちらつくのか、件の幕僚は懸命の反論を試みた。しかしその時、司令部内にドンっと鈍く重い音が響き渡った。
立ち上がった芹沢が拳で副長席の卓を殴りつけ、幕僚たちを睨め付けたのだ。
「貴様らは現在の戦況が分っているのか!!
我々は既に火星圏にまで敵に踏み込まれているのだぞっ!
一隻の戦艦の塗装色に四の五の言っている暇など、どこにあるっ!!」
そう怒鳴りつけた芹沢の鬼の形相に、幕僚たちは完全に色を失い、慌てふためきながら元の職務に復帰した。苦々しい表情でそれを一瞥すると、芹沢は大きな溜息を一度ついた後で通信士を呼んだ。
「時間断層工廠へ長官と私の連名で電文を送ってくれ。
貴工廠の尽力を謝す。臨機応変の対応見事なり。引き続き職務に邁進されたし――とな。
・・・・・・宜しいですな?」
最後の一言は藤堂に向けたものであったが、芹沢はその返事を待たず、視線も合わせないまま自らの席に戻った。それは見る者によっては酷く礼を欠いたように感じられる振舞いだったが、藤堂は芹沢に対し一瞬だけ面白そうな表情を浮かべたものの、こちらも何事もなかったように副長の隣――長官席に着いた。
芹沢の言う通り、彼らには対処しなければならない懸案が山積みだったからだ。
統括司令長官と司令副長の連名で発せられた電文の写しは、程なくして山南の元にも届けられた。
(まったく。沖田さんといい、藤堂長官といい、芹沢副長といい、本当に大したものだよ)
TCPに表示された電文を見た山南は、込み上げてくる笑いを抑えるのに苦労した。
古代や斉藤の前では一端の指揮官面をして見せても、やはり俺はまだまだあの人たちには敵わないらしい。あの人たちが後ろで支えてくれているからこそ、俺たちはこうして万全の状態で戦えるのだ。
(感謝します、長官、副長)
少なくともこれで、後顧の憂いはなくなった。
決意を固めた彼の瞳は今、火星沖からリアルタイムで送られてくる戦況図に注がれている。
増援であるガミラス艦隊――バレル大使直率艦隊――が大きく突出、それに喰らい付くようにガトランティスも艦隊ラインを前進させていた。更にアルデバランの谷艦長率いる第二艦隊がこれを迎撃し、戦場は一気に混戦の度合いを増す。
しかし、地・ガ連合艦隊の戦術行動は全て陽動。一隻でも多くの挺身艦隊が都市帝国に肉薄できるよう、彼らは積極的に前線を動かし続け、ガトランティス軍の戦力と注意を誘引しているのだ。だが、精鋭のガミラス軍を加えたとはいえ彼我の物量差は圧倒的であり、このような無茶な戦い方はそう長くは続けられない。
そして、戦場の実態もほぼ山南が想像した通りだった。第二艦隊旗艦AAAアルデバランの艦橋内は、既に数時間前から修羅場そのものの様相を呈している。
「バレル大使へ通信を繋げ!旗艦が突出し過ぎだ。あれでは“盾”もろとも喰われる。
103戦隊は前進、直衛につけ!」
「白色彗星の重力干渉波により通信リンク不調、繋がりません!」
「続けろ、大使が出るまで呼び出し続けろ」
「敵超大型空母より艦載機多数発艦!数およそ90、いえ・・・・・・200以上!!
ガミラス艦隊に向かう!!」
「阻止しろ!速射魚雷、多連装ミサイル発射準備!
続けて重力子スプレッド弾一斉射!――撃ぇぇぇぇ!!」
艦長と艦隊司令長官を兼任する谷は、戦闘開始以来、一時も休む暇なく艦と艦隊の指揮を執り続けていた。
(畜生、まるで第一次火星沖だ。いや、あの時よりも手荒く酷いぜ)
彼自身、連戦の疲労による注意力と判断力の低下を自覚しており、本当ならアルデバランの指揮だけでも副長に任せたいところであったが、その副長も経験が決定的に不足している以上、このまま踏ん張り続けるしかない。
加えて、今の彼にはもう一つ気がかりがあった。
(まったく。勇気は買うが、文官なら文官らしく後方にいて欲しいものだ)
ガミラス艦隊の先頭に位置しているのは、よりにもよって大ガミラス帝星在地球特命全権大使ローレン・バレルの座上艦であり、谷としては気が気ではない。たとえ座上艦が、ガミラス軍で最も高い直接・間接防御力を誇るゼルグート級であったとしても、だ。
ガミラスへの技術供与の結果完成したガ式空母型アンドロメダ――口さがない者は“ガミドロメダ”などとも呼んでいる――の運用指導を担当し、ガミラス軍関係者とも深い交流を持つ谷は、ローレン・バレルという男を最もよく知る地球人の一人だ。
デスラー失脚後のガミラスで俄かに権限を増した内務省保安情報局の出身、ガミラス本星とも太い政治的パイプを有するこのガミラス人は、その柔和で落ち着いた相貌からは想像できないほどの胆力と行動力を持ち、地球との外交交渉においてもその辣腕、剛腕ぶりは広く知られていた。にもかかわらず、ガミラスの強大な国力や軍事力を必要以上に誇示するようなことはせず、あくまで交渉相手との互恵性を重んじる彼の外交姿勢は、地球連邦大統領以下の要人たちにも概ね好評だった。
その点、地球とガミラスの歴史的経緯や、埋めようのない根本的な国力格差を考えれば、ローレン・バレルという男は、地球にとっても理想的な同盟国大使だったと言えるだろう。
谷の見るところ、どうやらガミラス軍はバレルのゼルグート級を餌に敵戦力を誘出、それを、ガ式空母型アンドロメダを主力とする快速戦闘団――バーガー戦闘団――で叩き潰すという戦術を採っているらしい。事実、緒戦においてバーガー戦闘団は、ゼルグート級を狙って突出してきた三隻の特殊砲艦とその護衛艦艇群を僅か数分で殲滅するという大戦果を挙げていた。
本来、一国の大使が軍人に“餌”や“囮”として利用されるなど、大激怒して当然であったが、谷には、バレル自身が喜んでその任を引き受けているように思えて仕方がなかった。そして同時に、彼がアンドロメダ級の運用を手ほどきしたフォムト・バーガーという若い艦長の(決して不快ではない)不敵な笑みを思い出すと、その想像は殆ど確信に変わる。
(まったく、ガミラス人って連中は、誰も彼もが妙な具合に戦慣れしてやがる)
とはいえ、何事にも限度というものがある。
ガトランティス軍もガミラス軍侮り難しと見て、艦隊旗艦と思しき超大型空母まで最前線に投入してきた。幸い、搭載していたのが通常兵装の艦載機であった為、先程は難を逃れたが、あれがもし、土星沖で初めて姿を見せた新型刺突式兵器の大群だったら、ゼルグート級といえども危なかったかもしれない。
(まだまだあなたに死なれては困るのですよ、大使。地球の為にも、ガミラスの為にも)
「バレル大使が出ました!」
ようやく通信が繋がった同盟国全権大使に後退を勧めた(実質的には叱りつけるように命令した)ことで、ようやく安堵した谷であったが、今度は、自らの置かれている状況が厳に戒められるべきワンマンフリート以外の何物でもないことに怒りを覚え始めている。この殺人的多忙の中、そんな点に思いを馳せている時点で、彼も中々に複雑な男であった。
(せめて――艦隊・戦隊指揮官と艦長だけでも分離できていれば)
国力と軍事力で圧倒的に優勢な敵軍を短期決戦で撃滅することを旨とする『波動砲艦隊構想』とそれに基づく建艦計画は、ガトランティス軍の第十一番惑星襲来後、極端なまでに先鋭化した。時間断層工廠での建造艦は、収束型と比べて圧倒的に高い艦艇撃破効率を誇る拡散波動砲を発射可能な最小艦――D級が大半を占め、それ以下の中小艦艇の建造はほぼ等閑に付されたのである。
その結果、火力はあっても機動力に乏しい戦艦級艦艇のみで編成された地球艦隊は、集団での波動砲戦についてはこれ以上ないほど効率的な運用が可能となったものの、それ以外の戦術状況においては柔軟性を欠く極めて硬直した戦力と化した。
つまり、この時の地球艦艇群は、最早“艦隊”というよりも“砲列”に近い戦力単位と化していたのである。
もちろんそれは、止むに止まれぬ苦渋の決断という側面が強かった。十一番惑星に襲来した二百万隻を超える大型戦艦群は、白色彗星本隊の露払い――前衛戦力――に過ぎず、彗星本隊による本格侵攻ともなれば、その物量が想像を絶する規模になることは確実だったからだ。
そして白色彗星が太陽系に襲来。地球艦隊は緒戦において波動砲艦隊と練りに練られた統制波動砲戦術をフルに活用することで、実に数十倍の規模を誇ったガトランティス艦隊を一度は退けることに成功した。しかしその直後、遂に前線にまで姿を現した白色彗星本体の強固過ぎる防御力によって、逆に地球艦隊は大損害を被ってしまったのである。
その結果、地球防衛艦隊は最も避けなければならなかった長時間の消耗戦に陥り、波動砲戦への特化の代償として切り捨てた要素――艦隊運用の柔軟性――の点で限界を露呈しつつあった。
彼らには、『艦隊』『戦隊』『艦』という戦力単位こそ存在したものの、ほぼ単一艦種で統一されたそれらは、単なる数的区分にしか過ぎなかった。各区分に求められる戦術判断のレベルも決して高くはなく、極論、波動砲戦のみを考えるのであれば、『進め』『止まれ』『並べ』『撃て』『下がれ』だけでも成立可能だった。
事実、地球艦隊はD級の大量配備(大量建造ではない)を実現する為に、圧倒的に不足する艦長や副長、各科長クラスの人員を極めて短期間に大量養成することで、大規模波動砲戦への対応をなんとか成し遂げた。しかしそれは、人員の能力を極限まで単能化することで成し遂げられた成果であり、そうして速成された人員に、波動砲戦以外の高度な戦術判断や独立した作戦遂行能力を望むのはあまりにナンセンスであった。
加えて、本来ならば設置されて然るべき戦隊司令部はもちろん、艦隊司令部すら、中級以上の指揮官の極度の不足から編成されず、全ては最先任の艦長が兼任する形での指揮体制が構築されたのである。もちろんこうした体制でも、波動砲戦に特化する限り、さしたる問題は発生しない。しかし現在の戦況は――という訳だ。
そして、こうした点をかねてより強く危惧していた谷は、何度なく艦隊及び戦隊司令部の開設を具申していた――たとえ十隻や二十隻のD級配備を諦めてでも、艦隊・戦隊司令部の設置は、それ補って余りある戦力増大効果を発揮する――と。しかし、彼の具申が容れられることは遂になかったのである。
(司令部と言っても、五人も十人も必要ないのだ。
戦隊なら司令と艦長を分離するだけでいい。艦隊なら、長官ともう一人補佐役の幕僚が加わるだけで、全く違うレベルの作戦展開が可能になるのだが・・・・・・)
内心ではそう毒つきつつも、アンドロメダ級艦長の中では最年長者である彼は、自分よりも経験の乏しい僚艦艦長についても案じずにはいられない。艦隊・戦隊司令部の不在はつまり、各艦隊の旗艦艦長に最も強い負荷と消耗を強いることになるからだ。
「アキレスと第五艦隊は?」
「十一時方向にて戦闘継続中。旗艦が撃沈された第八艦隊の指揮も兼任しています。
戦力は六二パーセントが健在、隊形も維持されています」
電測士の報告に谷は感嘆の吐息を漏らした。さすがは最年少でA級艦長を任されただけのことはある。
通常、軍事的に三十パーセントを超える損害を被った部隊は“全滅”と判定される。損害の大きさが部隊から士気と冗長性を奪い取り、戦力として維持できなくなるからだ。しかし、第五・第八艦隊は三割どころか四割近い損害を被りながらも、しぶとく戦闘を継続していた。しかも、両艦隊の艦艇の大半は、促成されたばかりの若い艦長らによって操られており、正直、モラルブレイクを起こして潰走していないのが不思議なくらいだった。
(大したものだ。あれだけの損害を受けてもなお、崩れないとは。
もうどんなヴェテランも、彼らを“粗製乱造”だの“雑木林”だのとは呼べんな)
谷が率いる第二艦隊も、艦隊司令部も戦隊司令部も置かれていない点では他艦隊と同様だったが、実戦経験を有する艦長が多く、地球艦隊では唯一柔軟な機動運用が可能な艦隊と目されていた。その結果、文句のつけようのない練度を有するガミラス増援艦隊と共に、数少ない機動予備戦力として先程から戦場を駆け回っていたのである。
これに対して、第二艦隊以外の地球艦隊は、短期養成故の練度・経験の不足と作戦能力の低さから、隊列をほぼ固定しての砲雷撃戦しか実質的に取り得る戦術がなかった。当然、自らの機動を捨て去ることで砲雷撃の命中率は向上するが、それは撃ってくる敵にとっても同様だった。
実は白色彗星本隊の襲来まで、この点が部内で問題視されることは殆どなかった。波動砲艦隊構想においては、必殺の波動砲戦で一気に決着をつけることが基本中の基本であったし、仮に波動砲戦後に通常の砲雷撃戦が生起することがあっても、彼らには波動防壁という鉄壁の防御システムがあったからだ。
たとえ練度や作戦遂行能力が低くとも、絶対的な安全が保障されたエリアから一方的に砲火を浴びせるだけならば、実行上は何の問題もない。
だが、地球側のそうした目論見は、土星沖での緒戦において脆くも瓦解する。ガトランティス軍が新たに投入した大型刺突式兵器――イーターⅠ――は、波動防壁中和・侵蝕機能を有しており、D級の波動防壁すら容易に貫いたからだ。
最大規模での統制波動砲戦を白色彗星に無効化されたことが地球艦隊にとって戦略級の衝撃であったとするならば、イーターⅠによる波動防壁突破は戦術級の衝撃だったと言えるだろう。
結果、地球艦隊は古代ギリシャ重装歩兵のファランクスを思わせる密集隊形で果敢に砲撃戦を挑んだものの、緒戦から損害が続出することになった。イーターⅠは高速な上に、前方投影面積も小さく、迎撃阻止が極めて困難だったからだ。
事実、現在に至るまで火星沖での地球艦隊の損害の殆どはイーターⅠと対消滅ミサイル、そしてカラクルム級の――
「っ!?第二八戦区のカラクルム級群、連結砲撃の兆候!」
「重力子スプレッドは!?」
「エネルギー充填中!残り46秒!!」
「二八戦区のカラクルム級を優先ターゲットγと認定、火力を集中しろ!撃たせるな!!」
「カラクルム発砲!!――第二二、三〇、八四戦隊消滅!!」
「くっ!後続の戦隊は?」
「二〇二及び二〇三戦隊が八分前に合流したばかりです」
「両戦隊に前進を命じろ!穴を塞げ!!絶対に突破させるな!!」
「第五、一八、一九、二四、二七戦隊、いずれも魚雷・ミサイルを全射耗。
後退と補給を要請しています」
「許可できない。砲撃での戦闘継続を命じろ」
ダメだ。ヴェテランも若い連中も歯を食いしばって頑張ってはいるが、このままでは艦も人間も参ってしまう。どれほど時間断層からの増援が後方から加わっても、元から戦っている連中を後方に下げられない以上、艦と乗員の疲労は蓄積される一方だ。遠からず限界がくる。
しかし――。
(俺たちは山南が戻ってくるまで、絶対に崩れる訳にはいかん。
山南、俺が総旗艦の艦長にお前を推したのは、お前の経験と技量、見識を見込んだからだ。
何も遠慮することはない。俺たちの肩を踏み台にして思い切り飛び込め)
そんな後輩への心の声を、この世の者ならざる誰かが聞き届けたのかもしれない。
「アンドロメダより入電!!」
通信士が叫ぶようにして入電を告げた。その声は紛れもない喜色に染まっている。
「読め」
「宛、アルデバラン艦長。発、アンドロメダ艦長。
本文、我之ヨリ戦闘ニ加入ス。今暫クノ健闘アレ。以上!」
――彼らが来たのだ。
谷は一瞬だけ瞑目した後、艦長席から立ち上がり、眦を決して叫んだ。
「本宙域にある全ての地球・ガミラス艦艇に第一級優先通信!
全艦にオート・スペシャルを許可!撃ち尽くして構わん!
一隻でも多くのガトランティス艦をこちらに引きつける!!」
その瞬間こそが、後に『ヤマト奪還作戦』や『第三次火星沖海戦』と呼ばれることになる地球・ガミラス連合艦隊の死戦の始まりだった。彼らはその後、実に総戦力の八割を喪いつつも、ヤマトとアンドロメダ、そして銀河が白色彗星内から脱出するまで、見事戦線を維持し続けたのである。
そして、地球沖――

「挺身艦隊、全艦ワープ開始!!目標、白色彗星内部、都市帝国直上 五〇〇〇!!」
山南の号令一下、ヤマトカラーに彩られたアンドロメダとアンドロメダ・ブラックの群が、漆黒の虚空に向かって一斉に突進を開始する。次の瞬間、目前の宇宙空間が眩い閃光に包まれるのを山南は見た。
(安田、見てろよ。そっちに行く前に、俺の本当の“最善”を見せてやる)
防人を乗せて艦は征く。
それは希望の艦。
土星沖での敗北と大損害から、不死鳥のように甦った復活の艦。
その艦を見送り、迎え入れる人々の祈りと願いと共に、今、防人は再び火星沖へと――。
――fin
(注)文中の『時間断層工廠』及び『工廠長』という表記は、2202の公式設定であればそれぞれ『時間断層工場』『工場長』と表記するのが正しいのですが、個人的な好みで文中の表現としました。
まずは本作に素晴らしい挿絵CGを御提供下さいましたHARUさんに厚く御礼申し上げます。
実は本作を書き出した頃に、丁度HARUさんが動画サイトに火星沖に向かって出撃する山南SPとアンドロメダブラック軍団の動画を公開されまして、それを一目見た時から、HARUさんに挿絵のお願いができないかと考えていました。
この度、思い切ってHARUさんに御相談しましたところ、快くお引き受けいただいたばかりか、更にオリジナル動画にはなかったドッグ内のCGまで新たにご用意いただきました。
お陰様で、私の味気ない文章にもこれ以上ない豪華な彩りを添えることができ、本当に感謝に堪えません。
ちなみに、私が一目惚れしたHARUさんのアンドロメダ動画はこちら↓です(^o^)
さてさて、本文のタイトルが『第二次火星沖海戦外伝』となっているのは、この文章はそもそも本夏公開予定の『MMD第二次火星沖海戦』の原作エンディング用に書き始めたものだったからです。
ところが、2202第6章の影響で山南さんへの想い入れ(笑)が強くなり過ぎ、文章も長くなり過ぎたものですから、独立した外伝として公開することにしました。
山南さんパートは概ね満足すべき仕上がりになりましたが、後半の谷さんパートはやや蛇足が過ぎて冗長になってしまったのが反省点ですね。
とはいえ、自分なりに宇宙戦艦ヤマト2202について思っていたこと、感じていたことを目いっぱい詰め込むことができたので、その点ではとても満足しています。
満足と言えば、実は本作は本ブログの創作物では初めての『小説』風作品となりました。
“風”としているのは、私は小説の書き方をちゃんと勉強したことがない為です。
書き終わってみると『やっぱり難しかったなぁ』というのが正直なところですが、いつもの説明調の文章では描くことが難しいキャラクターの心情を描くことができたのは面白かったです。
また機会があればやってみたいと思います。
さてさて、ではまたここから第二次火星沖海戦原作の方に戻ります。
本夏の公開までもう暫くお待たせしますが、引き続き宜しくお付き合い下さいませ(^o^)