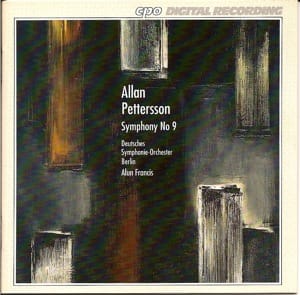JavaScriptの勉強がてらゲームを作ってみようと考え、とりあえずすぐにでも出来そうなやり方を使ってでっちあげてみました。JavaScriptはほとんど初めてなので要領が得られず、ソースを見られるのが恥ずかしいです。ブログではJavaScriptが実行できない(やり方がわからない)ので、以下でリンクしています。
こちらをクリック
プレイヤー「 i 」を動かし、ゴミ「 * 」を蹴って、ダストシュート「 o 」に入れるというルールのパズルゲームです。蹴られたゴミは何かに当たるまで止まりません。ボックス「 m 」は一度に一つだけ押せるので、ゴミの移動ルートを変える障害物としてうまく使ってください。壁「 M 」は動かせません。
プレイヤーの操作は、マウス、画面のボタン、テンキー、ijklキーのいずれかで行います。手詰まりになったら画面のリセットボタンまたはrキーを押してください。
bキーで一手だけ物(箱またはゴミ)を動かす前の状態に戻れますが、一度使うと次に物を動かすまで使えません。キーボード使用の場合、日本語入力はオフにしてください。マウスでプレイの場合は、クリックした場所に移動できる場合は最短距離で移動します。箱やゴミを動かす場合は、それらに隣接した状態でそれらをクリックしてください。マウスとキーボードを併用するとスムーズに操作できます。ステージはいつでも変更できます。クリアしたら、手動でステージを変更してください。
実はこれは私が25年ほど前に作ったゲームです。「倉庫番」にインスパイアされ、「ペンゴ」の要素を取り入れた、言ってみればパクリ王のようなゲームです。ステージマップは今回新たに作成しました。クリアまでのステップ数は、私の解法だと467でした。ですが想定外の解法があるかもしれません。
今回の移植ではグラフィックは使いませんでした。表とテキストだけで無理矢理表示しています。文字ばかりで見づらくて申し訳ありません。勉強が進んだらもっとまともなゲームを作りたいところです。
今回はMac版のSafari、FireFox、Google Chrome、Operaで動作確認済み。Windows環境のInternet Explorerで動作するよう修正(出来てなかったらお知らせください)。動作や表示の不具合報告や、ご意見ご感想、ハイスコア自慢などありましたらコメントいただけると嬉しいです。
【追記】
・画面にちょっとだけ色を付け、ソースを整理しました。445ステップでクリア。
・さらに想定外の解法の発覚により、一部マップを修正しました。
・またまた想定外。でも修正はなし。423ステップに。
・練習ステージ(ステージ0)を追加しました。画面を整理しました。
・Operaでのキー入力をサポートしました。419ステップでクリア(ステージ1)。
・399ステップでクリア(ステージ1)。
・ゴミの移動アニメーション、マウスに対応しました。
・自動で移動可能な場所をハイライトする機能を搭載。一手だけ物を動かす前に戻す機能を搭載。
・ステージ2を追加。

スクリーンショット