
「嘘つきアーニャの真っ赤な真実」 米原万里 著
例会開催日:2022年2月26日
まず菊池先生の言葉を多く引用してまとめます。
海外生活経験者もそうでない人も、参加者全員が自分の捉え方を自分の言葉で語っていて活気に満ちた面白い例会であった。
これは課題本の面白さが引き出していると思う。作品の構成もとても良い。3人のそれぞれ異なる人物を幼少期にソ連学校で出会ったときとそれから数十年後の人生の2つの舞台でそれぞれの人間性と友情が語られている。作者も自分の言葉で自分の体験を綴っていて、エッセイなのだが話の展開がドラマチックで物語として感動的な作品にできている。
参加者のコメントとして、次の部分が今回の例会で印象に残っている。
-既読であったが再読してまさしく今読む本(ロシアのウクライナ侵攻が始まった直後)だと思った。
-国外の学校にいると世界が動いていることを実感する。トルコがキプロスに侵攻したときのこと。同期生にプラハの春で戦車に向かって石を投げた人物がいた。この作品では、過去が追い付いてきたときに昔の友人と再会する。それぞれに批判的ではあるけれど、今の友を受け入れようとするところが人として素晴らしいと思う。
-海外生活をしても環境によって見えるものが違ってくる。自分が外国人になってみると他の国の、人の、いろいろな部分が見えてくる。
-「嘘つきアーニャの真っ赤な真実」の真っ赤とは「真っ赤な嘘」と共産主義の「赤」を掛けているのかとも思った。
-大人になっても探し出して会いたくなるような友人が自分にはいないと思った。この作者は子供時代にお互いの感情をストレートにぶつけ合うことができたから一生の友人となれたのだろうと思った。
-実在の人物を自分の視点で書く。創作にも見える。資料の集め方が凄い。自分のことを最小限に留めるところがエッセイとして面白さを出している。
-世界の共産党にもいろいろな違いがあることをこの本で知った。
-言葉の使い方、会話が読みやすいのは作者が通訳であったためと思う。人種、国、生活が違っていてもその人物を見ていかなければと思った。
-ヨーロッパの歴史、民俗、文化の複雑さを改めて実感した。
これらのコメントは印象に残っているだけでなく、私自身も共感した部分です。いつも皆さんのお話を聞けることで課題本の解釈が広がります。
特にお名前を挙げずにコメントとして書き出させていただきました。表現にずれが生じていましたらどうぞお許し、もしくはご訂正ください。
再び菊池先生の締めの言葉から引用して、「祖国、民族、血縁」これらは人間が生きてゆくうえでこれらに絡めとられていく要素だ。
「嘘つきアーニャの真っ赤な真実」を読み、まさしく私もそのように感じました。
関連する書物として、
『打ちのめされるようなすごい本』-米原万里著、
『サラエボのチェリスト』-スティーヴン・ギャロウェイ著、
『存在の耐えられない軽さ』-ミラン・クンデラ著、
『プラハの春』-春江一也著、
『征服者』-アンドレ・マルロー、
『テンピンルー』-柳沢隆行、
などが参加者または先生から挙げられた。
(推薦者:S)



















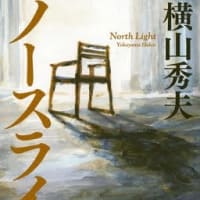






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます