
出席者は女性11名、男性3名
昭和30年から31年にかけて書かれた作品で「古臭い」と言う人がけっこう多いのでは、と危惧していましたが、思っていたより好評でした。
良くも悪くもポイントはヒロインの性格でしょうか。ヒロイン怜子について
・ 思ったまま、素直に行動しているのがいい
・ 朽ちていくものの中にいる輝き、感性と肉体のアンビバレンツ
・ こういう環境の中で、こういう鋭い感受性を持つことは、あり得るだろう
・ 結構恵まれた環境にいるのにわがままなイヤな子
・ ヒロイン像としてはいいが、こういう人が身近にいたらいやかも
等といろいろな意見あり。
女性出席者の中には昔読んだ人がかなりいて、
・ 25年前は怜子がピュアでなくて嫌だったが、今読むと素直に行動している、この若さが羨ましい
・ 今回は桂木夫人の方に感情移入した
といった感想がありました。
サガン作品、特に「悲しみよこんにちは」との相似を感じた人も多く、これはちょうど昭和30年に邦訳が出たようなので、連載中のどこかしらでヒントを得たのかも?
ヒロインの造型に関して、他に倉橋由美子「聖少女」や「青い山脈」の新子の名も挙がりました。
ヒロインの性格以外の否定的な意見としては
・ 文章に「わたしは」が多いのが気になる、特に「しかしわたしは」というのがやたら多い
・ 桂木夫人が書き込み不足
菊池さんから、当時の文学的な状況等にからめて
「昭和30年に「太陽の季節」が芥川賞受賞、翌年にかけて有力女流新人作家が次々に出たり、谷崎の「鍵」などの話題作が出たり、文学史上のエポック的な時代であった」
「怜子というヒロインの造型の新しさ、それが不倫という越境行為をモラルなしに行なって、そこで相手の妻と交流する、という新しさ」
「そしてこの後、不倫小説がブームに」
といったお話がありました。
その他、T氏からは「この規模の町でタクシーでホテルに乗り付けるのは大胆過ぎる」という貴重なご意見もありました。
たまたま太田和彦の「全国居酒屋巡礼」をパラパラ見ていたら、釧路の「炉ばた挽歌」というのが目に付いた。昭和32年開店、この本からとった店名だそうで、やはり大ベストセラーだったんですね。夏でもおでんがあるそうで、さすが北海道。
(推薦者&レポーター アビィ)



















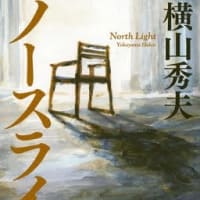






今の時代でも読み進ませる話の展開はうまいなと感じつつ、読み終えたところで「ある種のハーレクイーン?」てな思いを持ちました。
ヒロイン主体に描かれるのは仕方ないとしても
桂木夫妻というか、夫人は一体なんだったんだ?