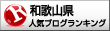引用:::
悠遊館21>余談・娯談・散談>両雄激突 両雄激突(2005年6月号)
今回は浜口儀兵衛と上野房五郎について書きます。
浜口儀兵衛と言うのは、銚子にあるヤマサ醤油の当主の名前です。1645年の初代以来続いており、現在でも12代当主がヤマサ醤油株式会社の社長です。今回の話は7代目浜口儀兵衛(1820-1885)のことです。文政2年紀州広村(現和歌山県有田郡広川町)に生まれた7代目儀兵衛は、当主となって、広村の本家と銚子を行き来していましたが、安政の大地震の時には、広村の本家に居りました。ところで、安政の大地震と言うのは、安政元年11月4日(新暦1854年12月23日)午前9時に起きた遠州灘沖を震源とするM(マグニチュード)8.4の安政東海地震(死者数千人)、翌5日午後4時の南海道沖を震源とする、前日と同じM8.4の安政南海地震(死者1万人)、それに翌安政2年10月2日(新暦1855年11月11日)の荒川河口を震源とするM6.9の安政江戸地震(死者1万人超)の3回の地震の総称です。11月5日(旧暦)夕刻、前日より遥かに激しい地震に見舞われた紀州広村は、続いて大津波に襲われました。儀兵衛は家族を避難させた後、夕暮れの中、自らは踏み止まりました。そして、自分の田にあった稲束(稲むら)に火を付けて村民に急を知らせ、多くの村民の命を救いました。身の危険や財産を顧みないこの行為はラフカディオ・ハーン(!★※小泉八雲)によって短編集で紹介され(1897年ロンドン刊)、また物語「稲むらの火」として1937年から1947年まで国定教科書に載せられました。地震の後儀兵衛は、生活基盤が壊滅した村民が離村するのを防ぐため、救援家屋を作り、農漁具を調達しました。更に、村民に現金収入を得させるのと将来の津波に備えるため、翌年から4年間をかけて、全長600m高さ5mの堤防を築きました。結局儀兵衛が広村救済に投じた自費は、!★※【合計4,665両】に達したと言います(紀州藩への具状書)。
1両=30万~40万円で換算すれば(19号『昔の値段』)この金額は、現在価値で【14億円から19億円】という巨額になります。
:余談:【鶴の恩返し】!★※【御歳暮送りました】
ヤマサ 【“鮮度の一滴”】 特選しょうゆ 500mlパウチ 1袋 273円
儀兵衛は、翌年の安政江戸地震で江戸店と銚子の本拠が 大被害にあいましが、にもかかわらず、この巨費を投じた!★※気前の良さには頭が下がります。
さて、明治維新後廃藩置県まで、大名領はそのまま残り、紀州藩も和歌山藩として残りました。この時、浜口儀兵衛は和歌山藩の
!★※【勘定奉行に取り立てられて藩政改革】に力を注ぎましたが、
に儀兵衛は、新政府から招かれ駅逓頭となりました。
次に上野房五郎です。天保6年越後の豪農上野家に生まれた房五郎は、父の死後生家を離れ世に出るため苦学を続けました。巻退蔵と改名して箱館開成所に入り箱館丸で日本を周航したり(1860年)、薩摩藩の英学教授になったり(1865年)しました。
慶応2年(1866年)幕臣前島家を継いで前島来輔と改名し幕府開成所に勤め、明治2年(1869年)12月28日前島密となって新政府に出仕しました。そうです、上野房五郎とは先月ご紹介した
前島密(1835-1919)のことなのです。その後、前島密は明治3年【駅逓 権 頭】となって、
!★※【6月17日】英国派遣を命じられ渡欧、翌年【8月15日】帰国します。
つまり、明治4年8月15日には、【駅逓頭】浜口儀兵衛(51歳)、【駅逓 権 頭】 前島密(36歳)という組合せであったわけです。 両雄は激突します。
翌日両者は面談し、儀兵衛から「通信の事はすでに飛脚屋あり、!★※【官営】は予の可とする所に非ず」との言を得た
前島は、最終 上司である【大蔵大輔 井上馨】に自分を駅逓頭とするよう訴えます(1956年刊前島密自叙伝)。
結局更に!★※【翌8月17日】前島密が【駅逓頭】となり、浜口儀兵衛は和歌山県大参事(和歌山県知事)に任ぜられて中央を去りました。その後の前島の苦心と活躍は先月申上げた通りです。
一体何のために、儀兵衛を駅逓頭に任命し、しかも!★※【半月後に更迭】したのか、
訳の分からない話です。儀兵衛はその閲歴から見ても分かる通り旧時代に名を成した人でした。それに対して前島は新時代に名を成すべく努力を続けてきた人ですので、新旧人材の対決で旧時代人が敗れたと言えるでしょう。
しかし、浜口儀兵衛は、堤防建設の目的を問われて、単に村民を救済して救済に慣れさせるのではなく、村民が働くことにより、いわば生産的に村民を救済するめに興したものであると言っています(1937年刊杉村広太郎『浜口梧陵伝』)。
また地震後の周辺村落を含めた行政経費の削減に儀兵衛が努力したことを考えると、
!★※【"官営"の限界】を知っていたのかも知れません。
「官営は予の可とする所に非ず」と言う彼(:濱口梧陵)の言葉の意味はもっと重かったのかも知れないのです。
話は全く違いますが、東京駅丸の内南口を出た所に東京中央郵便局が建っています。一方大阪駅桜橋口を出た所には、大阪中央郵便局が建っています。つまり、東西の中央郵便局は、同じ様な場所に建っていますが、これらは同じ設計者の設計で作られています。即ち、逓信省技師吉田鉄郎の作品で、東京が1933(昭和8年)、大阪が1939年(昭和14年)に完成しています。両ビル共70年の歴史を経て、シンプルながら趣のある姿となっています。これを郵政公社は壊して建替えるそうですが、本当ならモッタイナイ話ですね。
悠遊館21>余談・娯談・散談>両雄激突 両雄激突(2005年6月号)
今回は浜口儀兵衛と上野房五郎について書きます。
浜口儀兵衛と言うのは、銚子にあるヤマサ醤油の当主の名前です。1645年の初代以来続いており、現在でも12代当主がヤマサ醤油株式会社の社長です。今回の話は7代目浜口儀兵衛(1820-1885)のことです。文政2年紀州広村(現和歌山県有田郡広川町)に生まれた7代目儀兵衛は、当主となって、広村の本家と銚子を行き来していましたが、安政の大地震の時には、広村の本家に居りました。ところで、安政の大地震と言うのは、安政元年11月4日(新暦1854年12月23日)午前9時に起きた遠州灘沖を震源とするM(マグニチュード)8.4の安政東海地震(死者数千人)、翌5日午後4時の南海道沖を震源とする、前日と同じM8.4の安政南海地震(死者1万人)、それに翌安政2年10月2日(新暦1855年11月11日)の荒川河口を震源とするM6.9の安政江戸地震(死者1万人超)の3回の地震の総称です。11月5日(旧暦)夕刻、前日より遥かに激しい地震に見舞われた紀州広村は、続いて大津波に襲われました。儀兵衛は家族を避難させた後、夕暮れの中、自らは踏み止まりました。そして、自分の田にあった稲束(稲むら)に火を付けて村民に急を知らせ、多くの村民の命を救いました。身の危険や財産を顧みないこの行為はラフカディオ・ハーン(!★※小泉八雲)によって短編集で紹介され(1897年ロンドン刊)、また物語「稲むらの火」として1937年から1947年まで国定教科書に載せられました。地震の後儀兵衛は、生活基盤が壊滅した村民が離村するのを防ぐため、救援家屋を作り、農漁具を調達しました。更に、村民に現金収入を得させるのと将来の津波に備えるため、翌年から4年間をかけて、全長600m高さ5mの堤防を築きました。結局儀兵衛が広村救済に投じた自費は、!★※【合計4,665両】に達したと言います(紀州藩への具状書)。
1両=30万~40万円で換算すれば(19号『昔の値段』)この金額は、現在価値で【14億円から19億円】という巨額になります。
:余談:【鶴の恩返し】!★※【御歳暮送りました】
ヤマサ 【“鮮度の一滴”】 特選しょうゆ 500mlパウチ 1袋 273円
儀兵衛は、翌年の安政江戸地震で江戸店と銚子の本拠が 大被害にあいましが、にもかかわらず、この巨費を投じた!★※気前の良さには頭が下がります。
さて、明治維新後廃藩置県まで、大名領はそのまま残り、紀州藩も和歌山藩として残りました。この時、浜口儀兵衛は和歌山藩の
!★※【勘定奉行に取り立てられて藩政改革】に力を注ぎましたが、
に儀兵衛は、新政府から招かれ駅逓頭となりました。
次に上野房五郎です。天保6年越後の豪農上野家に生まれた房五郎は、父の死後生家を離れ世に出るため苦学を続けました。巻退蔵と改名して箱館開成所に入り箱館丸で日本を周航したり(1860年)、薩摩藩の英学教授になったり(1865年)しました。
慶応2年(1866年)幕臣前島家を継いで前島来輔と改名し幕府開成所に勤め、明治2年(1869年)12月28日前島密となって新政府に出仕しました。そうです、上野房五郎とは先月ご紹介した
前島密(1835-1919)のことなのです。その後、前島密は明治3年【駅逓 権 頭】となって、
!★※【6月17日】英国派遣を命じられ渡欧、翌年【8月15日】帰国します。
つまり、明治4年8月15日には、【駅逓頭】浜口儀兵衛(51歳)、【駅逓 権 頭】 前島密(36歳)という組合せであったわけです。 両雄は激突します。
翌日両者は面談し、儀兵衛から「通信の事はすでに飛脚屋あり、!★※【官営】は予の可とする所に非ず」との言を得た
前島は、最終 上司である【大蔵大輔 井上馨】に自分を駅逓頭とするよう訴えます(1956年刊前島密自叙伝)。
結局更に!★※【翌8月17日】前島密が【駅逓頭】となり、浜口儀兵衛は和歌山県大参事(和歌山県知事)に任ぜられて中央を去りました。その後の前島の苦心と活躍は先月申上げた通りです。
一体何のために、儀兵衛を駅逓頭に任命し、しかも!★※【半月後に更迭】したのか、
訳の分からない話です。儀兵衛はその閲歴から見ても分かる通り旧時代に名を成した人でした。それに対して前島は新時代に名を成すべく努力を続けてきた人ですので、新旧人材の対決で旧時代人が敗れたと言えるでしょう。
しかし、浜口儀兵衛は、堤防建設の目的を問われて、単に村民を救済して救済に慣れさせるのではなく、村民が働くことにより、いわば生産的に村民を救済するめに興したものであると言っています(1937年刊杉村広太郎『浜口梧陵伝』)。
また地震後の周辺村落を含めた行政経費の削減に儀兵衛が努力したことを考えると、
!★※【"官営"の限界】を知っていたのかも知れません。
「官営は予の可とする所に非ず」と言う彼(:濱口梧陵)の言葉の意味はもっと重かったのかも知れないのです。
話は全く違いますが、東京駅丸の内南口を出た所に東京中央郵便局が建っています。一方大阪駅桜橋口を出た所には、大阪中央郵便局が建っています。つまり、東西の中央郵便局は、同じ様な場所に建っていますが、これらは同じ設計者の設計で作られています。即ち、逓信省技師吉田鉄郎の作品で、東京が1933(昭和8年)、大阪が1939年(昭和14年)に完成しています。両ビル共70年の歴史を経て、シンプルながら趣のある姿となっています。これを郵政公社は壊して建替えるそうですが、本当ならモッタイナイ話ですね。