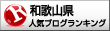戦時中は被災者援護の制度があった
政府は国民に危険な防空活動を義務づけた。その代わりにというべきか、空襲で被災した者には、「戦時災害保護法」(1942年2月制定)による援護が実施されていた。
政府広報誌「写真週報」1943年8月4日号(下記参照)は、被災者への援護措置を紹介している。士気高揚と民心安定を図るために、「被災したときには手厚い援護がある。だから安心して空襲に立ち向かえ」というわけである。
戦時中に存在した援護制度の中味は、次のように多様である。
・医療、埋葬
・生活資金扶助(1日60銭)
・就業支援
・遺族給与金(500円)
・就労不能による傷害給与金(700円)
生活資金援助は、当時の生活保護制度(救護法)による扶助費1日50銭より高かった。遺族給与金500円は、当時の教員の初任給の約10ヵ月分にあたる。他の救貧施策にはない手厚い制度が並んでいる。
ところが、1945年3月以降、全国で空襲が頻発化・大規模化すると、援護の実施は困難となっていった。援護の窓口となる役所自体が空襲で破壊されるからである。
広大な焼け野原が広がった大都市では尚更である。1945年3月10日の東京大空襲では、罹災家屋30万軒、罹災者100万人の大被害となった。役所も焼け落ち、全ての罹災者に復興住宅を用意できるはずもなく、罹災証明書の発行や生活資金扶助の申込受付すら困難となった。
多くの被災者が「戦災浮浪者」となり、親を失った孤児は「浮浪児」と呼ばれ、住む場所もなく地下道や駅の軒下に身を寄せた。1945年8月に戦争が終結し、冬になると多くの被災者が餓死・凍死で亡くなった。
こうした状況のまま、1946年2月に戦時災害保護法が廃止され、空襲被害者への援護制度が全て消滅した。軍人への補償制度も同時期に廃止された。同じ時期に、新たに生活保護法が制定されたが、空襲被害者への援護制度は一つも引き継がれなかった。
その後、1952年に軍人への補償は復活したが、空襲被害者への援護は復活しなかった。それが、軍人と一般市民との不平等の始まりである。
戦後の日本政府は「戦争被害の補償は軍人のみが対象である」と言っているが(前回記事を参照)、それを不動の前提とするのは間違いである。戦時中には一般市民への援護制度が存在したことを忘れてはいけない。
















 写真4
写真4