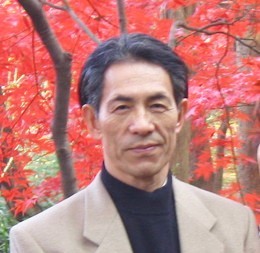写真は、戸建の内覧会の後の確認会で撮ったものです。確認会とは、内覧会で指摘した不具合の補修の出来具合を確認するものです。ここでご覧頂きたいのは、矢印で指した手すりです。この手すりは内覧会の時は、付いていなかったのですが、ロフトへの上り下りの際の安全のために付けてもらいました。ロフトとは天井を高くして、部屋の一部を2層式にした上部スペースのことを指します。建築基準法上、物置という扱いになりますので、面積は下の階の2分の1以下、天井高は1.4m以下、小屋裏に出入りするためのハシゴは固定式でないこと、などの規制があります。
写真は、戸建の内覧会の後の確認会で撮ったものです。確認会とは、内覧会で指摘した不具合の補修の出来具合を確認するものです。ここでご覧頂きたいのは、矢印で指した手すりです。この手すりは内覧会の時は、付いていなかったのですが、ロフトへの上り下りの際の安全のために付けてもらいました。ロフトとは天井を高くして、部屋の一部を2層式にした上部スペースのことを指します。建築基準法上、物置という扱いになりますので、面積は下の階の2分の1以下、天井高は1.4m以下、小屋裏に出入りするためのハシゴは固定式でないこと、などの規制があります。
このロフトへの上り下りにはハシゴを使いますが、安全上、気を使う点があります。それは、手すりが不十分であることです。上っていく際には両側にハシゴの手すりがありますが、上りきってロフトの床の乗ろうとする際に、持つべき手すりがないというケースがほとんどです。また、ロフトから下りる際も、つかまるところがありません。これでは、荷物を持って上り下りする際は、恐いと感じるでしょう。
こんな理由から、矢印で指した手すりを設置しました。ここに手すりがあれば、高い位置で、つかまるものがあるので、安心となります。ロフト付きの家を購入する際には、この手すりの設置もお考え下さい。下地の位置が分かれば、自分でも設置することは出来ます。(419)
 写真は、戸建の内覧会で、屋根裏の断熱材の様子を撮ったものです。屋根裏にはグラスウールやロックウールの断熱材が、一般的に敷き並べられます。戸建の屋根裏は、夏の間には60度以上になることもあるので、ここの断熱は極めて重要となります。
写真は、戸建の内覧会で、屋根裏の断熱材の様子を撮ったものです。屋根裏にはグラスウールやロックウールの断熱材が、一般的に敷き並べられます。戸建の屋根裏は、夏の間には60度以上になることもあるので、ここの断熱は極めて重要となります。
断熱材の施工と言っても、断熱材のマットを敷き並べるだけの簡単なものです。しかしながら、断熱材がしっかりと隙間なく並べられている、これが重要となります。断熱材が浮いていたり、隙間があったりしていれば、当然のことながら、断熱材の意味を成しません。家の中を断熱材で、布団のように、すっぽりと包み込んでしまう、これが断熱工事の基本です。
写真は、屋根裏にある点検口から、屋根裏内部を撮ったものです。断熱材の状態が極めて悪く、ばらけてしまっていて、2階の天井の裏が見えてしまっているのがお分かりになるでしょう。これでは何の為の断熱材かとなってしまいます。屋根裏は、まず開けないところですので、内覧会でチェックして直させなければ、ずーとこのままになるわけです。戸建をお買いになって、内覧会で家をチェックをされる際には、是非、屋根裏の断熱材の施工状態もご覧になって下さい。点検口があれば、業者に開けさせれば良いです。お住まいになられたら、まず、見るところではありませんので、要注意となります。(96)
 写真は戸建の内覧会で撮りました。写したところは、2階の天井にある点検口のカバーを開けて、2階の天井裏です。ここでご覧頂きたいのは、中央に横たわっている金属製の排気用のダクトです。このダクトの真ん中がつぶれてしまっています。つぶれてしまった原因は、建設時に作業員が、このダクトの上を踏んだからです。これでは排気の役に立ちません。見えないところだから良いだろう、こういうのは腹が立ちます。
写真は戸建の内覧会で撮りました。写したところは、2階の天井にある点検口のカバーを開けて、2階の天井裏です。ここでご覧頂きたいのは、中央に横たわっている金属製の排気用のダクトです。このダクトの真ん中がつぶれてしまっています。つぶれてしまった原因は、建設時に作業員が、このダクトの上を踏んだからです。これでは排気の役に立ちません。見えないところだから良いだろう、こういうのは腹が立ちます。
このダクトは、お風呂の上にある浴室乾燥機から中の空気を外に排気するものです。ですので、つぶれてしまったら、十分な排気が出来なくなります。一戸建ての内覧会では、普段見ないところ、例えば屋根裏、天井裏、床下、このようなところも点検口から覗いてみて下さい。(31.22)
 写真は戸建ての内覧会で撮ったものです。写したところは、キッチンの床下収納ボックスのカバーを開けて、収納ボックスを取ってみたところです。床下ですので、ここの部分はべた基礎の上面となります。収納ボックスの真下部分にあたる位置の基礎の上に袋が置かれています。この袋は何か分かりますでしょうか?
写真は戸建ての内覧会で撮ったものです。写したところは、キッチンの床下収納ボックスのカバーを開けて、収納ボックスを取ってみたところです。床下ですので、ここの部分はべた基礎の上面となります。収納ボックスの真下部分にあたる位置の基礎の上に袋が置かれています。この袋は何か分かりますでしょうか?
この袋の中には砂が入っています。つまり砂袋なのですが、これが置かれている目的は、プラスチック製の収納ボックスの底を支えるためです。収納ボックスは基礎から浮いた状態で設置されますので、長期間重いものを置いておくと、底がたわんできたり、床にも余計な荷重をかけてしまいます。それを防ぐのが、この砂袋です。まさに、縁の下ではなく床の下の力持ちです。
戸建ての内覧会に行きましたら、床下収納のカバーとボックスを持ち上げてみて、砂袋が設置されているかも確認下さい。砂袋が設置されていない場合、業者に言うか、大きめの布製の袋に砂をつめて置いておけば良いでしょう。その場合、砂袋と収納ボックスの底とが軽く接するようにしておいて下さい。(31)
 写真は一戸建ての内覧会で撮りました。ご覧になって頂きたいのは、インターホンと書いた矢印部分です。インターホンパネルがこの位置ですと、ドアを開けている時には、都度閉めないとインターホンパネルが使えません。これでは不便です。
写真は一戸建ての内覧会で撮りました。ご覧になって頂きたいのは、インターホンと書いた矢印部分です。インターホンパネルがこの位置ですと、ドアを開けている時には、都度閉めないとインターホンパネルが使えません。これでは不便です。
ここは建売り住宅ですが、インターホンパネルがこの位置では使いにくいと指摘したところ、移してくれることになりました。日常使用する設備の操作パネルが、使いにくいところに設置されている時には、売主に相談してみるのが大事と思います。(76)
 戸建の家を作る中で、難しいものの一つは階段です。玄関やリビングなどは平面的な見方でも感じが掴めますが、階段だけは、3次元の空間を意識しなければならないからです。ですから、階段の出来具合で大工さんの技量が分かる、とも言えるでしょう。また、階段は、転倒、落下など危険が高い場所でもあるので、建築基準法でもいろいろと条件を定めています。例えば、手摺の設置、階段の左右の幅は75㎝以上、踏み板の奥行き(踏面:ふみづら)は15㎝以上、踏み板の段差(けあげ)は23㎝以下などとしています。
戸建の家を作る中で、難しいものの一つは階段です。玄関やリビングなどは平面的な見方でも感じが掴めますが、階段だけは、3次元の空間を意識しなければならないからです。ですから、階段の出来具合で大工さんの技量が分かる、とも言えるでしょう。また、階段は、転倒、落下など危険が高い場所でもあるので、建築基準法でもいろいろと条件を定めています。例えば、手摺の設置、階段の左右の幅は75㎝以上、踏み板の奥行き(踏面:ふみづら)は15㎝以上、踏み板の段差(けあげ)は23㎝以下などとしています。
写真は、戸建の内覧会で階段部分を撮ったものです。写真を見て頂くと、階段の真ん中あたりの踏み板に赤い付箋が貼られています。この付箋は私が貼ったものですが、貼った理由は、踏み板に鳴りがあるからです。床鳴りと同じように、階段の踏み板にも、同じような現象が出ることがあります。階段を設置することは技術を要しますので、不具合が出やすい箇所と言えます。チェックの方法は、踏み板を足のかかとで、上からトントン軽くたたくようにすると分かります。(9726)
 写真は、一戸建ての内覧会で撮ったものです。台所の床下収納のカバーを取って、べた基礎の上を写しました。ご覧頂きたいのは、べた基礎の上が湿って黒くなっている部分です。こういうところが、どうして湿気ているのか、心配になります。
写真は、一戸建ての内覧会で撮ったものです。台所の床下収納のカバーを取って、べた基礎の上を写しました。ご覧頂きたいのは、べた基礎の上が湿って黒くなっている部分です。こういうところが、どうして湿気ているのか、心配になります。 写真は戸建の内覧会で撮りました。写した場所は、キッチンの床下収納のカバーを外して、床の下の部分です。ご覧になってお分かりのように、給水管(青色)もしくは給湯管(赤色)から漏水していて、べた基礎の表面が濡れています。調べた結果、給湯管の接合部(テープを巻いている部分)の金具が緩んでいて、漏水していることが判明しました。金具を締め直したら漏水は止まりました。
写真は戸建の内覧会で撮りました。写した場所は、キッチンの床下収納のカバーを外して、床の下の部分です。ご覧になってお分かりのように、給水管(青色)もしくは給湯管(赤色)から漏水していて、べた基礎の表面が濡れています。調べた結果、給湯管の接合部(テープを巻いている部分)の金具が緩んでいて、漏水していることが判明しました。金具を締め直したら漏水は止まりました。
戸建の場合、鉄筋コンクリートのべた基礎を採用するケースが多いです。地下の水分を止めるためのべた基礎ですが、このように床下で漏水がありますと、水は抜けません。床下が湿っていれば、土台や根太など重要な構造部分を腐らせ、シロアリも出やすくなります。
内覧会では、床下収納や点検口のカバーを外して、床の下もチェックしてみて下さい。床下の中に入るのは大変なので、カバーを開いて、懐中電灯を使って、中の奥の方も覗いて見ることです。チェックするポイントは、基礎の表面が濡れていないか、ゴミなどが散らかってないか、床下の断熱材はきちんと貼られているか、このような点になります。主に漏水の有無をチェックするので、床下を覗く前には、各所の水道を出しておくことが必要となります。(27)
 写真は一戸建ての内覧会で撮りました。天井の点検口のカバーを開いてみました。開いてみた目的は、天井裏の断熱材の施工状態を確認するためです。ここではご覧のように、しっかりと隙間なく断熱材が敷き込まれています。断熱材がこういう状態になっていれば合格です。
写真は一戸建ての内覧会で撮りました。天井の点検口のカバーを開いてみました。開いてみた目的は、天井裏の断熱材の施工状態を確認するためです。ここではご覧のように、しっかりと隙間なく断熱材が敷き込まれています。断熱材がこういう状態になっていれば合格です。
点検口のフタの上は、工事中に作業員が出入りするため、面倒なので断熱材を置いてなかったり、敷き忘れたりするケースがあります。断熱材は、部屋の中を隙間なく布団のように囲みこんでなければ断熱効果は半減してしまいます。
一戸建ての内覧会に行きましたら、天井にはこのような点検口がありますので、カバーを開けて、断熱材がしっかりと敷き込んであるのかも確認下さい。内覧会でそのような確認をしなければ、まず開ける所ではないので、ずーと、断熱材がないままの状態になってしまいます。(98)
 写真は一戸建ての内覧会で、洗面所にある床下点検口のカバーを開けてみたところです。本来、床下に貼られるべきポリスチレンフォームの断熱材が数枚重なって、その上にホコリが溜まっています。一体、なんでこんなところに断熱材があるのでしょう?この理由は、点検口の周りだけ、断熱材を切断したままで、床下に貼るのを忘れてしまったのです。
写真は一戸建ての内覧会で、洗面所にある床下点検口のカバーを開けてみたところです。本来、床下に貼られるべきポリスチレンフォームの断熱材が数枚重なって、その上にホコリが溜まっています。一体、なんでこんなところに断熱材があるのでしょう?この理由は、点検口の周りだけ、断熱材を切断したままで、床下に貼るのを忘れてしまったのです。
人が作るものだから、ウッカリミスも起きるものでしょうが、施工管理者が点検口のカバーを開けてみれば、これはおかしい!と気づく筈です。内覧会に行きましたら、床下や屋根裏の点検口も開けて、懐中電灯を使って、中を覗いてみて下さい。なんか腑に落ちない点がありましたら、売主に聞いてみることが大事です。(45)
 写真は戸建ての内覧会で撮りました。写した場所は、2階の天井にある屋根裏点検口を開けて、屋根裏の部分です。ご覧になって頂きたいのは、白い矢印で示した断熱材です。ここには、換気のダクトが天井裏を這ってます。ダクトの周りの断熱材を加工するのが面倒だったのでしょう。ダクトの上に、断熱材を載せただけになっています。
写真は戸建ての内覧会で撮りました。写した場所は、2階の天井にある屋根裏点検口を開けて、屋根裏の部分です。ご覧になって頂きたいのは、白い矢印で示した断熱材です。ここには、換気のダクトが天井裏を這ってます。ダクトの周りの断熱材を加工するのが面倒だったのでしょう。ダクトの上に、断熱材を載せただけになっています。
断熱材は、家の内側の温度を外側から守るために設置されます。ですので、家を包むように巻かなければなりません。隙間があっては効果は半減します。ですので、ダクトの周りに隙間が出来ないように、断熱材を敷き並べなくてはなりません。戸建ての内覧会では、天井に付いている点検口から屋根裏も見て、断熱材が隙間なく並べられているかも確認して下さい。(51)
 写真は、戸建の内覧会で撮りました。撮った場所はバスルームの天井の点検口を開けて、断熱材の状態を写しました。断熱材の仕様は、厚さ100㎜のグラスウールマットとなっています。ここを写した理由は、断熱材の置き方が悪いからです。断熱材は隙間があっては性能を発揮することはできません。考え方は、布団と同じで、隙間がない様に人を覆ってくれなければ、熱はそこから逃げていってしまいます。
写真は、戸建の内覧会で撮りました。撮った場所はバスルームの天井の点検口を開けて、断熱材の状態を写しました。断熱材の仕様は、厚さ100㎜のグラスウールマットとなっています。ここを写した理由は、断熱材の置き方が悪いからです。断熱材は隙間があっては性能を発揮することはできません。考え方は、布団と同じで、隙間がない様に人を覆ってくれなければ、熱はそこから逃げていってしまいます。
写真では、天井裏から、電気のケーブルが来ており、そのケーブルの重みで、断熱材が垂れ下がってきてしまっています。これでは、断熱材の意味を為しません。このような場合には、断熱材の隙間がなるべく少なくなるように、ケーブルを束ねて、支障のない位置から下に持ってくるようにしないとなりません。
戸建の内覧会に行きましたら、是非、お風呂の天井にある点検口を開けて、中を見てみて下さい。その際は、高さ1mほどの脚立と懐中電灯が必要となります。(17)
 写真は戸建ての内覧会で撮ったものです。ご覧頂きたいのは、窓の部分です。この窓はすべり出し窓となっていまして、手前のハンドルを回すと、窓が外側に開いて行きます。ここでの問題は、窓を開こうとすると、外側に付けた物干し金物にぶつかってしまって、これ以上開けないことです。物干し金物は、ベランダの手すり壁に付いています。戸建ての物干し金物は、最後に付けますが、この窓の開き具合を確認せずに、付けてしまったのでしょう。これでは、物干し竿を通したら、窓の開き具合は更に狭まります。戸建ての内覧会では、全ての窓が問題なく開くかも確認して下さい。この写真のケースでは、物干し金物を点け直すことになりました。(6327)
写真は戸建ての内覧会で撮ったものです。ご覧頂きたいのは、窓の部分です。この窓はすべり出し窓となっていまして、手前のハンドルを回すと、窓が外側に開いて行きます。ここでの問題は、窓を開こうとすると、外側に付けた物干し金物にぶつかってしまって、これ以上開けないことです。物干し金物は、ベランダの手すり壁に付いています。戸建ての物干し金物は、最後に付けますが、この窓の開き具合を確認せずに、付けてしまったのでしょう。これでは、物干し竿を通したら、窓の開き具合は更に狭まります。戸建ての内覧会では、全ての窓が問題なく開くかも確認して下さい。この写真のケースでは、物干し金物を点け直すことになりました。(6327)
 写真は戸建ての内覧会で撮りました。写したところは1階から2階へ上がる階段の手すりです。ご覧頂きたいのは、赤字で書いてある「キャップがない」というところと、上の「キャップがある」と書いてあるところです。
写真は戸建ての内覧会で撮りました。写したところは1階から2階へ上がる階段の手すりです。ご覧頂きたいのは、赤字で書いてある「キャップがない」というところと、上の「キャップがある」と書いてあるところです。
手すりを取り付ける金具をブラケットと呼びます。よく見て頂くと、上のブラケットにはビスを隠すためのキャップがありますが、下のブラケットには、キャップがないので、ビスがそのまま見えます。これは、単に、業者がキャップを忘れただけです。
キャップがなくても、使用上は問題はありませんが、ビスがそのまま見えては見栄えが悪いです。内覧会に行きましたら、手すりに隠れていて見難いところですが、こういう箇所もチェックして下さい。(47)
 写真は、戸建の内覧会でレンジフード上部のカバー(幕板:まくいた)を外した状態です。レンジフードの排気ダクトの断熱材の状況を確認するために、幕板を外させました。中を確認しますと、断熱材は隅から隅まで巻かれているし、壁との取り合いも気密テープが貼られていますので、これでOKとなりました。
写真は、戸建の内覧会でレンジフード上部のカバー(幕板:まくいた)を外した状態です。レンジフードの排気ダクトの断熱材の状況を確認するために、幕板を外させました。中を確認しますと、断熱材は隅から隅まで巻かれているし、壁との取り合いも気密テープが貼られていますので、これでOKとなりました。
通常、レンジフードのダクトは、亜鉛鉄板製で直径15㎝のスパイラルの丸ダクトが使われます。アルミのダクトは高温になるため使用されません。消防法では、熱源がガスであれば、排気ダクトを周りから10㎝以上離すか、金属以外の特定不燃材料(例えばロックウール)で50㎜(認定工法の場合は50㎜以下でも可)以上で巻くことと定めています。
戸建の内覧会では、レンジフードの上部の幕板も外して、中の排気ダクトの断熱材の状況も確認した方が良いでしょう。写真のように、しっかりと断熱材そして気密テープが貼られていれば良いです。そして、売主に、断熱材の仕様と厚さも聞いてみて下さい。断熱材の巻き方が不十分だったり、気密テープが貼られていない場合には、その旨指示すれば良いです。また、熱源がIHの場合には、消防法では規定はありませんが、熱を使うこと、将来ガスに変える可能性もあることなどから同じように断熱しておいた方が安全と思います。(29)