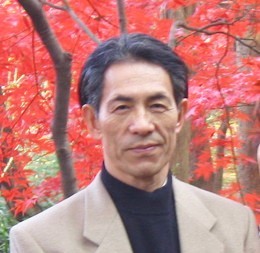写真はマンションの内覧会で撮りました。バルコニーに置いてある給湯器の室外機です。このマンションはオール電化ですので、エアコンの室外機と同じようなものが給湯機用の室外機として設置されます。
写真はマンションの内覧会で撮りました。バルコニーに置いてある給湯器の室外機です。このマンションはオール電化ですので、エアコンの室外機と同じようなものが給湯機用の室外機として設置されます。
ここでご覧頂きたいのは、室外機の下の矢印部分です。右側には2枚、左側には1枚の防振ゴムが敷かれています。ここはバルコニーで、雨水を流すため床に傾斜がありますので、室外機を水平にするために、室外機の右側には2枚、左側には1枚、それぞれ、防振ゴムが敷かれているわけです。
この防振ゴムは厚さが10mmなのですが、在ると無いとでは、大違いです。室外機には、高速で回転するファンが中に入っていますので、回転すればやはり振動が出ます。振動が出れば、外に置いてあっても、床を伝わって部屋内にも入ってきます。オール電化の場合には、夜間にお湯を作りますので、昼間には気にならない音でも、夜間になると気になる場合もあります。
内覧会に行きましたら、このような室外機の下も見て、防振ゴムが設置されているかも見て下さい。防振ゴムがない場合には、ホームセンターで購入し、適当な大きさにカッターで切って、自分で設置することも出来ます。(27)
 写真は、マンションの内覧会で、バルコニーの長尺シートの接着不良部分を撮ったものです。長尺シートとは、厚さ2㎜の、塩化ビニールを素材とした仕上げ材です。耐久性があるので、バルコニーなど気象条件の厳しいところに、接着剤で貼り付けられます。シートの周りは、全てコーキングをする場合も、しない場合も、また、ベランダの水上側(窓側)だけをする場合もあります。写真では、コーキングはありません。
写真は、マンションの内覧会で、バルコニーの長尺シートの接着不良部分を撮ったものです。長尺シートとは、厚さ2㎜の、塩化ビニールを素材とした仕上げ材です。耐久性があるので、バルコニーなど気象条件の厳しいところに、接着剤で貼り付けられます。シートの周りは、全てコーキングをする場合も、しない場合も、また、ベランダの水上側(窓側)だけをする場合もあります。写真では、コーキングはありません。
長尺シートの全周にコーキングを打つ時は、接着不良は生じにくいのですが、周りにコーキングを打たない場合には、写真のように、長尺シートの端部の接着が不十分で、手で簡単に持ち上がってしまうことがあります。この程度の接着不良で漏水が起きる事はありませんが、気象条件の極めて厳しいところですので、将来、シートが更にめくれたり、足に引っ掛かっても困ります。
バルコニーにシートが貼られている場合には、このような端部の接着不良だけではなく、シートの浮き、膨れはないか、シート同士の接続部はちゃんとなってるか、なども良くチェックして下さい。チェックの方法は、状態を見て、指の先で、表面を触ってみることです。(611)
 写真はマンションの内覧会で撮りました。ここはルーフバルコニー付きの部屋です。ご覧頂きたいのは、ベランダからルーフバルコニーへ出る2段のステップです。最初は1段しかなくて、内覧会の時に、「1段だけではパラペットをまたぐのは大変だ」と指摘したら2段付けてくれるようになりました。パラペットとは、屋根の周りの1段高くなっている部分です。屋根の防水層を立ち上げているので、屋根の床からパラペット上部までの高さは50㎝ほどになります。
写真はマンションの内覧会で撮りました。ここはルーフバルコニー付きの部屋です。ご覧頂きたいのは、ベランダからルーフバルコニーへ出る2段のステップです。最初は1段しかなくて、内覧会の時に、「1段だけではパラペットをまたぐのは大変だ」と指摘したら2段付けてくれるようになりました。パラペットとは、屋根の周りの1段高くなっている部分です。屋根の防水層を立ち上げているので、屋根の床からパラペット上部までの高さは50㎝ほどになります。ルーフバルコニー付きの部屋では、ベランダから出て、パラペットをまたぐことになります。パラペットの高さは、一般に40~50㎝程あるので、ステップがないと、またぐのが大変です。ルーフバルコニーの使用料も売値にはちゃんと入っていますので、便利なように作られていなくてはなりません。ルーフーバルコニー付きの部屋を購入した場合には、内覧会で、ベランダからルーフバルコニーへの歩きやすさも確認して下さい。(15)
 写真は、マンションのルーフバルコニーの隅にある樋(とい)の出口部分を撮ったものです。セットバックしているマンションでは、上の階のルーフバルコニーに降った雨は、ここに流れ出てきます。上の写真は内覧会の時のもので、縦樋の出口が写真のように、水平に切断されてました。これでは、屋根に降った雨が樋から大量に流れてきてうるさいし、撥ねるし、最後の部分にエルボ(曲がっているパイプ)を最下部に付けるように言いました。
写真は、マンションのルーフバルコニーの隅にある樋(とい)の出口部分を撮ったものです。セットバックしているマンションでは、上の階のルーフバルコニーに降った雨は、ここに流れ出てきます。上の写真は内覧会の時のもので、縦樋の出口が写真のように、水平に切断されてました。これでは、屋根に降った雨が樋から大量に流れてきてうるさいし、撥ねるし、最後の部分にエルボ(曲がっているパイプ)を最下部に付けるように言いました。 下の写真は内覧会の2週間後の再内覧会の時のものです。樋の最下部に、赤い矢印で示しているエルボが取り付けられています。こうすれば、樋から流れ出る雨水の向きも排水溝の方になります。また、雨の落ちる衝撃も和らげられるので、水の撥ねも少なくなります。ルーフバルコニー付きのお部屋を購入された方は、内覧会の時には、バルコニーの隅に行って、樋の出口部分の処理も見て下さい。上の写真のようになっていましたら、下の写真のようにするように要望して下さい。(873,18)
下の写真は内覧会の2週間後の再内覧会の時のものです。樋の最下部に、赤い矢印で示しているエルボが取り付けられています。こうすれば、樋から流れ出る雨水の向きも排水溝の方になります。また、雨の落ちる衝撃も和らげられるので、水の撥ねも少なくなります。ルーフバルコニー付きのお部屋を購入された方は、内覧会の時には、バルコニーの隅に行って、樋の出口部分の処理も見て下さい。上の写真のようになっていましたら、下の写真のようにするように要望して下さい。(873,18)
 写真は、マンションの内覧会の時のものです。この部屋のリビングには、エアコンが標準装備されています。ですので、エアコンも稼動させてみました。稼動させて暫くしましたら、エアコンの下部から水がこのように流れ出してきて、隣の住戸のバルコニーまで流れ出てしまいます。これでは、隣の人から苦情が来るでしょう。
写真は、マンションの内覧会の時のものです。この部屋のリビングには、エアコンが標準装備されています。ですので、エアコンも稼動させてみました。稼動させて暫くしましたら、エアコンの下部から水がこのように流れ出してきて、隣の住戸のバルコニーまで流れ出てしまいます。これでは、隣の人から苦情が来るでしょう。
この水は、エアコンのドレーンから流れ出てくるものです。ドレーン用の排水レールはあるのですが、排水溝への水勾配が不十分なので、レールの途中で床に流れ出してしまうのです。エアコンが標準装備されている場合には、エアコンのスイッチも入れてみて、ドレーン水がちゃんとレールに沿って、排水溝まで流れていくかも確認して下さい。(7103)
 写真はマンションの内覧会で撮りました。ご覧頂きたいのは、床の上を流れている水です。この内覧会の日は、とても寒く、売主も気を遣って床暖房を入れてました。ここの床暖房は、ガスによるもので、写真に見えるのが、ガス給湯器の室外機です。
写真はマンションの内覧会で撮りました。ご覧頂きたいのは、床の上を流れている水です。この内覧会の日は、とても寒く、売主も気を遣って床暖房を入れてました。ここの床暖房は、ガスによるもので、写真に見えるのが、ガス給湯器の室外機です。
設置されている給湯器は高効率タイプで、室外機からは、燃焼に伴って、僅かな水が排出されます。この排水(ドレン水と呼びます)を流すために、室外機にはドレンパイプが付けられ、ドレンパイプの先は、ドレンレールにつなぎ、ドレンレールに沿って水は流されて行きます。
写真では、このドレンレールの溝の深さ、勾配が適切でないので、ベランダの床に流れ出してしまっているわけです。これでは、ベランダの上を歩く際に、足元が濡れてしまいますし、ベランダの汚れも気になります。内覧会では、このような箇所も見て下さい。室外機が運転されていない場合には、小さなビンを持って行って、排水状態を確認するのも良いでしょう。写真の例では、ドレンレールに適切な水勾配を付けるように指示しました。(22)
 内覧会に同行させて頂いた方から相談がありました。内容は、ベランダの隣戸隔板の横の隙間から(赤の矢印部分です)、2歳の子供が隣戸へ行ってしまえるというものです。これでは困ります。赤の矢印の幅は、16.5㎝です。これぐらいの隙間があると、幼児は通り抜けが可能なのです。ここは避難経路となっているため、物を置いて子供を行かせなくすることも出来ません。
内覧会に同行させて頂いた方から相談がありました。内容は、ベランダの隣戸隔板の横の隙間から(赤の矢印部分です)、2歳の子供が隣戸へ行ってしまえるというものです。これでは困ります。赤の矢印の幅は、16.5㎝です。これぐらいの隙間があると、幼児は通り抜けが可能なのです。ここは避難経路となっているため、物を置いて子供を行かせなくすることも出来ません。
この隙間は、建築法規上、どのように位置づけされるかは断定できません。例えば、ベランダの手すり壁の手すり子(縦格子)として考えますと、住宅の品質確保の促進等に関する法律などでは、手すり子の間隔の内法寸法を11㎝以下と明記しています。この根拠は、隙間が11㎝以下であれば、幼児でも落下しない、というものです。
今回の問題は手すり子ではないので、落下の危険性と同等ではありません。しかしながら、法律的にどうであれ、絶対に通り抜け出来てはいけない、というところです。そう考えますと、隙間を11㎝以下にすべきでしょう。内覧会では、このような隙間があるか?その隙間の幅は?こういう点もチェックして下さい。お住まいになってからでも、このような危険な箇所があれば、売主に指摘して早急に直してもらうべきです。写真の例では、買主が対策を要望し、売主が予防策を実施しました。
 写真は、マンションの1階の部屋の内覧会で撮りました。1階ですから、リビングの外はテラス、その先は専用庭になっています。写真を写した場所は、その専用庭の中にある雨水の枡です。庭に降った雨はここに集められ、外部へと排出されて行きます。枡に落ちたら危険ですから、上面には金属のグレーチングのカバーが置かれています。
写真は、マンションの1階の部屋の内覧会で撮りました。1階ですから、リビングの外はテラス、その先は専用庭になっています。写真を写した場所は、その専用庭の中にある雨水の枡です。庭に降った雨はここに集められ、外部へと排出されて行きます。枡に落ちたら危険ですから、上面には金属のグレーチングのカバーが置かれています。
ここでご覧頂きたのは、見難いですが、グレーチングの下に置かれている金属のネット(網)です。このネットが敷かれている理由は、芝や葉っぱが枡の中に落ちて行かないようにすることです。また、ネットがあれば、カギやお金など大事な物を落とした時でも、枡の底にまで落ちて行かないので助かります。細かいことですが、ネットがあるかないか、大きな違いです。
マンションでも戸建てでも、上部がグレーチングのカバーとなっている場合には、その下に金属のネットがあるかないかも確認下さい。ネットが無く、売主に言っても付けてくれない場合には、ホームセンターで買って、合った大きさに切って敷かれることをお勧めします。(41)
 写真はマンションの内覧会で撮りました。写したところは、バルコニーに設置されているシンクの水道の外壁から出てきているところの継ぎ目部分です。継ぎ目の下の方に、小さい水滴が見えます。内覧会に行き、ベランダに出てみたら、壁に水滴があるので、気が付きました。すぐに水道を出してみると、水漏れしているので、売主を呼んで、その場で修理をさせました。バルコニーの水道についてはそれほど注意を払いませんが、このようなこともありますので、やはり、水を出して様子を見て、確認が要ります。マンションでの水漏れ事故は大惨事になることもあるので、特に注意が必要です。
写真はマンションの内覧会で撮りました。写したところは、バルコニーに設置されているシンクの水道の外壁から出てきているところの継ぎ目部分です。継ぎ目の下の方に、小さい水滴が見えます。内覧会に行き、ベランダに出てみたら、壁に水滴があるので、気が付きました。すぐに水道を出してみると、水漏れしているので、売主を呼んで、その場で修理をさせました。バルコニーの水道についてはそれほど注意を払いませんが、このようなこともありますので、やはり、水を出して様子を見て、確認が要ります。マンションでの水漏れ事故は大惨事になることもあるので、特に注意が必要です。
内覧会では、一般的には、水道は出ますので、全て出してみてチェックするのが良いでしょう。水道の栓をひねっても水が出ない場合には、一応、売主に元栓を開けて良いかを確認してから、それぞれの水道栓を開けた方が良いでしょう。(726)
 写真はマンションの内覧会で撮りました。写した場所は、バルコニーの手すり部分です。ご覧頂きたいのは、矢印部分で、ビス忘れと書いてあるところです。手すりに手をかけたら、なんかグラグラするので、変だなと思って手すりの下をのぞいてみました。そしたら、本来、ビスで締めるべきところを、忘れてしまっていたわけです。手すりの下だから、ウッカリとしてしまったのでしょう。場所が場所だけに、ウッカリ忘れたでは済まないのですが、内覧会では、こういうところも注意して見てみましょう。上からでは分かりにくいので、ビスのあるところは、上からも、下からも、覗いてみなければなりません。
写真はマンションの内覧会で撮りました。写した場所は、バルコニーの手すり部分です。ご覧頂きたいのは、矢印部分で、ビス忘れと書いてあるところです。手すりに手をかけたら、なんかグラグラするので、変だなと思って手すりの下をのぞいてみました。そしたら、本来、ビスで締めるべきところを、忘れてしまっていたわけです。手すりの下だから、ウッカリとしてしまったのでしょう。場所が場所だけに、ウッカリ忘れたでは済まないのですが、内覧会では、こういうところも注意して見てみましょう。上からでは分かりにくいので、ビスのあるところは、上からも、下からも、覗いてみなければなりません。
バルコニーの手すりにはいくつかのタイプがありますが、ここの手すりは、アルミの枠があって、中にガラスがはめ込んであるものです。手すりの左右の端の支柱は、壁にしっかりと固定されなければなりません。支柱が壁に固定されたら、手すりの上部は支柱にビスで、こちらも固定されなければなりません。手すりは、バルコニーの床から立ち上がっているだけので、手すりの左右の端部が壁に固定されなければ、グラついてしまいますし、危険でもあります。(125)
 写真はマンションの内覧会で撮りました。写したところはベランダ先端の手すりの根元部分で、左側がベランダで右側が外部になります。ベランダの床の先端には手すり壁が取り付けられます。手すり壁を設置する場合には、ベランダのコンクリート床の先端部の笠木(かさぎ)に穴を開けて、手すり支柱を取り付け、支柱に壁を設置します。
写真はマンションの内覧会で撮りました。写したところはベランダ先端の手すりの根元部分で、左側がベランダで右側が外部になります。ベランダの床の先端には手すり壁が取り付けられます。手すり壁を設置する場合には、ベランダのコンクリート床の先端部の笠木(かさぎ)に穴を開けて、手すり支柱を取り付け、支柱に壁を設置します。
写真の赤の矢印部分をご覧頂くと、穴が開いているのがわかります。手すりの支柱を設置する際に穴を開けますが、このように穴が残っていては、ここに雨が溜まります。雨が溜まれば、支柱の中には金属のアンカーが入っておりますので、これを錆びさせることになります。アンカーが錆びれば、将来、支柱が折れる可能性もあります。
外部に面するこのような箇所は、雨水対策は非常に大事です。この穴は、コーキングで埋めて、ウレタンの防水塗装を施すように指示しました。内覧会では、ベランダの支柱周りも確認して下さい。このような穴があったら、埋めるように指示して下さい。(4319)
 写真はマンションの内覧会で撮りました。写したところはバルコニーです。ご覧になって頂きたいのは、見難いのですが、ドレーンレールと書いたところとドレーンレールがない(付箋を貼ってます)と書いたところです。ドレーンレールとは、エアコンの室外機から出る結露水を流すためのレールです。これがないと、エアコンの稼働時、相当量の結露水が出ますので、流れ出た水は、ダラダラと広がってしまいます。そうならないように、レールを設置して、レールに沿って流れていくようにするためのものです。
写真はマンションの内覧会で撮りました。写したところはバルコニーです。ご覧になって頂きたいのは、見難いのですが、ドレーンレールと書いたところとドレーンレールがない(付箋を貼ってます)と書いたところです。ドレーンレールとは、エアコンの室外機から出る結露水を流すためのレールです。これがないと、エアコンの稼働時、相当量の結露水が出ますので、流れ出た水は、ダラダラと広がってしまいます。そうならないように、レールを設置して、レールに沿って流れていくようにするためのものです。
ここの壁には、2か所のエアコンのスリーブ(貫通孔)が見えます。つまり、こちら側はリビングのエアコンと室外機とを結ぶスリーブで、向こう側は、洋室のエアコンと室外機とを結ぶものです。従い、ここには2台の室外機が来ることを考えていますので、壁の2か所にスリーブがあるわけです。
室外機が2台付くことを考えていますので、当然、ドレーンレールも2か所に設置されねばなりません。手前の方は、実は、売主が付けるのを忘れてしまっていたのです。エアコンが設置される場所に、室外機とを結ぶスリーブがあるか、そして、結露水を流すためのドレーンレールも設置されているか、内覧会では、この点も確認して下さい。(43)
 写真は、マンションの内覧会でバルコニーに設置されているエコキュートの室外機の下を撮ったものです。赤い矢印部分をご覧になって頂きますと、排水口のホースの継ぎ目に水滴が付いているのが見えます。これは継ぎ目の処理が不十分なので漏水しているわけです。エコキュートは大気の熱を吸収してお湯を作ります。エコキュートの中に冷媒を入れておき、それを大気に接しさせ、熱交換させるものです。
写真は、マンションの内覧会でバルコニーに設置されているエコキュートの室外機の下を撮ったものです。赤い矢印部分をご覧になって頂きますと、排水口のホースの継ぎ目に水滴が付いているのが見えます。これは継ぎ目の処理が不十分なので漏水しているわけです。エコキュートは大気の熱を吸収してお湯を作ります。エコキュートの中に冷媒を入れておき、それを大気に接しさせ、熱交換させるものです。
冷媒は、大気と接し熱を吸収、その熱を水に伝えお湯にして、また、冷たくなって戻ってきます。室外機の中では、このような熱交換がされていますので、大気の温度よりも冷たくなっている部分もあります。大気の温度よりも冷たいので、その部分で結露が生じてしまいます。そうして出来た結露水を逃がす為に、室外機の下には写真のような排水パイプが付いているわけです。この排水パイプの継ぎ目がちゃんと施工されていないので、継ぎ目から結露水がポタポタと落ち、バルコニーの床に流れ出してしまっています。(床の少し黒い部分)排水パイプが本来の役目を果たせないのです。内覧会に行きましたら、エコキュートやエアコンが設置されている場合には、スイッチをONにして、室外機の下も覗いて、このようなことが起きていないかもチェックして下さい。(981)
 写真はマンションの内覧会で撮りました。写したところは、ベランダの樋(とい:雨水を流すための排水管)の裏です。ベランダの床には、長尺シートと呼ばれる、厚さ2㎜の塩化ビニール製のシートが貼られます。雨が掛かるところなので、基本的には、シートの継ぎ目は少ない方が良いです。継ぎ目がなるべく少なくなるように、トイレットペーパーのようなクルクル巻きの長いシートを貼っていくわけです。
写真はマンションの内覧会で撮りました。写したところは、ベランダの樋(とい:雨水を流すための排水管)の裏です。ベランダの床には、長尺シートと呼ばれる、厚さ2㎜の塩化ビニール製のシートが貼られます。雨が掛かるところなので、基本的には、シートの継ぎ目は少ない方が良いです。継ぎ目がなるべく少なくなるように、トイレットペーパーのようなクルクル巻きの長いシートを貼っていくわけです。
ここの部分には、樋があります。樋がありますので、シートに穴を開けなくてはなりません。穴を開けるために、シートを切り込んだわけです。シートを切り込んだのは仕方ないのですが、問題は、切った部分(白い矢印のところ)は、隙間が生じないように処置をしておかないと、雨水が入り込んでしまいます。本来、このような長尺シートの継ぎ目は、しっかりと溶接します。溶接すべきなのですが、樋の裏でもあるし、雨が掛かりにくいことも考えて、コーキングをするように指示しました。内覧会に行きましたら、このような箇所も見て下さい。写真のように、切ったまんま、になっていましたら、接合部にコーキングするように指摘して下さい。(113)
 写真はマンションの内覧会で撮りました。写した場所は、ベランダの壁に設置されているガス給湯器を下から見上げたところです。ここでガスを焚いて水をお湯に変え、お風呂などに供給します。水とガスは、玄関横に置かれたメーターボックスから、床下を通って、外壁を立ち上がり、壁に空けた穴から運ばれてきます。ここで作られたお湯は、また、外壁の穴から、床下を通って、お風呂などに運ばれて行きます。
写真はマンションの内覧会で撮りました。写した場所は、ベランダの壁に設置されているガス給湯器を下から見上げたところです。ここでガスを焚いて水をお湯に変え、お風呂などに供給します。水とガスは、玄関横に置かれたメーターボックスから、床下を通って、外壁を立ち上がり、壁に空けた穴から運ばれてきます。ここで作られたお湯は、また、外壁の穴から、床下を通って、お風呂などに運ばれて行きます。
ですので、写真で示したように、ガス管、給水管そして給湯管、3種類のパイプの入る穴が壁に空けられます。パイプが入った穴の周りは、しっかりと隙間がないようにコーキングされなければなりません。給湯器が上にありますので、雨は入りにくいところではありますが、パイプの表面の結露水、外気、虫などが入る可能性があります。従いまして、内覧会では、ベランダに出て、給湯器の下から覗いてみて、パイプの周りにしっかりとコーキングがされているかも確認下さい。(224)