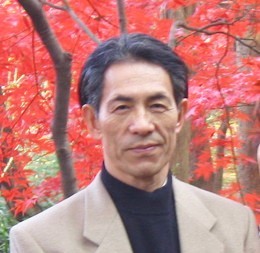隣の家の不注意により自分の家も燃えてしまった、この場合、隣の家に損害賠償は請求できるのでしょうか。民法の決まりでは、故意または過失により第三者に損害を与えたら、賠償しなくてはならないと定めています。しかし、火災は、この決まりは例外となっています。火災の場合、火元に重大な過失がない限り、火元に責任はないとしています。これは、火元の人も財産を失っており、更に周りの人の分まで責任を負わすのは酷であるという考えからです。ですから、一般的には、もらい火によって自分の家が消失してしまっても、火元の人から賠償を受けるのは難しいということになります。
隣の家の不注意により自分の家も燃えてしまった、この場合、隣の家に損害賠償は請求できるのでしょうか。民法の決まりでは、故意または過失により第三者に損害を与えたら、賠償しなくてはならないと定めています。しかし、火災は、この決まりは例外となっています。火災の場合、火元に重大な過失がない限り、火元に責任はないとしています。これは、火元の人も財産を失っており、更に周りの人の分まで責任を負わすのは酷であるという考えからです。ですから、一般的には、もらい火によって自分の家が消失してしまっても、火元の人から賠償を受けるのは難しいということになります。
もらい火によって、自分の家が焼失してしまった場合、頼りになるのは火災保険だけです。火災保険は建物が対象のものと、家財などが対象のものとがあります。マイホームの場合は両方に、賃貸の場合は家財を対象にした保険にのみ加入した方が良いでしょう。
 茨城県の常総市で、記録的な豪雨で鬼怒川の堤防が決壊して1ヶ月が経ちます。まだ、多くの人達が元の暮らしを取り戻せていません。こんな時、水災に備えた保険に入っていれば、まだ安心感はあります。水災は主に火災保険で補償されます。ですので、まず、現在入っている火災保険で水災も補償されるのかの確認が必要となります。水災の被害状況は浸水の高さなどで調べます。1階の天井まで浸水すれば「全壊」、床上1㍍までの浸水で「大規模半壊」、それより低い床上浸水は「半壊」となります。
茨城県の常総市で、記録的な豪雨で鬼怒川の堤防が決壊して1ヶ月が経ちます。まだ、多くの人達が元の暮らしを取り戻せていません。こんな時、水災に備えた保険に入っていれば、まだ安心感はあります。水災は主に火災保険で補償されます。ですので、まず、現在入っている火災保険で水災も補償されるのかの確認が必要となります。水災の被害状況は浸水の高さなどで調べます。1階の天井まで浸水すれば「全壊」、床上1㍍までの浸水で「大規模半壊」、それより低い床上浸水は「半壊」となります。
保険会社によりますと、水災補償の多くは、床上浸水か地盤面から45㌢を越える浸水などが生じた時には、契約の金額を上限に査定した損害額が支払われるとのことです。10年前に東京での豪雨で床上浸水した時には、被害が出た世帯に2300万円が支払われました。
保険金の算定方法には、「時価」の場合と、同等のものを新たに買うのに必要な「新価」の2種類があり、時価の方が保険金が少なくなるケースがあります。ですので、保険条件の確認が大事となります。保険料の目安として、都内で木造一戸建てで建物に2千万円、家財に500万円の保険をかけた場合、水災補償を付けた保険料は年間約3万8千円となり、水災補償がない場合より、1万2千円ほど高くなります。
 親等から相続財産がある場合、気になるのが相続税です。特に不動産の相続は税額を大きく左右するので、仕組みを知っておくべきと思います。土地の相続税額は、土地の課税評価額により決まります。これは、毎年7月に国税庁が発表する「路線価」が基本になります。路線価は国税庁のホームページで公開されているので、これで大まかな評価額は知ることができます。
親等から相続財産がある場合、気になるのが相続税です。特に不動産の相続は税額を大きく左右するので、仕組みを知っておくべきと思います。土地の相続税額は、土地の課税評価額により決まります。これは、毎年7月に国税庁が発表する「路線価」が基本になります。路線価は国税庁のホームページで公開されているので、これで大まかな評価額は知ることができます。
但し、左の図に示したような土地の場合には、評価額が減額されます。具体的にどのくらい減額されるかを知りたい場合には、不動産に詳しい税理士に相談するのが良いと思います。
また、相続時に、土地の評価額が最大8割減額される場合もあります。これは、100坪までの宅地が対象で、適用を受けることが出来るのは、次の相続人です。➀配偶者 ➁被相続人と同居している親族 ➂被相続人と別居だが3年以内に持ち家に住んでいない親族、などに限られます。ちなみに、相続税は現金で納めるのが原則となります。物納は現金分割払いでも全額納めるのが難しい場合に限られます。
 記事は7月17日の新聞からで、火災保険の値上げについてです。大手保険会社は、今年の10月から住宅の火災保険を2~4%引き上げる予定です。台風などの自然災害が増加していることによるもので、九州の一部や沖縄では、約3割の値上げとなります。表は台風被害が比較的多い福岡県と東京都の値上げの例です。福岡県の木造一戸建ての場合、現在の50,810円から264,730円(27%アップ)となります。台風被害などが比較的少ない東京都の場合は、現在の35,270円から35,510円(0.7%アップ)になります。台風被害等は増えているものの、火災件数は5年前と比べ2割減っています。従い、東京や北陸地方などに一部では、値下げになる例もあります。急激な値上げを緩和するため、10月から保険各社は割引プランも準備するとのことです。
記事は7月17日の新聞からで、火災保険の値上げについてです。大手保険会社は、今年の10月から住宅の火災保険を2~4%引き上げる予定です。台風などの自然災害が増加していることによるもので、九州の一部や沖縄では、約3割の値上げとなります。表は台風被害が比較的多い福岡県と東京都の値上げの例です。福岡県の木造一戸建ての場合、現在の50,810円から264,730円(27%アップ)となります。台風被害などが比較的少ない東京都の場合は、現在の35,270円から35,510円(0.7%アップ)になります。台風被害等は増えているものの、火災件数は5年前と比べ2割減っています。従い、東京や北陸地方などに一部では、値下げになる例もあります。急激な値上げを緩和するため、10月から保険各社は割引プランも準備するとのことです。
 親等から相続財産がある場合、気になるのが相続税です。特に不動産の相続は税額を大きく左右するので、仕組みを知っておくべきと思います。土地の相続税額は、土地の課税評価額により決まります。これは、毎年7月に国税庁が発表する「路線価」が基本になります。路線価は国税庁のホームページで公開されているので、これで大まかな評価額は知ることができます。
親等から相続財産がある場合、気になるのが相続税です。特に不動産の相続は税額を大きく左右するので、仕組みを知っておくべきと思います。土地の相続税額は、土地の課税評価額により決まります。これは、毎年7月に国税庁が発表する「路線価」が基本になります。路線価は国税庁のホームページで公開されているので、これで大まかな評価額は知ることができます。
但し、左の図に示したような土地の場合には、評価額が減額されます。具体的にどのくらい減額されるかを知りたい場合には、不動産に詳しい税理士に相談するのが良いと思います。
また、相続時に、土地の評価額が最大8割減額される場合もあります。これは、100坪までの宅地が対象で、適用を受けることが出来るのは、次の相続人です。➀配偶者 ➁被相続人と同居している親族 ➂被相続人と別居だが3年以内に持ち家に住んでいない親族、などに限られます。ちなみに、相続税は現金で納めるのが原則となります。物納は現金分割払いでも全額納めるのが難しい場合に限られます。
 東日本大震災を契機として地震保険への加入を検討する人が増えたと思います。私のマンションでも管理組合として地震保険に加入しました。地震保険に加入すると、地震によって生じた損害は補償してくれるようなイメージがありますが、実際はそうでもありません。左の表は最近の新聞からで、地震保険の概要についてです。
東日本大震災を契機として地震保険への加入を検討する人が増えたと思います。私のマンションでも管理組合として地震保険に加入しました。地震保険に加入すると、地震によって生じた損害は補償してくれるようなイメージがありますが、実際はそうでもありません。左の表は最近の新聞からで、地震保険の概要についてです。
地震保険は単独では入ることができず、火災保険とセットとなり、対象は住宅と家財です。地震保険として契約できる保険金額には上限があり、火災保険金額の30~50%の範囲で、かつ建物は5千万円、家財は1千万円までです。例えば、火災保険金額が2千万円なら、地震保険金額は600万~1千万円で契約出来ます。
保険金額は損害の程度によって支払われることになります。損害の程度は、「全損:地震保険金額の100%」、「半損:同50%]、「一部損:同5%」、この3区分に判定されます。判定は、住宅の損害の程度で、柱や梁、屋根など主要構造部の損傷状態で決められます。判定は損保会社の判定人が行うことになります。また、保険料は住宅がある都道府県と建物の構造で決まり、どの損保会社でも同額となります。但し、耐震等級や免震構造などによって10~50%の割引があります。
このように地震保険の損害の判定は専門性が高く一方的であるし、地震保険料は高いし、地震保険に入った方が良いのか?と悩みます。私は、建物の耐震性能、立地条件などにもよりますが、新築のマンションや一戸建ては、必ずしも地震保険に入る必要がないのでは、と思っています。
 住宅ローンの金利が低下してきて、現在では1%を割っています。それでは、ローンの借り換えと繰り上げ返済をした場合に、得になるのかどうかを考えてみます。左の表は新聞からで、住宅ローン残高1480万円、返済期間はあと10年、金利は年に1.4%で変動なし、と仮定します。このまま、ローンを返していくと、総返済額は1586万円となります。
住宅ローンの金利が低下してきて、現在では1%を割っています。それでは、ローンの借り換えと繰り上げ返済をした場合に、得になるのかどうかを考えてみます。左の表は新聞からで、住宅ローン残高1480万円、返済期間はあと10年、金利は年に1.4%で変動なし、と仮定します。このまま、ローンを返していくと、総返済額は1586万円となります。
➊のケースは、金利は10年固定、年0.9%のローンに借り換えをした例です。この場合、手数料や登記費用等の諸経費で約30万円かかります。この場合、総返済額は1578万円となります。
❷のケースは、借り換えをせず、毎年100万円ずつ繰り上げ返済をした例です。最大、6回の繰り上げが出来、この場合、総返済額は1546万円となります。
❸のケースは、借り換えも繰り上げ返済もした例です。この場合、総返済額は1552万円となります。
以上のようになります。現在では、住宅ローン金利が低いので、借り換えて返済額を少なくしようと思っても、ローンの残りの返済期間が10年以内では、あまり効果がないようです。
 遺産相続税について、現状の制度については前回の記事で書きました。今回は、2015年1月から変わる新制度について紹介します。新制度のポイントは二つです。一つ目は基礎控除の縮小、二つ目は税率の変更です。つまり、裕福な人への相続税が増えます。現状では亡くなった人の4%が相続税を納めてますが、新制度になると6%に増えると予想されています。
遺産相続税について、現状の制度については前回の記事で書きました。今回は、2015年1月から変わる新制度について紹介します。新制度のポイントは二つです。一つ目は基礎控除の縮小、二つ目は税率の変更です。つまり、裕福な人への相続税が増えます。現状では亡くなった人の4%が相続税を納めてますが、新制度になると6%に増えると予想されています。
左の表は現在の制度と2015年から施行される新制度との比較したものです。モデルとしているのは、4人家族で、夫が亡くなったケースです。夫には妻と子供二人の相続人がいます。夫には、自宅と預貯金で6080万円の財産がありました。現行の制度では、基礎控除が8000万円なので相続税はありません。
新制度になった場合、基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」になりますので、このケースの場合には、4800万円となります。財産から基礎控除を差し引いた1280万円が課税対象になります。法定相続の場合、妻が1/2、子供がそれぞれ1/4ずつになりますので、妻は640万円、子供は320万円に対して、相続税を払うことになります。このケースでは、妻は640万円×0.1=64万円、子供は320万円×0.1=32万円の相続税となります。
但し、新制度では、「小規模住宅の特例」という制度が改正されます。この制度は、亡くなった人の配偶者等が自宅を相続した場合、土地の評価額が80%減額されるものです。改正される点は、今までは住宅の土地の広さが240㎡だったのですが、新制度では、330㎡と広くなることです。
 左の表は遺産を相続した場合の税金について具体的に説明したものです。ある男性が、自宅や貯金などの財産1億2500万円を残して亡くなりました。葬儀費用は500万円で、妻が支払いました。亡くなった男性には妻と長男と長女がいました。法定相続人はこの3人となります。
左の表は遺産を相続した場合の税金について具体的に説明したものです。ある男性が、自宅や貯金などの財産1億2500万円を残して亡くなりました。葬儀費用は500万円で、妻が支払いました。亡くなった男性には妻と長男と長女がいました。法定相続人はこの3人となります。
まず、基礎控除額の算定です。控除額は「5千万円+1千万円×相続人の数」ですので、この場合、8千万円となります。この額よりも正味の遺産額が多ければ、その分が課税の対象になります。正味の遺産額とは、相続する遺産から、非課税税分や控除される財産を引いたものです。この例では、葬儀費用(500万円)が控除の対象となり、正味の遺産額は1億2千万円となります。正味の遺産から基礎控除を引いた差額の4千万円が課税対象となります。
法定相続の割合は、妻が1/2、2人の子供がそれぞれ1/4ずつです。課税対象額の4千万円をこの比率で分けると、妻が2千万円、子供はそれぞれ1千万となります。次に、この額をもとに、計算上の税額を出します。妻は税率は15%で控除50万円で税額は250万円、子供は税率が10%で控除0円で、それぞれ100万円となります。この税額の合計金額である450万円に対し、相続割合で税金も負担するので、妻は225万円、子供はそれぞれ112.5万円となります。
但し、特例があり、代表的なのが配偶者税額控除です。配偶者が実際に相続する遺産の額が、法定相続分の範囲内か、1億6千万円以下であれば、相続税はかかりません。ですので、一般的な相続の場合には配偶者が払う税金はないと言えます。現状では、亡くなった人の4%が相続税を納めています。このケースでも、妻が受け取るのは1億6千万円以下ですから、計算した225万円は納税する必要はありません。但し、納税しなくても、税務署への申告は必要となります。また、生命保険の死亡保険金を受け取る場合、保険金のうち「法廷相続人の数×500万円」は非課税扱いとなり、正味の遺産額を計算するときに差し引くことが出来ます。
 2年ほど前に、マンションの内覧会でお世話になった千葉県印西市に住むSさんからメールを頂きました。
2年ほど前に、マンションの内覧会でお世話になった千葉県印西市に住むSさんからメールを頂きました。
「ご無沙汰しております。今年から黒柴を飼いはじめました。フローリングが大変滑るため、DIYでワックスを購入して、塗布してみましたが、効果がありませんでした。そこで、コルクマットやタイルカーペットを考えましたが、コルクマットは引っ掻いてボロボロになりそうだし、タイルカーペットはダニが心配です。今のところ、クッションフロアがいいのでは、と思っております。ペットの足腰に負担がかからないで、滑りにくい床材がありましたら、お教え下さい。それから、千葉県印西市周辺でこのような床を施工できるお勧めの業者がいましたら、こちらも教えて下さい」というものでした。
ペットをお飼いになっていて、このような床材は良いよ、というお勧めがありましたら、お手数ですが、この記事に書き込んで頂ければ誠にありがたいです。よろしくお願い致します。写真は本文とは関係ありません。
 写真は戸建の敷地の境界点を示したものです。敷地の境界を明確にするため、一般的には、敷地の4方の隅に境界プレートが設置されます。境界プレートとは、上の写真では、上面が赤く塗ってあり、真ん中に矢印が入っています。矢印の先が境界点となります。(白い↑で指したところです)
写真は戸建の敷地の境界点を示したものです。敷地の境界を明確にするため、一般的には、敷地の4方の隅に境界プレートが設置されます。境界プレートとは、上の写真では、上面が赤く塗ってあり、真ん中に矢印が入っています。矢印の先が境界点となります。(白い↑で指したところです)この点が境界ですから、境界点の左側、右側、そして手前と3筆に区分けされます。ここでブロック塀は右側の敷地に入っていますので、右側の人の所有となります。ブロック塀が境界線上に立っていれば、所有権は半分ずつとなります。そして、手前の側溝は、通常、市の所有となります。所有するということは管理の責任も出てきます。
今回大きな地震が来ました。地盤の液状化などで、いろいろなところで土砂も噴出しています。これらの片付けは大変です。片付けや補修の範囲ですが、基本的には、所有権を持っているところが、その範囲内で、片付け、補修もすることになると思います。相当量の土砂で、範囲が不明確なところは、市などに聞いてみるのが良いと思います。(10.10)
 写真は、引渡し後2年半経った注文住宅の内部です。この家の構造部分は鉄骨造となっています。先日の大地震で、壁や天井のクロスが数十箇所裂け、部分的に石膏ボードもめくれ上がってきてしまっています。家の中がこのような状態になってしまった時には、どうすれば良いのでしょうか?
写真は、引渡し後2年半経った注文住宅の内部です。この家の構造部分は鉄骨造となっています。先日の大地震で、壁や天井のクロスが数十箇所裂け、部分的に石膏ボードもめくれ上がってきてしまっています。家の中がこのような状態になってしまった時には、どうすれば良いのでしょうか?
まず、法律的な点を確認してみます。新築住宅の売主の瑕疵担保責任については、民法だけでなく、平成12年4月1日以降の建物については、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)が適用されることになっています。この品確法には、売主の瑕疵担保として、①構造耐力上主要な部分 ②雨水の浸入を防止する部分について、引渡し後10年間、責任を負うことを定めています。①については、基礎、柱、壁、梁などで、②については、屋根、外壁などです。
②の雨水の浸入については、雨水の漏れ、滲みなどの瑕疵ですの分かりやすいです。でも、①の構造的な瑕疵については分かりにくいものもあります。柱や梁が曲がったり、キレツが入ったりしたら、これは瑕疵とわかります。でも、写真のように、クロスや石膏ボードの破損の場合には、どうなの?となってしまいます。
私の考えは、このような場合には、周り近所の家とのバランスと思います。周りの家の半分以上がこのような状態になっていたら、地震によるもの、周りの家のほとんどがなんともないのに、僅かの家だけが、このようになってしまったら、構造的な問題があるのでは、というものです。最近の建物で、今回の地震により、このような状態になってしまった場合には、売主に問い合わせるのが良いでしょう。
 今回の大震災は大きな被害を与えています。我々は不屈の精神の持ち主である日本人ですから、困難に立ち向かい、更に強い日本を築いて行きましょう。私は、マンションや戸建の内覧会に立ち会う仕事をさせて頂いてます。例年、3月末には引渡しというケースが多いです。3月31日に引渡しだけども、今回の地震で建物は大丈夫だろうか?引渡しをどうしたら良いのだろうか?このような不安を多くの方が抱いていると思います。
今回の大震災は大きな被害を与えています。我々は不屈の精神の持ち主である日本人ですから、困難に立ち向かい、更に強い日本を築いて行きましょう。私は、マンションや戸建の内覧会に立ち会う仕事をさせて頂いてます。例年、3月末には引渡しというケースが多いです。3月31日に引渡しだけども、今回の地震で建物は大丈夫だろうか?引渡しをどうしたら良いのだろうか?このような不安を多くの方が抱いていると思います。民法では、契約後で引渡し前に、土地・建物は、地震や火災などの不可抗力で消滅しても、買主は代金を支払う義務があると定めています。つまり、契約後の危険負担は買主となるわけです。しかし、この考え方は不公平である、という見地から、絶対にそうしなければならない強行規定ではなく、別途、当事者同士が、これとは異なる特約を定めることが認められています。
そして、この特約の内容は、引渡し前に、地震などの不可抗力によって不動産が、一部もしくは全部に損害を被った場合には、売主がその危険を負担する、とするのが一般的です。つまり、不動産は契約と実際の引渡しの間に相当の期間があるので、その間の危険に備えて、売主がその危険性を負う特約をつける必要性があると考えられているわけです。
一般的な特約の内容は、不可抗力によって、建物に契約履行できないような損害が生じても、買主は、売主の負担で補修しての引渡しを選択しても良いですし、契約解除を選んでも良いということになります。一般的に不動産の売買契約書には、特約として、所有権が買主に移転した時に代金を支払う義務(危険負担)が移転する旨を明記しているのです。今回の地震で、不安がある人は、再度、家を見てみることと、売買契約書の中の特約を確認してみることをお奨めします。