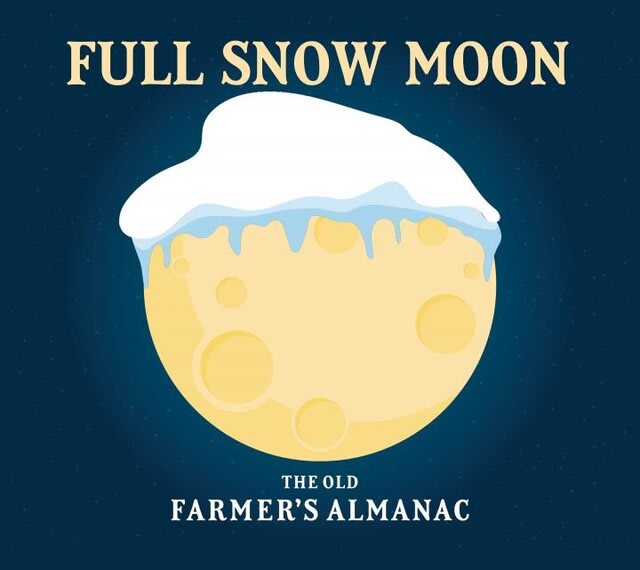
私の好きなThe Old Farmer's Almanac(老農夫の生活暦)の1988年号に、ロバート・X.・ペリーという人が寄稿した記事「満月と陣痛:出産民間伝承」という興味深い話を読んだ。この伝承は、私自身も5回出産して看護師や医師から聞いていたし、また先年ここのカトリック病院産科の看護師長を努めて引退した友人のグレイスからも聞いていた。「明日の晩は満月だから、忙しくなるわ」や「一昨日の満月の夜は、次から次へと産科では子供が生まれて大変だったわ」などと話していたのだった。それではまずはペリー氏の話から始めよう。
月の一月(29.5日)の間、月の形は毎日異なる。満ちていく月の見かけの形は、欠けていく月と一致して、完全な円として表示される。一致する2つの形状は、約2週間離れて空に現れ、それは「ムーンメイト(月仲間)」と呼ばれることもある。
第1四半期と第3四半期は仲間で、満月と新月も同様に仲間である。ムーンメイトは、形が相反することに加えて、人間に貴重な教訓を提供している。たとえば、ムーンメイトは、潮汐で証明されているように、地球上で同じ引力を生み出す。
潮汐表の作成中にペリー氏がわかったことだが、月の年齢と赤ちゃんの誕生との非常に興味深い関係があるように見えた。
そしてペリー氏は、3人の子供達と9人の孫の誕生日の月の状態を調べると、3人の子供達は満月から6日目に3人とも生まれ、孫のうち7人はそうした月のパターンに沿って生まれたとわかった。残りの二人の孫は、一人が早産、一人が帝王切開だった。そして隣人二人の家庭でもこのパターンは見られた。ペリー氏自身、もっと精密な検査やデータを集めなければならないと言う。それでもペリー氏は月と関係して誕生があるのを実際に経験しているわけだ。
ここでは満月の日ではなく、満月後二週間以内と言うことである。
さてこうした「伝承」について、反論するのは、ベイビーセンターというウェッブペイジでそのサイトのエデイターをするダリーアン・ホスリー・スチュワート女史である。彼女は「満月になると、より多くの赤ちゃんが生まれるというのは本当ですか?」という問いにこう答えている。
「いいえ、そうではありません。多くの産科看護師や母親は、満月の間に出産が急増すると誓うようにいいますが、科学的研究はその概念を反証しています。統計によると、満月の間に出生(または先天性欠損症)の増加はありません。
1950年代のニューヨーク市での研究では、満月後2週間で出生数が1%増加することが示されました。同じ研究で、満月の前後の数週間で1パーセントの増加が見られました。そして数年後、他の研究者が同じ地域での出生を調べ、満月の前に1パーセントの増加を発見しました。
それ以来、他の多くの研究がその関係性を探してきましたが、説得力のある結果は得られていません。過去10年間の少なくとも6件の研究では、出生と満月の間に関連性は見られませんでした。
2001年に発表された最大の研究では、天文学者で物理学者のダニエル・ケイトンが、国立衛生統計センターからの20年間のデータ(約7000万人の米国の出生)を調べました。彼は満月と出産との間に相関関係を見つけられませんでした。 (ほぼ同時に、フランスの研究者はヨーロッパでの1,450万人の出生を調べましたが、そのパターンさえ発見しませんでした。)
これらの発見は、満月の間に一気に出産することを確信している人々の心を変える可能性は低いですが、偶然をあてにしている場合は、満月に出産することを期待しないことです。ただし、それが予定日でない限り、偶然性はそれほど大きくありません。 (American College of Obstetricians and Gynecologistsアメリカ産婦人科医協会によると、出産予定日に生まれる赤ちゃんは約5%にすぎません。)
何百もの研究が「トランシルバニア効果」(月の満ち欠けと他の現象ー自殺、危機センターへの電話、災害、暴力的な行動、気分の変化などとの関連)も探しており、そこにも相関関係は見られませんでした。」
さて私は、夫と私、五人の子供達の誕生時の月について調べてみると、満月の前日に生まれた子供は一人、新月に向けて欠けていく状態に生まれた子供は一人で、満月の二日後、満ちていく月の日に生まれた子供は二人で、満月後15日目と8日目である。一人の子供は新月の日に生まれている。夫は満ちていく13日前に生まれ、私は欠けていく月の間に生まれ、満月9日目であった。こうしてみると、私たちの誕生は満月の2週間前後生まれのようである。9人の孫に至っては、数が多くて端折ることにして。
日本でもこのような言い伝えがあるのだろうか?
ちなみに27日は2月の満月夜である。アメリカ原住民、植民地のヨーロッパ人らによって呼ばれる名前は、雪の月である。これは例年大雪となることの多い2月だからである。実際には、この満月にはたくさんの原住民により呼び名がある。
今月の月の名前は、歴史的に動物と関係がある。 クリー族は伝統的にこれを白頭鷲の月または鷲の月と呼んでいた。 オジブウェ・ベアムーンとトリンギット・ブラックベアムーンは、クマの子が生まれた時期を指す。 ダコタ族はこれをアライグマの月とも呼び、特定のアルゴンキン族はそれをグラウンドホッグの月と呼び、ハイダ族は雁の月と名付けた。
今月の月の名前のもう1つのテーマは、希少性で、 骨の月と空腹の月という名前をつけたチェロキー族はこの時期食べ物を手に入れるのが困難であったという事実の証拠を示している。
こうした何の役にも立ちそうにないほとんど「駄」のつくような知恵を増やしてもどうにもならないが、だから私はThe Old Farmer’s Almnacが大好きで、勿論今年号もすでに買ってあるのだ。
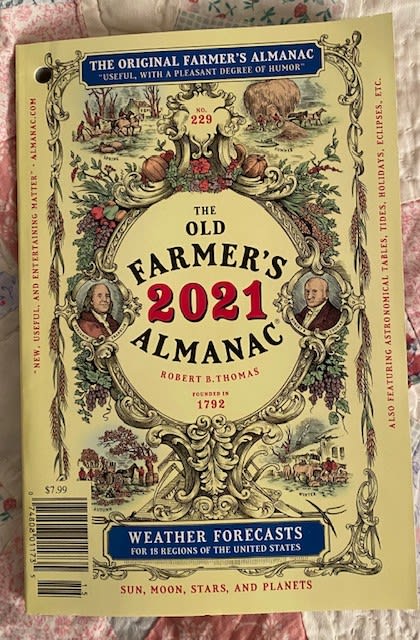
ほらね!

萩原朔太郎の「月に吠える」はどの月だったのだろうか。死や哀しみの詰まった詩集は、なんだかこの2月の雪月のような気がする。それでなければ1月の「狼の満月」かもしれない。とても3月の「ミミズの満月」には思えない。あるいは欠けていく痩せ細っていく月だったのだろうか。




















ありがとうございます💕
私が切迫早産で入院した時に助産婦さんが
この話をしていました。満月は出産や切迫が多いと。
以前買っていた猫のブリーダーさんは
潮の満ち引きのことを言っていました。
満ち潮の時に大体産気づくのでそれまでに仕事を終わらして家に帰ると。
生き物と自然の関わりって面白いですね。
お月さんと出産との関係、面白いですね。
話しはまったく違うのですが、私の場合は、魚釣りをしているとき、潮の干満にはかなり気を遣うようにしています。
で、自分なりですが、大潮(満月)から中潮、中潮から大潮といった具合に、潮の流れの変化が起こったときによく釣れると分析してます。
この場合、魚の食い気があがる理由として思うのが、ただお腹が減ったから…。産卵を控え食い気が上がったから…。
なにわともあれ、地上の生物たちにとってのお月さんからの恩恵、実に有難いことです(*´з`)
ですよね、やっぱり関係ありますよね。実際に産科医や産科看護師や助産婦さんなどの体験を聞いているとそう思います。
頑張り屋のマンマ様、どうぞお体にお気をつけてくださいね。
自然界では満月は多くの現象に関与していますね。毎年ある満月の夜にサンゴが幼生を一斉に海中に放つこととか、クリスマス島のアカガニが毎年雨季の前に海へと移動行進し、下弦の月の夜明けに放卵し、新月時に抱卵するなど、海洋生物は月の満ち欠けに密接して活動することをよく聞きます。人間だって自然界の一部ですから、そうした影響はあって当たり前のような気がします。ゆぅすけ様は、釣りを通してのご経験からのご意見ですから、やはりその通りだと思います。
ゆぅすけ様のブログはいつも的確で、明瞭で、楽しみにしております。