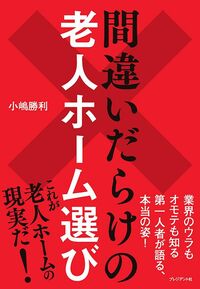下記の記事をハルメクWeb様のホームページからお借りして紹介します。(コピー)です。
「50代からの女性のための人生相談」は、専門家がハルメク読者のお悩みに答えるQ&A連載です。今回は55歳女性の「母親に優しくできない」というお悩みに、仏教の教えをわかりやすく説いて「穏やかな心」へ導く住職・名取芳彦さんが回答します。
 50代からの女性のための人生相談・16
50代からの女性のための人生相談・16
目次
- 55歳女性の「母親に優しくできない」というお悩み
- 名取芳彦さんの回答:普通に感謝して接すれば、それでいい
- 一緒に過ごした時間・空間、共通の経験を再確認しよう
- 子を持って知る親の恩…母と娘の共通項を作る大切な作業
- 慈悲の「慈」は相手に楽を与え、「悲」は苦しみを除くこと
55歳女性の「母親に優しくできない」というお悩み
私は一人っ子で、15歳で父が他界してから母と二人で暮らしていました。28歳で結婚してからは主人の両親と同居していますが、最近実母に認知症の症状が見えてきました。
母との仲は悪いと言うわけじゃないのですが、私は母に対して好きという感情が昔からあまりないのです。母は、ああしなさい、こうしなさいが多く、苦痛に感じていましたが、それに反発することもなく私は大人になりました。

義父母と同居するようになってこんな押し付けのない、自尊心を傷つけない親もいるのかと思うと、こういう育て方をしてもらいたかったなと、いまだに思ってしまいます。
お金の苦労は、まったくなく育ててもらいました。89歳で一人で今までがんばってきた母に、感謝と尊敬の気持ちはもちろんありますが、優しくできるときと、嫌味を言いたくなるときがあり、優しくできなかったときは自己嫌悪に陥ります。
これから先、これの繰り返しなのかと思うと、自分を責めながら生きていかなきゃならないのでしょうか? できれば、今、まだ母が元気でいるうちに優しく接して生きていきたいです。
私には2人の子どもがいますが、義母を見習い、自尊心を大事に育てています。今後のために、アドバイスをいただけたら助かります。よろしくお願いします。
(55歳女性・ホカロンさん)
名取芳彦さんの回答:普通に感謝して接すれば、それでいい
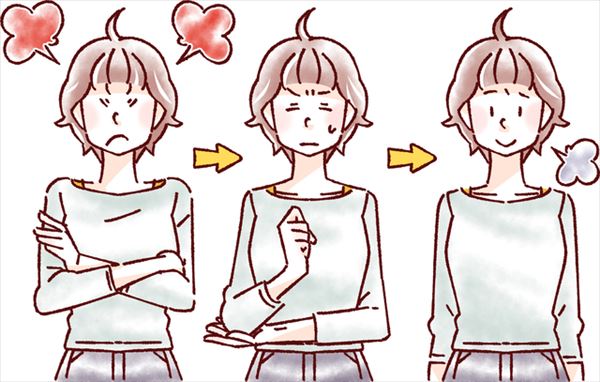
実のお母さんを無理に大好きにならなくてもいいでしょうし、優しくできないときの自分をそれほど責めなくてもいいと思います。普通に感謝して接すれば、それでいいですよ。
そこで、お母さんに感謝しているあなたが、普通に接するための心構えと優しさについてお伝えします。
自分のことを、母に優しくできないダメな娘だと思うことがあるようですが、「私は、まだまだだ」と思うのは、とても良いことです。お母さんに優しく接するため(結果的に心穏やかに生きるため)の「はじめの一歩」です。ダメな自分に気付くから直していけるのですから。
それは、学校のテストと同じ。テストの目的は、良い点数を取ることでなく、できないところを浮き彫りにすることです。できたところはそれ以上勉強しなくてよいことがわかり、できないところがハッキリするので、あとはそこを勉強すればいいのです。
あなたの場合も「お母さんに優しくできないことある」とハッキリしたのですから、そこをクリアすれば、100点満点の娘になれます。
一緒に過ごした時間・空間、共通の経験を再確認しよう

優しさは、仏教で言えば慈悲です。慈悲は「相手との共通項に気付くこと(持つこと)」が発生源だと私は考えています。
知らない者同士が「その日の天気」を口にするのは、共通の話題によって心の距離が縮まるのを、意識しなくてもわかっているのです。
場所が話題になって「私も行ったことがある」と話が盛り上がるのは、共通項に気付いて、優しさの蕾(つぼみ)が膨らむからでしょう。
私は「これ、おいしいよ」と家内にすすめられれば、共通項を作るために(優しさを発生させるために)「へぇ!どれどれ」と言って食べます。一緒に食事をするのも、大切な共通項作りだと思います。穀物(禾)を口にしながら、共に過ごす時間が「和」を生み出します。
すでに、あなたとお母さんには、数えきれないほどの共通項があるはずです。これまでの人生で、一緒に過ごした時間・空間、共通の経験を再確認することで、優しく接することができるようになります。
直接会えなくても大丈夫。電話で話すだけでも「話題」と「時間の共有」という共通項が生まれます。
子を持って知る親の恩…母と娘の共通項を作る大切な作業

子どもの頃に口うるさかったお母さんのことがまだ気になっているようですが、お母さんが口うるさかったのには、それなりの理由があったでしょう。
自分も親になった今だからこそ、その理由を考えてあげてみてください。それこそが、口うるさかった当時のお母さんの気持ちを共有して、あなたとお母さんに共通項を作る作業になるからです。
「確かに、お母さんは私のことをわかってくれようとしなかった。でも、夫に先立たれて、思春期真っただ中の一人娘の私をどう育てればいいのか悩んでいたお母さんの気持ちを、私もわかろうとしなかった」と、互いに“相手の気持ちをわかろうとしなかった”という共通項に気付けるかもしれません。
慈悲の「慈」は相手に楽を与え、「悲」は苦しみを除くこと

さて、仏教で説く慈悲の「慈」は相手に楽を与えること、「悲」は相手の苦しみを除くことです。
あなたがしてきた子育ては、おいしいご飯を作ったり旅行に連れて行ったりして子どもたちに楽を与え、病気になれば医者に連れて行って薬を飲ませ、子どものつらい気持ちに寄り添う・苦しみを除くなど、慈悲の実践そのものだったでしょう。
実は、お母さんへの接し方も、子育てと同じなのです。お母さんにとって何が楽なのかを考えて、それを提供し、どんなことで苦しんでいるのかを推し量って、それを取り除いてあげればいいと思います。
何で楽を与えられるかわからないなら、お母さんの誕生日やあなたの誕生日に「生んでくれてありがとう」とごちそうするのもいいでしょう。
認知症の症状が見えてきたお母さんにとっては、おっしゃることを受け入れて(同意しなくてもいいのです)、否定の言葉を返さずに接するだけでも、楽を与え、苦を除くことになります。
子どもは親を越えることで成長すると言われます。子どもの頃にお母さんから自尊心を傷付けられたあなたは、義理の両親と出会うことで、我が子の自尊心を大切にする人になりました。
その点で、あなたはお母さんを越えたのです。お母さんより、ひと回り人間的に大きくなったのですから、大きな心で接してあげてみてはいかがでしょうか。
回答者プロフィール:名取芳彦さん

なとり・ほうげん 1958(昭和33)年、東京都生まれ。元結不動・密蔵院住職。真言宗豊山派布教研究所研究員。豊山流大師講(ご詠歌)詠匠。写仏、ご詠歌、法話・読経、講演などを通し幅広い布教活動を行う。