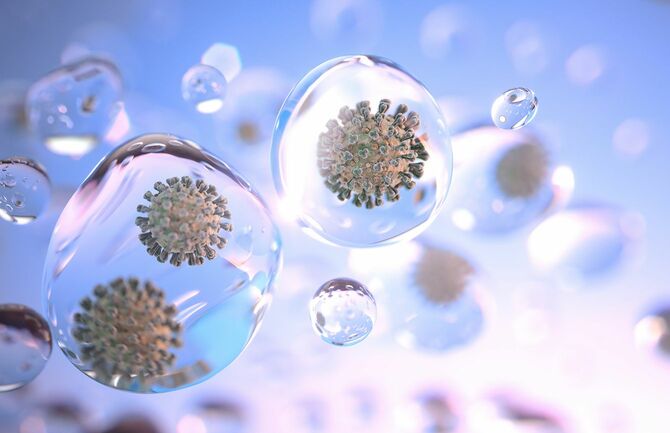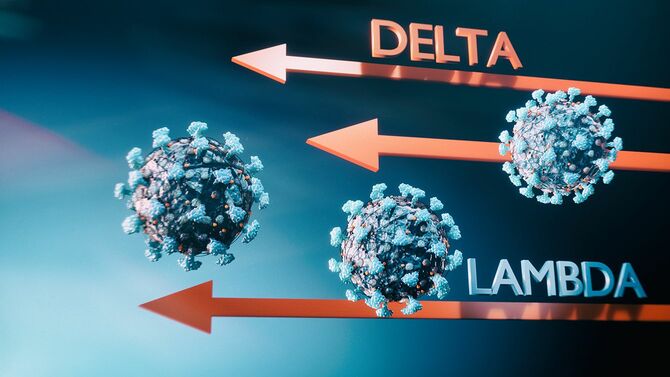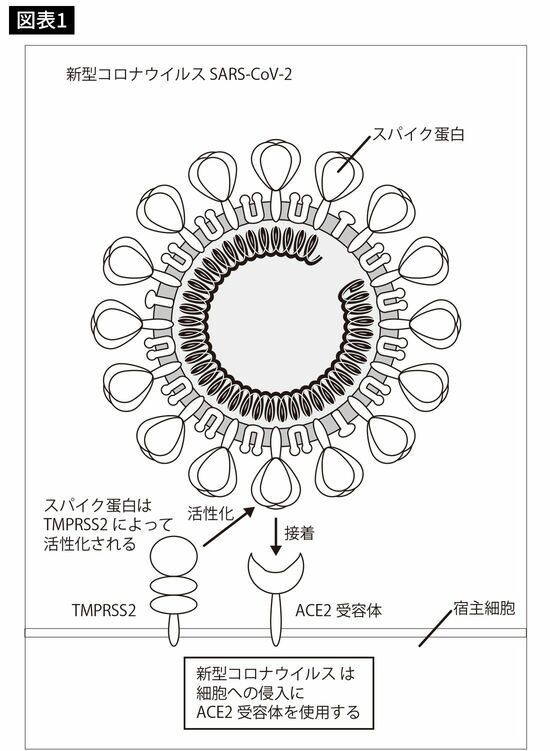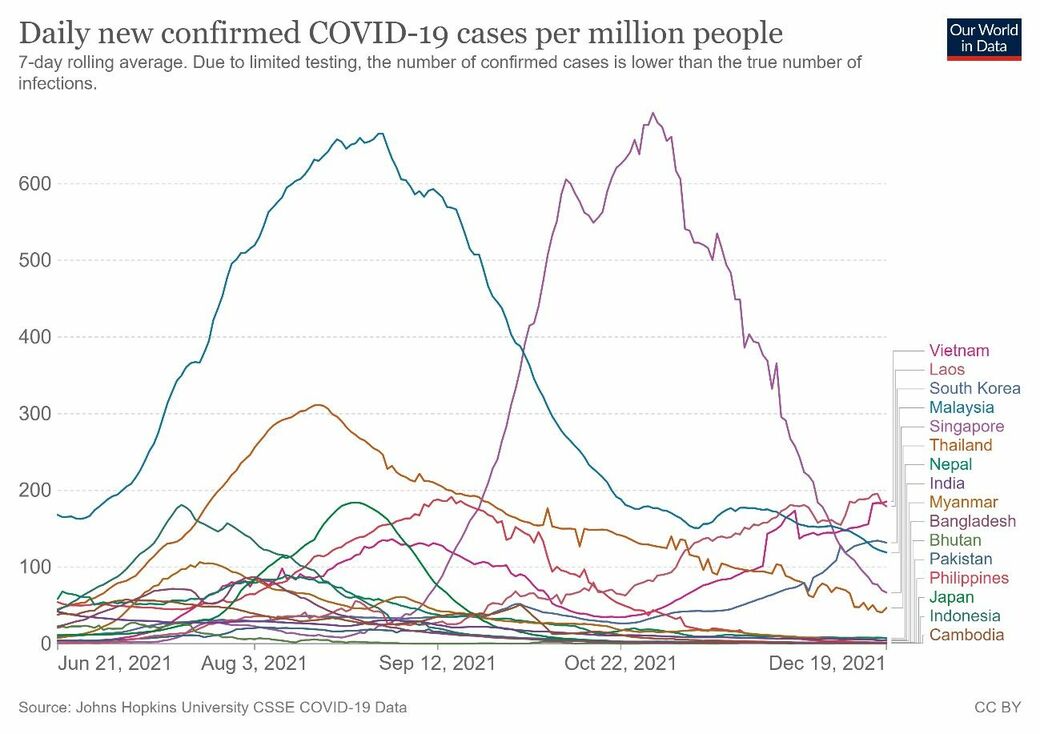下記の記事は東洋経済様のホームページからお借りして紹介します。(コピー)です。
医師や看護師たちが「自分の人生を変えたひとりの患者」について語ったインタビューをまとめたオランダの日刊紙『デ・フォルクスラント』のコラム「ある特別な患者」。
書籍化されオランダのベストセラーとなるとともに、アメリカをはじめ世界中で続々と翻訳出版されている。「コロナで死に瀕した女医を見守った看護師の回顧」(12月3日配信)、「嘘を通した母に殺された少女が残した悲しい教訓」(12月10日配信)に続いて、日本でも刊行された本書『ある特別な患者』の中から安楽死に関するコラムをお届けする。
人生の最盛期に迎えた悲しい宣告
●母親/パウラ・フルーネンダイク(看護師) 彼女は、活発で魅力的な20代後半の女性だった。夜遊びが好きで、流行に敏感で、休暇になると旅行に出かけて……まさに人生の最盛期にいた。
しかし、そうした日々はとつぜん終わりを迎える。ある日、彼女は末期の子宮頸がんだと宣告された。もはや治す手立てはなく、痛みを多少やわらげる以上のことはできなかった。
私の働く病院に入院していた彼女は、ある夜、私に向かってこんなことを言ってきた。
「ねえ、パウラ。こんなのもう耐えられない」
彼女の腹部と両足は薬の影響で腫れ上がり、表情には苦痛と憔悴の色がはっきりと見てとれた。
彼女はこう続けた。「人生でいちばんすてきな時期のはずなのに、こうして弱っていくことしかできないなんて」
私は夜間のシフトに入ることが多い。昼間に比べ、夜は患者の本音を聞くことが増える。見舞い客が家に帰り、医師が病室を出ていき、静寂と暗闇が訪れると、患者は内省的になるものなのだ。
本人からの安楽死の希望
ある夜、女性は私に「安楽死させてほしい」と言ってきた。その日は真剣にはとりあわなかったのだが、翌日の夜も同じことを言われたので、私は彼女の主治医にそのことを伝えた。
でもその医師は、安楽死について彼女に説明したあと、まだその判断を下すつもりはないと言った。痛みを緩和する方法はまだ残っているし、あと数カ月は容体も安定しているはずだ、と。
そう伝えると、彼女は憤慨した。
正直、彼女の気持ちもわからなくはなかった。私もかつては「患者は誰しも安楽死を遂げる権利をもつ」と考えていたからだ。
たとえ患者がまだ若かったとしても、例外にはならないと思っていた。看護師になって間もない20代前半のころ、私は医師とともに自殺幇助を行ったことがある。患者は末期症状に苦しむ若い女性だった。あのとき、同僚は誰ひとりとして手伝おうとはしてくれなかった。
その後も私は、安楽死はすべての患者に与えられた正当な権利だと思っていたし、医師が安楽死を拒んだときは少なからず腹を立てていた。
ところが最近になって、私の考えを大きく揺るがすできごとが起こった。
実はその2カ月前、私の息子が心臓発作を起こし、この病院で治療を受けていた。入院中、私は言葉にならないほどの不安にさいなまれながら、ベッドサイドに腰を下ろして息子を見守った。
あの若い女性のベッドサイドには、2カ月前の私と同じような顔をした母親の姿があった。私の息子とその母親の娘は同い年だった。
私の息子は無事に回復したが、その母親は娘にお別れを言わなければならない。
納得できない母親
とはいえ、その女性の娘が「人生を終わらせたい」と望む気持ちは、私にも理解できた。結局のところ、それは彼女の人生であり、決定権は彼女自身にあるのだ。
でも、そのことを彼女の母親に伝えたとき、私はいろいろな意味で居心地が悪くなった。
安楽死を決断するのが早すぎる、とその母親は声を荒らげた。そして、私の目を見据えてこう言ってきた。
「あなた……自分の子どもが同じ立場になったとして、同じことが言えるの?」
その言葉は、私の胸に深く突き刺さった。その母親の気持ちは痛いほどよくわかった。
最終的に、彼女の両親は娘を家に連れて帰った。そして数カ月後、彼女は亡くなった。
あれ以来、私の若い患者への接し方はすっかり変わったように思う。
それまでずっと、患者の家族が患者に苦しい闘いを続けさせようとするのを見るたびに、私はなんともいえない苛立ちを覚えていた。
でも、いまは違う。自分の息子が病院に運びこまれたことで、患者の両親が感じる恐怖と、わが子の安楽死を認めたくない気持ちがよくわかったのだ。
安楽死は、強制的に最後のお別れをもたらすものだ。
私はいま、末期症状に苦しむ若い患者のケアをするときは、彼らが少しでも長く快適な時間を過ごせるよう力を注いでいる。ときどき病院の外に連れ出したり、栄養のある食事をとらせたり、できるかぎり痛みをやわらげたりして、患者が「早く死にたい」などと考えないようにするのだ。
医師にもそれを拒む権利がある
わが子に別れを告げる覚悟ができていない親の気持ちも、若い患者の人生を終わらせたくないと思う医師の気持ちも、いまならよくわかる。
『ある特別な患者』(サンマーク出版)。
医師はみな、治療者(ヒーラー)としての信念をもっている。彼らにとって、自分の子どもと同じ、あるいはそれより若い患者に安楽死を施すことは、自らの信念に反する行為でもあるのだ。
安楽死は患者に与えられた正当な権利だが、患者の人生を終わらせたくないとき、医師にもそれを拒む権利があると私は思っている。
[安楽死に関する注記 ]
本エピソードの舞台であるオランダでは日本と違い、安楽死が合法である。オランダの医師たちは、患者から要望があると、その患者の人生を終わらせるための手伝いをする権限が与えられる。ただし、その行為には「デューディリジェンス[当然に実施すべき注意義務および努力]」がなければならない。
基準のひとつは、患者の苦痛の程度だ。患者が耐えがたい苦痛を感じていると判断され、かつ回復の見込みがないことが条件となる。判断にあたっては、主治医だけでなく、その患者の治療にかかわっていない第三者の医師による承認が必要になる。そうしたすべての基準を満たす場合のみ、医師は安楽死を施しても刑事責任を問われない。オランダでは、安楽死が死因全体に占める割合は4%で、その大半は末期がん患者のケースである。














 撮影=中西裕人
撮影=中西裕人