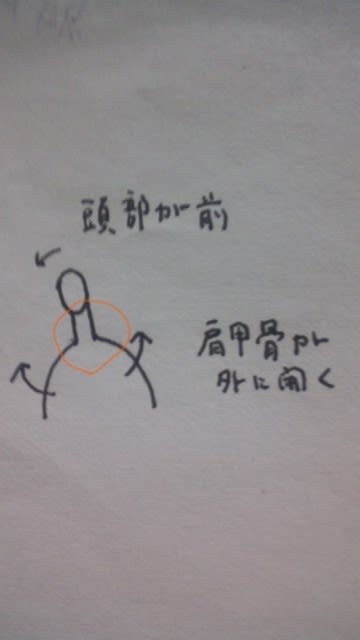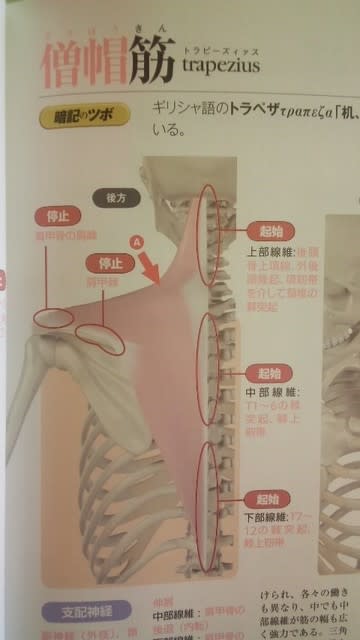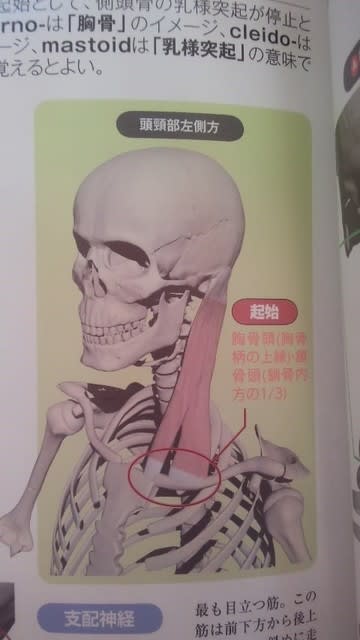昨日の日記のなかで触れられているようなある種の「気づき」を、
「マインドフルネス」あるいは「マインドフルな状態」と表現することがあります。
例えばピラティスワークを行う際は、身体の各部分を意識しながら、動きの
瞬間瞬間の変化に注意を傾けることが大切です。
呼吸に集中しながら「今ここ」の状態を意識すること。
過去のことに固執せず、未来のことを思い煩うことなく、純粋に連続する「今」を
捉え、身体が伝えてくる感覚に耳を傾けること。
…いつもクラスで行っているピラティスワークのなかにも、マインドフルネスの実践が
多く含まれていると感じます。
「マインドフルネス」の提唱者の一人であるティク・ナット・ハン氏は、その著作
のなかでこう述べています。
(『ブッダの幸せの瞑想』サンガ社より、以下長いですが引用いたします。)
マインドフルネスは、今この瞬間に気づき目覚めているというエネルギー
です。それは人生に深く触れることを、一瞬一瞬くりかえしていく実践です。
そのためにどこか特別な場所に行く必要はありません。自分の部屋の中でも、
どこかへ移動する途中でもできます。しかも、私たちが日常生活でいつも
しているのとほぼ同じことを通して行います。歩く、座る、働く、食べる、
話す…。ただし違うのは、それらをしっかりと自覚して行うことです。
ひとつの例をあげましょう。あなたは数人の仲間とともに美しい日の出を
眺めています。ほかの人たちは景色を楽しんでいるというのに、あなたの心は
苦しんでいます。頭がいろいろな計画や心配ごとでいっぱいで、過去や未来の
ことばかり考えているからです。日の出を見ようにも、あなたはそこにいません。
そして、すばらしい日の出の瞬間を楽しまずに見過ごしているのです。
ここで、少し違うアプローチをとってみましょう。とりとめのない思考が
起こったとき、意識を吸う息と吐く息に向けてみたらどうでしょうか。
まずは深く呼吸して、今この瞬間に自分を戻します。すると体と心はひとつ
になり、あなたは美しい景色を目のあたりにし、しっかりと眺め、楽しむ
ことができます。自分の呼吸に「帰る」ことで、あなたは日の出の美しさを
取り戻すのです。
(…中略)
人生の恵みを本当に味わいたいのなら、生活の様々な場面でマインドフルネス
の瞑想を活用することです。歯を磨きながら、朝食をつくりながら、車を運転
しながら、仕事に向かう途中で、ぜひ試してみてください。あなたの一歩、
一呼吸が、喜びと幸せを呼ぶチャンスになります。
人生は苦しみに満ちています。幸せをじゅうぶんにたくわえておかないと、
失意におそわれたときに打つ手がありません。どうぞリラックスして、やさしい
気持ちで実践してください。(…中略)マインドフルネスを生かせば自分の中に
喜びを保つことができ、人生の荒波にもっとうまく対処できるようになるでしょう。
自分の中に慈しみと自由と平和の土台をつくるのです。
私たちは、いっけんなんでもないような日常の生活とそれが与えてくれる恩恵を、
ほんとうに受け取って生きているのでしょうか?「いま・ここ」にしっかりと根を
下ろし、呼吸とともに、微笑みながらそれを迎え入れた時、目の前にはきっと
いままでとは違った景色が広がっていることに気づくでしょう。
筆者は1926年生まれの、ベトナム出身の禅僧です。
平和運動を実践しながら、マーティン・ルーサーキング氏の盟友となり、また
ベトナム反戦運動に積極的に参加した経歴があります。
91歳の現在もフランスを中心に活動されています。

「マインドフルネス」あるいは「マインドフルな状態」と表現することがあります。
例えばピラティスワークを行う際は、身体の各部分を意識しながら、動きの
瞬間瞬間の変化に注意を傾けることが大切です。
呼吸に集中しながら「今ここ」の状態を意識すること。
過去のことに固執せず、未来のことを思い煩うことなく、純粋に連続する「今」を
捉え、身体が伝えてくる感覚に耳を傾けること。
…いつもクラスで行っているピラティスワークのなかにも、マインドフルネスの実践が
多く含まれていると感じます。
「マインドフルネス」の提唱者の一人であるティク・ナット・ハン氏は、その著作
のなかでこう述べています。
(『ブッダの幸せの瞑想』サンガ社より、以下長いですが引用いたします。)
マインドフルネスは、今この瞬間に気づき目覚めているというエネルギー
です。それは人生に深く触れることを、一瞬一瞬くりかえしていく実践です。
そのためにどこか特別な場所に行く必要はありません。自分の部屋の中でも、
どこかへ移動する途中でもできます。しかも、私たちが日常生活でいつも
しているのとほぼ同じことを通して行います。歩く、座る、働く、食べる、
話す…。ただし違うのは、それらをしっかりと自覚して行うことです。
ひとつの例をあげましょう。あなたは数人の仲間とともに美しい日の出を
眺めています。ほかの人たちは景色を楽しんでいるというのに、あなたの心は
苦しんでいます。頭がいろいろな計画や心配ごとでいっぱいで、過去や未来の
ことばかり考えているからです。日の出を見ようにも、あなたはそこにいません。
そして、すばらしい日の出の瞬間を楽しまずに見過ごしているのです。
ここで、少し違うアプローチをとってみましょう。とりとめのない思考が
起こったとき、意識を吸う息と吐く息に向けてみたらどうでしょうか。
まずは深く呼吸して、今この瞬間に自分を戻します。すると体と心はひとつ
になり、あなたは美しい景色を目のあたりにし、しっかりと眺め、楽しむ
ことができます。自分の呼吸に「帰る」ことで、あなたは日の出の美しさを
取り戻すのです。
(…中略)
人生の恵みを本当に味わいたいのなら、生活の様々な場面でマインドフルネス
の瞑想を活用することです。歯を磨きながら、朝食をつくりながら、車を運転
しながら、仕事に向かう途中で、ぜひ試してみてください。あなたの一歩、
一呼吸が、喜びと幸せを呼ぶチャンスになります。
人生は苦しみに満ちています。幸せをじゅうぶんにたくわえておかないと、
失意におそわれたときに打つ手がありません。どうぞリラックスして、やさしい
気持ちで実践してください。(…中略)マインドフルネスを生かせば自分の中に
喜びを保つことができ、人生の荒波にもっとうまく対処できるようになるでしょう。
自分の中に慈しみと自由と平和の土台をつくるのです。
私たちは、いっけんなんでもないような日常の生活とそれが与えてくれる恩恵を、
ほんとうに受け取って生きているのでしょうか?「いま・ここ」にしっかりと根を
下ろし、呼吸とともに、微笑みながらそれを迎え入れた時、目の前にはきっと
いままでとは違った景色が広がっていることに気づくでしょう。
筆者は1926年生まれの、ベトナム出身の禅僧です。
平和運動を実践しながら、マーティン・ルーサーキング氏の盟友となり、また
ベトナム反戦運動に積極的に参加した経歴があります。
91歳の現在もフランスを中心に活動されています。