「国を愛する心」や「心のノート」に代表される新国家主義と「学校間競争」や「グローバル競争の勝ち組になるためのエリート教育」や「習熟度別学級編成」等に代表される新自由主義が絡み合いながら、権利としての教育が「教育基本法改正」という形で国家戦略としての教育に変質させられようとしています。数値としての学力向上政策や国庫負担外しや公務員制度改革も同様の流れなのでしょう。とりわけ国庫負担外しと教育基本法第3条の「教育の機会均等」の部分の文言変更は、学習権保障の面から考えると学校教育が階層格差や希望格差を再生産する場にさせられる恐れがあり重大です。
教職員は政策としての教育改革の流れの中で、一方は「個人の尊厳」を重んじ「平和的な国家及び社会」のもとで子どもたちの切なさや叫びに寄り添い成長発達を保障する立場、もう一方は競争と管理と差別で子どもたちを締め上げながら自らも疲弊して、やがては子どもたちを戦場に送るための国家の使いになる立場、教職員はどちらの立場に立つのかが試されているのではないでしょうか。
長いものには自ら巻かれていくのに、弱い者に対してはいじめるか徹底的に無視する雰囲気が広がっているような気がします。誰かに誉められたいわけでもないけれど、もう少し寛容さがあってもいいような気がします。
教職員は政策としての教育改革の流れの中で、一方は「個人の尊厳」を重んじ「平和的な国家及び社会」のもとで子どもたちの切なさや叫びに寄り添い成長発達を保障する立場、もう一方は競争と管理と差別で子どもたちを締め上げながら自らも疲弊して、やがては子どもたちを戦場に送るための国家の使いになる立場、教職員はどちらの立場に立つのかが試されているのではないでしょうか。
長いものには自ら巻かれていくのに、弱い者に対してはいじめるか徹底的に無視する雰囲気が広がっているような気がします。誰かに誉められたいわけでもないけれど、もう少し寛容さがあってもいいような気がします。















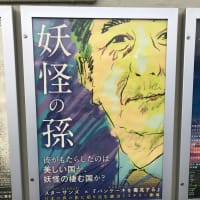










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます