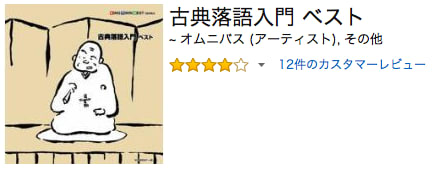落語に興味をもった、きっかけのひとつ。
落語に興味をもった、きっかけのひとつ。
夫が誰かから、「名作だよ」とすすめられて、いっしょに聴いた(you tubeだけど)
『浜野矩随』(名工 浜野矩随 メイコウ ハマノノリユキ)
江戸時代に実在した腰元彫りの名人の立志伝みたいな話です。
もともと講談話だったので、落語のテーマとしては、わりと真面目でシビアな内容。
ざっくりとしたストーリーをば、コチラ ↓
http://rakugo.ohmineya.com/?p=400
浜野矩安(のりやす)という腰元彫りの名人、女房とまだ二十五の息子矩随(のりゆき)を残して早世します。
後を継いだ矩随ですが、腕は並以下。取引してくれるところもありません。
先代に世話になったからと、矩随が拙い細工を持ってくるたびにこれを買ってくれるのが、芝神明前にあります袋物屋・若狭屋新兵衛。
今日も彫った馬を持って若狭屋を訪ねてきます。
若狭屋はこれを見て矩随に尋ねます。
「矩随さん、馬っていうのは足は何本だ?」
「四本です」
「この馬は三本しかないが?」
「すみません、明け方にふとウトウトとして足を一本落としてしまいました」 (テヘペロかいっ?)
(テヘペロかいっ?)
これを聞いて若狭屋は怒り出します。
お前の父親にずいぶん世話になったご恩返しのつもりであんたのものを引き取ってきたが、もう愛想がつきた!!!
五両の金を渡して、これは手切れ金だ。金輪際うちの敷居は跨いでくれるな、下手な職人は生きてる価値がないから死んでしまえ!!!と厳しい言葉を投げかけます
最初に聞いた噺家さんが誰だったか、覚えてないんですが・・・
面白いんで、何人かの噺家さんを聞き比べてみました(you tubeだけど)
時代順に。
古今亭志ん生
三遊亭円楽(五代目)
古今亭志ん朝
立川志の輔
うん、はじめて聞いたのは、志の輔さんか、しん朝さんだった気がする・・・
噺家さんによってアレンジが加わるので、筋が少し変わったり、『のりゆき』さんの人となりも、微妙に違ったりして、聞き比べると、面白いですね!
明治時代、初代の三遊亭円楽が、もともと講話の題材を落語にしたのがはじまり。けっこう好き嫌いが別れる作品らしいですが、名作だと思います私は
『のりゆき』さんに、激とばす若狭屋さんの人柄が、とてもいいですね。
お人好しが積もり積もって、つい、言わなくてもいいことを激ってしまう。
しん朝さんか、志の輔さんバージョンでは、激高しながらも、他に商売変えすることをすすめたりもして、やんわりと冷静に現代的な諭し方が取り入れられてますが、
聴いた中で一番古い時代の志ん生さん(といっても五代目)では、激高するのみ。
「職人が手抜き仕事をしれっと持ってきて、はい、お代ちょーだい♥たあ、どういった了見でいっっっ!!死んじまえっっ!!」てな具合。
怒られている内容といい、若狭屋さんの思わずキレてしまった感じといい、非常にリアルでシビアなシーンでございます。
さて、こうまで言われた『のりゆき』さんの行く末や如何に?(末は名工になるんだけど)
彼の心情は噺家さんによって、味付けは違うものの、
「悔しい」
言われたとおり、さらりと商売変えもできない『のりゆき』さん。
なぜ、できないか?意気地がないからか?
追いつめられて、答えががでない。「うん、死のう」と思う。ということは、
彫り師の仕事に少しでも、矜持のようなものをもっているようです。半端だけれども。
まあ、本当に死のうとしたかは別として、死にたい気持ちは本当でしょう。
母親に、手切れでもらった五両を渡し、これからお伊勢参りにいくから、道中なにがあるかしれませんから、と出て行こうとすると、
母親は母親のカンで、若狭屋でなにかあったか?と問いただします。
「そうか、わかった。お前がそう思うならば、死ぬも良い。ただその前にひとつだけ、お前の形見となるものを、この母に残して欲しい。」
と言って、五寸ほどの観世音菩薩像を、彫らせます。もちろん、ちょちょいっと彫れるもんじゃありませんから(細かそうだし)
『のりゆき』さんはじめて、寝食を忘れ、何日も、ただただ、母親のためだけに菩薩像を仕上げるのです。
そしてっっっ、
そのっっっ、
出来たるやっっっっ!!!



 うっそだろう!!
うっそだろう!!



 『のりゆき』さん、本気出してなかっただけやないの?
『のりゆき』さん、本気出してなかっただけやないの?
あとで、若狭屋さんが、名工『のりやす』(のりゆきの亡き父)の作と見間違うほどの像が仕上がるのです!!!
寝食わすれようが、どれだけ、必死になろうが、ヘタはヘタ、なはずです。
ただこの時の『のりゆき』さんの心情と、形見として彫った観世音菩薩像というテーマが、うまーーーくハマったのでしょう。キセキです。
人の目を覚まさせるような、はじめて、魂がはいった、というか。(きっとヘタには違いないが)
「彫る」ことの心を知った、とでもいうんでしょうか?
この『のりゆき』さんの変貌ぶり、物語なんだから、急に上手くなったっていいんだけれど、これだけ、興味深い人間ドラマ。
ただキセキがおこった、母親の念が天に届いた、とかじゃないと思うんです。タイミングが奇跡的ってだけで。
この観世音菩薩、いつもとどう違ったのでしょう? 
ただ、上手いでは、人は魅力を感じません。亡き父『のりやす』さんも、技巧だけでなく、人の心を打つ何かを以て、名工と言われた人なんでしょう。
きっと、今までの『のりゆき』さんは、何を以て完成とするか? 心無く、ただ生活のためには適当に、父の仕事への畏怖もあるしで、あと一歩、踏み込んだ仕事ができないでいた。
ただモチーフをなでさすりだけするような、ヌルイ彫り方してたんじゃないだろか? ウジウジと・・・だから、河童彫るはずが、途中で狸みたいになったり・・・つまらない失敗もする。
周りに対しての甘えと、父親の仕事に対して、「おれあ、あんなことできないよお」とだらしなく、自分で自分を縛り付けていた・・・
そんなところだったんじゃないでしょか?
こおいうだらしのなさ、なんかよくわかるんで・・・・つい、書きすぎちゃいました・・・
さて、この菩薩の一件がきっかけで、ようやっと世に認められる名工へ、その第一歩を踏み出すにいたった『浜野矩随』
これで、あれよあれよとスターダムにのっかった・・・かどうかは知りませんが、数々の名作をのこしていったそうです。
そして、結果的に彼をプロデュースしたことになる、『若狭屋』さんですが、
かなりの好人物 
母親に促され、くだんの菩薩像を手に、おずおずと若狭屋を訪ねてきた『のりゆき』さんを、
あっけらかんの平謝りで迎えます。
噺家さんによって、違いはありますが、だいたいこう。 ↓↓↓↓
「いっやーーーよく来ておくれだね、ささっ、今日は何持ってきたい?いっやーーーーこないだは悪かった!!!なに、あれだ、先日の酒がのこっとったんでねえええ、ちょいと虫の居所が悪くてさっ、悪かったねえええ、 あれから女房にどやされちまってねえええ、何かまちがいでもあったら、どうするってさ、今日あたりこっちから、様子見にいってみようかと思ってたとこさーーーー、いやいやいや、よっっっくきつくれたねええええ!!!」
当代一の謝り上手。でもとても温かくて、ほっとする場面でもあります。あれだけ追い込んどいて・・・・・ヒドイね。
私は円楽さんバージョンの謝り方が気に入ってます。
https://www.youtube.com/watch?v=FOUoDhtBcyA
ところで、『のりゆき』さんが初期に作った、河童だけど狸になってしまった「カッパダヌキ」
この話は多分、噺家さんの後付けっぽいですが、もし本当にあるなら、見てみたい気もします。
バカにされるってことは、ある意味人の心をとらえてる訳で、ユルキャラ?として、人気でそうじゃない?











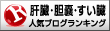




 とりあえず、これ、ポチリました ↓↓↓↓↓↓
とりあえず、これ、ポチリました ↓↓↓↓↓↓