
ナチュラリストクラブ2012年6月のコケの観察、
毎年1回は通盛先生にお願いしてコケの観察を指導していただいている
京都山科の毘沙門堂でコケを観察
10時に山科駅に集合、そこから歩いてまずは山科疎水に。山科疎水は1890年(明治23年)に琵琶湖から水を引くために造られました。疎水沿いの道には桜が植えられ、春の頃はとても見事だそうです。奥に見えるトンネルは琵琶湖から引いた水の出水口です。
ルーペで木にぴったりくっつくようにして観察。通りすがりの人から「何をしているんですか」と聞かれました。木に付くコケは種類が15~20種類と限られているそうです。ここで見たのはナガハシゴケ、フルノコゴケ、サヤゴケなど。コケの観察はペースがゆっくりで木一本に一時間かけることもあるそうですがこの木もたっぷり30分かけて観察。
予定より大幅に遅れて11時半ごろ毘沙門堂に到着。普通に歩けば20分の道のりです。右の写真の階段を上がれば仁王門があり、それをくぐると本堂ですが・
石の下の方にはコバノチョウチンゴケ、エダツヤゴケ、ウマスギゴケ、ホソバオキナゴケ、シノブゴケなどがありました。銅の縦樋(写真:右)の下にはホンモンジゴケがびっしり。ホンモンジゴケは銅イオンの集積している場所に育つそうです。堂内の見学を超特急で終え、何とか予定通り12時30分に観察会終了
<本日観察した生物>
ナガハシゴケ、フルノコゴケ、サヤゴケ、サワゴケ、ツノゴケ、ウメノキゴケ、コバノチョウチンゴケ、エダツヤゴケ、ウマスギゴケ、ホソバオキナゴケ、シノブゴケ、ホンモンジゴケ、ホソウリゴケ、オオツノゴケ、スギゴケ、コスギゴケなど














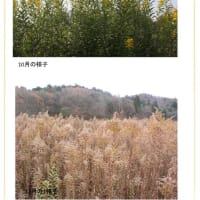
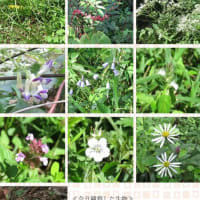
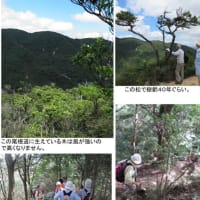
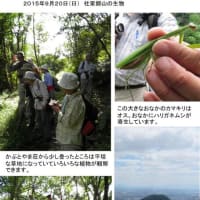



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます