
ジョウビタキ(ツグミ科)
全長は、約14cmで、地上では、両足をそろえて、はねるように歩きます。昆虫や木の実を食べます。翼には白斑があり、下面及び腰、尾は赤褐色で、全休に赤っぽさが目立ちます。雑木林や里山など、明るく開けた場所に生息します。冬鳥
ツグミ(ツグミ科)
全長は、約24cmで、上面は暗褐色、翼は栗色です。目の上に白色のすじがあります。河川敷や公園など明るいところを好みます。 4月末の渡去前には大きな声で美しい声でさえずりますが、それまでは目をつぐんだようにクイッ、クイッと鳴きます。冬鳥
キジ(キジ科)
全長は、オスは約80cm、メスは約60cmです。オスは、顔が赤く、首から腹 にかけて緑色で、鮮やかですが、メスは全休が茶色で、目立ちません。どちらも長い尾をもっています。山林や河川敷で見られます。オスはケーッ、ケーッと大きな声で鳴きます。挑太郎の話にも出てくる日本の国鳥です。留鳥
キジも鳴かずばうたれまい
昔、吹田の垂水(たるみ)あたりにまだ海の水が打ち寄せていた頃、島(洲)を結ぶ橋は大水などですぐに流されました。人々が神様にお願いしたところ、「人を埋めて橋柱として、橋を架ければよい。」とお告げがありました。朝廷に申し上げて人柱を立てることになりましたが、誰にするか困っていました。
通りかかったある人が、「袴(はかま)につぎがあたっている者を捕らえて人柱にすれば、成功します。」といいました。ところが、その人がはいている袴につぎがあたっていたので、人々は、すぐその人を捕らえて人柱にしました。橋は立派に完成して、もう流されませんでした。人々は心から感謝しました。
人柱になったその人は、垂水の長者でした。長者には美しい娘さんかおり、河内の禁野(きんや)というところにお嫁にいきましたが、誰とも口をききませんでした。
おこった夫は実家へ返すことになりました。垂水あたりまで来ると、葦(あし)の繁みからキジが大きな声で「ケッ、ケーッ」と鳴きました。弓矢でそのキジを射た夫に対して、お嫁さんは思わず目を開いて、
「ものいわじ父は長柄(ながら)の人柱 なかずば雉(きじ)もうたれざらまし」
と和歌を詠みました。夫は口をきかなかったわけを理解し、お嫁さんを許し河内へつれて帰って幸せに暮らしたそうです。
(日本の民話:大阪編より)














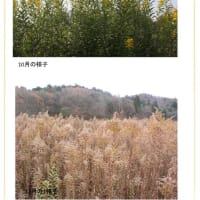
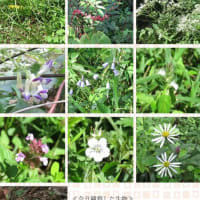
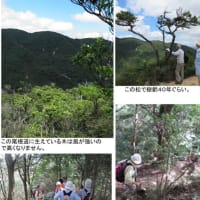
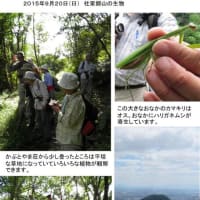



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます