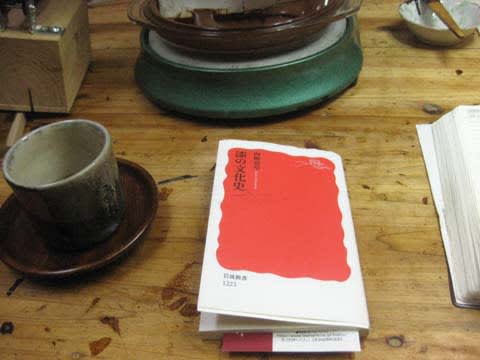年末に遊んでしまったので、今日が仕事納め。

やりかけの、インシュレーターに漆を塗り、綿布で拭き取りました。拭き取り2回目です。
コースターは、欅の導管を漆でしっかり埋めるため、研ぐ前に、2回目の刷毛摺りをしました。
これだけやって、後は工房の片付けです。

朝から降り続いていた雪は夜まで降り続き、昼には道路も車も真っ白になりました。こんなに降るのは久しぶりです。

真っ白な雪の中、炭山の里の大晦日は静かに暮れていきます。
1年間ご覧いただきまして、ありがとうございました。
では、皆様、良いお年をお迎えください。

やりかけの、インシュレーターに漆を塗り、綿布で拭き取りました。拭き取り2回目です。
コースターは、欅の導管を漆でしっかり埋めるため、研ぐ前に、2回目の刷毛摺りをしました。
これだけやって、後は工房の片付けです。

朝から降り続いていた雪は夜まで降り続き、昼には道路も車も真っ白になりました。こんなに降るのは久しぶりです。

真っ白な雪の中、炭山の里の大晦日は静かに暮れていきます。
1年間ご覧いただきまして、ありがとうございました。
では、皆様、良いお年をお迎えください。


















 写真をクリック。
写真をクリック。