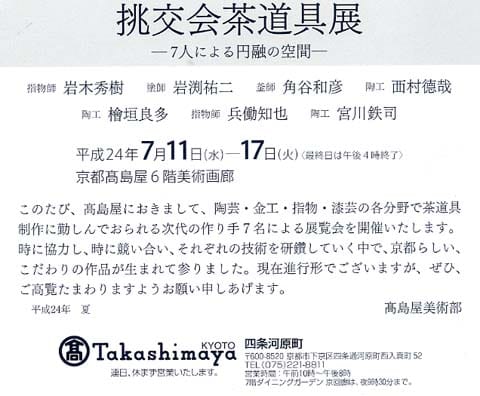桑の小抽斗の制作
このところ桑を使った制作が続いています。
(ともさんに教えていただいた「小青竜湯」のおかげで、鼻炎も治まっています。)
この桑も昔、信州の叔父が私のために集めてくれた貴重な桑です。
叔父の長女、つまり私の従妹の依頼で、叔母のための制作です。
久しぶりに工程の解説です。

機械で木取り、荒削り、雇核を入れて接ぎ合わせした板を鉋で削って平面を出し、厚みを揃えます。

直角を正確に出し、仕上がり寸法で寸法取り。

毛引き、直角定規、白柿を使って墨付け。

角鑿盤でほぞ穴をあけ、精密横切盤でほぞを切ります。
板の厚みが9mmなので、角鑿盤では深く掘れないため、鑿で底をさらえます。

天板と側板の接合は隠し蟻にしますので、鑿で刻みます。
側板にほぞを刻み、

天板にほぞ穴の墨を付け、

ほぞ穴を掘ります。

留木口台で留めを仕上げます。

仮組みして微調整。OKなようです。

裏板を嵌める小穴を突き、底板や棚板、背板を付けて仮組み。
この後、正面に出る木端をややアールを付けて仕上げ、台輪を嵌めるほぞと小穴を突き、
組立て。

接着剤、はみ出した接着剤を取る刷毛、ハタガネ、当て木など準備して組立てに掛かります。
今日は、気温が高い上に乾燥しているので手際よくしないと糊がすぐに乾いてしまいます。

引き出しの外側ができました。
追加
今日の京都の最高気温は、36.4℃。ここ炭山の最高気温は33℃。工房内は30℃そこそこ

娘の作ってくれた弁当を食べ、しばらくここで昼寝。
風が心地よく、汗もすっかり引きました。
このところ桑を使った制作が続いています。
(ともさんに教えていただいた「小青竜湯」のおかげで、鼻炎も治まっています。)
この桑も昔、信州の叔父が私のために集めてくれた貴重な桑です。
叔父の長女、つまり私の従妹の依頼で、叔母のための制作です。
久しぶりに工程の解説です。

機械で木取り、荒削り、雇核を入れて接ぎ合わせした板を鉋で削って平面を出し、厚みを揃えます。

直角を正確に出し、仕上がり寸法で寸法取り。

毛引き、直角定規、白柿を使って墨付け。

角鑿盤でほぞ穴をあけ、精密横切盤でほぞを切ります。
板の厚みが9mmなので、角鑿盤では深く掘れないため、鑿で底をさらえます。

天板と側板の接合は隠し蟻にしますので、鑿で刻みます。
側板にほぞを刻み、

天板にほぞ穴の墨を付け、

ほぞ穴を掘ります。

留木口台で留めを仕上げます。

仮組みして微調整。OKなようです。

裏板を嵌める小穴を突き、底板や棚板、背板を付けて仮組み。
この後、正面に出る木端をややアールを付けて仕上げ、台輪を嵌めるほぞと小穴を突き、
組立て。

接着剤、はみ出した接着剤を取る刷毛、ハタガネ、当て木など準備して組立てに掛かります。
今日は、気温が高い上に乾燥しているので手際よくしないと糊がすぐに乾いてしまいます。

引き出しの外側ができました。
追加
今日の京都の最高気温は、36.4℃。ここ炭山の最高気温は33℃。工房内は30℃そこそこ

娘の作ってくれた弁当を食べ、しばらくここで昼寝。
風が心地よく、汗もすっかり引きました。