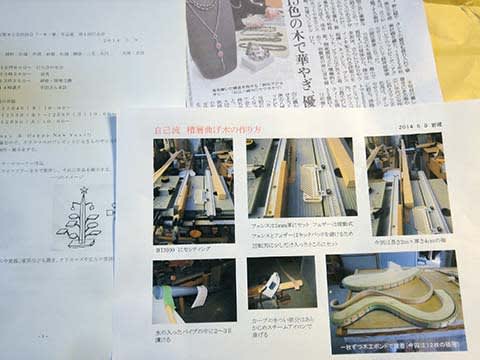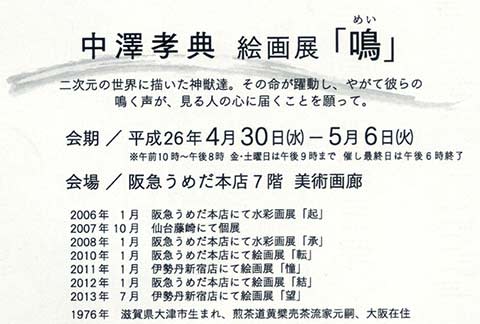伝統工芸近畿展の京都展はあと2日を残すだけになりました。
工房では次に向けての制作が始まっています。

乾燥のすんだ板を薄く挽き、3枚貼り合わせて合板を作ります。
プレス機がないので、あて盤を使ってクランプで圧縮。

できた合板の断面。
所定の厚さまで削り、板の狂いができては困る部分に使います。

別の木で試作しながら構想や制作工程を練ります。

こちらは来月開かれる、日本工芸会近畿支部小品展に出品する予定のアクセサリー類。
拭き漆が完了しました。

こんなものも・・・
小品展についてはこちらをご覧ください。

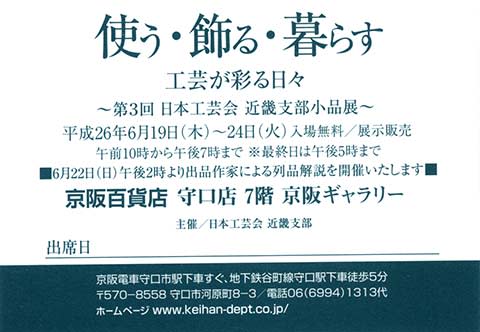
先月から制作していた茶托も完成し、箱に収めました。

明日納品させていただきます。
当初いただいた注文は20枚でしたが、追加をいただき26枚に。
予備も含め26枚制作していたのでちょうどぴったり!
私って予知能力があるのでしょうか??
工房では次に向けての制作が始まっています。

乾燥のすんだ板を薄く挽き、3枚貼り合わせて合板を作ります。
プレス機がないので、あて盤を使ってクランプで圧縮。

できた合板の断面。
所定の厚さまで削り、板の狂いができては困る部分に使います。

別の木で試作しながら構想や制作工程を練ります。

こちらは来月開かれる、日本工芸会近畿支部小品展に出品する予定のアクセサリー類。
拭き漆が完了しました。

こんなものも・・・
小品展についてはこちらをご覧ください。

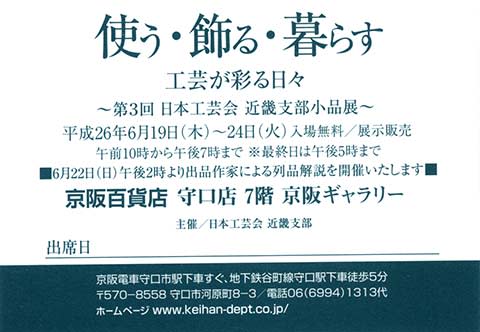
先月から制作していた茶托も完成し、箱に収めました。

明日納品させていただきます。
当初いただいた注文は20枚でしたが、追加をいただき26枚に。
予備も含め26枚制作していたのでちょうどぴったり!
私って予知能力があるのでしょうか??