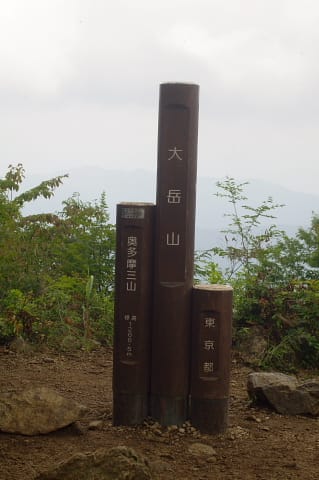今回の尾瀬沼探訪ではニッコウキスゲの大群落は見られなかったものの、夏から秋にかけて咲く花たちにたくさん出会うことが出来た。
まずは大江湿原の中のヤナギランの丘から。ヤナギランは此処尾瀬では他では見たことがないので、植えられたものなのだろうが、優しげな色合いで尾瀬沼にはよく似合っていると思う。



ヨツバヒヨドリ。残念ながらこの花の好きな渡りチョウのアサギマダラには出会えなかった。

八月中旬のこの時季、湿原の至る所で見られたのはオゼヌマギク


ユキザサやルイヨウボタンと言った 緑色の花には何故か慈しみたくなるような気品を感じる。この花の名はタカネアオヤギソウという。

沼山峠から湿原までの林地に多く見られたミヤマカラマツ、キンポウゲ科に属する。

ヤマオダマキは本当に上品な花だ。この花も尾瀬ではあまり見かけない。私が見かけたのは三平下の小屋の付近。以前見かけたのも温泉小屋付近だったので、全て植栽されたものなのだろうか。

野アザミの仲間、細かいことは分からない。

たくさんの虫を集めていたミヤマシシウド

オゼヌマギクと共に湿原では多く見られたイワショウブの花。オゼソウと同じユリ科の花。


蕾には赤い縁取りがあってそれもまたきれいだ。

数は少ないが存在感はたっぷりのサワギキョウ。


光線が変わるとこんなに色合いが変わってしまう

この時期赤系統の花は少ないので、よく目立っていたコオニユリ。オニユリのようにはムカゴは出来ない。良く似た花にクルマユリがあるのだが、尾瀬沼では見つけられなかった。



これも同じ赤系の花、ワレモコウ。こんなにきれいに咲くとは知らなかった、低地で見るものとは大違いだ。

トリカブトはまだ蕾の花がほとんどだった。大江湿原の休憩スポットの所で、この株だけが見事に咲いていた。これはオクトリカブトというらしい。


何といっても一番多いのはアキノキリンソウ、マルバタケブキ、オタカラコウ等の黄色系の花たち。



湿原を埋め尽くし星のように輝いていたキンコウカは、残念ながらもう終わりの時期を迎えていた。


山地の林道沿いの斜面に見られたチョウジギク。白く長い柄の先に6~9個の頭花をつける。至仏山で見かけるウサギギクと同じ仲間。

これも山地でよく見かけるオトギリソウ

色合いの鮮やかさでサワギキョウに目が行くのだが、同色の紫色のコバギボウシも結構たくさん咲いていた。


地味なアブラガヤもこうして撮ってみると、なかなか風情があるではないか。

丈高い湿原の草たちの中に隠れるように咲いていた、ミヤマモジズリ。

ミツガシワの花が一株だけ咲き残っていた。

お終いは湿原にも林道沿いでも見かけたモウセンゴケ、言わずと知れた食虫植物の仲間だ。

朝靄の水滴が長い線毛の先に着いていた。和名は毛氈苔。朱色の葉を毛氈に、小さいことを苔としたもののようだ。

これが花。

虫や鳥たちは近近の次回で。