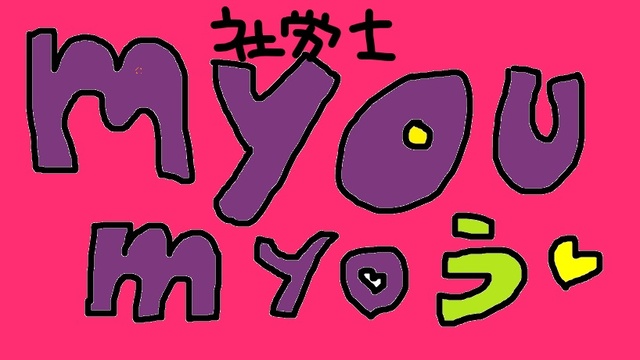公開中の映画「ANNIE/アニー」現代版は、里親宅で他の里子数人と暮らす10歳の女の子アニーが、ケータイ会社社長のニューヨーク市長選に利用される話となっています。
原作は新聞連載漫画の「小さな孤児アニー」で、1977年にブロードウェイミュージカルとして初めて上演されています。映画化も何度かされており、日本版も出ています。
世界大恐慌直後のニューヨーク、10年前に捨てられたアニーは孤児院で生活しています。いつか本当の両親が迎えに来ることを信じて、夢と希望を持っています。
クリスマス休暇を一緒に過ごす孤児を探していた大富豪オリバーは、アニーを自宅に招待します。両親をみつけたいというアニーのけなげな気持ちに心を打たれたオリバーは、彼女の本当の両親をみつけたものに報奨金を出すことにしました。お金目当てに大勢の人が、自分こそアニーの本当の両親だと名乗りをあげるのですが…最後はFBIの調査で、すでに死亡していることがわかります。
アニーはホワイトハウスを訪れ、閣僚たちを前に、希望を失わないことを説き、フランクリン・ルーズベルトはニューディール政策を発案する、というのが原作です。
時代によって細かい部分は変わっていますが、どんな状況にあっても希望を失わないというメッセージだけは変わりません。
現代版では、孤児院(施設)はでてきません。唯一、里親がアニーを追っ払う先としてグループホームが出てくるだけです。
アニーは里親宅を転々としています。アニーだけではなく、様々な事情で他の里子たちもなかなかひとつところに落ち着くことがないのが、現在のアメリカでの児童養護事情のようです。どの子も「家に帰りたい」「実の親と暮らしたい」と思っています。里親宅がいいなんて当然ながら誰も思っていません。
それでも、里親から「お前の面倒を見るのはもうやめた。おしゃべりな子は面倒見れないよ(市の福祉課の職員が来たとき、余計なことをしゃべっちゃったので)今度は人様のとこじゃないよ。施設さ!グループホームさ!」と言われたアニーのつらさ、がっかりさは子役の素晴らしい演技でよくわかりました。
日本では里親制度はまだまだ普及しておらず、要擁護の子どもたちは多くが施設で生活しています。厚労省は数年前に施設から家庭へと大きく方向転換し、施設入所は減ってきてはいますが、里親は簡単にその数を増やすことができないので、なかなか進みません。
今現在、里親家庭はやや緩和されたとはいえ、けっこう厳しい基準があります。基準を下げるべきかどうかという議論はおおいにやるべきですが、それだけでは行き詰まるのが目に見えています。
支援する人・される人というのが厳然と分かれている状態では、一部の裕福な人・社会的に安定した人しか里親になれません。しかし、不動の安定ということなどそもそもあり得ないのです。会社社長がホームレス状態になることだってあるのです。ホームレス状態の人がそこから抜け出すことも可能です。
映画ではキャメロン・ディアーズが最低の里親(落ちぶれた歌手で独身。4~5人の里子を預かってその収入で生活をしています)を演じています。里親になる人はあったかくて親切でやさしくていい人で…という幻想をいいかげん捨てないといけないと思います。
里親だって子どもたちの実の親と同様に、にっちもさっちもいかない状態に陥ることがあり、支援がないと立ち直れないこともあります。
児童養護だけではなく、障がい者支援、高齢者支援などにもいえることだと思います。
お金が目的で里親をしているのではなく、むしろ持ち出しのほうが多い。これ事実です。しかし、里親は無償ではない。これも事実。必要以上に美化したり、貶めたりすることはないです。
ようやく里親の更新用紙を提出した里親の一人として。
原作は新聞連載漫画の「小さな孤児アニー」で、1977年にブロードウェイミュージカルとして初めて上演されています。映画化も何度かされており、日本版も出ています。
世界大恐慌直後のニューヨーク、10年前に捨てられたアニーは孤児院で生活しています。いつか本当の両親が迎えに来ることを信じて、夢と希望を持っています。
クリスマス休暇を一緒に過ごす孤児を探していた大富豪オリバーは、アニーを自宅に招待します。両親をみつけたいというアニーのけなげな気持ちに心を打たれたオリバーは、彼女の本当の両親をみつけたものに報奨金を出すことにしました。お金目当てに大勢の人が、自分こそアニーの本当の両親だと名乗りをあげるのですが…最後はFBIの調査で、すでに死亡していることがわかります。
アニーはホワイトハウスを訪れ、閣僚たちを前に、希望を失わないことを説き、フランクリン・ルーズベルトはニューディール政策を発案する、というのが原作です。
時代によって細かい部分は変わっていますが、どんな状況にあっても希望を失わないというメッセージだけは変わりません。
現代版では、孤児院(施設)はでてきません。唯一、里親がアニーを追っ払う先としてグループホームが出てくるだけです。
アニーは里親宅を転々としています。アニーだけではなく、様々な事情で他の里子たちもなかなかひとつところに落ち着くことがないのが、現在のアメリカでの児童養護事情のようです。どの子も「家に帰りたい」「実の親と暮らしたい」と思っています。里親宅がいいなんて当然ながら誰も思っていません。
それでも、里親から「お前の面倒を見るのはもうやめた。おしゃべりな子は面倒見れないよ(市の福祉課の職員が来たとき、余計なことをしゃべっちゃったので)今度は人様のとこじゃないよ。施設さ!グループホームさ!」と言われたアニーのつらさ、がっかりさは子役の素晴らしい演技でよくわかりました。
日本では里親制度はまだまだ普及しておらず、要擁護の子どもたちは多くが施設で生活しています。厚労省は数年前に施設から家庭へと大きく方向転換し、施設入所は減ってきてはいますが、里親は簡単にその数を増やすことができないので、なかなか進みません。
今現在、里親家庭はやや緩和されたとはいえ、けっこう厳しい基準があります。基準を下げるべきかどうかという議論はおおいにやるべきですが、それだけでは行き詰まるのが目に見えています。
支援する人・される人というのが厳然と分かれている状態では、一部の裕福な人・社会的に安定した人しか里親になれません。しかし、不動の安定ということなどそもそもあり得ないのです。会社社長がホームレス状態になることだってあるのです。ホームレス状態の人がそこから抜け出すことも可能です。
映画ではキャメロン・ディアーズが最低の里親(落ちぶれた歌手で独身。4~5人の里子を預かってその収入で生活をしています)を演じています。里親になる人はあったかくて親切でやさしくていい人で…という幻想をいいかげん捨てないといけないと思います。
里親だって子どもたちの実の親と同様に、にっちもさっちもいかない状態に陥ることがあり、支援がないと立ち直れないこともあります。
児童養護だけではなく、障がい者支援、高齢者支援などにもいえることだと思います。
お金が目的で里親をしているのではなく、むしろ持ち出しのほうが多い。これ事実です。しかし、里親は無償ではない。これも事実。必要以上に美化したり、貶めたりすることはないです。
ようやく里親の更新用紙を提出した里親の一人として。