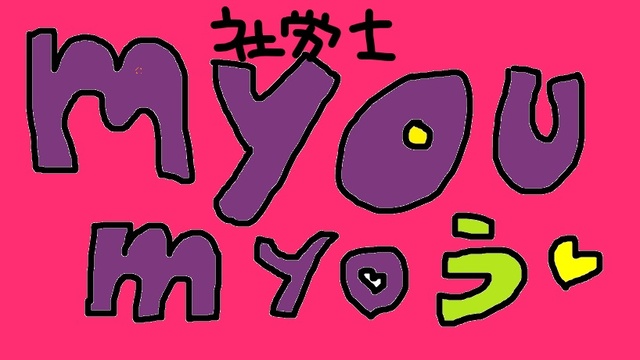ハローワークがブラック企業の求人を受け付けない。
大きな一歩だと思います。
1月の雇用対策基本問題部会の後、メディアでは大きく取り上げられていました。
しかし、働く人は期待をし過ぎず、自分にできることをしないといけません。
法政大学教授でブラック企業対策プロジェクトのメンバーである上西充子さんは、ハローワークに限定された取り組みであり、若者の多くが利用するインターネットの民間就職情報サイトへの掲載まで規制するものではなく、ハローワークの不受理期間も6か月程度なので、効果は極めて限定的であると指摘しています。
若者、特に新卒の若者はハローワークにはほとんど行かないので、こういう取り組みは民間就職情報サイトにも広げていかないと効果は得られないと思います。
企業側の情報提供については、離職者数の情報などは、企業が「重要な機密」に当たると主張しており、なかなか開示が進まないようです。
企業側が情報をきちんと提供すると同時に、求職する側には、その情報を正確に読み取り分析する能力が求められます。
会社四季報や就職四季報を読んでもさっぱり…という人がいるかもしれません。私もですが。
東洋経済オンライン編集長の田宮寛之さんの『転職したけりゃ「四季報」のココを読みなさい』には、企業を見分けるヒントが盛りだくさんです。
四季報と言えば株の投資をする人が読むものと思われていますが、求職者にも大いに役立つ本だと田宮さんは力説しています。
学生時代に労働に関する法律を学ぶのも重要です。なぜか重要視されていませんが。学校のカリキュラムに入れるには時間がかかりますが、自ら学ぶ意志さえあれば、今はその環境は十分そろっています。
そして、今のアルバイトの労働条件をぜひ確認してみてください。ちょっと提案なんかもしてみたらいいと思います。
疎まれてシフトに入れなくなる?
いいじゃないですか、他のバイトを探せば。
レッツトライ!
大きな一歩だと思います。
1月の雇用対策基本問題部会の後、メディアでは大きく取り上げられていました。
しかし、働く人は期待をし過ぎず、自分にできることをしないといけません。
法政大学教授でブラック企業対策プロジェクトのメンバーである上西充子さんは、ハローワークに限定された取り組みであり、若者の多くが利用するインターネットの民間就職情報サイトへの掲載まで規制するものではなく、ハローワークの不受理期間も6か月程度なので、効果は極めて限定的であると指摘しています。
若者、特に新卒の若者はハローワークにはほとんど行かないので、こういう取り組みは民間就職情報サイトにも広げていかないと効果は得られないと思います。
企業側の情報提供については、離職者数の情報などは、企業が「重要な機密」に当たると主張しており、なかなか開示が進まないようです。
企業側が情報をきちんと提供すると同時に、求職する側には、その情報を正確に読み取り分析する能力が求められます。
会社四季報や就職四季報を読んでもさっぱり…という人がいるかもしれません。私もですが。
東洋経済オンライン編集長の田宮寛之さんの『転職したけりゃ「四季報」のココを読みなさい』には、企業を見分けるヒントが盛りだくさんです。
四季報と言えば株の投資をする人が読むものと思われていますが、求職者にも大いに役立つ本だと田宮さんは力説しています。
学生時代に労働に関する法律を学ぶのも重要です。なぜか重要視されていませんが。学校のカリキュラムに入れるには時間がかかりますが、自ら学ぶ意志さえあれば、今はその環境は十分そろっています。
そして、今のアルバイトの労働条件をぜひ確認してみてください。ちょっと提案なんかもしてみたらいいと思います。
疎まれてシフトに入れなくなる?
いいじゃないですか、他のバイトを探せば。
レッツトライ!