樫田秀樹氏の『自爆営業~そのおそるべき実態と対策』(ポプラ新書)を書店でパラ読みし、即購入して読んでみた。
全国の郵便局にはびこる自爆営業の実態や他業種にも広がる自爆営業とその背景、自爆営業を拒否するにはどうしたらよいか、自爆営業は必要ないといった内容で大変興味深く、かつ心強い新書である。
私は以前から郵便配達の人のことが気になっていた。家にいることが多いので、書留の類や小包などの受け取りで配達員さんとよく顔を合わせる。配達のほとんどが非正規雇用でまかなわれ、その労働条件が非常に厳しいということは知っていた。なので、ある配達員さんからかもめ~るの購入をすすめられたときは、「非正規なのに大変だな」と気の毒に思った。注文用紙に名前が書いてあったので、きっとノルマとして決まった枚数を売らなければいけないのだろうと察した。局によって違いはあるのだろうが、この本を読んで、想像をはるかに超えたものであることがわかった。
程度の差はあるが、自社製品を「売上アップのために」つまり、「売り上げが少ないことの責任を問われないようにするために」、自腹を切って購入することを、働く人はわりとフツーに受け取っているようだ。本書でも、「そんなのよくある話」「自分もたまにやってる」といった言葉が紹介されている。
私は以前知人から「自社商品の買取りをしなくてはいけない。これって違法ではないのか。」との相談を受けた。自社商品が欲しい人は従業員割引で購入することができるのだが、知人はよく定価で購入し、売り上げに貢献していた。それでもいよいよ苦しくなり、購入量を増やさねばならなくなったのだ。詳しく話を聞くと、ノルマらしきものはあるが、明文化はされておらず、本社から直接購入を強制するような言葉はないとのことだった。だが売り上げは個人別に管理され、上司も同僚も(知人を含め全員非正規)定価での購入で売り上げを補っており、売り上げ減によるシフト減を恐れているということである。相談にのっていて、なにかズレている、おかしいという気がしてもどかしかった。なぜなら知人は、「売れない(売る能力がない)のなら、自分で責任をとるべし」「でもさすがに、ある程度の金額を超えるとキツイ」「売れないのに自分で購入しないのはおかしい」「でももしこれが違法だったらこわい」と言うのである。ちょっと違うんじゃないかと意見を言ってはみるが、溝は埋まらなかった、というか深くなるばかりだった。手持ちの札では、違法とは言い切れない。実態をもっと知る必要があると伝えると、知人は「違法ではないんですね!それならいいんです」とホッとした様子であった。
自社製品を自腹で購入することの他に、会社が負担すべき経費を自分が支払うことや、サービス残業なども自爆営業といえるのではないか。だが、これらのことを多くの人が「当然」と思っていれば、労働規制を強めたところで、絵に描いた餅となってしまう。労働法規の整備は当然なくてはならないが、労使ともにそれらを軽んじるなら、なくてもいいということである。働く人の多くは、規制などないほうが、自由でいいということなのか。私は自由という言葉そのものがインチキくさく、都合よく使われることが多いのでいけ好かないが。












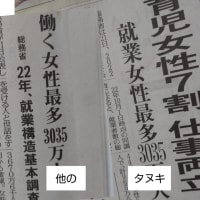
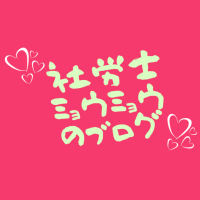
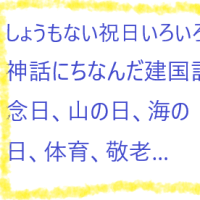




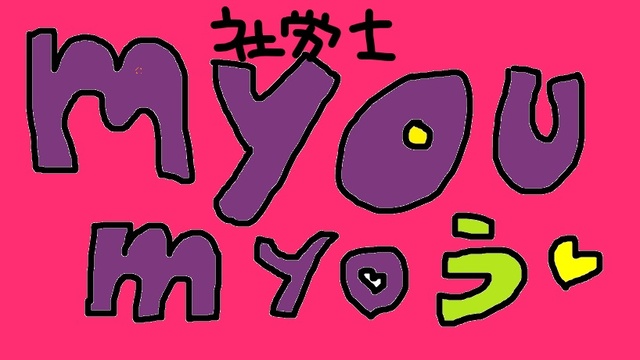

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます