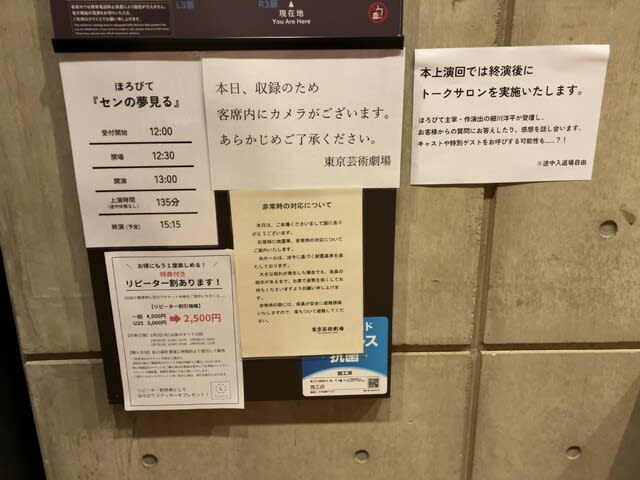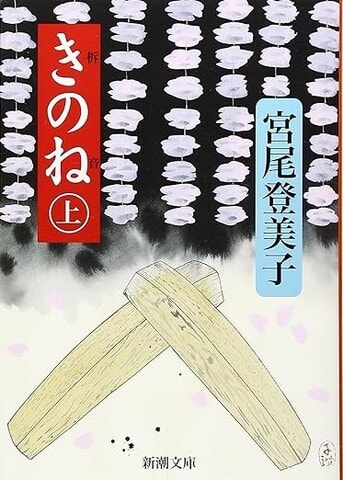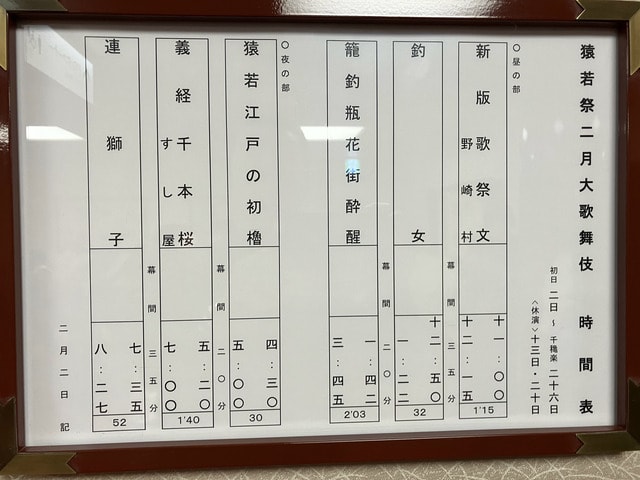東京文化会館小ホールで開催された佐伯周子第32回(ピアノ)リサイタルに行ってきた。3,000円、席は自由席。19時開演、20時50分終演。サブタイトルに「べーレンライター新シューベルト全集に拠るピアノソナタ全曲演奏会Vol.3」とある。
この「べーレンライター新シューベルト全集」についてちょっと調べてみると、ドイツの出版社であるべーレンライター社が出版したシューベルトの全楽譜集で、シューベルトの全作品を包括的に収録しており、未完の作品も含まれているものだ。1997年頃全巻が揃った。

佐伯周子は、宮崎市出身、洗足学園音楽大学大学院修了。これまでに、宮村京子、阪本幹子、林美奈子、矢野裕子、小林仁に師事。2016年11月シューマンのピアノ協奏曲をアンサンブル金沢と共演。2004年より「シューベルトピアノソロ曲完全全曲演奏会」を行い2019年に全26回完結。チェコ音楽コンクール2010年第1位。伊福部昭氏との縁をもとに現代曲の演奏、また近年では室内楽にも力を入れている。
今日の公演は、「シューベルトピアノソナタ完全全曲演奏会 全8回連続演奏会」を2028年シューベルト没後200年に向けて遂行中のうちの第3回目だ。
曲目
シューベルト:
ピアノソナタ 10番、嬰へ短調 D571+D570
ピアノソナタ 8番、イ長調 D664
ピアノソナタ 16番、イ短調 D845
当日配布されたプログラムに書かれた曲の解説では、
D664は技術的には易しく、可愛らしいソナタの作曲を要請されて作ったもの、第2楽章主題再現部が小さく変奏されている。D845は変奏曲とロンドで人気のあったシューベルトがその両方を楽曲に盛り込んだ作品。第1グランドピアノソナタと呼ばれる。この曲以降のソナタ・弦楽四重奏曲・交響曲の「時間的な大きさ」を確立した曲。
彼女の演奏を聴くのは初めてだし、曲目も初めてで、ぶっつけ本番で聴きに行った。ただシューベルトのピアノが好きだと言う理由のみで選んだ公演だったが、実際に聴いてみて良い曲だったし、彼女の演奏も素晴らしいと思った。

さて、この日の彼女の演奏会だが、東京文化会館の小ホールに集まった客は100人もいなかったかもしれない。東京に雪が降った翌日の交通の混乱を心配し、チケットを買ったけど来なかった人も少なくないかもしれないが、見た感じがら空きだった。これではあまりに寂しい。
本人はもとより、主催者、後援者としてパンフレットに載っている組織の人たちがもっと動員をかける必要があったのではないか。そういう努力が十分でなかったのではないか。SNSやいろんな手段で少なくとも半分くらい埋まるようにすべきだろう。こういったところも改善してほしい。
ネットで調べるとYouTubeには彼女のアカウントがあるがアップされている動画はわずかで訪問者も2桁しかない。Facebookもあるが投稿が少ない。Xなどをもっと有効に使うべきではないか。うまく使っているピアニストや音楽家は多いので参考にしてはどうか。練習が大変でそんなことやっている時間はないし知識もないよ、ということかもしれないが、まわりの詳しい人にサポートしてもらうとか、もっと努力しないといけないのではないか。
今夜の公演のプログラムを読むと、曲の解説などが書いているが、非常にわかりにくかった。もっと素人にもわかりやすい書き方が必要ではないか。特にピアノソナタ10の説明は素人には何を言っているのか全くわからなかったし、シューベルティアーデ推移というのが書いてあるが、なぜ唐突にこれが最初に紙幅を取って書いてあるのかよくわからない、その後の曲の解説も難しい。

一方、この夜の公演では途中、休憩時間が1回あり、その際、ホワイエで飲み物はワインなどすべて無料とのアナウンスがあった。これは粋な配慮というものだろう、関係者がこのくらいの知恵が働くなら、もっと他にも知恵を出して彼女をサポートしてほしい。
また、この日の公演では、3曲演奏した後、拍手に答えてアンコールを1曲弾いてくれたが、その前に来場の御礼とアンコールの曲の紹介を彼女自らの声で話したが、これは良いことだ。これについても、もう少し話す時間があっても良いのではないか、シューベルトに対する思いとか、何でも良いのだ、来ている人は彼女がどういう人なのか、話を聞いてその人柄や音楽に対する考え方の一端でも知りたい。そうしたことをやって少しでもファンを増やして欲しい。
今夜の終演後、彼女はホワイエに出てきて聴きに来てくれた友達などと談笑していたが、これも良いことだ。一般の人にもどんどん声をかけて欲しい。見たところずけずけと人前に出ていって話すようなタイプの女性ではないようだが、積極性も時に必要だ。自分をどんどんさらけ出して欲しい。きっとファンが増えると思う。
最近売れっ子の藤田真央の小説「指先から旅をする」を読んだら、彼がヨーロッパでリサイタルをした当初は座席が1割か2割くらいしか埋まらなかったと書いてあった。それにもめげずに彼は頑張った。私は多くの日本人音楽家を応援したい。もっと多く集客できて、チケットの値段ももっと高くても売れるようになって欲しい。今後も、日本人の公演を聴きに行って支援したい。彼女の来年の第4回の公演も絶対に観に行くので、いろいろ改善の上、是非頑張ってもらいたい。