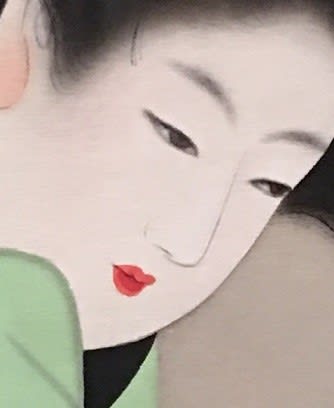東博の楽しみスポットのひとつ、屏風襖絵ルーム。この日の三作も圧巻だった。
呉春(1752(宝暦2年) ~1811(文化8年))「山水人物図襖」18世紀

襖に広がるすてきな時間。水辺で着物の前をはだけて、うちわでぱたぱた。暑い日に涼を得る。

文人たちの理想の境地。この襖を開けて入った者は、お茶を入れる下男ににこやかに迎えられ、納涼おじさんたちのお仲間いり。
「衣服の柔らかな質感描写、樹木や岩のボリュームある立体表現」は応挙の影響、とある。特に岩は応挙に重なる。呉春ははじめ与謝蕪村に学び、31歳で師蕪村を亡くす。生涯蕪村を敬愛しつつ、それから応挙との付き合いを深め、影響を受ける。
これは呉春晩年の作。人物の表情はしっかりと描きだしつつ文人画のゆるさも漂うのは、蕪村を思い起こしたりする。
3室の冒頭には、「室内を仕切ることにより場を作り出し、空間を演出する機能をもつ屏風や襖には、権力を象徴し、場を荘厳するなどの目的のために、絵が描かれたり、書が揮毫されたりしました。ここでは安土桃山時代から江戸時代の屏風を展示し、これら大画面の作品によって生み出される空間の効果を感じ取っていただきます。」と。
芸事や俳諧、食も楽しむ文化人であり、社交的な呉春のもとには、面白い面々が訪れたでしょう。だらりと飲んだり興を尽くしたり、そんな時間にこの襖はぴったり。江戸初期の権力の象徴のような機能の屏風や襖絵と違って、文化も成熟した感。
作者不詳の「紅白梅図」17世紀 東京・光林寺

細部びっしり埋める花の濃厚さ。大きな黒い月、水の流れ。
この屏風で生み出される空間は、なんとドラマティック。気持ちも煽られそう。外に行かなくてもここでデートできでしまうくらい、ロマンティックにも耐えうる。(でもお寺だったか...)。
勢いのある町絵師が描いたのかなと想像する。


中村芳中「許由巣父・蝦蟇鉄拐図屏風 」6曲1双 に、目が釘付け。
(これだけ写真不可だったので、2014年の千葉市美術館の芳中展のチラシから)

画像が小さいので、記憶をよすがに不完全に記録。
右隻は許由と巣父
中国故事の理想の高士、栄華を嫌う二人。帝から天下を譲ろうと聞いた許由は、耳が穢れたと川の水で耳を洗っている。
巣父は、そんな穢れたものを流した川の水を牛に飲ませることはできないと、牛をひいて引き返す。(どれだけ潔癖なん...)。
とにかく光琳に私淑した芳中、岩も草も牛もたらしこみがこれでもかと。特に牛は、顔の輪郭が判別しがたいくらいにたらしこみまくり。草のピンピンとした自由な感じも心地よい。楽しそうな芳中が目に浮かぶ。
そして人の顔がいいのです。ゆるふわの犬などかわいい芳中ですが、このおじさんたちはちょっとだけヒトクセあり。
岩場にしゃがんで指で耳の中まで洗う許由の顔は、意外と垂れ目で平常心な顔。
巣父は、あ、そういう水って俺イヤだからみたいに、しれっと引き返していく。たらしこみでほとんどまだらみたいになった黒牛まで、くるっと。その巣父と牛のシンクロぶりがなんともいい感じ。のど乾いているでしょうに、さすが飼い牛までしつけが行き届いている。その黒牛の眼は、達磨みたいに立派。
二人+一牛を見ていると、理想の高士というより、Going My Wayな感じ。気持ちがおおらかになる。
左隻は、蝦蟇鉄拐。
鉄拐仙人は、ふううと気を吐いている。気は画面の外へ広がっていく。
蝦蟇仙人は、肩に蝦蟇を乗せて、その蝦蟇がまた気を吐いている。こちらの気はくるりと一回転している。
この二人と蝦蟇の顔がまたいいのです。特に上を向いた蝦蟇の顔が、えらそうで。下の蝦蟇仙人のほうが、重いよどけよみたいにちょっと困り顔。
蝦蟇仙人は多くの絵師に描かれ、肩や頭の上に蝦蟇を背負っているのも多いけれど、だいたいは豪快に笑っている蝦蟇仙人。芳中の描く人は、高士も仙人も全然えらそうじゃない。平常心。
そして、たらしこみの竹の美しさ。見とれて動きがたい。
右隻も左隻も、線もとげとげしくなくゆるく、自由。描き込んだ絵も好きだけど、こんなふうに線の数が少ないのもいいもの。この屏風で演出された「場」は、ゆるくて肩の力も抜ける。
「空間の効果」ならば、大きく空いた余白は、その向こうにも広がりを生み出し、頭の中の空き容量も増やしてくれそう。
**
隣の部屋には、芦雪(1754~99)の蝦蟇仙人図 18世紀

これもまた、定型をぶち壊した蝦蟇仙人。画面いっぱいに、後ろ姿が妙にどっしり存在感。荒野をいく孤高の男と相棒、といった感じ。蘆雪の破天荒ぶり。
ガマは定型の三本足だけど、なぜ背負おって描こうとと思ったのかな。わからないけれど、つながった仙人の手とカエルの手には、二人の絆は感じる。後ろ足が一本のガマが肩に上るのをひっぱってあげているのかな。
もう時間が無くなってきたので、あとは急いで。
「夜着 紫緞子地鶴模様」 18世紀 インパクトあるかけ布団。鶴のびっくり目と、絞りの細密さと地の光沢が美しい。

梅樹据文三味線 石井直 1798 鉄刀木の胴に螺鈿の棹。

胴部は、金銀、象牙をちりばめた梅の花。こんな宝物のような三味線があるなんて。

琳派の経脈が並んでいました
尾形乾山「桜に春草図」、ほっこり

酒井抱一の弟子たち 花や枝の戯れが見えるようで、抱一のエッセンスを受け継いでいるよう
山田抱玉「紅白梅図屏風」

田中抱ニ「梅鴛鴦・春草図」 抱一の晩年の五年を学んだ


丸い背中の山に、松の木のコドモ、タンポポやすみれ、ワラビが遊んでいて、思わず目じりが下がる。
狩野探幽の大作もさらっと展示する東博。「周茂叔・林和靖図屏風」

前景に近い時代、古い時代は奥の方に。中国故事の有名人が散らばっている。
右隻に、北宋の故事
蘇東坡のロバかわいい。

林和靖は梅を眺め、お供の鶴もちゃんといる。雪がふんわり積もっている。

左隻に、東晋の王義之

元信を見た後なので、江戸に移って、探幽になるとずいぶん線が細くなったと実感。
浮世絵はいつも残り五分になってしまう。今度は浮世絵から先に観なくては。
北斎「信州諏訪湖 水氷渡り」 北斎では今日のベスト

その北斎に私淑した、ご近所さんの渓斎 英泉。最近、英泉のクールで妖艶な美人画にひかれるているので、風景も楽しみにしていた。
この日は木曽街道シリーズ
渓斎 英泉「木曽街道 野尻伊奈川駅遠景」

渓斎 英泉「木曽街道 馬籠駅より遠望の図」

美人画や春画のなめらかですべらかな感じと違って、風景は硬質な感じなのが意外。でも色が大人。
歌川広重「木曽街道 六十九次のうち三渡野」

↓のところが好きで。

最後に、通路わきに普通にあった黒電話。ぽっちゃりかわいい形。またね。