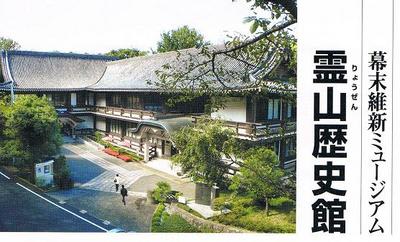● 金閣寺、正しくは鹿苑寺。御所北西の盆地の縁にあるので足利義満の夏の別荘でした。23年前の金箔貼替えで輝いています。この位置は修学旅行者や外人観光客などでごった返していて1秒ほどしか確保できなかったので近景を入れることは無理でした。

● 知恩院 (東山区林下)
この三門は南禅寺に引けをとらない雄大さです。寺院への拝観料はありません。
来年は法然上人800年大遠忌なのでその準備に入っています。
『 月影のいたらぬ里は なけれども
ながむる人の こころにぞすむ 』
注約:月の光は誰にでも注いでいるが、月を眺める人以外にはその美しさは解らない

日本三大梵鐘の一つ。どうやって坂の上の鐘楼まで運んで吊り下げたか不思議です。

本堂(御影堂)の庇の下に棟梁だった左甚五郎が魔よけのために置いて行ったという唐傘の頭が除いていました。また550メートルの廊下はうぐいす張りになっています。

● 京都 おはし工房 (左京区花園)
おはしの専門店です。箸は身長や体重に合わせて(手の大きさと力が異なるから)慎重に選ぶとは知りませんでした。硬い木ほど先端が細く出来るので小さなゴマ粒までつかめます。
ちなみに黒檀や紫檀で1万5千円でした。

● 大覚寺、正しくは 旧嵯峨御所大覚寺門跡 (右京区嵯峨)
嵯峨天皇の孫の親王(女性)が入ったので門跡、南北朝時代に南朝の御所になったのでその名があります。

古流、草月流に対して嵯峨御流の活け花の家元(?)です。

御所だけあって海に例えられた白妙の広い庭には舞楽用の舞壇もあります。

廊下の床板には釘の頭が見えません。板の裏側のミゾにL字金具を打ち込み、その端を釘で固定しています。古くなるとその釘と金具が緩むので歩くと音がするウグイス張りとなるそうです。知恩院の本堂北側縁側もそうでした。我が家の床も今は鴬張りになっています。

老夫婦を引率してその仲人をした家庭にお世話になった4日間でした。皆親しい間柄でしたがやはり疲れました。年なのでしょうか。

● 知恩院 (東山区林下)
この三門は南禅寺に引けをとらない雄大さです。寺院への拝観料はありません。
来年は法然上人800年大遠忌なのでその準備に入っています。
『 月影のいたらぬ里は なけれども
ながむる人の こころにぞすむ 』
注約:月の光は誰にでも注いでいるが、月を眺める人以外にはその美しさは解らない

日本三大梵鐘の一つ。どうやって坂の上の鐘楼まで運んで吊り下げたか不思議です。

本堂(御影堂)の庇の下に棟梁だった左甚五郎が魔よけのために置いて行ったという唐傘の頭が除いていました。また550メートルの廊下はうぐいす張りになっています。

● 京都 おはし工房 (左京区花園)
おはしの専門店です。箸は身長や体重に合わせて(手の大きさと力が異なるから)慎重に選ぶとは知りませんでした。硬い木ほど先端が細く出来るので小さなゴマ粒までつかめます。
ちなみに黒檀や紫檀で1万5千円でした。

● 大覚寺、正しくは 旧嵯峨御所大覚寺門跡 (右京区嵯峨)
嵯峨天皇の孫の親王(女性)が入ったので門跡、南北朝時代に南朝の御所になったのでその名があります。

古流、草月流に対して嵯峨御流の活け花の家元(?)です。

御所だけあって海に例えられた白妙の広い庭には舞楽用の舞壇もあります。

廊下の床板には釘の頭が見えません。板の裏側のミゾにL字金具を打ち込み、その端を釘で固定しています。古くなるとその釘と金具が緩むので歩くと音がするウグイス張りとなるそうです。知恩院の本堂北側縁側もそうでした。我が家の床も今は鴬張りになっています。

老夫婦を引率してその仲人をした家庭にお世話になった4日間でした。皆親しい間柄でしたがやはり疲れました。年なのでしょうか。