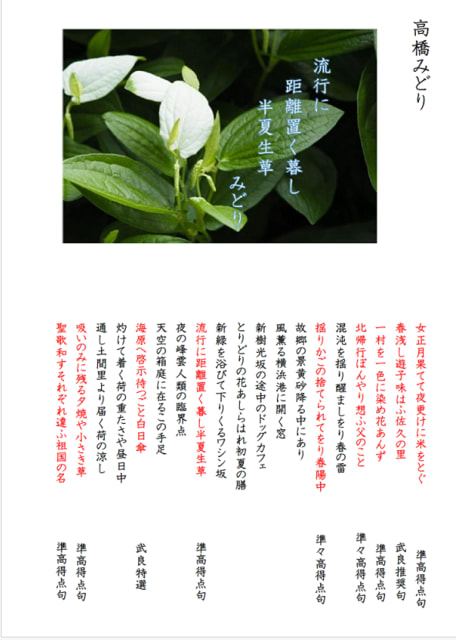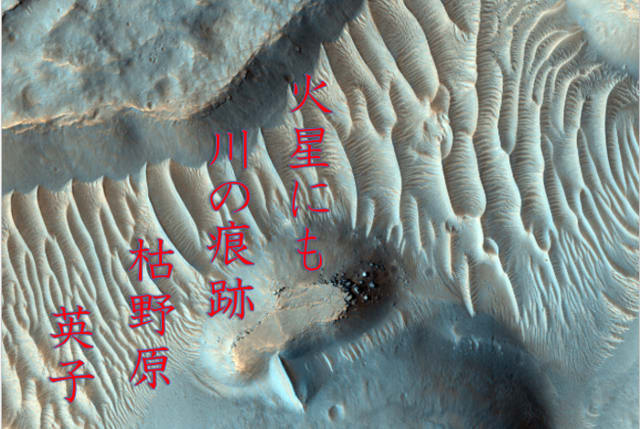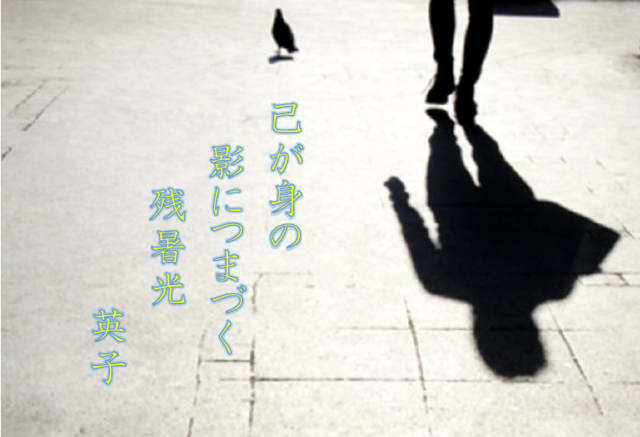あすかの会・藤の会 合同句会 12月 兼題「離 冬の花」 あすかの会会長 大本尚
野木桃花主宰
名木に深き瑕あり石鼎忌 武良推奨句

宅地化のここまで迫る返り花
飴色は里の甘味や吊るし柿
日向ぼこ記憶の底に父と母
◎ 野木主宰特撰
心ひらくまでの長さよ冬薔薇 さき子 野木主宰特撰 武良推奨句

◎ 武良特撰
茶の花やつましき寡婦の暮しむき みどり 武良特撰 野木主宰・大本会長推奨句

〇 以下、高得点順
〇 準高得点句
夕映えの光離さぬ枯芒 玲 子 大本会長・武良推奨句

〇 準々高得点句
本線を離れ支線へ山眠る 典 子 野木主宰・武良推奨句

石蕗の花日暮の早き坊泊り 典 子
人生の夕暮れにあう時雨かな さき子 大本会長・武良推奨句
今日なぜか軋む裏木戸花八つ手 尚
綿虫や隠しやうなき手に齢 孝 子 野木主宰・大本会長推奨句
風荒ぶ落葉の流離はじまりぬ 市 子 野木主宰推奨句
静もれる離陸の機内冬日入る ひとみ 大本会長推奨句
機を織るゆるやかな里冬桜 悦 子 武良推奨句
エンディングノート余白の日向ぼこ 孝 子
初雪や検査の結果聞く朝 ひとみ
ひとひらの記憶の重さ冬薔薇 玲 子 野木主宰推奨句
つくづくと父母居ずなりぬ藪柑子 みどり
夕餉時離農の庭の蕪を抜く 典 子
十二月くるくる回す膝小僧 さき子 武良推奨句
「ゆりかもめ」交差す小春の中空に トシ子
サンタにも廻る順番寝落ちの児 礼 子 武良推奨句
離れまで冬満月の肩借りぬ 市 子 武良推奨句
手の平で団栗転がす警察官 都 子 武良推奨句
離れてもなほ君想ふクリスマス 礼 子
街後にして柊の郷の花 礼 子
波音の日向日陰に石蕗の花 尚
離れから洩れる歌声師走かな 都 子
侘助落つ静寂の中の古刹かな トシ子 大本会長推奨句
ますみ空木洩れ日拾ふ落葉道 トシ子
まずつける句誌に折り目や新年号 一 青
足で弾く静謐な音聖夜のミサ 悦 子
大木の伐らるるままに冬青空 ひとみ
離れ家の母に顔みせクリスマス 孝 子
年忘れ盛会にゐて孤島めく みどり
花八ツ手木の表札の古りにけり みどり
数へ日や耕の終りに立つ煙 悦 子
厭離穢土戦旗駆けこむ冬の原 悦 子
闇しんしん闇寂寂と霜の夜 トシ子
咲き残る畑の隅の黄菊かな 一 青
木枯や子は離れゆくばかりなり 一 青
年毎に構え衰う太極拳 一 青
返り花千鳥ヶ淵の丘の上 都 子
コピー機の日日を吐き出す紅葉山 都 子
黒塀のくぐり戸そとの雪しぐれ かづひろ
結界や定家葛の枯れ姿 かづひろ
厭離穢土バット吸ひたる雪女 かづひろ
透析の血の色赤し水仙花 かづひろ
山村は暮るるに早し藪柑子 孝 子
日溜や狭庭に探す福寿草 玲 子
朝霜や一輪白く立ち上る 玲 子
親離れ出来て真っ赤なシクラメン 典 子
極月の顔の映りし車窓かな さき子
慰めの言葉に代えて冬薔薇 ひとみ
袈裟懸けに鳥の目指すは竜の玉 礼 子
離陸して右へ旋回北颪 尚
離農夫の手指ざらざら皹す 尚
山茶花の白際立たせ雨上る 市 子
ひそと咲く柊白く地を染むる 市 子
参考 特別参加 武良竜彦
最高得点句
地に眠るものにやさしく霜の花 野木主宰・大本会長推奨句

茎揃へ剪らるる花束十二月
仇名禁止師走の門を潜る子ら
離農者の続く寒村寒椿