
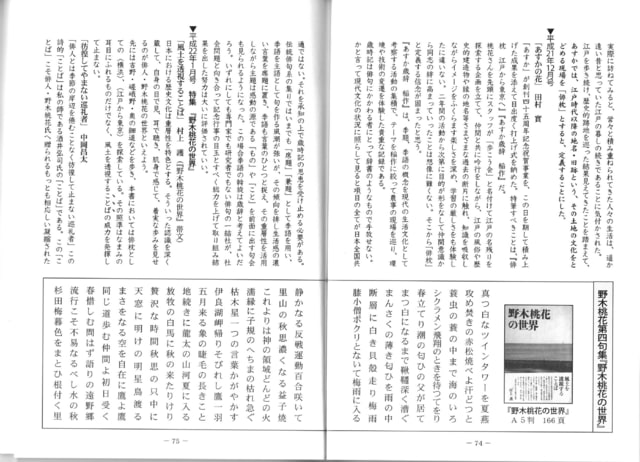








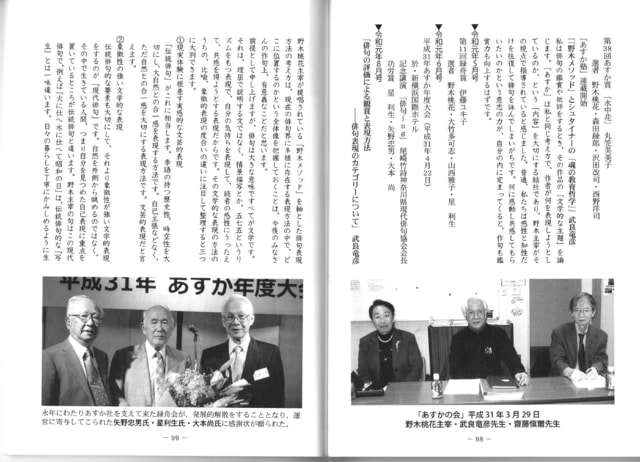


「あすかの会」五月の秀句から 季題「若葉」・兼題「白」
◎ 野木桃花主宰句
行くほどに若葉濃くなる大社
白壁の照り陰りして柿若葉
☆ 野木桃花主宰特選句
トルソーの白き鎖骨に緑さす さき子
☆ 武良竜彦特選句
フルートを吹く肘高く若葉風 みどり
◎ その他の秀句から 【支持・評価の高かった順】
白ばらや控え目に開くアーチ窓 みどり
ハープ弾くやうに若竹そよぎをり 英 子
若葉して幹のざらりとしていたり さき子
窓若葉書棚に夫のコンサイス さき子
知らぬ間に脛に青痣走り梅雨 尚
白牡丹咲き極まりて碧ざむる かづひろ
生きて此処若葉照る中そよぐ中 市 子
薔薇一本選ぶとしたらけふは白 市 子
ぎこちなき白詰衿や若葉風 典 子
厳島時を背負ひて若葉風 都 子
かきつばた寺に借りたる女傘 かづひろ
森閑と御陵に緑十重二十重 悦 子
復活の三社に神田祭来る 典 子
隧道の出口切り取る若葉光 みどり
空覆ふ並木の道や若葉雨 ひとみ
広重を思ふ白雨の橋走る ひとみ
木下闇結界となる石仏 玲 子
今日もまた老鶯に覚む朝ぼらけ 玲 子
白装束の去りたる月山大夕立 悦 子
庭に干す手びねりの壺柿若葉 悦 子
垣間見る襟に後れ毛白日傘 尚
人は軒鳥は若葉で雨宿り 英 子
柿若葉月日の移ろひ映り込む 都 子
※ 武良竜彦の句 参考
葉桜の恋か枝垂れて水面撫づ
師の葬の帰路に薔薇の白深し
「あすか」誌五月号作品鑑賞と批評
《野木メソッド》による鑑賞・批評
「ドッキリ(感性)」=感動の中心
「ハッキリ(知性)」=独自の視点
「スッキリ(悟性)」=普遍的な感慨へ
◎ 野木桃花主宰の句「牡丹寺」から
飛花落花迷へる羊となりしかな
「迷える羊」という言葉の由来は、新約聖書「マタイ伝一八」のイエスの言葉からのものです。「もし百匹の羊を飼っていたとして、そのうちの一匹がいなくなったら、だれだって、残りの九九匹を放っておいてでも、いなくなった羊を探しに行くでしょう。そして、見つかったら大喜びすることでしょう。それと同じように、迷いの多い人間が一人、救われないでいることは、神の御心ではないのです」という言葉です。弱くて罪深い人間に対する神の深い愛を表しているとされる言葉です。それを踏まえて、繚乱たる花吹雪に包まれた心境を表現した句ですね。
春筍を探り当てたるスニーカー
農家の人が専用の鍬で掘り出している景ではなく、観光農園でスニーカーを履いた若い人が、芽を出したばかりの筍を発見したというような景ですね。その若やいだ雰囲気が「春筍」の新鮮な生命力に相応しいですね。
やはらかく声をかけ合ふ牡丹寺
牡丹寺と呼ばれる寺院は全国にたくさんありますが、作者のお住まいの横浜市からいちばん近いのは、最後の薬王院でしょうか。総本山の奈良長谷寺から移植された牡丹百株が約四十種千株にまで増え、見頃を迎える四月中旬から下旬にかけて美しく雅やかな光景を見せてくれるそうです。掲句は人の声のようでもあり、牡丹同士が声を掛け合っているような景も浮かびますね。花びらと日差しの「やわらかさ」が伝わります。
〇「風韻集」 感銘秀句から
読影の医師の沈黙余寒なほ 大本 尚
エックス線や心電図、内視鏡などの検査画像を一枚一枚丁寧に読み解き、医師が診断することをいいます。 読影する医師のことを読影医と呼びます。その専門医の「沈黙」。どんな診断が下されるのか、どきどきの瞬間ですね。下五の「余寒なほ」が効いていますね。
蝶といふ遥かなものを旅立たす 奥村安代
中七の「遥かなもの」という比喩の遠望感が独創的で詩的ですね。自分の代りに春に舞う蝶に心を託して心を羽搏かせているようです。
妻の墓初蝶供華に寄り添ひて 加藤 健
愛する人への思慕敬慕がにじみ出ている表現ですね。
啓蟄や日を跳ね返す力石 金井玲子
力強さを増してくる春光の気配を「力石」の照りで巧みに表現した句ですね。「力石」は力試しに用いられる大きな石で、伝説的な人物が投げたと言い伝えられる力石も各地にあり、神社の庭に碑文が添えられているものもありますね。
日陰りしとき白梅の素顔なる 鴫原さき子
春光の中で輝いていた白梅の花が、日陰になって楚々とした色合いに変化した瞬間を捉えて、自分の繊細な心の動きを投影した見事な表現ですね。
てのひらに落花ことばのやうに受く 高橋みどり
「ことばのやうに受く」という素直な直喩が効いていて、読者を手放しの共感に誘う表現ですね。植物たちの「もの問いたげな雰囲気」を常に敏感に感じ取る日本的感性の美質ではないでしょうか。
蒔く種や指先湿し一つずつ 服部一燈子
やさしく種蒔きをしている作者の心が伝わる表現ですね。
初蝶の触れゆく墓碑の真新し 丸笠芙美子
新しく建てられた鎮魂の墓碑。その追悼の思いを初蝶の繊細な動きに託して表現した句ですね。追悼の深い想いが伝わります。
日傾き尖る沢音草つらら 宮坂市子
日没に「沢音」が「尖って」聴こえたという繊細な表現が効いていますね。草につららができているような山中の冷え冷えとした空気感が伝わります。
赤錆の騎馬武者花は搦手 矢野忠男
城内に建立されて時を経ている騎馬武者像でしょうか。「搦手」の比喩が詩的ですね。「搦手」の第一義は「人をからめとる人や捕手(とりて)」のことですから、桜の花が騎馬武者をまるで包囲して捉えようとしているようだ、という意味になるでしょうか。あるいは、第二義に「城の裏門」、第三義として「城の裏門または敵の背面を攻める軍勢」も指すことばですから、面的な広がりの中の景のようにも感じられる表現ですね。
とろり超ゆ堰の川幅花筏 山尾かづひろ
観察眼の冴えた表現ですね。私は多摩川の大きな堰の側に住んでいるので、堰を超えるときの川面の、つるりとした輝きを見た記憶を呼び覚まされました。この句はそれを「とろり」と独創的に表現し、そこに「花筏」を配して、春の流れを表現しているのですね。
東風吹くやびくとも動かぬ力石 大木典子
神社などの庭に置かれた、力試しの大きな石の不動の様を、「東風」という季節風の中に置いて表現したのが効果的ですね。
〇「風韻集」印象に残った佳句
銀髪の軽き足取り木の芽吹く 坂本美千代
待春やふたつの白帆風切つて 摂待信子
盆栽は百年の幹梅二輪 高橋光友
ひとくちの白酒故郷に山河あり 本多やすな
徳利にさして主役の水仙花 村上チヨ子
果てしなき空の涙か春の雪 柳沢初子
剪定や声掛け合うて兄弟 吉野糸子
寒風の刺さる峠路経ケ坂 磯部のり子
三寒四温すずめつまづく今朝の庭 稲葉晶子
片足の鷺の長考春の泥 大澤游子
「あすか集」感銘秀句から
大欅の狼煙のやうに芽吹き初む 村田ひとみ
大欅のいっせいに芽吹くさまは、たしかにうすみどりの煙のように見えます。その直感的な感覚に引き付けて春の到来を寿ぎ詠んだ句ですね。
口紅を点せば心の麗けし 望月都子
春の灯を点すように口紅を差したという比喩表現が、春のかすかなときめき感に相応しいですね。
濡れ縁に猫と分け合ふ冬日向 飯塚昭子
「濡れ縁」という言葉がいいですね。縁側が庭に面した屋内の廊下であるのに対して、濡れ縁は外付けで、外気に晒されています。昨夜の雨の湿り気も感じます。そこで猫といっしょに日向ぼこをしている景ですが、それを「猫と分け合ふ」と表現したことで、愛猫への作者の気持ちまで伝わりますね。
クライミング手捌き確と胡瓜蔓 内城邦彦
胡瓜の蔓が支柱に巻き付くようにして先を伸ばしてゆく様を、巧みなクライミングのさまに見立てた表現で爽やかな句ですね。
梅真白樹齢百寿を噴き上げて 小川たか子
下五の「噴き上げて」がダイナミックで巨樹の生命力に相応しい表現ですね。
かすかなる鳥語の宿る姫椿 金子きよ
中七の「鳥語の宿る」が詩的ですね。幼い鳥が葉陰に潜んでいるのか、あるいはまるで姫椿自身の囁きのようでもありますね。
くちなはの檻は空つぽ春浅し 近藤悦子
捕らえて檻に入れてあった「くちなは」が知らぬ間に抜け出して行方をくらましていた、という小さな「事件」の表現で春の到来を詠んだ句ですね。
利休の忌序奏のやうに涙雨 紺野英子
茶道の基となる「わび茶」を完成させた利休は、秀吉に理不尽なる切腹を賜りました。それを踏まえて「利休の忌」に「涙雨」添えて詠んだ句ですね。
筍を二本かついで友来る 齋藤 勲
「二本」という具象的な数詞がいいですね。二人の友情のさまがうかがえます。
円かなる若草山や草萌ゆる 乗松トシ子
草木の盛んな萌え出の季節、冬枯れの時期と比べて、野山全体がこんもりと盛り上がった印象に変化します。それを「円かなる」と表現したのが詩的ですね。
駅からの坂道ほどよし梅づくし 林 和子
たぶん上り坂が駅からすぐ続いている景でしょう。それも急な坂ではなく、適度な負荷が足に掛る程度のゆるい上り坂。周りには梅の花が見ごろ。早春の散策の心地よさが伝わります。
供えるは紅梅一枝酒一合 緑川みどり
一と一の繰り返しのリズムに切れがあり、作者の心のさまが伝わりますね。
〇「あすか集」印象に残った佳句
火事跡に献花一輪水に濡れ 大谷 巖
母の忌や供花に降り注ぐなごり雪 大竹久子
卒業す泣いて笑つて喧嘩して 小澤民枝
きれい好き過ぎるマンション沈丁花 風見照夫
新緑やパンケーキの朝ごはん 柏木喜代子
灌木の庭の落葉と遊ぶ夕 金井和子
うらうらと蒟蒻温灸背に二枚 木佐美照子
蠟梅や年に一度の健診日 城戸妙子
鶏の朝の知らせに春を知る 久住よね子
立春の青き大空独り占め 齋藤保子
春ショール物産展のずんだもち 須賀美代子
医療費のお知らせ一通冴返る 須貝一青
猫舌の夫が真顔で蜆汁 鈴木ヒサ子
二度三度鍵たしかむる春の月 鈴木 稔
ふくらんで棘のあらはや更紗木瓜 砂川ハルエ
紙雛もあらざる日々や國敗る 高野静子
眉のごと遠き山影春夕焼 高橋富佐子
そよ吹けば競ひあふなり春の木木 滝浦幹一
苗札に贈り主の名書いておく 忠内真須美
春うらら亀の子ブイに乗つてをり 立澤 楓
ひな納め水汲み官女の衣の褪せて 丹治キミ
紅梅やふくらみほどけこの一枝 千田アヤメ
のどけしや低空飛行の鴉行く 坪井久美子
父と子の影重なりて野に遊ぶ 中坪さち子
満水の水瓶めがけ百千鳥 成田眞啓
早梅のホツホツホツと陽を受くる 西島しず子
初めての素顔に戸惑ひ卒業す 沼倉新二
春耕やくいくいくいと鳥の声 浜野 杏
かりがねや石に刻まる童唄 星 瑞枝
蜆売りぽいとお負けの三つ四つ 曲尾初生
菜の花に囲まる川や海へ五里 幕田涼代
香と花と亡き人つなぐ彼岸かな 増田綾子
朝の森初音に丸い脊を押され 宮崎和子