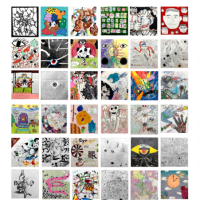一人芝居からまもなく一ヵ月ですが、もう遠い昔のことのように思うのは、一月、二月と公演の稽古が続くからでしょうか。次回公演のことは次の機会として…。
奈良町にぎわいの家で11月半ばに公演した一人芝居の二本目は、岡本かの子の「家霊」が原作です。アラフィフの小町座代表の西村智恵と、篠原佳世が演じました。この二人の芝居の出来上がるまでの過程がいつもと全く違い…困ったり良かったり、中々、大変でした。
前回のブログに書いた「鮨屋の娘」同様、この芝居は「どじょう屋」の店の娘が主人公です。女学校を出て、職業婦人になり、母親の病気で店に戻り、そのまま、店を仕切る暮らしをしています。
娘は昔から、「精力の消費者の食事療法をしている」ような店が嫌、しかも父親は放蕩、母親はそれにも耐えて帳場に座り店の主となっている。そんな状況に不満を持っています。
その「不満」の持ち方が何というか、「微妙」なのです。例えば、不満や怒りがあるということは、そこから生まれるエネルギーもあるはずで、その不満を何ものかにぶつけたり、時には自分を虐げたり、形として現れることもあるでしょう。
ところが、この娘の場合、そんな「不満」の出し方が「微妙」なのです。自分の状況をハナから諦めている…なら、逆に諦念から、別の次元にすっきりと自分自身を整えていくかもしれないが、そういうのとも違う。
どじょう屋の娘は、店も父母も好きではないが、しかし「そこにいる」。もちろん、積極的にいるわけではないが、かといって、積極的に去ろうともしない。もちろん、病気の母を見捨てられない現状があるが、しかし、娘そのものが、何というか、少し、不思議なのです。
原作「家霊」では、女学校を出た後に家出同然で職業婦人になった三年間をこう書いています。
「三年の間、蝶々のように華やかな職場の上を閃いて飛んだり、男の友達と蟻のように触角を触れ合わせたりした、ただ、それだけだった。それは夢のようでもあり、いつまで経っても同じ繰り返しばかりで飽き飽きしても感じられた。」
最後の傍線は私が引きましたが、ここが気になって仕方なかったのです。つまり、店の外の世界も自分の生きる場所とは思えななかったのでは、そんな感覚を受けたのです。
となると、母親が病に倒れ、店に戻るとなった時も、もしかすると逃げることもできたが、戻ってきたのかも…そのように娘をみると、娘にとっての嫌悪すべき「いのちの店」の正体が、また別のものに見えてきます。
そのあたりのヒントが小説のタイトル「家霊」に見えるのです。「家」の「霊」ですから、ただならぬ感じがする言葉ですが、このタイトルは、大地主の娘として育った(その後、家は落ちぶれるのですが)かの子にまま、つながるでしょう。過去につながる血脈や土地と人の時間、自分につながる亡者たちの声をひきつれたまま、今に生きている、かの子自身を反映した、タイトルであるからです。
この「家霊」に抗いつつも、そこを引きずるからこその、独自のまなざしと体温がある…。かの子の作品全般に感じる、独特のぬめり感と暗さ、妙な明るさと汚れのないまっすぐな感覚は、「家霊」があってのものと、かの子は苦しみつつも心得ているのではないか、そんな風に思うのです。
そう考えると、どじょう屋の娘が単に「店を嫌悪している」というわかりやすい気持ちでは、演じらないのです。ここに、演者は苦しみました。特に小町座代表の西村は。
西村の良さは、自分がまま前にばーんと出るところ。昔から小町座の少年役を続けてきたので、元気の良い明暗がはっきりとした気持ちの良い役柄はピカいちで、前回の本公演「万博物語」では、観客から大絶賛されました。
ところが、どじょう屋の娘はそんなキャラクターからは程遠く、いつもの「彼女のまま」では到底できません。彼女の場合、自分の中にある、割合、明確な気持ちの流れから人物をとらえ、作っていくので、わかりやすい役柄にどうしてもなってしまいます。しかし、今回の娘は先に書いたように「わかりにくい」のです。店は嫌い、というのを前にだすだけでは、どうにも作りきれません。
とはいえ、この物語には娘の外側に大きなドラマがあり、それが毎夜、支払うあてもないのに、どじょう汁をせがみにくる、彫金師の徳永老人と、自分の母親です。二人の秘めたつながりを娘が知ることで、明らかに娘の中で、嫌悪していた「どじょう」が親しいものに変わる、ここがドラマの山のの一つです。西村の芝居では、この娘の変化を、前に強く出す演技としました。
ところで、西村のキャラクターは本番一週間前まで平坦に固まってしまっていたので、とりあえず、私が頭から読むのを聞いてもらいました。そしたら次の稽古で、なんとまあ、すっかり変わっていたのです。この変化に私は驚きました。彼女の良さは演じないで自身がそのまま出る時なので、それと正反対のいわゆる「演技」をしたことに、本当に驚いたのです。もちろん、形だけの演技なら、誉めはしませんが、「演技」ができるんだなあ、と。彼女の努力は大変なものがあったと思います。自分とは全くかけ離れた、気持ちを寄せるのも難しい役柄なんですから。
さて、私は良かった、間に合った、と思っていたところ、公演後、西村のファン、特に男性から、辛口のコメントが寄せられたのです。前回の少年役とはあまりに違うというのもあるでしょうが、おそらく、どじょう屋の娘のキャラクターのつかみにくさと、いつもの西村のリズム感が全くないのに、困惑したのではないかと思います。一方、女性の感想はそうでもなかったので、今回ほど、感想に男女差が出た芝居は初めてかもしれません。何しろ、お客様に「家霊」というタイトルの持つ印象を芝居の中で伝えるのは、とても難しいと思いました。
一方、篠原佳世の芝居は、割合、早い段階から、落ち着いたものとして仕上がってきました。彼女は、初期段階では、役柄をとらえる時、形として「芝居らしく」読む傾向があり、語尾などが一定の音域でパターンとしておさまることが多いのですが、今回は「芝居というより語りのように」と伝えると、いい感じに役柄の空気感が出ました。彼女の声はとても良い声なのですが、その声色が、今回の役柄の陰影にぴったりだったのです。大袈裟でない、淡々と、しかし、どこが憂いがあり、決して昂らず、といった空気感が、なんともいい感じで出たのです。いつもは、役の仕上げに時間がかかる彼女が、今回は早くて、そこが何とも面白く、まさに「当たり役」だったと思います。
そんな篠原の感想を小町座FBから抜粋しました。
一人芝居『いのちの店の娘』を終えて
今年で3年連続で一人芝居をさせてもらった。
振り返ってみても、未熟な私が3本も一人芝居を演ったなんて不思議な感じがする。
そんな環境にいて幸せだったと思う。
舞台の本番がある度に、大きな何かを得ている。
特に一人芝居では、見えない相手や周りの状況、少し離れた所にいる人を、より鮮明に感じられるようになったことであったり、1人で二役の会話を演るときにどんな間合いで演るのが観やすいのかを感じ取ったり、またその二役を演る時に、それぞれのキャラクターとその背景を瞬時にチェンジすることであったり…
そういうことに少しずつ踏み込めるようになってきた。今回の『いのちの店の娘』は、作品を初めて読んだときに自分が持ったイメージをそのまま深めていけたので、比較的演りやすかったと思う。
おそらく、どじょうやの娘にしても、その母のおかみさんにしても、彫金師の徳永老人にしても、ずっと内に秘めたものや強い想いがあって、それが私自身と重なるものがどこかあったのではと思う。
娘がずっと母親を見てきて、どんな風に思い自分に重ね合わせているか、またその心持ちで徳永老人に対処した時の心の動き。
徳永老人は、若い頃から何十年もおかみさんを想ってきて、強い気持ちがありながらも言葉に出さず、想いを、命を簪に刻み込む。おかみさんが毎晩よこしてくれた、どじょう汁を食べながら。自分の作った簪をおかみさんが付けてくれることでおかみさんと交わる。
その為に生きてきた、彫ってきたようなもの。
おかみさんは、旦那から受ける仕打ちに思うことは多々あるものの、自分の務めを果たすことと意地のようなもので静かに自分を保ち続けた。徳永の想いに気づきながら、どじょう汁と引き換えに、命が想いが刻み込まれた自分の為だけに作られた簪に慰められながら、道を逸れずに生きてきた。
この3人の心の芯の部分の絡み合いが、すごく演じ甲斐のある、脚本だったと思う。
自分なりの解釈で、言葉で言うほど表現できていたとは思わないが、登場人物のその場その場の心情に沿って発する台詞が自分の思うスピード感で自然に言えるのが心地良かった。
なお、この一人芝居は「娘」「母」「徳永老人」と三人を演じ分けるのですが、西村、篠原ともに「老人」が一番落ち着いて見えました。確かに、この老人は迷いがなく、「ただ毎晩どじょう汁」がほしい、この一点に気持ちが集約されていくので、演じやすかったでしょう。
それと、最後までできなかったのは、娘の母が亡くなる前に、徳永老人が自分のために作ってくれた、簪のことを語るシーンがあります。原作では
一通り話をした後、最後に「ほ ほ ほ ほ」(原作まま)と笑うのです。これを脚本にも書きましたが、この笑いが、全くできない、というか、芝居にならない。ただ、変な笑い?にしかならず、結局、この笑いは舞台で無しとしました。
この母の「ほ ほ ほ ほ」の笑みを、ぜひ舞台で聞きたい。これが私の夢です。どんな女優さんがこんな風に笑うんでしょうか。
いや、もしかすると、声は無しで…顔で見せるのか?演出する側としては、本当にこの母の死の直前の笑い声は、何とも大きな魅力です。
それにしても、大変な芝居をやり遂げた小町座の二人に拍手!お疲れ様でした。


奈良町にぎわいの家で11月半ばに公演した一人芝居の二本目は、岡本かの子の「家霊」が原作です。アラフィフの小町座代表の西村智恵と、篠原佳世が演じました。この二人の芝居の出来上がるまでの過程がいつもと全く違い…困ったり良かったり、中々、大変でした。
前回のブログに書いた「鮨屋の娘」同様、この芝居は「どじょう屋」の店の娘が主人公です。女学校を出て、職業婦人になり、母親の病気で店に戻り、そのまま、店を仕切る暮らしをしています。
娘は昔から、「精力の消費者の食事療法をしている」ような店が嫌、しかも父親は放蕩、母親はそれにも耐えて帳場に座り店の主となっている。そんな状況に不満を持っています。
その「不満」の持ち方が何というか、「微妙」なのです。例えば、不満や怒りがあるということは、そこから生まれるエネルギーもあるはずで、その不満を何ものかにぶつけたり、時には自分を虐げたり、形として現れることもあるでしょう。
ところが、この娘の場合、そんな「不満」の出し方が「微妙」なのです。自分の状況をハナから諦めている…なら、逆に諦念から、別の次元にすっきりと自分自身を整えていくかもしれないが、そういうのとも違う。
どじょう屋の娘は、店も父母も好きではないが、しかし「そこにいる」。もちろん、積極的にいるわけではないが、かといって、積極的に去ろうともしない。もちろん、病気の母を見捨てられない現状があるが、しかし、娘そのものが、何というか、少し、不思議なのです。
原作「家霊」では、女学校を出た後に家出同然で職業婦人になった三年間をこう書いています。
「三年の間、蝶々のように華やかな職場の上を閃いて飛んだり、男の友達と蟻のように触角を触れ合わせたりした、ただ、それだけだった。それは夢のようでもあり、いつまで経っても同じ繰り返しばかりで飽き飽きしても感じられた。」
最後の傍線は私が引きましたが、ここが気になって仕方なかったのです。つまり、店の外の世界も自分の生きる場所とは思えななかったのでは、そんな感覚を受けたのです。
となると、母親が病に倒れ、店に戻るとなった時も、もしかすると逃げることもできたが、戻ってきたのかも…そのように娘をみると、娘にとっての嫌悪すべき「いのちの店」の正体が、また別のものに見えてきます。
そのあたりのヒントが小説のタイトル「家霊」に見えるのです。「家」の「霊」ですから、ただならぬ感じがする言葉ですが、このタイトルは、大地主の娘として育った(その後、家は落ちぶれるのですが)かの子にまま、つながるでしょう。過去につながる血脈や土地と人の時間、自分につながる亡者たちの声をひきつれたまま、今に生きている、かの子自身を反映した、タイトルであるからです。
この「家霊」に抗いつつも、そこを引きずるからこその、独自のまなざしと体温がある…。かの子の作品全般に感じる、独特のぬめり感と暗さ、妙な明るさと汚れのないまっすぐな感覚は、「家霊」があってのものと、かの子は苦しみつつも心得ているのではないか、そんな風に思うのです。
そう考えると、どじょう屋の娘が単に「店を嫌悪している」というわかりやすい気持ちでは、演じらないのです。ここに、演者は苦しみました。特に小町座代表の西村は。
西村の良さは、自分がまま前にばーんと出るところ。昔から小町座の少年役を続けてきたので、元気の良い明暗がはっきりとした気持ちの良い役柄はピカいちで、前回の本公演「万博物語」では、観客から大絶賛されました。
ところが、どじょう屋の娘はそんなキャラクターからは程遠く、いつもの「彼女のまま」では到底できません。彼女の場合、自分の中にある、割合、明確な気持ちの流れから人物をとらえ、作っていくので、わかりやすい役柄にどうしてもなってしまいます。しかし、今回の娘は先に書いたように「わかりにくい」のです。店は嫌い、というのを前にだすだけでは、どうにも作りきれません。
とはいえ、この物語には娘の外側に大きなドラマがあり、それが毎夜、支払うあてもないのに、どじょう汁をせがみにくる、彫金師の徳永老人と、自分の母親です。二人の秘めたつながりを娘が知ることで、明らかに娘の中で、嫌悪していた「どじょう」が親しいものに変わる、ここがドラマの山のの一つです。西村の芝居では、この娘の変化を、前に強く出す演技としました。
ところで、西村のキャラクターは本番一週間前まで平坦に固まってしまっていたので、とりあえず、私が頭から読むのを聞いてもらいました。そしたら次の稽古で、なんとまあ、すっかり変わっていたのです。この変化に私は驚きました。彼女の良さは演じないで自身がそのまま出る時なので、それと正反対のいわゆる「演技」をしたことに、本当に驚いたのです。もちろん、形だけの演技なら、誉めはしませんが、「演技」ができるんだなあ、と。彼女の努力は大変なものがあったと思います。自分とは全くかけ離れた、気持ちを寄せるのも難しい役柄なんですから。
さて、私は良かった、間に合った、と思っていたところ、公演後、西村のファン、特に男性から、辛口のコメントが寄せられたのです。前回の少年役とはあまりに違うというのもあるでしょうが、おそらく、どじょう屋の娘のキャラクターのつかみにくさと、いつもの西村のリズム感が全くないのに、困惑したのではないかと思います。一方、女性の感想はそうでもなかったので、今回ほど、感想に男女差が出た芝居は初めてかもしれません。何しろ、お客様に「家霊」というタイトルの持つ印象を芝居の中で伝えるのは、とても難しいと思いました。
一方、篠原佳世の芝居は、割合、早い段階から、落ち着いたものとして仕上がってきました。彼女は、初期段階では、役柄をとらえる時、形として「芝居らしく」読む傾向があり、語尾などが一定の音域でパターンとしておさまることが多いのですが、今回は「芝居というより語りのように」と伝えると、いい感じに役柄の空気感が出ました。彼女の声はとても良い声なのですが、その声色が、今回の役柄の陰影にぴったりだったのです。大袈裟でない、淡々と、しかし、どこが憂いがあり、決して昂らず、といった空気感が、なんともいい感じで出たのです。いつもは、役の仕上げに時間がかかる彼女が、今回は早くて、そこが何とも面白く、まさに「当たり役」だったと思います。
そんな篠原の感想を小町座FBから抜粋しました。
一人芝居『いのちの店の娘』を終えて
今年で3年連続で一人芝居をさせてもらった。
振り返ってみても、未熟な私が3本も一人芝居を演ったなんて不思議な感じがする。
そんな環境にいて幸せだったと思う。
舞台の本番がある度に、大きな何かを得ている。
特に一人芝居では、見えない相手や周りの状況、少し離れた所にいる人を、より鮮明に感じられるようになったことであったり、1人で二役の会話を演るときにどんな間合いで演るのが観やすいのかを感じ取ったり、またその二役を演る時に、それぞれのキャラクターとその背景を瞬時にチェンジすることであったり…
そういうことに少しずつ踏み込めるようになってきた。今回の『いのちの店の娘』は、作品を初めて読んだときに自分が持ったイメージをそのまま深めていけたので、比較的演りやすかったと思う。
おそらく、どじょうやの娘にしても、その母のおかみさんにしても、彫金師の徳永老人にしても、ずっと内に秘めたものや強い想いがあって、それが私自身と重なるものがどこかあったのではと思う。
娘がずっと母親を見てきて、どんな風に思い自分に重ね合わせているか、またその心持ちで徳永老人に対処した時の心の動き。
徳永老人は、若い頃から何十年もおかみさんを想ってきて、強い気持ちがありながらも言葉に出さず、想いを、命を簪に刻み込む。おかみさんが毎晩よこしてくれた、どじょう汁を食べながら。自分の作った簪をおかみさんが付けてくれることでおかみさんと交わる。
その為に生きてきた、彫ってきたようなもの。
おかみさんは、旦那から受ける仕打ちに思うことは多々あるものの、自分の務めを果たすことと意地のようなもので静かに自分を保ち続けた。徳永の想いに気づきながら、どじょう汁と引き換えに、命が想いが刻み込まれた自分の為だけに作られた簪に慰められながら、道を逸れずに生きてきた。
この3人の心の芯の部分の絡み合いが、すごく演じ甲斐のある、脚本だったと思う。
自分なりの解釈で、言葉で言うほど表現できていたとは思わないが、登場人物のその場その場の心情に沿って発する台詞が自分の思うスピード感で自然に言えるのが心地良かった。
なお、この一人芝居は「娘」「母」「徳永老人」と三人を演じ分けるのですが、西村、篠原ともに「老人」が一番落ち着いて見えました。確かに、この老人は迷いがなく、「ただ毎晩どじょう汁」がほしい、この一点に気持ちが集約されていくので、演じやすかったでしょう。
それと、最後までできなかったのは、娘の母が亡くなる前に、徳永老人が自分のために作ってくれた、簪のことを語るシーンがあります。原作では
一通り話をした後、最後に「ほ ほ ほ ほ」(原作まま)と笑うのです。これを脚本にも書きましたが、この笑いが、全くできない、というか、芝居にならない。ただ、変な笑い?にしかならず、結局、この笑いは舞台で無しとしました。
この母の「ほ ほ ほ ほ」の笑みを、ぜひ舞台で聞きたい。これが私の夢です。どんな女優さんがこんな風に笑うんでしょうか。
いや、もしかすると、声は無しで…顔で見せるのか?演出する側としては、本当にこの母の死の直前の笑い声は、何とも大きな魅力です。
それにしても、大変な芝居をやり遂げた小町座の二人に拍手!お疲れ様でした。