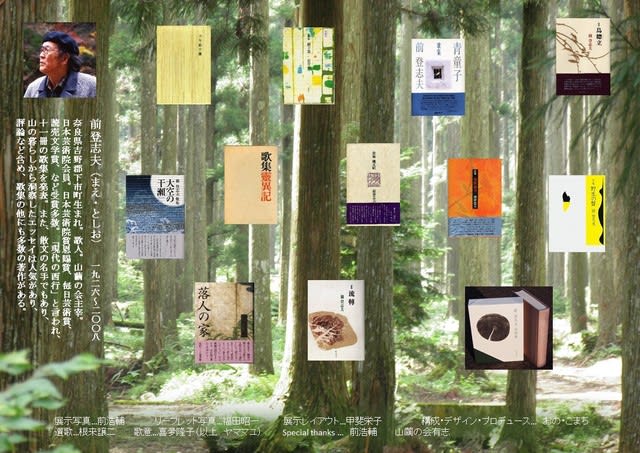奈良町にぎわいの家の休館が5/31まで延長となりました。例年は、一番来館者の多い時期で、いつもなら、来館者参加型でこいのぼりを作ります。
今年は、スタッフがこいのぼりを作りました。以下、ご覧ください。
こいのぼりに願いを込めて 奈良町にぎわいの家
毎年、にぎわいの家では、皆さんに参加していただいて
制作したこいのぼりを、町家格子に飾っています。
今年の春は残念ながら、コロナ対策で、閉館となりました。
来年こそは、また、皆さんの願いを書いたこいのぼりが、
掲示できますように、そして、今の私たちを取り巻く状況が
良くなり、また再び、お会いできるようにと、今年は当館
スタッフがこいのぼりを作りました。
「つよく、やさしく」、いろんな困難が乗り越えられますよう願いをこめて…。皆さん、どうぞお大切にお過ごしください。


今年は、スタッフがこいのぼりを作りました。以下、ご覧ください。
こいのぼりに願いを込めて 奈良町にぎわいの家
毎年、にぎわいの家では、皆さんに参加していただいて
制作したこいのぼりを、町家格子に飾っています。
今年の春は残念ながら、コロナ対策で、閉館となりました。
来年こそは、また、皆さんの願いを書いたこいのぼりが、
掲示できますように、そして、今の私たちを取り巻く状況が
良くなり、また再び、お会いできるようにと、今年は当館
スタッフがこいのぼりを作りました。
「つよく、やさしく」、いろんな困難が乗り越えられますよう願いをこめて…。皆さん、どうぞお大切にお過ごしください。