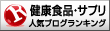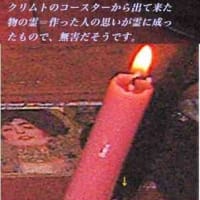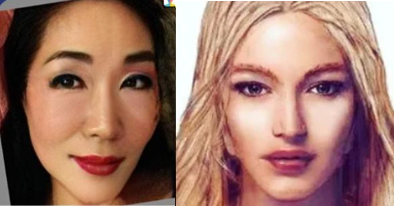今日も夜に2時間練習して来ました。
センターは、部屋が空いてないと使えないので、一週間ぶりです。
雪が酷くて、歩くと疲れるし、この状態だと一週間にいっぺんでも良いかと思っています。
一週間あけて疲れは取れていたし、今日は目を覚まさずに8時間眠れたので、調子は良かったです。
今まででは、一番マシでした。
とは言え、まだまだコンサートが出来る様な状態ではありません。
声帯が閉まらない状態に成って、歌う事もできない状態からのリハビリで、高音も出せず、変わり目の処理も出来なかったのが、大分、スムーズに2オクターブのスケールも出来る様に成りました。努力は実ります。
最近youtubeのお勧めに流れて来た、マリア・カラスが38歳の時のイギリスの”Royal Festival Hall of London”1962年の録音で、ウェーバーの「オベロン」を一曲目に歌っているのが、とても迫力の有る、まだ全盛期に近い声で歌っているのを聴いて、とても気に入り、この頃は毎日聴いています。
カラスは、コロラトゥーラが歌える事を知って貰えるまでは、ワーグナーを歌っていた位で、迫力と重量感の有る声で、聴いていると元気が出ます。そう、声からパワーを貰える感じなのです。
カラスの全盛期は30代までで、1960年代後半になると、あまり良い声の録音はありません。
私はカラスの全盛期だった、20代~30代の録音を聴いて勉強したので、衰えて来た声を聴くと、悲しくなります。
メドベッドがあったなら、未だに歌っていられたのに・・・・と残念に思ってしまいます。
38歳で、まだ声が残っていた時でも、この録音の最後の「アンナ・ボレーナ」では、難曲の大曲を4曲も歌った後だから、もう体力が残ってなくて、ブレスが短くなっています。そりゃそうですね、と思いました。いくら若くても、これだけ歌うのは、限界に挑んている様なものです。
それで、彼女の「オベロン」を聴いていたら、歌えそうな気がしたので、今日は楽譜を持って行き、初めてアリアの前半部分を歌ってみました。
すると、意外と楽に歌えました。💗思っていたよりも、大変ではなかったです。
私はワーグナーに興味も無く、ワグネリアンでもないので、「トリスタンとイゾルデ」も歌った事は無いのですが、カラスがイタリアで、イゾルデをイタリア語で歌っていたのは知っているので、イゾルデも歌えるかな?と思って、挑戦してみました。
勿論、独語でです。こちらも、特に大変ではありませんでした。
やはり一番大変なのは、ベッリーニやドニゼッティの、「ドラマティック・コロラトゥーラ」の「ノルマ」や「アンナ・ボレーナ」なので、それを歌っているから、ワーグナーもそれ程難しくない事が分かりました。でも、この役を歌う気はありません。
リヒャルト・シュトラウスの「サロメ」は、私の声に合っているし、容姿にも合っていると言われたので、ちょっと興味は有ります。
このオペラは、サロメが「七つのベールの踊り」と言う、ストリップをやるので、それを観たさに、チケットが完売するんだから、笑ってしまいます。オペラ歌手のストリップが見たいとは、物好きだねぇ🤣
私はクラシックバレエを8年間、真剣にやっていたので、踊りは他の歌手よりは、上手く踊れると思います。
それもこれも、メドベッドに入ってからの話ですが。
やるとしたら、「肉襦袢」でも着るさ🤪
『オベロン、あるいは妖精王の誓い』(J. 306)は、カール・マリア・フォン・ウェーバーが1825年から1826年にかけて作曲した、台本に台本をつけた全3幕のロマンチックなオペラである。ウェーバーが作曲した唯一の英語オペラで、ジェームズ・ロビンソン・プランシェによる台本は、クリストフ・マルティン・ヴィーラントのドイツ語の詩『オベロン』に基づいており、この詩自体はフランスの中世物語である叙事詩ロマンス『ボルドーの女』に基づいている。[1] 初演は1826年4月12日ロンドンで行われた
Maria Callas Concert in London (27 February 1962) [In-house Recording]
1.Weber : Oberon 2. Massenet : Le Cid 3. Rossini : La Cenerentola 4. Verdi : Macbeth 5.Donizetti : Anna Bolena