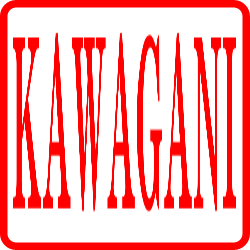<DQX毛皮を着たヴィーナス>

そのとき、ヴィーナス夫人はとても色っぽかった。
彼女は、ヴィーナスという匿名で、競争相手のクレオパトラ嬢などにいどみかかる世間なみの気まぐれな女性などとはまったく違っていて、愛の女神そのものであった。

彼女の目は動かず顔は無表情であったが、すばらしく美しかった。豪華な毛皮のなかに大理石のような肌の五体をすっぽりとつつんで、猫のようにふるえながらじっとうずくまっていた。
「どうも僕にはわからない」
「この二週間ばかり、陽気はすっかり春めいてきたのに、あなたはちょっと神経質すぎるんじゃないですか?」

「ご親切さま」「クシュ!」「クシュ!」
彼女は石のようにかたく低い声で答えてから、二度ばかり、女神のようなしぐさで、くしゃみをした。
「わたし、こんな土地にもう、がまんできないわ。わたしにも様子がわかってしまったから・・・」

「なにがですか?」
「わたし、信じられないようなことが信じられはじめたので、それでわからないようなことが、わかりはじめたのよ。つまり、ドイツ人の婦徳とか、哲学とかが、急にわかってきましたのよ。あなたのような北国の人が恋の仕方をご存じなくても、わたし、もうおどろかないわよ」
「クシュ‼」「クシュ!」「クシュ!」「くしゃみが」
「ふふ、それだからこそ、わたし、いつもあなたのために、つくしてあげてきたのよ。こんな毛皮を着ていても、風邪ばかりひいてるけど、ちょいちょい会いにきてあげているではないの。はじめてお会いしたときのことを、おぼえていらっしゃる?」

「忘れてなんかいるもんですか。あなたは髪の毛を鳶色のカールにして、鳶色の目と紅の唇をしていました。リスの毛皮を着て緑どった紫がかった青いアクセサリーをつけていました。」
「あなたは、わたしの衣装に恋したのね。ですからあなたって人は、わたしには扱いやすかったわ」
「それであなたは、ボクに恋愛がどんなものかを教えてくれたのですね」
「わたしがあなたにつくしてあげた誠実は、なにものにもくらべようがなかったほどよ」
「それが誠実というものであったのなら」
「まアひどい、恩知らずの義理しらず」
「いや、ボクはあなたを責めているわけではありません。あなたはわたしの女神です。しかし女はやはり女ですから、恋愛には残酷ですね」

「女性の愛情の根源で、女性の持って生まれた性質なのよ。愛する者には、自分の全部をあたえるし、喜ばしてくれるものなら、なんでも愛するという自然の要素なのよ」
「愛する女性が不実、これ以上、男性にとって残酷なことはありません」
「わたしたちは、愛しているかぎりは決して心変わりなんかしないわ、それなのに男って変よ。愛していないのに女には貞節を要求するし、なんの喜びもあたえてくれないのに、身を捧げろ、身体を許せとおっしゃるですもの。これではどちらが残酷でしょうか。女のほう、それとも男のほう?北国のかたは恋をするにもかた苦しく考えすぎるわね。たのしみだけを問題にしてればいいのに、すぐに義務がどうの、こうのというのね」
「それは、わたしたちの愛情が尊敬すべきもので、誠実なもので、わたしたちの関係が永遠のものだからですよ」
「そのくせいつも満足しないで、異教の裸像であるわたしを慕っていらっしゃるのね。神様の純粋な恋の最高の喜びは、反省の子供のような近代人のものではないわね。喜びの恋愛は、あなた方の心のなかでは、悪徳にだけ結びついているのだわね。あなた方の世界ではわたし、こごえてしまいますわ ゴフォゴフォ」

「しかし男と女とは・・・」
「あなた方の明朗な太陽の輝く世界でも、ボクたちの霧が立ち込める世界でも、仇同士ですよ。これだけは、いくらあなたでも否定できないでしょう。ほんの短い間だけならば、恋愛のなかで男と女は融合してひとつの人格ともなり、ひとつの思想、ひとつの感覚、ひとつの意志にもなれますが、そのあとでは前よりずっと遠くへ離れてしまいます。どちらかが相手を服従させそこなうと、たちまち足で首根っこをふみつけられます。それだからこそ、ボクは幻想を抱かないのです」

するとヴィーナス夫人は傲然としたあざけりの調子で叫んだ。
「するとあなたは、なんの幻想も抱かないで、わたしの奴隷になっているわけね。いいわ、それならその意味で、これからはわたしは、容赦なくわたしの足の重みを十分感じさせてあげるわね」

「そんなバカなこと!」
「そうよ、わたしは残酷よ、あなたはこの言葉をとても好んで喜んでいらっしゃいますからね。・・・・どういうふうに男を征服し、奴隷にし、おもちゃにし、笑いながら裏切ってやるか、それを知らない女性は利口じゃないわね」
「それはあなただけの考えでしょう」
「何千年もの経験の結果よ」
彼女は白い指で暗色の毛皮をもてあそびながら、皮肉にいった。そして言葉をつづけて、
「女が献身的になればなるほど、男はいよいよ落ちついて権威をふるうけど、女が薄情になり、不実になって、手ひどく男を扱い、勝手気ままにほかの男たちとたわむれれば、それだけ男の欲望をそそり、男から愛され、崇拝されるものよ」
「たしかに」
「このうえもなく男をひきつけるのは、美しく情熱的で残虐で暴虐な女でしょう。移り気で平気で男をかえて気ままな恋をする女で・・・」
「そのうえで毛皮を着ている女」
「それはどういう意味ですか?」

「あなたのお好みよ」
「あなたは、この前あったときにくらべて、ずいぶん魅力的になりましたね」
「どこが?」
「あなたの白い肌のからだをひきたてるには、黒い毛皮以上に効果的なものはありまん。それから・・・」
「あなたは夢を見ていらっしゃるのよ。さあ、お目をさまして!」
といって、白い手でわたしの胸をぎゅっとつかみ、「さあ、お目をさまして!」と低音のしゃがれ声でくり返した。

わたしはハッとしてその手を見た。すると、耳に響いたのは、コサック生まれの酒のみ下男のドラ声であった。六尺豊かな大男の彼が、わたしの前にぬっくと立っているのだった。
「おきてくだせえ、旦那さま、みっともねえですよ」
「なにが?」
「外出着のまま、本をほうり出してねむっているなんて!」

「哲学者ヘーゲルの本か。それはともかく、もうゼフェリンさまのお宅へお出かけねばならぬ時刻です。お茶の用意をして待っておられるそうですから」

「奇妙な夢ですなア」
毛皮につつまれているヴィーナス!わたしはその絵を指さして、そう叫ぶとともに、
「ボクが夢のなかでみた彼女も、あんなふうでしたよ」
と、そばのゼフェリンに言葉をかけた。すると彼も、
「そう、ぼくも見たのだ」と応じてから、
「ただ君と違うのは、ぼくは目を開いたままあの夢をみたのさ」
「ほんとうですか?」
「そう、でもぼくのはつまらない話さ」
「しかし、とにかくこの絵はボクの見た夢を暗示しているようだ」
「それなら、こちらの複製画をみてくれ」
「鏡のヴィーナス」と呼ばれてる絵の写しであった。
ゼフェリンは身を起こして、指先でその絵の愛の女神のからだに着せてある毛皮を示しながら、
「これも毛皮を着たヴィーナスさ」といって、かすかに笑った。
次回
『DQX毛皮を着たヴィーナス』ゼフェリン