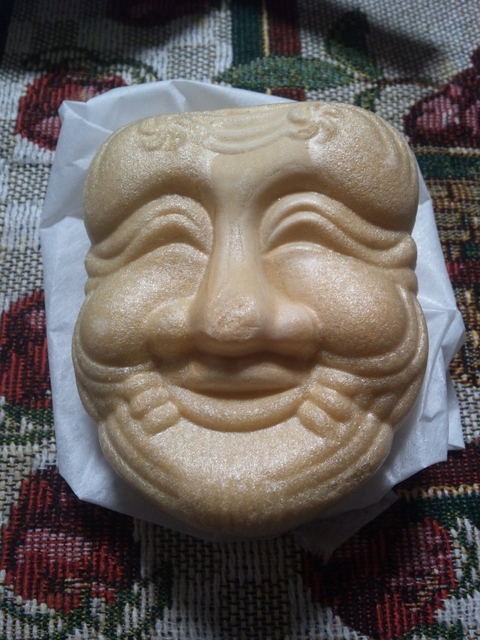昨日に延期にした栗駒山登山を本日、決行です。昨日と同様に雨の確立が高かったが、朝の時点では降っていなく、雨雲の動きを見ると一時は降るがその雨雲が抜けてくれそうだったので、誕生日前日でもあったことから記念登山をすることにしました。同行二人のSⅮHと一関ICで待ち合わせ。9時に自宅を出発する頭で行動していたが、どうやら1時間間違ってしまったらしい。集合時間が9時だったんですねえ。SⅮHを待たせてしまい申し訳なかったです。
一関ICから須川高原温泉方面の一般国道342号を通り、厳美渓を過ぎてから左折して宮城県栗駒市に入り、八幡平アスピーテラインと似たような道中から栗駒レストハウス(日曜営業)がある、いわかがみ平登山口へと向かいました。広々とした駐車場には10台ぐらいは停まっていましたかねえ。山頂ではSⅮHが持参してくれた缶ビール150mlで乾杯し、誕生日祝いをして貰いましたよ。明日から新たな人生が始まります。
「暗闇も 二人で歩けば 怖くない 死出の山も 二人で歩けば 怖くない 大師(弘法大師)と共に 同行(どうぎょう)二人」
《今日の血圧》左から高、低、脈拍、計測時刻となります。かっこ書きは先週の高の数値です。
朝:152(169)97 59 4:20 昼:測定せず 夜:106(140)59 94 19:25
一関ICから須川高原温泉方面の一般国道342号を通り、厳美渓を過ぎてから左折して宮城県栗駒市に入り、八幡平アスピーテラインと似たような道中から栗駒レストハウス(日曜営業)がある、いわかがみ平登山口へと向かいました。広々とした駐車場には10台ぐらいは停まっていましたかねえ。山頂ではSⅮHが持参してくれた缶ビール150mlで乾杯し、誕生日祝いをして貰いましたよ。明日から新たな人生が始まります。
「暗闇も 二人で歩けば 怖くない 死出の山も 二人で歩けば 怖くない 大師(弘法大師)と共に 同行(どうぎょう)二人」
《今日の血圧》左から高、低、脈拍、計測時刻となります。かっこ書きは先週の高の数値です。
朝:152(169)97 59 4:20 昼:測定せず 夜:106(140)59 94 19:25