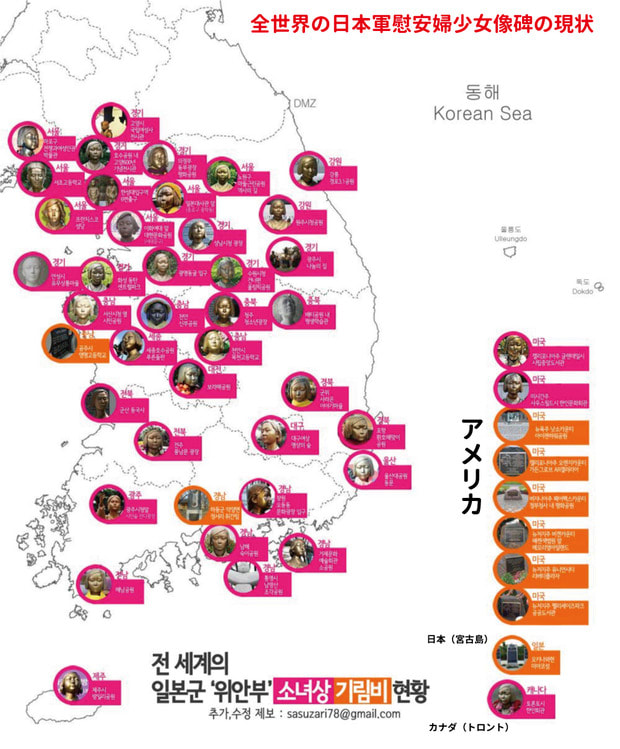『ダメおやじ』と高度経済成長期の狂気――古谷三敏インタビュー【あのサラリーマン漫画をもう一度】
HARBOR BUSINESS Online 4/30(日) 16:20配信
『ダメおやじ』と高度経済成長期の狂気――古谷三敏インタビュー【あのサラリーマン漫画をもう一度】
「BARレモンハート」でインタビューに答える古谷先生
忘れられないあの漫画。そこに描かれたサラリーマンは、我々に何を残してくれたのか。「働き方改革」が問われる今だからこそ、過去のサラリーマン像をもう一度見つめなおして、何かを学び取りたい。現役サラリーマンにして、週刊SPA!でサラリーマン漫画時評を連載中のライター・真実一郎氏が、サラリーマン漫画の作者に当時の連載秘話を聞く連載企画。
第3回目に取り上げるのは、1970年代に社会現象にまでなった過激な少年漫画『ダメおやじ』。家庭でも会社でもサディスティックに虐待される史上最弱のダメ人間は、当時の子供たちに強烈なトラウマを残し、日本人のサラリーマン観に大きな影響を及ぼした。
著者である古谷三敏先生は、1936年生まれの戦中派。焼け跡から高度経済成長期とバブルを経て現在に至る日本の盛衰を、漫画を通して見つめ続けてきた一人だ。そんな古谷先生に、『ダメおやじ』から『BARレモンハート』に至る創作の裏話を、お孫さんがバーテンダーとして腕を振るう「BARレモンハート」で伺った。
◆『ダメおやじ』がいきなり少年サンデーの人気トップに
――僕は子供の頃に『ダメおやじ』を読んで、会社ってこういうシビアな場所なんだなって思ってました。「サラリーマン=ダメおやじ」というイメージだったんです。
古谷:「地震・雷・火事・おやじ」という言葉があったけれど、当時はおやじの権威がまだ残っていて、でもそれが失墜しはじめているかも、というのは何となく感じていたんです。だから、家の中で子供にまでバカにされるお父さんの漫画を描こうと思った。最初は家庭漫画として考えたけど、副編集長から「どうせなら会社でもいじめられることにしたら」というアドバイスをもらって、それは面白いということで、主人公をサラリーマンにしたんです。僕はサラリーマンの経験は無かったけれど、当時はお父さんの50%以上はサラリーマンでしたからね。
――サラリーマンが主人公の少年漫画って、当時としてはかなり珍しいですよね。
古谷:少年雑誌だから、主人公を大人にするのはどうなのか、とは思いました。みんな子どもが主人公だったから。でも、もともと赤塚不二夫先生と違う漫画を描かなきゃいけないというのがあったから。先生は少年漫画で明るい笑いだから、僕はダークな感じの笑いを目指した。感覚的にも江戸川乱歩とか怪奇小説を読むのがすごく好きだったし。先生よりちょっと大人っぽい漫画を描けば違う方向に行けるのでは、と意図的に考えてましたね。
――結果的に大成功して、社会現象みたいになりましたよね。
古谷:権威だったはずのおやじが子供にバカにされる、というのがウケたんですよね。子供はそれを見てゾクゾクしたらしくて。特に女の子から「いじめたりない!」という手紙がたくさん来た(笑)。たった5ページで始まった漫画なのに、あれよあれよという間に少年サンデーの人気投票でトップになっちゃった。当時の渡辺静夫編集長が「はっきりいって古谷さん、僕はこの漫画嫌いです」と言われたけど、人気があるからしょうがない、やめるわけにはいかない、ということになった。
――連載を始めてからどれくらいで人気トップになったんですか?
古谷:すぐですよ。1970年10月に、ひっそりと後ろのほうで目立たない感じで連載が始まったのに、初回から人気がいきなり3位。本当は全8回で年内に終わる予定だったのが、これは凄いということで増ページして。翌年にいろんな人の新連載が次から次へと始まるんだけど、『男どアホウ甲子園』を連載していた水島新司さんとエレベーターで会った時に「古谷さん聞いた?たくさん連載始まったのに、古谷さんと俺のが1位、2位だよ」って言われて。それで「あ、この漫画はウケるな」っていう感触を感じたんですよね。最終的に13ページになって、扉がついたり巻頭カラーになったりした。
――『ダメおやじ』の初期は、赤塚不二夫先生も手伝ってくれていたという話ですよね。
古谷:そうです。当時僕はフジオプロにいて、赤塚先生のゴーストというかブレーンをやっていたわけです。『おそ松くん』とか『もーれつア太郎』とか『天才バカボン』とか、全部の連載のアイディアを僕が出していたんですよね。先生の横にいて、とりとめもない話をしながら作り上げていく。僕は『ダメおやじ』一本しか連載がないけど、先生は10本くらいあったから、「ダメおやじを早く終わらせて俺の漫画を手伝え」っていうことで、『ダメおやじ』を手伝ってくれたんです。
――そういうことだったんですね。
古谷:はじめの10本くらいは先生がネームを入れてくれました。絵は僕が描いたけど、話はバーっと作ってくれた。ほかのアシスタントからは「古谷さんの漫画なのに、なんとも思わないのか」と言われたりしたけど、なんたってギャグの王様がネームを入れてくれるんだから、こんなにありがたいことはないと思って(笑)。『ダメおやじ』が最初からウケた原因は、それもあったと思う。先生はページをめくるリズムが飛びぬけて上手かったので。
――では、頭を釘で打つとか眼球が飛び出るといった残酷な虐待描写も、赤塚先生が考えていたんですか?
古谷:あれは僕ですね(笑)。どんなに死にそうになっても次の日に元気になっている、これはそういう芝居だと勝手に決めちゃっていた。でも、足を縛って天井から逆さに吊るして目に鍵をかける、というのは赤塚先生が考えた(笑)。そんなこと、普通は思いつかないですよね。
◆映画版のオニババ役は和田アキ子になるはずだった?
――ダメおやじのモデルになる人物っていたんですか?
古谷:最初はいたんですよ。フジオプロのみんなで酒を飲みに行ってお金を払うときに、いつもちょうどトイレに入ったり眠っていたりして払わない人がいた。「あいつって汚いよな」という話になって、じゃあこれからあいつのことを「およばれおじさん」って言おうと赤塚先生が言って(笑)。スタッフの中で重要な人だったから、面と向かっては言えなかったんだけど。その人がもとになって、そういうせこいやつを主人公にしようということになった。
――そもそも『ダメおやじ』っていうタイトルが強烈ですが、どうやって思いついたんですか?
古谷:タイトルは自然に出ちゃった感じですね。違うタイトルにしていたら、もう少し企業とかの宣伝に使われたんだろうけど、『ダメおやじ』だとねえ。みんなパチンコのコラボですごく稼いでいたので、僕も「なんとか使ってよ」と言ったんだけど、「タイトルがねえ、球が出ない感じがして無理なんですよ」と言われた(笑)。
――「ダメおやじ」とか「オニババ」は、当時の流行語みたいにもなりましたよね。オニババがとにかく怖かったです。
古谷:大人にとっては、かなりショックなテーマだったかもしれないですね。僕と永井豪さんの『ハレンチ学園』が同時期にPTAでやり玉にあがって、PTAのおばさんたちと対決するという事件があったんだけど、永井さんが逃げたので(笑)、僕だけが10人くらいの女性に「なんで女の人をこれだけ嫌な風に描くんですか!」と言われて。でも、彼女たちもちゃんと読んでないんですよね。だから「よくみてください。確かに主人をいじめたり殴ったりしてるけど、女としてやることはちゃんとやってます、洗濯も掃除もご飯も。ただ給料が少ないから、怒ってるだけなんです」と逆切れっぽく言って黙らせた。
――アニメ化もされましたが、意外と長くは続いてないんですよね。
古谷:あの頃は、なんでもかんでもちょっと人気が出るとアニメにしてたんだよね。でも、アニメが終わると同時に漫画も終わる、というジレンマもあった。アニメにされてもそんなにお金にもならないし、ヒットしないで消えた漫画もずいぶんあるので、結構怖かったんですよね。それに僕の漫画は紙でやってるからいいけど、あれが動くとなると、自分でも恐ろしいなって。本当に悪い漫画を描いてるな、子供に見せられないなという感覚があったから、2クールやった時点で、もういいですやめましょう、と言ったんです。
――三波伸介さん主演で映画化もされましたが、先生は深く関わっていたんですか?
古谷:映画はね、すごいモメたっていうかね。監督が野村芳太郎先生ですよ、すごいよね。脚本がジェームス三木さんだし。作る前から松竹に子供たちから電話がたくさんあって、期待はされていたんですけどね……。
――でも完成した映画は完全に大人向けのサラリーマン映画になっちゃっていたという。
古谷:あれはもうちょっと気楽に作ればよかったのに、さすが野村芳太郎先生という映画になっちゃった。だから思ったほどヒットしなくて、一本で終わった。松竹としてはお金をかけて、いいスタッフで作ったけど。僕はまずキャスティングが良くないと思った。もともとオニババは和田アキ子さんに、ダメおやじはせんだみつおさんにしたいと言ったんだけど(笑)。和田さんにはイメージが悪くなるからという理由で断られたらしい。さもありなんだよね。
――和田アキ子さん版、見てみたかったです!
古谷:オニババ役になった倍賞美津子さんは、アントニオ猪木さんと結婚しているときだったからいいんじゃないかといわれたけど、どんどん真面目な感じの映画になっていったんだよね。洗濯機の中にダメおやじを入れてグルグル回すシーンをどう描こうかと野村芳太郎先生が悩んでいましたよ。
――残酷描写は、あくまで夢の中でちょっと出てくるだけなんですよね。
(次回に続く)
<文/真実一郎>
【古谷三敏】
1936年、旧満州生まれ。漫画家。終戦とともに茨城県に移る。’55年、少女マンガ『みかんの花さく丘』でデビュー。手塚治虫、赤塚不二夫のアシスタントを経て『ダメおやじ』を発表。現在、「漫画アクション」誌上にて『BARレモン・ハート』を連載中
HARBOR BUSINESS Online 4/30(日) 16:20配信
『ダメおやじ』と高度経済成長期の狂気――古谷三敏インタビュー【あのサラリーマン漫画をもう一度】
「BARレモンハート」でインタビューに答える古谷先生
忘れられないあの漫画。そこに描かれたサラリーマンは、我々に何を残してくれたのか。「働き方改革」が問われる今だからこそ、過去のサラリーマン像をもう一度見つめなおして、何かを学び取りたい。現役サラリーマンにして、週刊SPA!でサラリーマン漫画時評を連載中のライター・真実一郎氏が、サラリーマン漫画の作者に当時の連載秘話を聞く連載企画。
第3回目に取り上げるのは、1970年代に社会現象にまでなった過激な少年漫画『ダメおやじ』。家庭でも会社でもサディスティックに虐待される史上最弱のダメ人間は、当時の子供たちに強烈なトラウマを残し、日本人のサラリーマン観に大きな影響を及ぼした。
著者である古谷三敏先生は、1936年生まれの戦中派。焼け跡から高度経済成長期とバブルを経て現在に至る日本の盛衰を、漫画を通して見つめ続けてきた一人だ。そんな古谷先生に、『ダメおやじ』から『BARレモンハート』に至る創作の裏話を、お孫さんがバーテンダーとして腕を振るう「BARレモンハート」で伺った。
◆『ダメおやじ』がいきなり少年サンデーの人気トップに
――僕は子供の頃に『ダメおやじ』を読んで、会社ってこういうシビアな場所なんだなって思ってました。「サラリーマン=ダメおやじ」というイメージだったんです。
古谷:「地震・雷・火事・おやじ」という言葉があったけれど、当時はおやじの権威がまだ残っていて、でもそれが失墜しはじめているかも、というのは何となく感じていたんです。だから、家の中で子供にまでバカにされるお父さんの漫画を描こうと思った。最初は家庭漫画として考えたけど、副編集長から「どうせなら会社でもいじめられることにしたら」というアドバイスをもらって、それは面白いということで、主人公をサラリーマンにしたんです。僕はサラリーマンの経験は無かったけれど、当時はお父さんの50%以上はサラリーマンでしたからね。
――サラリーマンが主人公の少年漫画って、当時としてはかなり珍しいですよね。
古谷:少年雑誌だから、主人公を大人にするのはどうなのか、とは思いました。みんな子どもが主人公だったから。でも、もともと赤塚不二夫先生と違う漫画を描かなきゃいけないというのがあったから。先生は少年漫画で明るい笑いだから、僕はダークな感じの笑いを目指した。感覚的にも江戸川乱歩とか怪奇小説を読むのがすごく好きだったし。先生よりちょっと大人っぽい漫画を描けば違う方向に行けるのでは、と意図的に考えてましたね。
――結果的に大成功して、社会現象みたいになりましたよね。
古谷:権威だったはずのおやじが子供にバカにされる、というのがウケたんですよね。子供はそれを見てゾクゾクしたらしくて。特に女の子から「いじめたりない!」という手紙がたくさん来た(笑)。たった5ページで始まった漫画なのに、あれよあれよという間に少年サンデーの人気投票でトップになっちゃった。当時の渡辺静夫編集長が「はっきりいって古谷さん、僕はこの漫画嫌いです」と言われたけど、人気があるからしょうがない、やめるわけにはいかない、ということになった。
――連載を始めてからどれくらいで人気トップになったんですか?
古谷:すぐですよ。1970年10月に、ひっそりと後ろのほうで目立たない感じで連載が始まったのに、初回から人気がいきなり3位。本当は全8回で年内に終わる予定だったのが、これは凄いということで増ページして。翌年にいろんな人の新連載が次から次へと始まるんだけど、『男どアホウ甲子園』を連載していた水島新司さんとエレベーターで会った時に「古谷さん聞いた?たくさん連載始まったのに、古谷さんと俺のが1位、2位だよ」って言われて。それで「あ、この漫画はウケるな」っていう感触を感じたんですよね。最終的に13ページになって、扉がついたり巻頭カラーになったりした。
――『ダメおやじ』の初期は、赤塚不二夫先生も手伝ってくれていたという話ですよね。
古谷:そうです。当時僕はフジオプロにいて、赤塚先生のゴーストというかブレーンをやっていたわけです。『おそ松くん』とか『もーれつア太郎』とか『天才バカボン』とか、全部の連載のアイディアを僕が出していたんですよね。先生の横にいて、とりとめもない話をしながら作り上げていく。僕は『ダメおやじ』一本しか連載がないけど、先生は10本くらいあったから、「ダメおやじを早く終わらせて俺の漫画を手伝え」っていうことで、『ダメおやじ』を手伝ってくれたんです。
――そういうことだったんですね。
古谷:はじめの10本くらいは先生がネームを入れてくれました。絵は僕が描いたけど、話はバーっと作ってくれた。ほかのアシスタントからは「古谷さんの漫画なのに、なんとも思わないのか」と言われたりしたけど、なんたってギャグの王様がネームを入れてくれるんだから、こんなにありがたいことはないと思って(笑)。『ダメおやじ』が最初からウケた原因は、それもあったと思う。先生はページをめくるリズムが飛びぬけて上手かったので。
――では、頭を釘で打つとか眼球が飛び出るといった残酷な虐待描写も、赤塚先生が考えていたんですか?
古谷:あれは僕ですね(笑)。どんなに死にそうになっても次の日に元気になっている、これはそういう芝居だと勝手に決めちゃっていた。でも、足を縛って天井から逆さに吊るして目に鍵をかける、というのは赤塚先生が考えた(笑)。そんなこと、普通は思いつかないですよね。
◆映画版のオニババ役は和田アキ子になるはずだった?
――ダメおやじのモデルになる人物っていたんですか?
古谷:最初はいたんですよ。フジオプロのみんなで酒を飲みに行ってお金を払うときに、いつもちょうどトイレに入ったり眠っていたりして払わない人がいた。「あいつって汚いよな」という話になって、じゃあこれからあいつのことを「およばれおじさん」って言おうと赤塚先生が言って(笑)。スタッフの中で重要な人だったから、面と向かっては言えなかったんだけど。その人がもとになって、そういうせこいやつを主人公にしようということになった。
――そもそも『ダメおやじ』っていうタイトルが強烈ですが、どうやって思いついたんですか?
古谷:タイトルは自然に出ちゃった感じですね。違うタイトルにしていたら、もう少し企業とかの宣伝に使われたんだろうけど、『ダメおやじ』だとねえ。みんなパチンコのコラボですごく稼いでいたので、僕も「なんとか使ってよ」と言ったんだけど、「タイトルがねえ、球が出ない感じがして無理なんですよ」と言われた(笑)。
――「ダメおやじ」とか「オニババ」は、当時の流行語みたいにもなりましたよね。オニババがとにかく怖かったです。
古谷:大人にとっては、かなりショックなテーマだったかもしれないですね。僕と永井豪さんの『ハレンチ学園』が同時期にPTAでやり玉にあがって、PTAのおばさんたちと対決するという事件があったんだけど、永井さんが逃げたので(笑)、僕だけが10人くらいの女性に「なんで女の人をこれだけ嫌な風に描くんですか!」と言われて。でも、彼女たちもちゃんと読んでないんですよね。だから「よくみてください。確かに主人をいじめたり殴ったりしてるけど、女としてやることはちゃんとやってます、洗濯も掃除もご飯も。ただ給料が少ないから、怒ってるだけなんです」と逆切れっぽく言って黙らせた。
――アニメ化もされましたが、意外と長くは続いてないんですよね。
古谷:あの頃は、なんでもかんでもちょっと人気が出るとアニメにしてたんだよね。でも、アニメが終わると同時に漫画も終わる、というジレンマもあった。アニメにされてもそんなにお金にもならないし、ヒットしないで消えた漫画もずいぶんあるので、結構怖かったんですよね。それに僕の漫画は紙でやってるからいいけど、あれが動くとなると、自分でも恐ろしいなって。本当に悪い漫画を描いてるな、子供に見せられないなという感覚があったから、2クールやった時点で、もういいですやめましょう、と言ったんです。
――三波伸介さん主演で映画化もされましたが、先生は深く関わっていたんですか?
古谷:映画はね、すごいモメたっていうかね。監督が野村芳太郎先生ですよ、すごいよね。脚本がジェームス三木さんだし。作る前から松竹に子供たちから電話がたくさんあって、期待はされていたんですけどね……。
――でも完成した映画は完全に大人向けのサラリーマン映画になっちゃっていたという。
古谷:あれはもうちょっと気楽に作ればよかったのに、さすが野村芳太郎先生という映画になっちゃった。だから思ったほどヒットしなくて、一本で終わった。松竹としてはお金をかけて、いいスタッフで作ったけど。僕はまずキャスティングが良くないと思った。もともとオニババは和田アキ子さんに、ダメおやじはせんだみつおさんにしたいと言ったんだけど(笑)。和田さんにはイメージが悪くなるからという理由で断られたらしい。さもありなんだよね。
――和田アキ子さん版、見てみたかったです!
古谷:オニババ役になった倍賞美津子さんは、アントニオ猪木さんと結婚しているときだったからいいんじゃないかといわれたけど、どんどん真面目な感じの映画になっていったんだよね。洗濯機の中にダメおやじを入れてグルグル回すシーンをどう描こうかと野村芳太郎先生が悩んでいましたよ。
――残酷描写は、あくまで夢の中でちょっと出てくるだけなんですよね。
(次回に続く)
<文/真実一郎>
【古谷三敏】
1936年、旧満州生まれ。漫画家。終戦とともに茨城県に移る。’55年、少女マンガ『みかんの花さく丘』でデビュー。手塚治虫、赤塚不二夫のアシスタントを経て『ダメおやじ』を発表。現在、「漫画アクション」誌上にて『BARレモン・ハート』を連載中